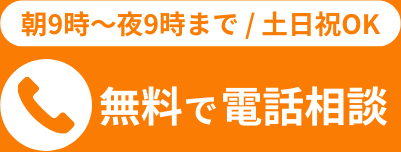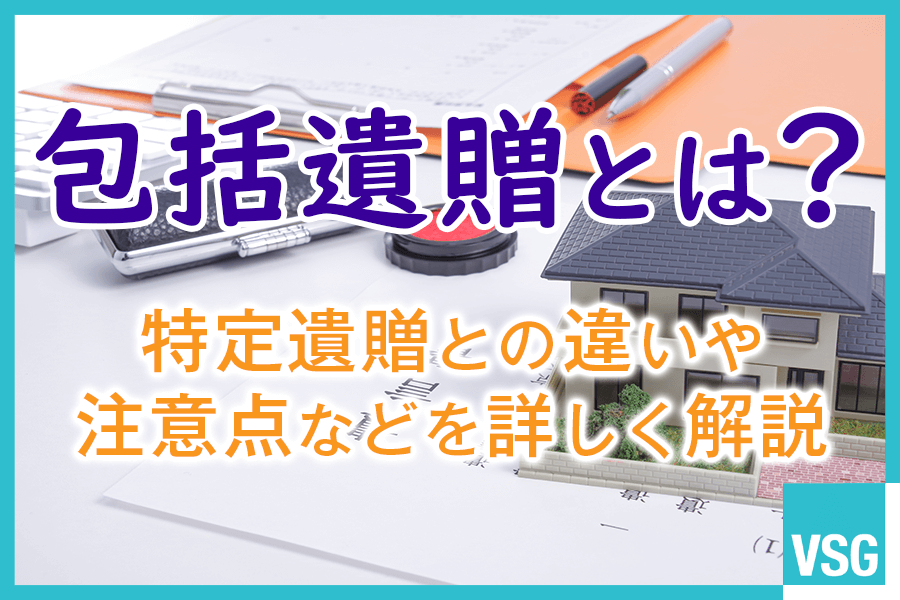記事の要約
- 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する
- 包括遺贈と特定遺贈は、単に財産の指定方法が異なるだけではない
- 遺言者が包括遺贈を検討する場合、「相続税の2割加算」など注意点がある
「遺言書について調べたときに、包括遺贈と特定遺贈という言葉が出てきたけど、どう違うんだろう」
こうした疑問を抱えていらっしゃる方に向け、この記事では「包括遺贈」について解説します。包括受遺者は相続人と同じ権利や義務を持つことから、特定遺贈の場合の受遺者と異なる点がいくつかあるのです。
包括遺贈の基本的な知識から、特定遺贈との違い、遺言者が包括遺贈を考慮する場合の注意点など、詳しく解説します。
目次
包括遺贈とは
包括遺贈とは、遺言によって、「全財産」や「財産の3分の1」といった割合を指定して、特定の人や団体(受遺者)に財産を譲り渡すことです。
包括遺贈の大きな特徴は、民法第990条によって「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」とされる点です。
民法第990条
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。引用元 民法 | e-Gov 法令検索
したがって、包括受遺者が法定相続人ではなくとも、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も指定された割合に応じてすべて引き継ぐことになります。
包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈には、財産の全部または一定の割合を指定して譲り渡す「包括遺贈」と、土地や預金など特定の財産を指定して譲り渡す「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈と特定遺贈は、単に財産の指定方法が異なるだけではありません。受遺者の権利や義務、税金の取り扱い、手続きの期限などの面に、大きな違いがあるのです。
ここからは、以下のような包括遺贈と特定遺贈の違いについて、それぞれ詳しく解説していきます。
- 負債(債務)の承継義務
- 遺贈の放棄手続きと期限
- 不動産取得税の課税の有無
- 遺産分割協議への参加義務
負債(債務)の承継義務
包括遺贈と特定遺贈の大きな違いの一つが、債務の取り扱いです。
包括受遺者は、前述の通り「相続人と同一の権利義務を持つ」と民法で定められています。
そのため、遺言者に借入金や未払金といったマイナスの財産(債務)がある場合、受け取る財産の割合に応じて、包括受遺者はその返済義務も引き継がなければなりません。
これに対し、特定遺贈は「指定された特定のプラスの財産のみ」が取得の対象となることから、原則として特定受遺者が遺言者の債務を承継することはありません。
もし、実際は包括遺贈であるにもかかわらず、自身を特定遺贈の受遺者だと誤認してしまうと、後述する熟慮期間を過ぎてしまうかもしれません。
その結果、包括遺贈の場合の放棄ができなくなり、意図せず債務を承継してしまう可能性があります。
遺贈の放棄手続きと期限
包括受遺者が遺贈を放棄する場合、相続人と同様の扱いとなるため、遺贈の放棄も相続放棄と同じルールが適用されます。
包括受遺者が遺贈を放棄する場合、「自己のために遺贈があったことを知った時から3カ月以内」の熟慮期間内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、放棄の申述を行わなければなりません。
また、特定遺贈のケースとは異なり、包括遺贈者は財産の一部だけを放棄することはできません。(借金は放棄し、プラスの財産だけを受け取るなど)
一方、特定遺贈の場合は、原則として放棄の期限はありません。特定受遺者はいつでも放棄の意思表示ができます。
家庭裁判所での手続きも不要で、他の相続人や遺言執行者に対して放棄の意思を伝えさえすれば、「遺贈された財産を放棄した」と扱われます。
ただし、他の相続人をはじめとする利害関係者から「承認または放棄をすべき旨の勧告」を受けた場合は、指定された期間内に意思表示をしないと、遺贈を承認したものと見なされます。
不動産取得税の課税の有無
包括遺贈と特定遺贈では、不動産を遺贈された場合にも税務上の大きな違いがあります。
地方税法では、「相続による不動産の取得には不動産取得税が課されない」と定められており、この「相続」には包括遺贈が含まれます。
地方税法第73条の7
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
したがって、包括遺贈により被相続人(遺言者)の不動産を取得した場合は、財産を受け取った人が相続人であるかどうかに関わらず、不動産取得税は非課税となります。
不動産取得税とは
一方、特定遺贈によって不動産を取得した場合、受遺者が相続人以外であれば、不動産取得税が課税されます。
遺産分割協議への参加義務
包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」ことから、たとえ法定相続人でなくとも、他の相続人と共に遺産分割協議に参加する必要があります。
特に「財産の2分の1を遺贈する」といった割合での包括遺贈の場合、「どの財産をどれだけ受け取るのか」を、他の相続人全員と話し合って具体的に決める必要があるためです。
一方、特定遺贈の場合は、遺言書で受け取る財産が具体的に指定されているため、原則として特定受遺者は遺産分割協議に参加する必要はありません。
遺言者が包括遺贈を検討する場合の注意点
遺言者が包括遺贈を検討する場合、税制面と法律関係で以下の点に留意しなければなりません。
- 相続税額の2割加算
- 不動産登記にかかる登録免許税の増加
- 遺留分侵害のリスク
ここからは、それぞれの注意点ごとに解説いたします。
相続税額の2割加算
被相続人の遺産のプラスの財産からマイナスの財産を引いた額(正味の遺産額)が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税がかかります。
ポイント
財産を受け取った包括受遺者が、亡くなった方(遺言者)の配偶者または一親等の血族(子や父母)以外である場合、その人が納めるべき相続税の額が2割増しになります。
この「相続税額の2割加算」により、受遺者が実際に手にする財産が税金で大きく減ってしまう可能性があるため、遺言を作成する際は、財産を渡す相手も考慮して慎重に検討しましょう。
不動産登記にかかる登録免許税の増加
遺贈によって法定相続人以外の人が不動産を取得した場合、相続登記時にかかる登録免許税の税率が、相続人が取得する場合に比べて高くなります。
遺贈を受けた人が法定相続人であれば、登録免許税の税率は「登記時点の固定資産税評価額の0.4%」である一方、法定相続人以外なら「固定資産税評価額の 2.0%」となります。
このように、財産を受け取るのが法定相続人以外の場合、登録免許税の税率が5倍にもなるため、不動産の評価額が高いほど、名義変更にかかる費用が大幅に増加します。
遺留分侵害のリスク
遺言書は、原則として法定相続よりも優先されますが、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には、民法で最低限保障された遺産の取得割合である「遺留分」が認められています。
遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合、遺産を受け取る権利のある法定相続人(遺留分権利者)から、包括受遺者に対して「遺留分侵害額」に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。
受遺者と遺留分権利者とのトラブルにつながる恐れもあるため、遺言書の作成時には注意が必要です。
包括受遺者には、遺留分は認められていない
遺留分は被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている権利です。そのため、法定相続人ではない包括受遺者は、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
包括遺贈で遺贈をする場合のポイント
包括遺贈の内容を遺言書に記載する際は、「遺言者は、その所有する財産の全てを包括して遺贈する」や「私の全財産の3分の2を、孫〇〇に包括して遺贈する」のように、財産全体に対する割合を指定します。
このケースでは、相続人の組み合わせによって法定相続分が以下のように変わる点に注意しましょう。
また、遺言書の作成時は、形式不備で無効となるリスクを避けるため、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」の形式で残すことをおすすめします。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が内容や形式を確認しながら作成する遺言です。
自筆で作成する場合と比べ、法律上の要件を満たさずに無効となるリスクを抑えられるほか、原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。
包括遺贈に関する疑問は専門家へご相談を
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、負債の承継義務が発生したり、遺産分割協議の参加義務があったりと、特定遺贈とは異なる点がいくつかあります。
また、相続税が2割増しとなるケースなど、遺言者と包括受遺者との関係次第で、相続税負担が増す可能性もある点も注意が必要です。
このような包括遺贈に関する疑問が生じた場合は、相続の専門家へのご相談がおすすめです。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。