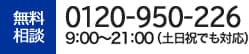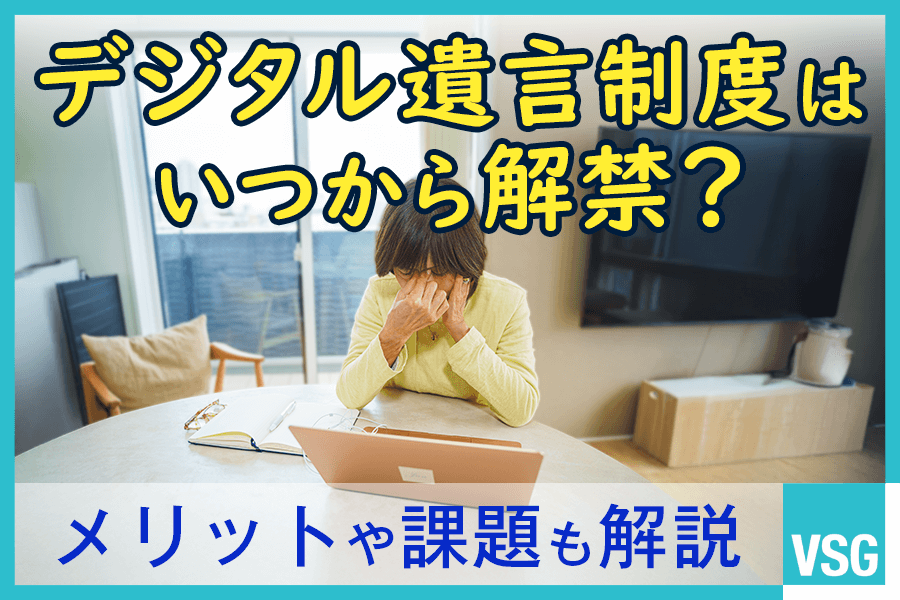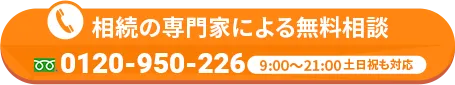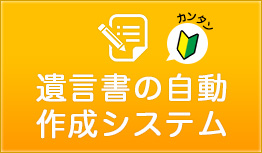この記事でわかること
- パソコン入力で遺言を残せる「デジタル遺言制度」の導入が検討されている
- デジタル遺言は、手書き不要で利便性が高いというメリットがある
- 一方、デジタル遺言の導入には不正アクセスやフェイク動画への対応などの課題が残っている
「遺言書を書いたことはありますか?」
と聞かれたとき、大半の人は「書いたことがない」と答えるでしょう。
現行の制度で認められている遺言書は、「すべて自筆」または「公証人に作成してもらう」という方法が中心です。
しかし、パソコンやスマートフォンが普及し、手書きの機会が少なくなった現代では、自筆による遺言書作成が手間だと思う人が多いかもしれません。
そこで、政府は今、パソコンやスマホで作成できる「デジタル遺言」 の創設を検討しています。
この記事では、デジタル遺言制度の概要や導入案、デジタル遺言のメリットやデメリットを解説します。
目次
デジタル遺言とは
デジタル遺言とは、従来の遺言書のほかに導入が検討されている「デジタル機能を組み合わせた遺言書」です。
いわば「遺言書の電子化」といえるもので、現在、法務省の法制審議会を中心に、公的なデジタル遺言制度の実現に向けた制度設計が進められています。
すでに「デジタル遺言サービス」を提供している民間企業もありますが、現時点では法的効力が認められていません。
現行の法律において、法的に有効とされる遺言は「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」など、民法に定められた方式で作成されたものに限られています。
そのため、動画やメール、パソコンやスマートフォンで作成した遺言は無効とされ、法的拘束力はありません。
デジタル遺言の検討が進められている背景
デジタル遺言制度の導入検討の要因には、社会環境の変化があります。
現在の日本は、少子高齢化が進み、一人暮らしの高齢者が増えています。
相続人がいない人も多く、「誰にどのように自分の財産を引き継ぐか」を決めていない土地や、家の名義が曖昧になってしまうケースも増加しており、遺言の重要性はこれまで以上に大きくなっています。
そのため政府は、土地の持ち主がわからない「所有者不明土地」の解消や、土地の所有者の名義変更をする「相続登記」が促進されるよう「より使いやすい遺言制度」の整備を進めています。
また、現在の遺言制度の基本的な仕組みは、明治時代に作られました。
パソコンが普及する前の制度のまま、130年前から大きくは変わっていません。
2019年、財産目録はパソコンで作成できるよう改正されました。ただし、遺言制度自体には改正はなく、現代社会にそぐわない点が目立つようになっています。
この点も、政府がデジタル遺言を導入することを検討している大きな理由です。
現状の遺言制度と不便な点
遺言にはいくつかの種類がありますが、中でもよく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、最も手軽で費用もかからない方法です。
全文・日付・氏名をすべて手書きし、書面に押印して作成します。
また、「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば法務局で遺言書を預かってもらえますので、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
しかし、自筆証書遺言には、以下のような不便な点があります。
- 握力や視力が落ちた高齢者にとって、手書きでの遺言作成は負担が大きい。
- 作成年月日の記入や押印漏れなどがあると、無効となることがある。
- 法務局に預ける場合は、用紙のサイズや余白の幅などの細かいルールがあり、作成に手間がかかる。
- 法務局以外の場所に保管されていた場合は、家庭裁判所の検認が必要。
一方、公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え、公正証書で遺言を残す方法です。
自分で遺言書を書く必要がないため、手間が省ける点が特長です。
ただし、公正証書遺言を作成するには、原則として公証役場に行って打ち合わせをする必要があります。
また、遺言書作成時には証人2人の立ち会いが必要であり、公証人手数料がかかる点も考慮しなければなりません。
なお、2025年10月1日からは、「公正証書のデジタル化」がスタートし、公正証書遺言もオンライン上で作成を進められるようになりました。ただし、すべての公証役場で利用できるわけではなく、順次、指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
デジタル遺言の3つの中間試案について
以上の背景を踏まえ、2025年7月、法務省は以下の中間試案を公表しました。
- 普通方式における新たな方式の遺言の創設
- 自筆証書遺言等の方式要件の更なる緩和の検討
- 特別方式の遺言に関する見直し
このうち「特別方式の遺言に関する見直し」は、急な生命の危機的状況で遺言をする必要がある場合の取り扱いを見直すものです。
この記事では、「普通方式における新たな方式の遺言の創設」と「自筆証書遺言等の方式要件の更なる緩和の検討」を中心に紹介します。
新たな遺言の創設案と自筆証書遺言の緩和
法務省は、以下の3案のうち、「1案」または「複数の案」を創設することを検討しています。
| 案名 | 書式 | 概要 | 検認 |
|---|---|---|---|
| 甲案 | パソコン等の電磁的記録に、遺言の全文等の文字情報を記録する | 【甲1案】証人の立会いを要件とする
遺言者は、証人2人以上の前で遺言の全文等を朗読。 |
必要 |
| 【甲2案】証人を要せず、これに相当する措置を要件とする
遺言者が遺言の全文等を朗読している様子を、録音・録画する。 |
|||
| 乙案 | 遺言の電磁的記録を公的機関にて保管申請する。 その際、遺言者は遺言の全文を朗読する。 |
不要 | |
| 丙案 | 遺言をプリントアウト等し、署名をしたうえで公的機関へ保管申請する。 その際、遺言者は遺言の全文を朗読する。 |
3案とも、遺言の全文等が文字情報として記録された「電磁的記録」を作成します。
「Wordなどのテキスト形式で、パソコンで遺言内容を入力する」といったイメージがわかりやすいでしょう。
また、これらの3案は「遺言を公的機関に預けなくてもよい甲案」と、「公的機関で保管してもらう乙案および丙案」に分類されます。
さらに、自筆証書遺言等の方式要件の更なる緩和の検討として、「自署押印を不要とする甲案および乙案」と、「引き続き必要とする丙案」が挙げられています。
甲案:本人が遺言書を朗読している様子を録音・録画する
甲案は、「遺言を電磁的記録として残し、遺言者による全文等の朗読を録音・録画して遺言とする」方式です。
遺言者はWordなどで遺言の全文を作成し、遺言書の内容を読み上げている様子を録音または録画します。
また、甲案には証人の立ち会いを要件とする「甲1案」と、証人を要せずこれに相当する措置を要件とする「甲2案」があります。
「甲案1」における証人は、Zoomなどのウェブ会議を通じた立ち会いも検討されています。また、証人になれる人・なれない人は、現行の公正証書遺言の証人と同じ基準で検討されています。
「甲2案」では、証人立ち会いの代わりに作成した遺言データには電子署名を付け、偽造やなりすましではないことを証明します。
電子署名とは、インターネット上の電子文書に付与する署名です。紙の文書における署名や捺印に相当し、本人証明の役割を果たします。
なお相続発生後、甲案のデジタル遺言は、家庭裁判所での検認を必要とします。
また、甲案の遺言日付は「遺言が完成した日を遺言者が記録する」としています。
甲案の電磁的記録は自宅保管でも構いませんが、後述「乙案」の要件を充たせば、公的機関で保管してもらうことができます。
乙案:電子署名をした遺言書データを、公的機関で保管する
乙案は、「遺言の電磁的記録に電子署名を付したうえで、公的機関で保管してもらう」方式です。
現時点では、法務局が公的機関の候補として挙がっています。
遺言者は公的機関に対し、電子署名を付した電子的記録の保管を申請します。
保管申請の際には本人確認をしますが、対面のほか、ウェブ会議の画面越しに身分証明書を提示する方法も考えられています。
また、遺言者は「遺言は自分の意思である」ことを申述し、遺言の全文を朗読します。
本人確認と遺言内容の申述後、公的機関は電磁的記録の遺言を保管します。
乙案の方式で保管された遺言は、家庭裁判所での検認は不要です。
遺言者が亡くなったあと、相続人等は遺言書を閲覧したり、証明書を請求したりすることができます。
相続人のうち1名が遺言の閲覧をすると、他の相続人にも通知される規定も設けられる予定です。
乙案の遺言日付は、遺言が完成した日(=遺言を保管した日)を公的機関が記録するとされています。
丙案:プリントアウトした遺言書に自筆署名のうえ、公的機関で保管する
丙案は、「遺言の電磁的記録を印刷・自筆署名をしたうえで、書面を公的機関で保管してもらう」方式です。
基本的な手続きは乙案と同じですが、電子署名の代わりに、紙の遺言書に署名をする点が大きく異なります。
丙案は、「パソコンで文章を作成できるものの電子署名には不慣れな人」や、「全文を自筆するのは億劫だが、自筆署名程度なら苦にならないといった人」でも、デジタル遺言制度を利用できるように想定された方式です。
また、遺言書は公的機関で保管します。
丙案の遺言書も、家庭裁判所による検認は不要となる予定です。
デジタル遺言のメリット
デジタル遺言制度が導入された場合、以下のようなメリットがあると考えられます。
書き直しの手間が減り、遺言書作成が楽になる
デジタル遺言は、全文を手書きする必要がなく、書き損じても簡単に修正できます。
また、資産が多い人や法定相続人が多数いる人の場合、自筆で「誰に財産を引き継ぐか」したためていくだけでも、大変手間がかかります。
しかし、パソコン入力ができる人なら、デジタル遺言制度導入後は従来よりも簡単に遺言書を作れるようになるでしょう。
紛失リスク・改ざんリスクが軽減できる
遺言の内容はクラウド上にデータとして保管されるため、紙の遺言書のように紛失したり、筆跡をまねて偽造されたりする心配が少なくなります。
公的機関に保管される乙案や丙案であれば、より安全性が高いでしょう。
また、遺言者の死後に相続人の1人が遺言書を閲覧請求すると、他の相続人に通知される仕組みも検討されています。
この方法は、相続人による不正な閲覧や改ざんの防止にもつながります。
遺言書の選択肢が増える
デジタル遺言は、電磁的記録による新たな遺言方式です。
丙案のように、紙と電子のハイブリッド型方式もあるなど、幅広い世代・状況に対応できる方法も考えられています。
また、デジタルデータで遺言内容を共有できるようになれば、相続人への連絡や遺産分割協議に向けた諸手続きを、スムーズに進められる可能性があります。
デジタル遺言のデメリット・懸念点
一方、デジタル遺言制度は、下記の懸念点が挙げられています。
不正アクセスや改ざんのリスクがある
改ざんやなりすましのリスクをどのように抑えるか、セキュリティ面の安全性を確保するかは、まだ議論の途中段階です。
また、フェイク動画の判断方法もこれからの課題と言えるでしょう。
なお、偽造リスクの対策としては、ブロックチェーンの技術活用などが検討されています。
本人の意思がわかりにくく、遺言能力の有無が判断しにくい
現行の遺言制度では、筆跡や文章の言葉遣い、対面で話した結果などを勘案し、遺言者の意思や遺言能力を判断します。
しかしオンライン上では、「本人の意思に基づく遺言か、遺言能力があるか」という判断がしにくいのではないか、という懸念も残ります。
デジタルデバイスの操作に慣れていないと利用しづらい
電子署名はもちろん、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない人も一定数います。
普段からデジタルデバイスを使っていない人にとって、デジタル遺言はハードルが高いでしょう。
データ消失のリスクがある
うっかりデータを削除してしまったり、パスワードの漏洩によりデータが消えてしまったりする可能性もあります。
データ削除を防ぐような対策が求められます。
海外のデジタル遺言制度について
デジタル遺言制度は海外でも検討が進んでおり、すでに導入されている国もあります。
アメリカでは、2人以上の証人の前で電子署名を行うことでデジタル遺言が有効とされており、一部の州では生体認証による方式も認められています。カナダも原則として証人の立ち会いが必要です。
中国や韓国でも、録音・録画による遺言が法整備されています。
一方、ニーズの少なさや偽造・変造の可能性を理由に、電磁的記録を原本とする遺言制度が未整備の国もあります。
ただし、イギリスではパソコン入力の遺言書も認められている、ドイツでは自筆遺言の要件緩和が検討されているなど、何らかのデジタル化の動きが見られます。
デジタル遺言制度はこんな人におすすめ
デジタル遺言制度は、以下のような人が使いやすいでしょう。
- デジタル機器の利用に慣れている人
- 財産の種類や金額、相続人が多い場合
- 遺言書の紛失や改ざんのリスクを避けたい人
パソコンやスマートフォンを使い慣れている人や、生前のうちから準備を進めたい人にとっては、手書きの手間が省けるデジタル遺言は利便性が高いと言えます。
また、全国に相続人がいる場合などは、デジタルデータで遺言内容を共有することができるようになれば、各相続人への連絡や手続きをスムーズに進められます。
そして、デジタル遺言制度の導入により遺言書を作成する人が増えれば、「誰が財産を引き継ぐのかわからない」といったケースが少なくなることも期待されます。
弊社の「ビデオ遺言サービス」もご検討ください
弊社には、遺言書作成サービスのオプションとして「ビデオレター遺言」のサービスがあります。
プロのカメラマンおよびスタッフが、遺された家族へ伝えたい想いを動画撮影・編集し、DVDにしてお渡しいたします。
「遺言書だけでは伝えきれない想いを、大切な家族に残したい…」
そのような気持ちを伝えるために、ぜひ本サービスもご検討ください。
「遺言」の重要性はより高まる?
デジタル遺言は、デジタル社会に対応した新たな遺言方法として注目が集まっています。
一方、デジタル遺言制度の導入には課題もあります。
ネット上での顔認証やマイナンバー認証、電子署名の運用、遺言の訂正や取り消し方法などは今後も議論や検討が続くでしょう。
なお、本記事で紹介した甲・乙・丙の3案については、2025年9月23日まで意見募集(パブリックコメント)をしています。
そして、財産を誰に引き継ぐかを明確に示す手段である遺言の重要性は、さらに高まっています。
しかし、せっかく遺言書を書いても、形式や内容に不備があると無効と判断されてしまう可能性もあります。
そのため、遺言書は専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
「遺言書を作成したいけれど、どのように書けばいいのだろう?」
そのような場合は、VSG相続税理士法人にご相談ください。
当法人では、相続に詳しい税理士のほか、グループ内の行政書士や司法書士と連携し、ワンストップで遺言書作成に関するご相談に対応しています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。