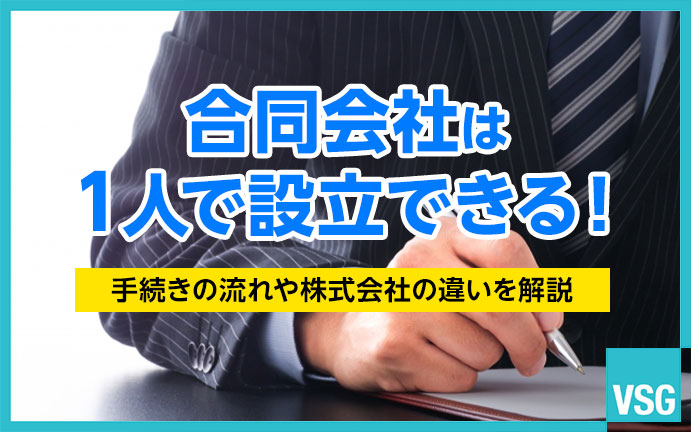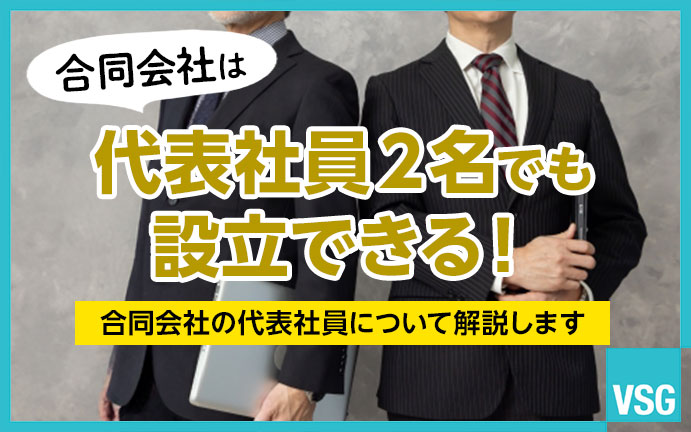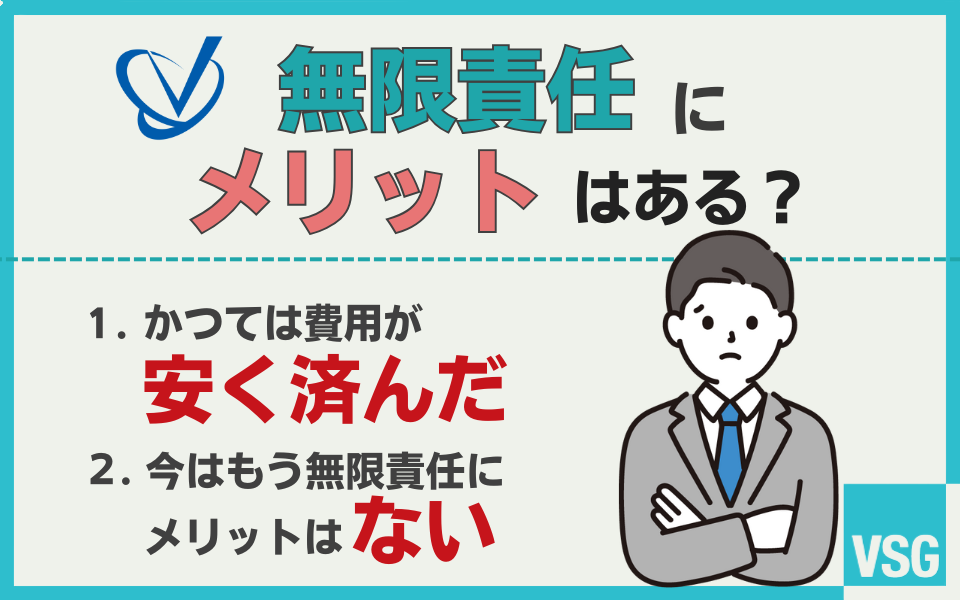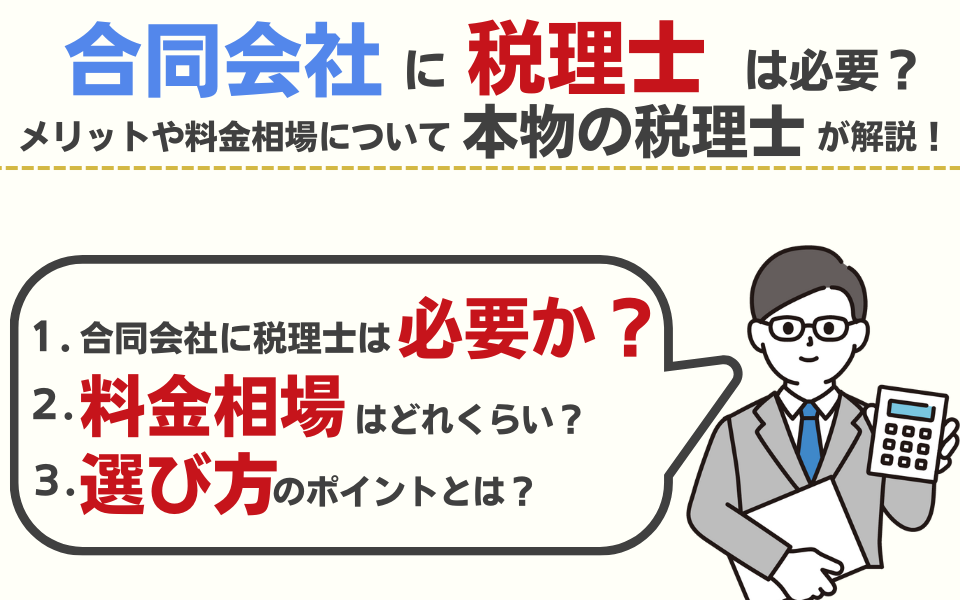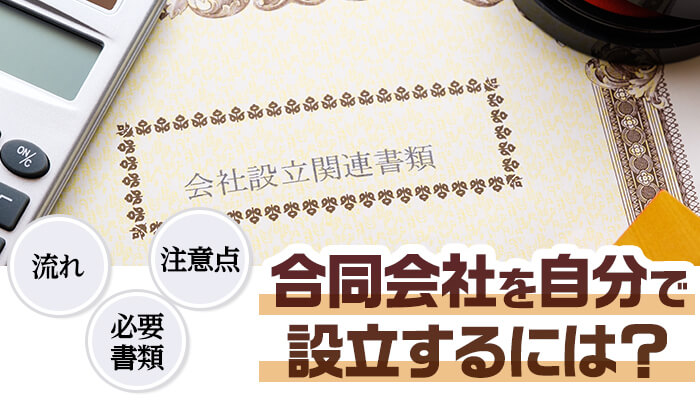最終更新日:2025/4/11
合同会社はやめとけ?やばい?合同会社が向いている事業とは?

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

「会社」と聞いて、真っ先に浮かぶ会社形態と言えば株式会社でしょう。
一方で、合同会社という形態もあるものの、こちらはあまり一般に浸透しているとはいえません。
「合同会社ってよく聞くけど、詳しくはわからない…」
「株式会社と何が違うんだろう…」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
この合同会社ですが、実は近年設立された営利法人の4つに1つが合同会社であり、今まさに急増中の会社形態なのです。
なぜ合同会社が近年急増しているのか、そもそも合同会社とはどういう形態なのか、どんな事業が向いているのかなど、合同会社を取り巻く現状について詳しく解説していきます。
合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正時に新しく設立できるようになった会社形態のことです。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに作られたことから、日本版LLCとも呼ばれます。
合同会社がどんな形態の会社なのかは、株式会社と比較するとよくわかります。
まず、最も違いが顕著なのが資金調達方法です。
株式会社は、自社の株式を発行して株主から出資金を調達して事業を運営します。
一方で合同会社は、社員自身が出資してその資金で事業を運営します。
ここでいう「社員」は、主に業務を行う株式会社の社員とは意味が異なり、会社に出資をして経営に関わる人たちのことを指します。
経営者と社員が「同等」の扱いとなり、出資した社員それぞれが議決権を持つことになります。
株式会社では、会社を株主が所有して取締役が経営を行う、いわゆる「所有と経営の分離」の形をとっていますが、合同会社では社員が会社の所有と経営を行う「所有と経営の一致」という形になります。
つまり外部から株式によって資金を調達できない代わりに、社内のことを自分たちである程度自由に決められるのが、合同会社の特徴のひとつです。
経営者の肩書きも、株式会社であれば「代表取締役社長」ですが、合同会社では社員の中の代表という位置づけで「代表社員」ということになります。
この肩書きにあまりピンとこない場合は、名刺には自由に肩書きを付けられるため、社長やCEO(最高経営責任者)と表記することもあるようです。
合資会社・合名会社との違い
2006年に会社法が改正される前までは、営利法人は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「有限会社」の4形態でしたが、改正後は「株式会社」と「持分会社」の2形態に分類されました。
この持分会社に含まれるのが、「合同会社」「合資会社」「合名会社」になります。
社員が自ら出資して事業を営む点は、合同会社・合資会社・合名会社のどれも同じです。
これら3つの会社は、「有限責任社員」と「無限責任社員」の存在によって分類されています。
有限責任社員とは、会社が倒産した場合に、金融機関が回収できなくなった債務など弁済の必要がある損害に対して、自己の出資額の限度内で責任を負うことになる社員のことです。
無限責任社員とは、会社が倒産した場合の弁済責任を、自己の財産を含めて無限の範囲での責任を負うことになる社員のことです。
有限責任社員に比べてリスクが高い分、強い業務執行権を持つことができます。
- ・合同会社は、有限責任社員のみ
- ・合名会社は、無限責任社員のみ
- ・合資会社は、有限責任社員と無限責任社員
という構成上の違いがあります。
会社を構成するのに必要な社員数も、合同会社・合名会社は「1名以上」ですが、合資会社は有限責任社員と無限責任社員を持つ必要があるため「2名以上」となります。
また、合名会社・合資会社はお互いの信用や労働力を資産とみなすことで、資本金が0円でも設立できるのも大きな特徴です。
かつては会社設立の際に最低限必要な資本金が非常に高く、株式会社は1,000万円以上、有限会社という形態でも300万円以上が必要でした。
そのため、資本金がなくても設立できて自由に経営しやすい合名会社・合資会社にも一定のニーズがありました。
しかし現在は会社法が改正され、株式会社や合同会社が資本金1円から設立できるようになったため、出資者のリスクが大きい合名・合資会社はあまり設立されなくなっています。
合同会社のメリット
合同会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
この点も株式会社と比較して、その特徴を詳しく見てみましょう。
1. 設立の費用が抑えられる
株式会社の設立にかかる費用は、20万~30万円程度がひとつの目安になります。
合同会社の設立にかかる費用は、10万円程度です。
スタート時から10万~20万円も負担が減るのは大きなメリットといえるでしょう。
2. 設立の手続きが比較的容易
手続きの完了までに株式会社が1~2カ月の期間を要するのに対して、合同会社は数日~2週間程度で全て完了させることができます。
3. 決算情報を公示する義務がない
株式会社であれば、国が発行している官報に決算情報を公示する義務があります。
そのため毎年6万~7万円程度の官報掲載費が発生しますが、合同会社には決算情報公示の義務がないため、この公示の手続きや費用を抑えることができます。
4. 定款の書き換えが少なく済む
株式会社の役員の場合、任期がそれぞれに定められているため、一定の期間での役員変更が必要になります。
その変更に伴って定款の書き換えが必要となり、その度に数万円の費用が発生します。
合同会社は役員の任期が定められていないため、変更をしない限り定款の書き換えの費用もかかりません。
5. 社員の意思で決定ができる
株式会社の場合、出資者と取締役が必ずしも同一ではないので、外部の出資者が議決権を持っていることも多々あります。
何らかの意思決定をする際にも、その都度出資者の意思確認と調整との機会が必要になります。
合同会社の場合は、出資者がそのまま社員という形なので意思決定がスムーズに進みます。
6. 利益配分を自由に決定できる
株式会社の場合、出資比率に応じて出資者への利益の配分が決まります。
合同会社の場合、出資比率に関係なく定款において、出資者へ利益の配分を自由に決めることができます。
出資金が少ないものの会社への貢献度が高い社員に対して、利益の配分を多めに設定するなどもできます。
7. 株主総会の必要がない
株式会社では株主総会を開催する必要がありますが、合同会社では必要ありません。
重要な決定事項は、定款に特別な記載がなければ、総社員の同意によって決議されます。
総社員の同意と聞くとハードルが高そうですが、実際には株主総会のように全員が一堂に集まる必要がなく、外部の人間である株主も絡まないため、迅速な意思決定が見込めるのです。
合同会社のデメリット
合同会社の形態にはメリットだけでなく、デメリットも存在しています。
1. 大規模な資金調達がしにくい
株式会社の場合、株式の発行や譲渡によって大規模な資金調達を実施することが可能です。
合同会社の場合、株式発行ができないので資金調達の幅が大きく制限されます。
株式会社が大規模事業向け、合同会社が小規模事業向けであると言える最たる理由でしょう。
2. 社会的信用で不利なことがある
株式で資金調達できない、外部に意思決定者を持たない、などの閉鎖的な性質から社会的な信用において不利になることがあります。
また、急増している会社形態ではあるものの、日本ではまだまだ合同会社の認知度が低く、その面でも取引先の信用度において株式会社に劣ってしまう傾向があります。
3. 上場ができない
合同会社には株式という概念自体が存在しないため、株式上場をすることができません。
社会的信用を高める方法のひとつに株式上場がありますが、その方法を使うことができないので、理想とするこれからの事業展開を十分に検討しておく必要があります。
4. 利益配分によるトラブルが起きる可能性がある
利益の配分を出資率に関わらず自由に決められるという利点を前述しましたが、これは見方を変えれば社員同士のトラブルを引き起こす可能性を含んでいます。
定款で利益配分を決める際には、不要な確執を生み出さないようにくれぐれも慎重な検討が必要です。
5. 経営陣の関係性が経営自体を左右してしまう
外部の株主が介入する株主総会がなく、内部の社員のみで意思決定をするため、経営陣の関係性が悪化すると、経営状況が危ぶまれる事態に直結する恐れがあります。
意見の対立によって経営から外れることになれば、その分の資本金の払い戻しが発生する場合もあります。これからの経営の方向性は経営陣の関係性にかかっていることは、押さえておくべきポイントです。
新設法人の中での割合が急増している

冒頭でも述べたように、近年新設法人の中で合同会社が急増しています。
法人の設立件数は年々増加傾向にありますが、そのなかでも合同会社は毎年比率を伸ばし、2023年の時点で前年比増加率は株式会社を抜いてトップを記録しています。
新設法人の中での割合は26.5%に及び、新設法人の4社のうち1社以上が合同会社といえる状況です。
参考:2023年の「合同会社」の新設法人、初の4万社超 他の法人格にはないメリットとインボイス制度が寄与か|株式会社東京商工リサーチ
合同会社が増えた背景には、安価な設立費用や経営の自由さ、インボイス制度の導入などがありますが、次のような事情も関係しています。
個人の不動産投資で急激に増えた
サラリーマンが不動産投資をしていることは珍しくなく、投資が軌道に乗れば給料と合わせた収入が1,000万円を超えることもあります。
これぐらいの収入になってくると、ケースによっては個人と法人での税率の差が30%にまで及ぶため、法人化を検討するタイミングとなってきます。
しかし、勤めている会社で副業禁止の規定などがあると、簡単に本人名義で会社を設立することができません。そのため、配偶者などを代表者にして合同会社を設立する人が急激に増えました。
会社勤めをしながらでも設立の手続きができてしまうほど、合同会社の手続きが簡単であることも、こうした事情を後押ししています。
あの大企業たちも実は合同会社
アメリカでは株式会社と同程度に一般にも浸透している合同会社(LLC)ですが、日本ではいまだに認知度そのものがあまり高くありません。
しかし、実は名だたる大企業たちも、すでに日本で合同会社の形を取っているのです。
以下は一例です。
- ・Apple Japan
- ・グーグル
- ・アマゾンジャパン
- ・西友
- ・ユニバーサルミュージック
- ・日本アムウェイ
- ・IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
- ・ワーナーブラザースジャパン
- ・フィリップモリスジャパン
- ・ユー・エス・ジェイ
- ・DMM.com
このように多くの大企業が、「株主総会の必要がない」「決算公告の必要がない」「意思決定を柔軟かつ迅速に行える」などのメリットを考慮して、合同会社を選んでいるのです。なかには株式会社から合同会社に形態を変えた企業も数多くあります。
規模が大きくなればなるほど、株式会社において実施が必要な手続きの工数や時間は膨れ上がります。日々変動していく社会に柔軟に対応して生き残っていくために、経営の自由度が高い合同会社を選ぶのはとても合理的な選択だといえるでしょう。
こうした理由から、合同会社は現在では小規模な事業者だけでなく、大企業にも広く選ばれ、利用されています。
特に外資系企業は、本来であれば国ごとに違う会計や課税のルールを母国のルールに合わせやすいといった理由で、合同会社を選びがちです。
AppleやAmazonなどの大企業も、そうした理由からアメリカ本社は株式会社としつつ、日本での法人は合同会社を選択しています。
どういう事業に向いているのか
合同会社のメリット・デメリット、合同会社を取り巻く環境についてわかってきたところで、どういう事業が合同会社という会社形態に適しているといえるのかについて見ていきましょう。
1.一般消費者向け(B to C)事業
合同会社のデメリットとして、社会的な信用度が低い傾向があることを述べましたが、これは対会社(B to B)での傾向であって、一般消費者向け(B to C)に関してはこの限りではありません。
一般消費者向けの商品やサービスを展開した時に、「ブランド名」「店舗名」を気にする人はいても、「会社名」まではなかなか気にされないものです。
前項で挙げた有名な合同会社の中に「合同会社だと知らなかった」という企業があれば、一般消費者としては普段利用している会社でも、その正式な会社名までは気にしていなかったということの裏付けになるでしょう。
こうした理由から、小売業やサービス業などのB to C事業は合同会社に向いているといえます。
2.小規模事業
大企業も合同会社を選択することは少なくないものの、本来は株式会社と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の大きな違いは事業展開の規模の大きさですから、合同会社はやはり小規模事業に向いているといえます。
個人事業主からの法人成り、家族経営、仲間内での起業など、とにかく規模が小さく、これから先の展開でも拡大路線を狙わないのであれば、合同会社が向いています。
想定される具体的な事業は多岐に渡りますが、個人での不動産投資や、少人数で短期間に革新的な事業を展開していくスタートアップ事業にも向いているといえるでしょう。
3.資金を持った人とノウハウを持った人が共同で始める事業
「資金提供できる人・企業」と「新商品・サービスのノウハウを持っている人・企業」とで共同で事業を始めるケースでは、株式会社の形態だと利益配分において不都合が生じてしまいます。
合同会社の形態であれば、出資者もノウハウ提供者も平等な立場で利益配分を考えることができるため選択されることが多いです。
合同会社の設立で悩みがあるときは税理士などに相談しよう
2006年の会社法改正で誕生して以来、合同会社は新設法人の中での存在感を年々増してきています。
元々小規模事業向けの形態であるにもかかわらず、その特徴を効果的に活かした事業運営を取り入れた大企業も増え、これからは株式会社と変わらずポピュラーな存在になっていくでしょう。
情勢の変化が激しい現代で企業の生き残り戦略を考えるとき、合同会社や株式会社の特徴を適切に捉え、どのスタイルを取り入れるかを決断するのはとても重要です。
もし合同会社の設立や運営に不安や疑問があるときは、ぜひベンチャーサポートの無料相談を活用してください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。