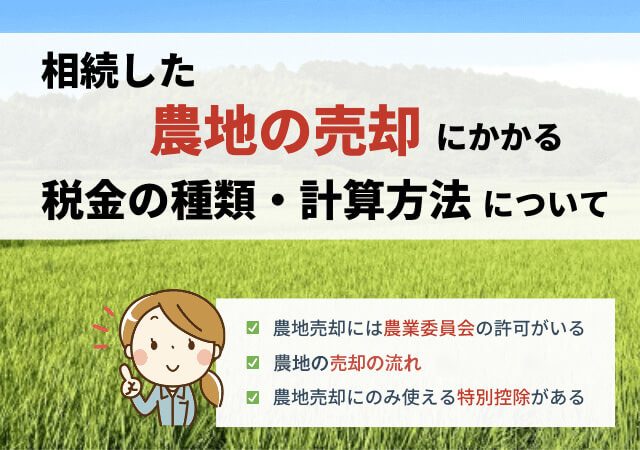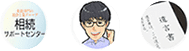この記事でわかること
- 相続した農地の売却でかかる税金の種類
- 相続した農地を売却するときの税金の計算方法
- 農地の売却に使える特別控除
親の遺産に農地がある場合、「農業を継ぎたくない」「遠方に住んでいるため農業の継続は難しい」などのお悩みを抱えているひとは少なくありません。
農業をしないにしても、農地は定期的に整備していないと、草木が生い茂ったり、害虫や害獣が発生したりするため、近隣の農家に迷惑をかけることに繋がります。
そこで考えられるのが農地売却ですが、不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
今回は農地の売却にかかる税金の種類や売却の流れをわかりやすく解説します。
農地を相続した方や、今後農地を相続する予定の方はぜひ参考にしてください。
目次
相続した農地の売却でかかる税金の種類
相続した農地を売却したときにかかる税金は、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税(以下、「譲渡所得税」はこの3つを指すこととします)・印紙税・登録免許税です。
印紙税と登録免許税は必ずかかりますが、譲渡所得税は譲渡益(農地を売った儲け)に対して課税されるため、利益が出たときだけ課税されます。
次に各税金について詳しく解説していきます。
特に譲渡所得税は高額になるケースもあるため、農地の売却を検討している方は計算方法をしっかり理解しましょう。
印紙税
印紙税は「課税文書」と呼ばれる文書類にかかる税金です。
農地の売却では、売買契約書が課税文書に該当します。税率は売買契約書に記載された契約金額(売却額)によって異なり、5,000万円以下の場合、以下のようになります。(2027年3月31日までの間に作成された文書は軽減税率が適用されます)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
課税文書の種類や印紙税額について詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表
引用元 国税庁
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
引用元 国税庁
登録免許税
登録免許税は新たに不動産や会社を登記簿への登録またはすでに登記簿に記載されている内容を変更するときにかかる税金です。
農地の売買にかかる登録免許税は「固定資産税評価額×税率(2%)」で計算することができます。(2026年3月31日までに登記した場合、登録免許税の税率の軽減措置により税率は1.5%)
なお、登録免許税は売主と買主どちらが負担してもよいのですが、買主が登録免許税を負担することが一般的です。
譲渡所得税
譲渡所得税は、土地や建物の売却で発生した譲渡益(利益)にかかる税金ですが、短期間の転売による土地の値上がりを抑制する観点から、土地や建物の所有期間によって税率が異なります。
- 所有期間5年以内の場合:39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
- 所有期間5年超の場合:20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
所有期間が5年を超えているかどうかで、税率が2倍近く変わるため、所有期間の判定方法をしっかり把握しておきましょう。
譲渡所得税の課税対象の所有期間は、取得日から数えるのではなく、取得した年の翌年1月1日が起算日となります。
そのため、たとえば2015年4月に取得した農地を2020年5月に売却した場合、所有期間は5年2カ月ではなく、4年9カ月とカウントしなければいけません。
相続した農地を売却するときの譲渡所得税の計算方法
農地の譲渡所得税は、以下の計算式を使って求めます。
譲渡所得税の計算式
取得費とは農地を取得するのにかかった費用のことで、購入代金の他、取得の際に負担した測量費用、購入時に納めた登録免許税、不動産取得税、印紙税などが挙げられます。ただし、事業所得などの必要経費として算入したものは取得費に含めることはできません。
そのため、相続した農地の譲渡所得税を計算する場合、被相続人が農地を取得したときの登録免許税などを必要経費に含めていたかどうかは事前に把握しておいた方がいいでしょう。
譲渡費用とは、農地を売るために支払った仲介手数料、契約書に貼付けした印紙税などが該当します。
譲渡所得税の計算例
では以下の条件で、所有期間が5年以下の場合と5年超の場合の譲渡所得税を計算し、税額を比較してみましょう。
- 譲渡価格:2,000万円
- 取得費:500万円
- 譲渡費用:100万円
長期譲渡所得(所有期間5年超)の譲渡所得税
短期譲渡所得(所有期間5年以下)の譲渡所得税
事例のようにその他の条件が同じでも、対象の不動産が短期譲渡所得と長期譲渡所得のどちらになるかで税額に約271万円の差が出てしまいます。いかに短期譲渡所得の税負担が大きいかがおわかり頂けたと思います。
なお、所有期間は先代(親や祖父母)の取得時期から起算されるため、相続した農地の売却では多くの場合、長期譲渡所得が適用されます。
農地の取得費がわからないときの計算例
農地は「先祖代々引き継いできたものであるため、いくらで買ったかわからない」というケースは多いです。
このように取得費がわからない場合、譲渡価格の5%を概算取得費として差し引くことができます。しかし、取得費がわかっている場合より、譲渡所得税が高くなってしまう傾向にあります。
- 譲渡価格:2,000万円
- 取得費:不明のため譲渡価格の5%(概算取得費:100万円)
- 譲渡費用:100万円
取得費が不明なときの譲渡所得税(長期譲渡所得)
譲渡価格の5%を取得費とする場合、土地の取得に際して支払った土地の埋立てや土盛り、地ならしをするための造成費用や土地の測量費などがわかっていても、概算取得費にこれらを加算することはできません。
そのため、取得価格はわからないが取得にかかった費用の一部がわかる場合は、概算取得費5%といずれか大きい方を取得費にすることができます。
相続した農地を売却するには農業委員会の許可が必要
農地は国策として保護されているため、農業委員会の許可がなければ売却できません。
農地のままであっても、宅地へ転用する場合でも、いずれにしても売却するときは農業委員会の許可が必要です。
無許可で売却した場合は、売却そのものが無効になる可能性が高いので注意してください。
農地を売却する場合の流れ
農地のまま売却する場合
①買い手を探す
農地を農地のまま購入できるのは農業従事者か新規農業参入者に限られます。また、売却にあたっては農業委員会の許可が必要です。
不動産会社に依頼して買い手を探してもらう、農業委員会にあっせんを依頼する、近隣の農家に声をかけるなどして買い手を探します。
②売買契約を締結する
買い手が見つかったら、売買契約を締結します。このときに、農業委員会の許可が下りなかった場合に備え、農業委員会の許可が下りなかった場合は契約が無効となる旨の条項を入れた契約書を作成しましょう。
③農業委員会に許可申請を行う
農業委員会への提出書類は、売却する農地を管轄する農業委員会によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
また、農業委員会の審査は、締め切りまでに受け付けた申請を月に一度まとめて審議するといったスケジュールで動いていることが多く、すぐに許可がもらえないこともあります。申請段階で、結果がいつ頃わかるか確認しておきましょう。
④所有権移転登記を行う
農業委員会の許可が下りたら、売買代金の受け渡しと所有権移転登記を行います。
農地以外に転用して売却する場合
農地以外に転用して売却する場合、そもそも転用可能な農地かどうかの確認が必要です。
たとえば、優良農地である甲種農地や第一種農地は原則、転用は認められませんが、第三種農地は原則、転用が認められ、第二種農地は条件を満たせば認められます。
①買い手を探す
農地以外に転用して売却する場合、不動産会社に依頼することになりますが、依頼する会社は地元の農地売買の経験がある会社を選びましょう。
農地の転用は通常の売買と異なる手続きがあるため、流れをわかっている不動産会社の方がスムーズに進められます。
②売買契約を締結する
買い手が見つかったら、売買契約を締結します。このときに、農業委員会の許可が下りなかった場合に備え、農業委員会の許可が下りなかった場合は契約が無効となる旨の条項を入れた契約書を作成しましょう。
③農業委員会に許可申請を行う
農地の転用は農地法第5条による許可申請書を提出しますが、売り手、買い手の共同申請となります。添付書類や詳細については事前に農業委員会に確認しておきましょう。
④所有権移転登記を行う
農業委員会の許可が下りたら、売買代金の受け渡しと所有権移転登記を行います。
農地の売却に使える特別控除がある
農地売却したときの譲渡所得には以下の特別控除もあります。
| 800万円の特別控除 | (1)勧告に係る協議、調停又はあっせんにより譲渡した場合 (租税特別措置法第34条の3第2項第1号、第65条の5第1項第1号) |
|---|---|
| (2)農地中間管理機構に譲渡した場合 (租税特別措置法第34条の3第2項第1号、第65条の5第1項第1号) |
|
| (3)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画により譲渡した場合 (租税特別措置法第34条の3第2項第2号、第65条の5第1項第2号) |
|
| 1,500万円の特別控除 | 農業経営基盤強化促進法に基づく買入協議により農地中間管理機構に買い入れられた場合 (租税特別措置法第34条の2第2項第25号、第65条の4第1項第25号) |
| 2,000万円の特別控除 | 農業経営基盤強化促進法の地域計画の特例に基づき農地中間管理機構に買い入れられた場合 (租税特別措置法第34条第2項第7号、第65条の3第1項第7号) |
いずれも細かな適用要件があり、控除を受けるための必要書類も多いため、農業委員会に詳細を問い合わせてみるとよいでしょう。
また、土地収用法に基づく農地の買取り(公共事業を目的とした買取り)であれば、5,000万円の特別控除を受けることもできます。
まとめ
相続した農地を売却するときは、買い手探しと農業委員会の許可がハードルになります。
しかし、耕作放棄をしても維持管理費や固定資産税はかかり続けるため、時間をかけてでも買い手を探した方がよいでしょう。
また、農業委員会の立場としても耕作放棄地の拡大は防ぎたいため、相談すれば買い手を見つけてくれるケースもあります。
譲渡益が発生した場合は、確定申告が必要となります。特別控除の適用の可否を含め、申告書の作成や必要書類の準備には手間と時間がかかります。忙しい方や作成に自信のない方は、税理士に相談してみることをおすすめします。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。