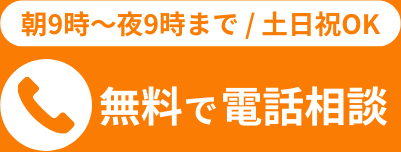記事の要約
- 相続税の基礎控除の改正内容
- 相続税の基礎控除の改正はいつからか
- 相続税の基礎控除の改正による影響
平成25年(2013年)度の税制改正において、現在でも影響が及ぶほどの相続税法に関する大きな変更が行われました。
中でも、平成27年(2015)年1月1日から施行された相続税の基礎控除額の引き下げは、施行前との比較で相続税申告・納税者の大幅な増加に繋がりました。
この記事では、平成25年度の税制改正における相続税の基礎控除の改正内容を解説します。改正理由や改正前後の違いも解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
相続税かかる人とかからない人の違いは?誰が払う?基礎控除の仕組みと税額シミュレーション
動画の要約相続税の基礎控除額ってご存知ですか? 実は、財産が一定額以下なら相続税の申告も納税も不要に!さらに、特例や控除を活用すれば、基礎控除額を超えていても納税がゼロになることも。詳しい計算方法や具体例は動画でチェック
平成25年度税制改正の相続税に関する改正点とは?
平成25年(2013年)度の税制改正で相続税法の一部が改正され、平成27年(2015)年1月1日から施行されました。改正された相続税法の主なポイントは、次の4点です。
基礎控除額の引き下げ
まず、遺産に係る「基礎控除額」の引き下げです。
改正前は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、改正後は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。
これにより、相続税の課税対象となる方が約2倍に増えました。
この「基礎控除額」の改正について、詳しくご説明いたします。
税率構造の変更
2つ目は、「税率構造」の変更です。
改正前の税率は、以下のとおりです。
左の金額は、各法定相続人の取得金額、右が税率です。
【改正前】
| 取得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円超~3,000万円 | 15% |
| 3,000万円超~5,000万円 | 20% |
| 5,000万円超~1憶円 | 30% |
| 1憶円超~3億円 | 40% |
| 3億円超 | 50% |
改正後の税率は、以下のとおりです。
【改正後】
| 取得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円超~3,000万円 | 15% |
| 3,000万円超~5,000万円 | 20% |
| 5,000万円超~1憶円 | 30% |
| 1憶円超~2億円 | 40% |
| 2億円超~3億円 | 45% |
| 3億円超~6億円 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
税額控除の改正
3つ目は、「税額控除」の改正です。
未成年者控除の控除額が、20歳(※現在は18歳。令和4年3月31日以前の相続または遺贈に関しては20歳)の1年につき「6万円」が、同じく20歳の1年につき「10万円」に引き上げられました。
また、障害者控除の控除額は、85歳までの1年につき「6万円(特別障害者12万円)」が、同じく85歳までの1年につき「10万円(特別障害者20万円)」に引き上げられました。
小規模住宅等の特例の改正
4つ目は、「小規模住宅等の特例」の改正です。
「小規模住宅等の特例」とは、被相続人(亡くなった方)または被相続人と生計を同じにしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供された住宅等がある場合に適用される制度です。
一定の要件において遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。
居住用の宅地等(特別居住用宅地等)の限度額が、改正前は「限度面積」が240㎡(減額割合80%)だったのが、改正後は「限度面積」が330㎡(減額割合80%)に拡大されました。
また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が、改正前は「特定居住用宅地等240㎡」、「特定事業用等宅地等400㎡」で「合計400㎡」だったのが、改正後は「特定居住用宅地等330㎡」、「特定事業用等宅地等400㎡」で「合計730㎡」に拡大されました。
相続税の基礎控除の改正内容

改正後の相続税の基礎控除は平成27年1月1日に施行されており、改正前の最低額は6,000万円でしたが、現在は3,600万円になっています。
相続税がかかるかどうかのハードルが2,400万円も引き下げられたため、相続税申告が必要になる家庭も増加することになりました。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続税の申告・納税が必要かどうかを切り分ける財産額による判断基準になっており、以下のように計算します。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除の最低額は3,600万円となり、相続財産が基礎控除額を超えない限り相続税はかかりません。
また、相続財産が基礎控除を超えている場合、相続財産全体ではなく基礎控除を超えた部分のみ課税されます。
改正前の相続税の基礎控除
平成26年12月31日までは、相続税の基礎控除を以下のように計算していました。
相続税の基礎控除:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
仮に法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合、基礎控除を計算すると以下のようになります。
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
改正前の基礎控除は高い水準になっていたため、一般的なサラリーマン家庭で相続税が発生するケースはほとんどなく、相続税対策も必要ありませんでした。
しかし、平成27年1月以降は基礎控除の水準が引き下げられており、資産家や富裕層とはいえない家庭にも相続税がかかるようになっています。
改正後の相続税の基礎控除
平成27年1月1日に施行された現在の相続税の基礎控除は、以下のように計算します。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
3,000万円の部分を定額控除、カッコ内を比例控除といい、どちらも大きく引き下げられました。
仮に法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合、基礎控除は以下のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
法定相続人の数は改正前の例と同じですが、控除額は3,200万円ほど下がっています。
共働きの夫婦が定年退職まで勤めた場合、貯蓄と退職金にマイホームの資産価値も合わせると、相続財産が4,800万円を超えるケースはかなり多いでしょう。
相続税の基礎控除が改正された理由
相続税の基礎控除は過去にも何度か改正されていますが、平成27年改正には以下のような理由がありました。
- 税収確保
- 地価下落への対応
- 社会保障費の確保
相続税の納税額は平成バブル期にピークとなり、バブル崩壊後は20年以上にわたって減収が続いたため、税収確保が急務とされていました。
当時は急激な地価上昇もありましたが、バブル崩壊とともに下落し、相続税を納める土地オーナーも減少しています。
さらに高齢化社会が到来したため、労働人口の減少で所得税などの税収が下がり、社会保障費の確保も難しくなりました。
結果的に今後は「多死社会」が到来するため、税収を見込んで相続税法を改正したという背景があります。
相続税の基礎控除が改正されたことによる影響
相続税の基礎控除が改正されたことにより、相続税とは無縁だった家庭に以下のような影響が出ています。
また、相続税率も一部改正されたため、もともと相続税がかかる家庭にも影響するケースがあります。
基礎控除は今後も改正される可能性があるため、平成27年以降にどのような影響が出ているか参考にしてください。
相続税の申告・納税が必要な人が増えた
相続税の基礎控除の改正により、改正前後の課税割合は以下のようになっています。
なお、課税割合とは、各年の死亡者数に対する「相続税申告が必要な被相続人の数」の割合です。
- 平成26年分:4.4%
- 平成27年分:8.0%
改正後は前年の2倍近くまで課税割合が上がっているため、相続税の申告・納税を必要とする家庭も倍増したことになります。
ただし、国民の総資産が倍増したわけではなく、あくまでも基礎控除の引き下げが原因です。
また、コロナ禍の影響によって申告期限を延長するなど、一時的に申告数が減少した年もありましたが、令和6年の課税割合は10.4%になっています。
相続税の納税額が増えた
平成27年の税制改正は基礎控除の引き下げだったため、相続税とは無縁だった人にも課税されるようになり、もともと相続税がかかる人は納税額が増えています。
税制改正の前後をみると、相続税の納税額(国内総額)は以下のように上昇しています。
- 平成26年分:1兆3,908億円
- 平成27年分:1兆8,116億円(前年比130.3%)
仮に6,000万円を法定相続人1人が相続する場合、改正前の基礎控除を差し引くと非課税になりますが、改正後は2,400万円の課税額になります。
また、一部の相続税率も改正されており、課税額が2億円を超えた場合、税率が5%上昇するケースもあるため注意しなければなりません。
改正前と改正後の違いを事例とともに紹介
ここからは、相続税の計算方法を事例を使いながら、改正前と改正後に分けてご紹介します。
仮に夫が預貯金4,000万円、土地5,000万円、建物3,000万円、合計1億2,000万円を残して亡くなったとしましょう。法定相続人は、妻(配偶者)子ども2人(長男、長女)の3人だとします。
改正前の基礎控除に基づいた相続税の計算例
最初に、改正前の「基礎控除額」で相続税を計算します。改正前の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」で、「5,000万円+(1,000万円×3=8,000万円)」となります。
したがって、基礎控除後の課税価格は、「1億2,000万円-8,000万円=4,000万円」です。
次に、相続人の取得分を「法定相続分」に従って、算定します。
【改正前】相続人の取得分
- 妻…4,000万円×1/2=2,000万円
- 長男…4,000万円×1/4=1,000万円
- 長女…4,000万円×1/4=1,000万円
前述した値をもとに法定相続人のそれぞれの相続税を計算し、合計します。
【改正前】相続税額
- 妻…2,000万円×15%−50万円=250万円
- 長男…1,000万円×10%=100万円
- 長女…1,000万円×10%=100万円
- 250万円+100万円+100万円=450万円
合計すると相続人の納付額は、次のようになります。
【改正前】納付額
- 妻…450万円×1/2=225万円
- 長男…450万円×1/4=112.5万円
- 長女…450万円×1/4=112.5万円
紹介した事例の家族が納めることになる改正前の相続税額は、配偶者控除によって妻の相続税は非課税となるため、「112.5万円×2=225万円」です。
改正後の基礎控除に基づいた相続税の計算例
次に、改正後の「基礎控除額」で相続税を計算します。
改正後の相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のため、今回の事例では「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となります。
したがって、改正後の基礎控除後の課税価格は、「1億2,000万円-4,800万円=7,200万円」です。
次に、相続人の取得分を「法定相続分」に従い算定します。
【改正後】相続人の取得分
- 妻…7,200万円×1/2=3,600万円
- 長男…7,200万円×1/4=1,800万円
- 長女…7,200万円×1/4=1,800万円
前述した値をもとに法定相続人のそれぞれの相続税を計算し、合計します。
【改正後】相続税額
- 妻…3,600万円×20%−200万円=520万円
- 長男…1,800万円×15%−50万円=220万円
- 長女…1,800万円×15%−50万円=220万円
- 520万円+220万円+220万円=960万円
合計すると相続人それぞれの納付額は、次のようになります。
【改正後】納付額
- 妻…960万円×1/2=480万円
- 長男…960万円×1/4=240万円
- 長女…960万円×1/4=240万円
配偶者控除によって妻の相続税は非課税となるため、改正後の相続税は「240万円×2=480万円)」になります。
改正前の相続税が225万円である点を踏まえると、相続税法の改正によって、この事例の家族は2倍以上の相続税を納めることになります。
参考:相続税改正|国税庁
基礎控除額は改正前後で変化大!専門家への相談もおすすめ
相続税法の改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられ、税率構造も変更されました。改正前は相続税の納税や申告が必要なかった人でも、改正後は納税が必要になる人が増えています。
また相続税の負担も大きくなったため、控除の利用や生前贈与などの節税対策がこれまで以上に重要です。自分たちに合った節税方法がわからない場合は、相続税に詳しい専門家に相談してみましょう。
VSG相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。
初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。