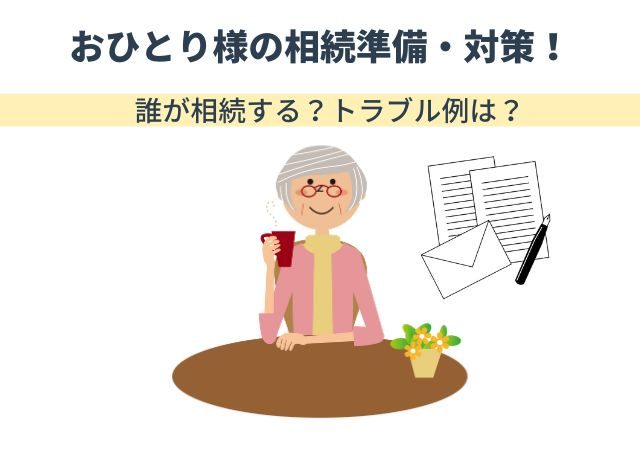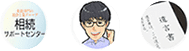この記事でわかること
- おひとり様の遺産は誰が相続するのか
- おひとり様の相続で起こりやすいトラブル
- おひとり様がしておくべき相続準備や対策
近年、未婚率の上昇や出生率の低下から、同居する家族がいない「おひとり様」の世帯が増えています。
子どものいない夫婦で配偶者を亡くし、1人世帯になるという方もいるでしょう。
おひとり様の中には、「もし自分が死んだら遺産が誰の手に渡るのか」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、おひとり様の遺産相続について解説します。
おひとり様の遺産を承継する相手や相続時に起こり得るトラブル例、生前にできる相続準備や対策など詳しく解説するので参考にしてください。
目次
おひとり様の遺産は誰が相続する?
亡くなった方の遺産を相続できるのは、法定相続人と遺言書で指定した人です。
ここでは、おひとり様の遺産を相続できる人について解説します。
法定相続人
おひとり様に親族がおり、遺言書がない場合、遺産は法定相続人に引き継がれます。
法定相続人とは、法律上、亡くなった人の遺産を相続する権利がある人のことをいいます。
亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は、①子ども(直系卑属)、②父母(直系尊属)、③兄弟姉妹の順で法定相続人となります。
配偶者と子どものいないおひとり様の場合、親が健在であれば遺産はすべて親が相続し、両親ともに健在であれば両親の相続分は2分の1ずつです。
両親が亡くなっているときは兄弟姉妹が法定相続人となり、仮に兄弟が3人いれば、3分の1ずつ遺産を相続します。
兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、兄弟姉妹の子どもである甥っ子または姪っ子が代襲相続人として、おひとり様の遺産を相続することになります。
遺言書で指定した人
おひとり様が遺言書で財産を渡す人を指定していたときは、指定された人が財産を取得することになります。
「あの人にとてもお世話になったから、自分の財産を譲りたい」などの意思がある場合、遺言書を作成すると、自分の希望する相手に遺産を受け渡すことができます。
ただし遺言書を残す際は、「遺留分」に注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる相続分で、法律上、ご両親(直系尊属)のみが相続人になる場合は相続財産の3分の1が遺留分です。
配偶者や子どもが相続人になる場合は相続財産の2分の1です。
たとえば、おひとり様のご両親が健在のうちに、財産をすべて血縁関係のないAさんに相続するという内容の遺言書を残して亡くなったとしても、ご両親が遺留分を主張すれば、Aさんはすべての財産を受け継ぐことができません。
そうなる状況が事前に想定できる場合は、遺言書を作成する際に遺留分を事前に考慮しておき、それ以上の権利主張の余地をなくしておくことが有効と言えます。
おひとり様の相続で起きやすいトラブル
一般的な相続では、相続財産の取り分をめぐって相続人間でトラブルになるケースがあります。
一方、おひとり様の相続では、一般的な相続とは違った問題が生じる可能性があります。
財産状況の把握が難しいケース
1つ目に、財産状況の把握が難しいケースです。
相続が発生したとき、まずは亡くなった人の財産状況を調べます。
しかし、おひとり様の場合、生前に財産状況を誰にも伝えておらず、財産状況を把握するのが難しいことがあります。
特に、最近はネット銀行の利用が増えたことから、亡くなった人の預貯金や証券口座などを見逃しやすい傾向にあります。
また、ログインIDやパスワードを知らされていない場合は、閲覧するまでに時間がかかってしまうでしょう。
おひとり様の場合、財産状況を誰にも共有していないことがあり、相続財産の把握が難航する可能性があります。
相続人の把握が難しいケース
2つ目は、相続人間の関係が希薄で、相続人の把握が難しいケースです。
おひとり様で両親も亡くなっている場合、法定相続人は兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹もすでに亡くなっているときは、兄弟姉妹の子ども(甥または姪)に代襲相続されます。
しかし、このようなケースでは、相続人間の関係が希薄である、あるいはお互い面識がないということも少なくありません。
その結果、遺産分割協議が行えず、遺産がそのまま放置されてしまう可能性があります。
場合によっては、甥や姪のところに遺産である不動産の税金や、亡くなった人の債務の請求がいき、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
おひとり様がしておきたい相続準備・対策

おひとり様の場合、将来のトラブルを避けるために事前に対策を行うことが重要です。
具体的な相続準備や対策方法として、以下の3つが挙げられます。
- 遺言書を作成しておく
- 所有財産目録を作成しておく
- 任意後見契約を締結する
ここからはそれぞれの方法について詳しく解説します。
遺言書を作成しておく
「法定相続人の他に遺産を渡したい人がいる」「法定相続人がいない」という場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
自筆遺言証書は、遺言者本人が遺言書の全文を自書し自分で保管する方法で、公正証書遺言は公証人に依頼して遺言書を作成してもらい、公証役場で保管してもらう方法です。
また、遺言書の内容を秘密にしながらも公証人に遺言書の存在を証明してもらいたい場合は、秘密証書遺言の方法を選択できます。
自筆証書遺言は、自由に作成・内容の修正ができますが、形式上の不備があると無効となる・紛失するリスクがあります。
確実かつ安全に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
法定相続人が1人もいない場合、原則としておひとり様の遺産は国庫に帰属し、国のものとなります。
財産を渡したい相手がいれば、先述した遺留分に注意しながら遺言書を作成しておくとよいでしょう。
所有財産目録を作成しておく
おひとり様の場合、財産状況の把握が難しいことがあります。
そのため、自分の財産をすぐに把握してもらえるよう財産目録を作成しておくことをおすすめします。
また、ネット銀行を利用している場合は、銀行名や支店名、口座番号やID、パスワードなども明記しておくとよいでしょう。
任意後見契約を締結する
任意後見とは、判断能力がしっかりしているうちに、本人自らの意思で後見人を選任しておく方法です。
任意後見契約を締結しておくことで、将来自分が認知症などで判断能力が落ちたときに、任意後見人に財産管理を行ってもらえます。
適切な財産管理を行ってもらうことで、死後の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
なお、任意後見人には信頼できる人を選任する必要があり、該当する人がいない場合は弁護士などの専門家に依頼します。
まとめ
おひとり様の場合、法定相続人や財産状況の把握が難しくなるケースがあります。
万が一のときに、スムーズに相続手続きを進められるよう、所有財産を整理したものを作成し、必要に応じて遺言書や任意後見契約などの相続準備を行っておくことが重要です。
何から着手すればよいのかわからない、手続きに不安があるという場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。