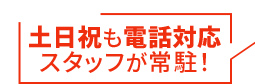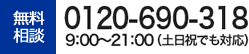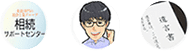相続税対策として、親から子どもに生前贈与することがあります。
しかし、預金口座の管理方法や両者の認識、使途や支払いのタイミングなどにより、
贈与税がかからない場合・贈与税がかかる場合・贈与と認められず親の財産とみなされる場合など
税制上の扱いが意図通りにならないケースが多々見受けられます。
贈与税がかかってしまうのはどのようなケースか、ケース別に詳しく解説します。
目次
親の口座から子どもの口座へ資金を移したときに贈与税がかかるケース
親から子ども名義の口座に送金した場合は、基本的には生前贈与として贈与税の対象になります。
どんなケースが贈与税の対象となるのでしょうか。
贈与税がかかる5つのケースについて解説します。
年間110万円を超える場合
1年間に移動した資金の総額が110万円を超えた場合、贈与税の対象になります。
たとえば、子どもの口座に500万円入金すると、贈与税額は下記の計算式になります。
500万円―110万円(基礎控除)×20%(税率)―25万円(控除額)=53万円
お年玉や児童手当を貯めていて、一度に110万円以上子どもに渡した場合も贈与税の対象になります。
1回の入金が110万円以下であっても毎年入金していた場合などは、税務署に暦年贈与と認められない場合があります。
暦年贈与と認められない場合は、年間110万円以下でも贈与税がかかる可能性があります。
毎年贈与契約書などを作成しておくことによって、暦年贈与について双方合意があったと証明できれば、年毎に贈与されたと見なされ、非課税になる可能性があります。
贈与契約は、口頭でも成立しますが、税務署などの第三者に対しては証明できないため、贈与契約書などを作成して、証明できるようにしておきます。
教育資金として1,500万円超を入金する場合
教育資金として1,500万円超を贈与する場合、超えた部分の金額は贈与税の対象になります。
一定の適用要件を満たした贈与については1,500万円まで非課税となるこの制度は2026年3月末まで適用される制度です。
30歳未満の子どもまたは孫に適用されます。
教育資金とは、以下のものが対象になります。
- 学校の入学費や授業料
- 教材代
- 文具費用
- 通学の交通費
- 塾や習い事などの月謝
この制度では、教育資金を受け取った子どもや孫が30歳までに教育資金として使い切る必要があります。
使い切れなかった残額は贈与として課税されるため、注意が必要です。
非課税措置を受けるためには、金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。
教育資金として使用したという証明も必要になるため、領収書等の保管も必要です。
生活費以外の仕送りをする場合
生活費以外の目的で仕送りとして入金していた場合、贈与税の対象になります。
いっぽう、遠方の大学に行っている子どもに仕送りをしたり、生活困窮のために生活費を援助したりするケースは基本的には贈与税の対象とはなりません。
しかし、生活費の援助として仕送りをしていたとしても、それを子どもが貯金や投資、遊興費など生活費以外のために使用していた場合は、生活費以外の仕送り=贈与と見なされる可能性があります。
仕送りではなく、贈与と見なされた場合は、上記と同じように年間110万円を超えると贈与税がかかることになります。
住宅購入資金として500万円超を入金する場合
2026年12月末までの「住宅取得等資金の非課税の特例」で、親や祖父母(直系尊属)から住宅取得資金として500万円を超えて入金された場合、超えた部分の金額には贈与税がかかります。
なお、省エネ等住宅に該当する住宅購入目的であれば上記500万円から1,000万円まで非課税の枠が広がります。
この制度を利用するためには、住宅資金として利用された証明が必要になります。住宅購入に関する資料は保管しておきます。
贈与税の申告も必要です。
子どもの結婚・子育て資金として1,000万円超を入金する場合
2025年3月末まで適用される制度「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」で、18歳以上50歳未満の子どもや孫に対して、結婚や子育て資金として1,000万円超を入金する場合に贈与税がかかります。
1,000万円以下の非課税とされる部分についても、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づいて預け入れする等、一定の要件があるため注意が必要です。
親の口座から子どもの口座へ資金を移すときに贈与税をかからなくする方法
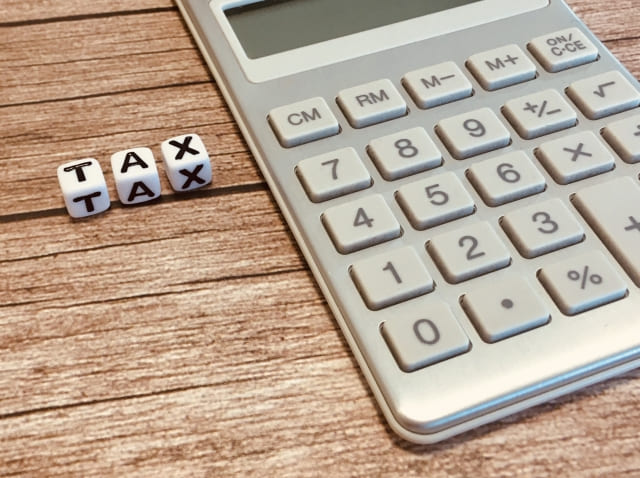
様々な控除を利用すると、贈与税をかからなくすることができます。
上述した暦年贈与、教育資金贈与、住宅取得資金贈与、結婚・子育て資金贈与などの要件を満たした上で生前贈与すれば、一定金額以下については贈与税がかからずに子どもに資金を移動させることができます。
その前提として、贈与が成立しているということが重要なポイントです。生前贈与が成立するために抑えておくべき重要な2つの要素について解説します。
預金を子ども自身に管理させ、贈与であることを子どもに認識させる
子ども名義の口座に入金しておけば生前贈与が成立したと思われがちですが、通帳印鑑を親が持って管理していたら、親の財産とみなされることがあります。
誰の財産であるか?は名義だけではなく、実質が問われるということですね。
生前贈与を成立するのは、贈与があったことを子ども自身が認識していて、かつその口座を子ども自身が管理・運用している場合となります。
贈与契約書を作成する
当事者間で贈与だと認識していても、税務署から見ればそれが本当に贈与だったのか、何の目的の贈与だったのかがわかりません。
贈与契約書を作成しておけば、控除の際に、誰から誰への贈与だったのか、何の目的の贈与だったのかを証明することができます。
制度利用のためにも、贈与契約書を作成することが大切です。
まとめ
親の預金を子ども名義の預金口座への移した場合、金額や目的、手続きなどによって、贈与税がかかったり、かからなかったりするケースがあります。
教育資金や住宅取得資金、結婚・子育て資金は「贈与税非課税の制度」として、金融機関を経由することで多額の金銭を無税で子どもに渡すことができます。
それぞれの制度にどういう要件があるのか、どういう渡し方をすると税務署に目をつけられるのか、すべてを自分で把握するのはとても大変で複雑です。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。