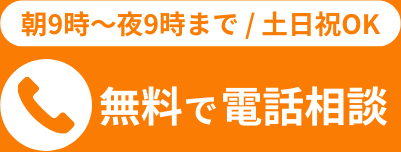この記事でわかること
- 相続財産の総額が1,000万円なら相続税はかからない
- 自分が相続する財産が1,000万円なら、遺産総額を調べる必要がある
- 相続税の計算方法と減額できるポイント
親や親戚から1,000万円を相続した場合、相続税はいくらかかるのでしょうか?
結論からいうと、相続財産の総額が1,000万円の場合、相続税は一切かかりません。そのため、税務署に相続税の申告をする必要もありません。
ただし、自分が相続する財産が1,000万円で、他の親族もそれぞれ財産を相続するような場合は、遺産総額を調べなければ相続税がかかるかどうかは判断できません。
相続税の計算方法と、間違いやすい注意点について解説します。
目次
相続財産が1,000万円なら相続税はかからない
相続財産の総額が1,000万円だった場合、相続税はかからず、税務署への手続きは一切必要ありません。
相続税は、国が定める基礎控除という金額を超えた部分の相続財産にのみ課税されます。
相続税の基礎控除額は、
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
で計算される金額です。
相続発生により残された家族の生活に配慮して、一定の財産額以下の家庭には相続税がかからないしくみになっています。
令和6年、全国で約160万人の方が亡くなりましたが、この基礎控除額を超えて相続税の対象となった方は約16万6,000人でした。
つまり、全国で上位約10%に入る財産を持って亡くなった方のご家族だけが、相続税を支払うこととなります。
ここでの注意点は2点あります。
1つは、相続税の基礎控除額と比較する財産額は、自分一人が相続する財産の額ではなく、「亡くなった方の遺産総額」であるということです。
全員が相続する財産額の合計を、基礎控除額と比較してください。
もう1つは、遺産総額にどういった財産を含めて計算するか?という点です。現預金の他、株式や不動産、保険金や家財等も含めて計算することに注意してください。
遺産1,000万円という計算自体が間違っているケースに注意
- 配偶者や子どもの名義の口座にお金を貯めていた
- 亡くなる前7年以内に配偶者や子どもに預金移動(贈与)していた
- 100万円以上のタンス預金がある
- 多額の死亡保険金を受け取った
これらのケースは、「相続財産」に当てはまらないと考えて相続税の計算から除外してしまっていることが多いですが、相続税法のルールではこれらも遺産に含めて計算しなければなりません。
専門的で複雑な計算になるため、無料相談をうまく活用して自分一人の計算結果で判断しないようにしましょう。
自分が相続する財産が1,000万円なら遺産総額を知る必要あり
「1,000万円の遺産にかかる相続税はいくらですか?」という質問を受ける場合、だいたいは「自分が相続する財産が1,000万円」で他の相続人が受け取る財産については情報がないことが多いです。
この場合、「相続税はいくらかかるかわからない」というのが正しい答えになります。
さきほど相続税の基礎控除額の計算で説明したとおり、相続税がかかるかどうかは「遺産総額」で決まります。
自分一人が相続する財産の額ではなく、「亡くなった方の遺産総額」を知らなければ、相続税がかかるかどうか、税務署への申告・納税が必要かどうかは判断できません。
たとえば、亡くなった方の遺産総額が2,000万円で、そのうち半分の1,000万円を相続する場合は、
2,000万円 ≦ 基礎控除額4,200万円
となるため、相続税はかかりません。
仮に、亡くなった方の遺産総額が1億円で、相続人は自分を含めた兄妹5人。遺言書により自分が相続する財産は1,000万円の預金のみという場合、
1億円 > 基礎控除額6,000万円
となり、同じ1,000万円の相続でもこの場合は40万円※の相続税がかかるため、納税後、手元に残るのは960万円となります。
- ※
-
1億円-基礎控除額6,000万円=4,000万円
4,000万円÷5人=800万円
800万円×相続税率10%=80万円
80万円×5人=相続税額400万円
400万円×自分が相続する財産額1,000万円÷遺産総額1億円=40万円
相続財産の対象になるもの・ならないもの
相続財産の総額が1,000万円であれば、相続税はかからないことがわかりました。
しかし、もうひとつ注意しなければならないのは、相続財産の総額にどんな財産が含まれるか?ということです。
間違いやすいものを挙げると、預金引き出し、生前贈与、保険金なども相続財産に含めて計算しなければなりません。
不動産のように相続財産には当然含まれるものの、金額算定が難しい財産も存在するので注意が必要です。
相続財産の対象になるもの
被相続人が保有していた財産のうち、金銭的価値のあるものはほとんどが相続財産になると覚えてください。
預貯金以外の財産として相続財産に含まれる代表例として、土地や建物などの不動産が挙げられます。
自身で利用しているものだけでなく、人に貸している土地や建物も相続財産に含まれます。
また、土地を借りて使用している場合の借地権なども、相続財産の対象に含めなければなりません。
このほか、有価証券や車、美術品や骨董品などの財産も、すべて相続財産となります。
いずれも、基本的には相続発生時の時価が相続税評価額となります。
さらに、被相続人が亡くなったことに起因して相続人が生命保険金を受け取る場合、その保険金は相続財産の対象となります。(ただし、500万円に法定相続人の数を乗じた金額の非課税枠があるため、それを除いた残額が相続財産となります。)
預貯金などの目に見えてわかりやすい財産だけでなく、様々な財産が相続財産となります。
これらのすべての財産の所在を確認した上で、相続税の計算を行う必要があるのです。
相続財産の対象にならないもの
相続財産の対象とならないものは、金銭的な価値が認められないものや、社会通念上、相続税をかけるべきでない一部の財産に限定されます。
具体的には、墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚といったものは、相続財産に含まれません。
また、相続人が受け取った生命保険金については、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるとご紹介しました。
この非課税枠内の生命保険金も、相続財産に含まれない財産と考えることができます。
相続税の税率・計算方法
相続税の対象となる相続財産にどのようなものが含まれるかわかったら、実際に相続税の計算を行うことができます。
ここでは、相続税の計算方法を流れに沿ってご紹介します。
相続財産の合計額を計算する
相続財産の対象となる財産をすべて洗い出したら、その相続税評価額を計算し合計額を求めます。
預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券、車、骨董品など、被相続人が保有する財産のほとんどが相続財産となります。
その評価方法は財産の種類により異なるため、それぞれ確認しながら評価額を計算しましょう。
また、死亡により受け取った生命保険金も相続財産になります。
さらに、相続時点では相続人の財産でも、相続発生前7年以内に被相続人から贈与された財産は相続財産に含まれます。
過去に被相続人から贈与されたものがないか、確認しなければなりません。
なお、被相続人が債務を抱えたまま亡くなった場合には、その債務はマイナスの相続財産となります。
借入金や未払金などの支払いが残っている場合には、その金額を相続財産から差し引く計算を行わなければなりません。
また、葬儀費用として支払った金額も相続財産の額から差し引く計算を行います。
例えばプラスの相続財産の金額が1億5,000万円、借入金が600万円、葬儀費用が200万円の場合、正味の相続財産は以下のようになります。
計算例
1億5,000万円 - 600万円 - 200万円 = 1億4,200万円
基礎控除の金額を求める
相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
法定相続人の人数が増えるほど、基礎控除の金額は大きくなります。
養子がいる場合、代襲相続となった場合など、法定相続人の数を間違えないように注意しましょう。
法定相続人が配偶者と子ども1人の計2人の場合、基礎控除額は以下のようになります。
計算例
3,000万円 +(600万円×2人)= 4,200万円
課税対象となる金額を計算する
相続財産の金額から基礎控除を差し引いた後の金額が、実際に課税対象となる金額です。
この段階で相続財産の額より基礎控除の額の方が大きくなった場合、相続税は発生しません。
相続税が発生しないだけでなく、相続税の申告もする必要がなくなります。
一方、相続財産の方が基礎控除額より大きい場合は、相続財産の額-基礎控除額の計算を行います。
この金額が、相続税の課税対象となる金額です。
相続財産が1億4,200万円、基礎控除額が4,200万円の場合、課税対象となる金額は以下のとおりです。
計算例
1億4,200万円 - 4,200万円 = 1億円
相続税の総額を求める
課税対象となる金額を求めたら、その課税対象金額を法定相続分に分割します。
先ほどの事例で、1億円の課税対象となる金額を配偶者と子ども1人で分割すると、それぞれ5,000万円ずつとなります。
実際に相続する財産の額とは無関係に、ここでは法定相続分という割合を機械的に使用します。
次に、相続税の速算表を使って、相続税の計算を行います。
| 法定相続分で分割した金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
分割後の金額が5,000万円の場合、5,000万円×20%-200万円=800万円となります。
相続人ごとに相続税を計算したら、その合計額が相続人全員で負担すべき相続税額となります。
今回は5,000万円の法定相続人が2人ですから、800万円+800万円=1,600万円が相続税の総額になります。
個別の納税額を計算する
相続税の総額を求めたら、その金額を実際に相続した遺産の金額の割合に応じて按分します。
この事例で、子どもが1,000万円、残り1億3,200万円を配偶者が相続した場合、それぞれの納税額は以下のようになります。
計算例
| 配偶者 | 1,600万円 × | 1億3,200万円 | = 1,487万円 |
| 1億4,200万円 | |||
| 1,487万円 - 1,487万円(配偶者控除) = 0円 | |||
| 子ども | 1,600万円 × | 1,000万円 | = 113万円 |
| 1億4,200万円 |
相続税の節税に使える控除・特例
個別の相続税の納税額が決まっても、その後に控除が適用できることで、相続税の節税ができる場合があります。
相続人の状況によって、控除の適用ができるかどうかが決まるため、その要件を確認しておきましょう。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した相続財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方の金額まで相続税がかからない制度です。
配偶者は被相続人と同一生計にあり、亡くなった後も相続財産で相続後の生活を維持していくケースが多くなります。
そこで、配偶者が相続した財産から多額の相続税が発生しないようになっているのです。
ただし、配偶者が相続した財産の金額が確定しなければ適用できないため、遺産分割協議書が作成されていなければ適用できません。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その相続人が成人になるまでの年数×10万円の相続税が減額される制度です。
未成年者は被相続人の扶養家族となっている場合が多く、相続発生後も相続した財産で生活を怒らなければなりません。
しかし、多くの財産を相続すればその分、相続税の負担も大きくなってしまいます。
そこで、未成年の相続人が相続した財産について、一定の金額を減額してくれるのです。
障害者控除
障害者である相続人がいる場合、その人について発生する相続税から、85歳になるまでの年数×10万円が控除されます。
障害の程度が重い特別障害者については、1年あたりの控除額が20万円に増額されます。
残された家族の生活保障という意味から、相続人のなかに障害者が存在するご家庭はとくに手厚く保護されなければいけません。
そこで、その障害者の年齢に応じて金額が計算される、障害者控除という制度が設けられています。
相続で知っておきたいこと
相続が発生したら、相続の意思決定や支払期限が民法で決まっているため、早々に手続きを進める必要があります。
正しく相続するために、知っておきたい内容は大きく以下の3つです。
- 相続税の申告について
- 法定相続人の確定
- 相続放棄について
それぞれの内容について詳細を解説します。
相続税の申告について
遺産相続がある場合、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告・支払を済ませなければなりません。
万が一期限を過ぎた場合は、収めるべき相続税に加えて延滞税のなどペナルティがあります。
延滞税の割合は、原則としてほかの国税と同様で以下のパターンで計算されます。
- 期限の翌日から2カ月を経過する日まで:「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
- 期限の翌日から2カ月経過以降:「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
なお、控除により相続税が発生しなければ申告は不要ですが、特例を使用し相続税がかからない場合は、申告が必要のため忘れず対応しましょう。
法定相続人の確定
相続できる人の範囲と相続人の順位を確定させましょう。
人数が確定しなければ、正しい相続税を計算することはできません。
相続人を確定させるには、被相続人の家族構成から相続順位を明らかにし、相続の意思を伺う必要があります。
民法で相続人の順位は、以下の通り定められています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位 :直系卑属(子または孫)
- 第二順位 :直径尊属(親または祖父母)
- 第三順位 :兄弟または姉妹、甥、姪
仮に被相続人に「配偶者、子ども2人、父母、姉」がいた場合、法定相続人は配偶者と第1順位の子ども2人の計3人で遺産を相続します。
相続放棄について
相続財産は必ずしもプラスの資産だけではありません。
借金のようなマイナス資産の方が大きい場合も借金を相続することになるため、相続放棄をすると借金の相続もなくなります。
相続放棄は、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に選択しなければいけません。
一般的にはマイナス資産が大きい場合に相続放棄を選択しますが、相続トラブルに巻き込まれたくない場合でも自身の判断で相続放棄を選べます。
正しく申告しないと税務調査のリスクも
相続税の申告は、家族間での預金移動や不動産の評価が複雑なため、他の税金に比べて申告後の税務調査で追徴課税される割合が高いです。
国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、令和6事務年度に実施された相続税の実地調査は9,512件で、そのうち7,826件(82.3%)は申告に誤りがあり追徴課税されたと公表されています。1件あたりの申告漏れ課税価格の平均は3,093万円と高額なことも驚きです。
税務調査で指摘されると、本来納めるべきだった相続税に加えて、過少申告加算税と延滞税という追加の金銭的なペナルティが生じます。
ありがちなミスを犯して、本来払う必要のないお金をことにならないよう、確実な計算と手続きを行いましょう。