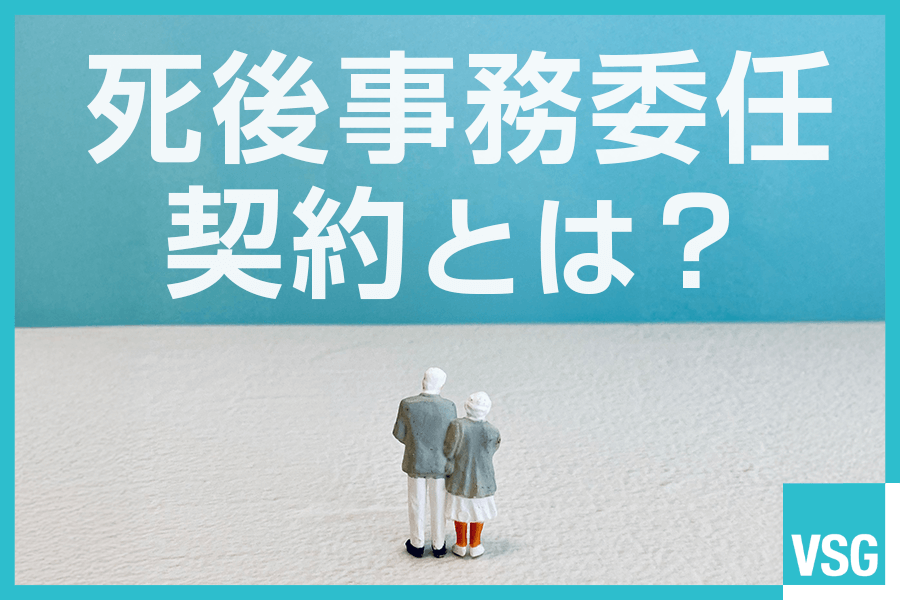この記事でわかること
- 死後事務委任契約がどのような制度か
- 遺言や成年後見との役割の違い
- 契約や手続きにかかる費用の相場
- 依頼できる専門家の種類と選び方のポイント
- 相談から契約完了までの具体的な流れ
「身寄りがなく、自分のもしもの時、一体誰が手続きをしてくれるのだろう…」
「親戚はいるけれど、遠方に住んでいるし、面倒なことで迷惑はかけたくない…」
自身の将来について考えたとき、そのような漠然とした、しかし拭い去れない不安を感じてはいませんか?
その不安を解消するための具体的な備えが、「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
この契約を生前に結んでおくことで、葬儀や埋葬、遺品整理といった、亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、信頼できる専門家に託すことができます。
この記事では、死後事務委任契約とは何か、メリット・注意点、費用の相場、そして「誰に依頼できるのか」という専門家の選び方まで、分かりやすく解説します。
目次
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった後のさまざまな手続きを、生前のうちに信頼できる第三者に依頼しておく契約」です。
少子高齢社会の現代では、「おひとりさま」で頼れる身寄りがいなかったり、親族はいても高齢だったり遠方に住んでいたりするケースが増え、死後に誰にも迷惑をかけたくないと考える人が多くなっています。
そうした背景から、葬儀や埋葬、家財道具の片付けといった「もしも」のときの手続きを、元気なうちに専門家などへ正式にお願いしておける制度として、この「死後事務委任契約」が注目を集めています。
契約は、親族や知人のほか、弁護士や司法書士・行政書士などの専門家、あるいはNPO法人などのサービス提供団体と締結することができます。
遺された家族の負担を減らしたい人はもちろん、自分の望む形で最期を迎えたいと考える人にとっても、将来の不安を解消できる心強い制度です。
【一覧表】死後事務委任契約で頼めること・できないこと
具体的にどのようなことを依頼できるのか、主な内容を以下の表にまとめました。
| 頼めることの例 | 内容 |
|---|---|
| ①行政手続き | 死亡届や国民保険資格喪失届※、年金受給権者死亡届の提出 介護保険資格喪失届の提出や、介護被保険者証の返却
|
| ②葬儀・埋葬 | 遺体の引き取り、葬儀や火葬・納骨に関する手続き |
| ③支払い関係 | 医療費や入院費、施設利用料などの未払金清算 |
| ④遺品整理・デジタル遺品整理 | 自宅の片付け、家財道具や身の回り品の整理・処分。パソコンやスマートフォンのデータ整理、SNSアカウントの閉鎖 |
| ⑤各種解約手続き | 電気・ガス・水道、携帯電話、インターネットなどの解約、住居の退去手続き |
| ⑥関係者への連絡、その他 | 親族や友人、知人への訃報連絡、ペットの飼育に関する手続き |
死後事務委任契約は、契約者の「死後」の事務手続きを行う契約です。
そのため、生前の財産管理や生活の見守りは契約対象外です。
また、遺産相続に関する手続きも、契約に含まれません。
| できないことの例 | 内容 |
|---|---|
| × 相続財産の分割 | 預貯金や不動産を誰に相続させるかの決定、銀行の解約や不動産の売却などの相続手続き |
| × 遺言の執行 | 遺言書の内容の実現 |
| × 身分行為 | 子の認知 |
| × 生前の財産管理 | 自身が元気なうちの財産管理や日常生活の世話(身上監護)、医療行為への同意 |
「長子A子に預金を相続させたい」といった財産承継に関する希望は、別途「遺言書」を作成しておく必要があります。
また、遺言書に遺言執行者を明記しておき、相続手続きを行います。
死後事務委任契約は、遺言だけでは実現できない、相続財産以外の事務手続きを確実に行うための制度と言えるでしょう。
【徹底比較】遺言・成年後見制度との違いは?
死後事務委任契約を検討し始めた多くの人が「遺言と何が違うの?」「成年後見制度では代わりにならないの?」といった疑問に行き当たります。
結論から言うと、これらは目的も、効力を発揮するタイミングも全く異なる制度です。
ここからは遺言や成年後見制度、身元保証サービスとの違いを紹介します。
遺言との違い
遺言と死後事務委任契約の最も大きな違いは、その目的にあります。
遺言は「財産」を誰にどう引き継がせるかを決めるものであり、死後事務委任契約は「手続き」を誰にどう実行してもらうかを決めるものです。
| 遺言 | 死後事務委任契約 | |
|---|---|---|
| 目的 | 財産の引き継ぎ方を指定する | 死後の事務手続きを依頼する |
| できること | 財産の相続指定、子の認知、遺言執行者の指定など | 死亡の届出、マイナンバーカードなどの返却、葬儀や埋葬の手続き、遺品整理 など |
| できないこと | 葬儀の手配や遺品整理などの手続き(書いても構わないが法的効力はない) | 相続財産の指定、子の認知、遺言執行者の指定 など |
財産を巡るトラブルを防ぐために「遺言書」を準備し、死後の手続きで家族に迷惑をかけないために「死後事務委任契約」を結ぶなど、2つを組み合わせることもできます。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、認知症などで本人の判断能力が不十分になってしまった場合に財産管理や身上監護といったサポートを受ける制度です。
成年後見制度には、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに本人が任意後見人を選ぶ「任意後見制度」の2種類があります。
つまり、成年後見制度は「生きている間」に支援が受けられる制度であり、死後事務委任契約とはサポートを受けるタイミングに違いがあります。
また、基本的に成年後見人の仕事は、本人が亡くなった時点で終了します。原則として、成年後見人は亡くなった人の葬儀や埋葬を行う権限を持っていません。
死後のサポートを受けるためには、死後事務委任契約をする必要があります。
身元保証サービスとの違い
死後だけでなく、施設への入居や入院時の手続きなど 「生前」のサポートも希望する場合 には、「身元保証サービス」を利用する方法もあります。
身元保証サービスは、家族や親族の代わりに身元保証人の役割を担う仕組みで、多くの場合は亡くなった後の手続きもプランに含まれています。ただし、監督官庁が存在せず、サービスの内容や質は事業者によって大きく異なるのが現状です。
なお、2025年11月には 業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」が設立予定であり、今後は一定の基準やサービス整備が進むことが期待されています。
身元保証サービスを検討する際には、サービス内容のほか、基本料金や追加料金も確認しましょう。
死後事務委任契約を結ぶ5つのメリット
それでは、死後事務委任契約を結ぶと、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
①身寄りがなくても死後の手続きを確実に執行してもらえる
おひとりさまや、頼れる親族がいない人にとって、これは何より大きなメリットです。
自分に何かあった時の不安は、心に重くのしかかります。
死後事務委任契約を結んでおけば、依頼を受けた人が手続きを進めてくれることでしょう。
特に、専門的な知識・経験のある士業や団体と契約すれば、確実かつ迅速に進めてもらえる安心感があります。
②家族や親族の負担を大幅に減らせる
家族や親族がいる人にとっても、この契約は非常に有益です。
大切な人を亡くした直後のご家族は、深い悲しみの中にいます。しかし悲しみに浸る間もなく、役所での煩雑な手続きや葬儀の手配など、膨大な作業に追われることになります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、物理的な負担の多くを第三者に任せることができます。死後事務委任契約は、大切な家族に負担をかけない「思いやり」の役割もあります。
③法定相続人以外の人(パートナー等)にも公式に依頼できる
法律上、亡くなった人に関する事務手続きを行えるのは法定相続人(配偶者や子など)です。長年連れ添った内縁のパートナーや同性のパートナー、親しい友人などは、血縁や戸籍上の関係がないことで、手続きを進められないケースがあります。
しかし、死後事務委任契約を結べば、本人の意思に基づき「この人に託す」と指定した相手に死後の手続きを公式に依頼することができます。
ただし、死後事務委任契約で「相続権」を与えることはできません。財産を渡したい場合は遺言を残しておきましょう。
④葬儀の方法など自分の希望を詳細に反映できる
「葬儀はせずに、親しい人だけで集まって音楽を聴きながら送ってほしい」「お墓はいらないから、海に散骨してほしい」など、自身のエンディングについて具体的な希望を持つ人は少なくありません。
口頭で希望を伝えておくだけでは、残された家族間で意見が分かれてしまう可能性もありますが、死後事務委任契約の契約書に希望を明記しておくことで、その実現をより確実にすることができます。
最期のあり方を自分で決めておけるという点も、メリットの1つです。
⑤生前に決めておくことで精神的な安心感が得られる
これまで挙げてきたメリットの根底にあるのがこの「精神的な安心感」です。
将来への漠然とした不安は、日々生活に影響を与えることがあります。あらかじめ、死後の備えを整えておくことで、「必要な準備は済ませた」という気持ちが生まれ、不安感も軽くなります。
死後のの備えをすることは、決してネガティブな行為ではありません。むしろ、これからの人生を安心して過ごすためのポジティブな取り組みといえます。
契約前に知るべき3つの注意点(デメリット)
死後事務委任契約は、将来の安心を約束してくれる心強い制度ですが、万能ではありません。契約を結んでから後悔しないために、知っておくべき注意点を紹介します。
①専門家への依頼費用がかかる
死後事務委任契約にかかる費用には、契約書を作成する際に支払う「契約時費用」と亡くなった後の手続きを実行してもらう「死後実行費用」の2つがあります。
具体的な金額は依頼する専門家や委任する内容によって異なります。
一見高額と思われるケースもありますが、見方を変えれば「将来の安心への投資」ともいえます。
契約を検討する際は、複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスをしっかり比較検討することが大切です。
②信頼できる受任者(依頼相手)を見つける必要がある
もし、契約した相手(受任者)が不誠実だった場合は、希望どおりの手続きがされない、預けたお金(預託金)が適切に管理されないというリスクもあります。
受任者選びは、相手の人柄や料金体系の明確さなども慎重に確認しましょう。
③生前の財産管理はできない
認知症の備えや入院時の対応など、生前のサポートも整えておきたい場合は、任意後見契約や身元保証サービスを利用する方法があります。
また、これらの制度と死後事務委任契約を組み合わせることで、生前から死後までを通した体制を準備しておくことができます。
【料金相場】死後事務委任契約にかかる費用はいくら?
専門家や支援団体に依頼をする場合は、相応の費用がかかります。
費用は、大きく契約を結ぶときに支払うお金と、亡くなった後に使われるお金の2つに分かれます。
契約時にかかる費用
これらは、法的に有効で確実な契約書を作成するために、最初に必要となる費用です。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| コンサルティング料・契約書作成費用 | どのような内容を委任するか、自身の希望に沿ったオーダーメイドの契約書を作成してもらう | 10万~30万円 |
| 公正証書作成費用 | 作成した契約書を、法的に強力な効力を持つ「公正証書」にするために、公証役場に支払う手数料 | 1万~3万円 |
契約時には10万~30万円程度が必要になると考えておくとよいでしょう。
亡くなった後に必要になる費用
こちらは、死後の手続きを実行してもらうために、あらかじめ専門家に預けておくお金です。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 預託金(よたくきん) | 葬儀代、医療費の支払いや遺品整理の実費など、死後事務を行うための費用 | 100万~200万円(葬儀形式や遺品整理の規模による) |
| 専門家への執行報酬 | 死後事務を滞りなく実行した専門家に対して支払う「成功報酬」。通常、上記の預託金の中から支払われる | 30万~50万円 |
これらの費用を見ると、大きな金額に感じられるかもしれません。
しかし、葬儀代や遺品整理代などは誰かが必ず支払わなければならない費用です。
生前のうちに費用を準備し、信頼できる専門家に託しておくことで、残された家族の負担を大幅に減らすことができます。
死後事務委任契約を依頼できる専門家の種類と比較
これらの大切な契約は、一体誰に託せばいいのでしょうか?
ここからは、士業などの専門家や団体の特徴を紹介します。
| 依頼先 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 弁護士 | ・法的トラブルが発生しても対応できる ・対応できる業務範囲が最も広く、信頼性が高い |
・費用が他の専門家より高額になる傾向がある |
| 司法書士 | ・不動産の相続登記など、財産関連の手続きもスムーズに依頼できる | ・弁護士と違い、法的な紛争代理人にはなれない(業務範囲に制限あり) |
| 行政書士 | ・契約書の作成を得意とする ・費用が比較的安価な場合が多い |
・法的な紛争対応や登記業務は行えない |
| 終活支援を行うNPO法人など | ・サービスが体系化され分かりやすい ・身元保証など、付随サービスが充実している場合もある |
・サービスの質や経営の安定性に差がある |
【簡単5ステップ】死後事務委任契約の結び方・流れ
「契約」と聞くと、複雑で難しい手続きを想像されるかもしれません。しかし、死後事務委任契約を結ぶまでの流れは非常にシンプルです。
STEP1:専門家への相談
多くの士業事務所や専門団体では、初回の相談を無料で行っています。
この段階では、「契約をしなければ」と気負わず、「自分の場合はどうなんだろう?」「費用はどれくらい?」といった疑問や不安を率直に伝え、担当者の雰囲気や人柄かを確かめる場だと考えてください。
STEP2:委任する内容の決定
相談を通じて「この専門家になら任せられる」と感じたら、次に契約に盛り込む具体的な内容を決めていきます。
- 葬儀はどのような形式で行うか?(一般葬、家族葬、火葬のみ、など)
- 埋葬はどこにしてほしいか?(お墓、納骨堂、散骨、など)
- 誰に訃報の連絡をしてほしいか?
- 遺品はどのように整理してほしいか?(形見分け、処分、など)
- SNSアカウントやパソコンのデータはどうするか?
- ペットの世話を誰に託すのか
など、専門家からのアドバイスを受けながら、自身の希望を一つひとつ丁寧に整理していきます。
STEP3:契約書(案)の作成
STEP2で決まった内容をもとに、専門家が法的に有効な「死後事務委任契約書」の原案を作成します。
原案が完成したら、抜け漏れはないか、ご自身の希望が正確に反映されているか、隅々までチェックしましょう。
修正したい点や追加したい希望があれば、遠慮なく相手に伝えてください。
なお、相続人がいる場合は、自分の死後に相続人によって契約が解除されてしまう可能性もあります。
そのため、契約書には「解除制限特約」を盛り込んでおくとよいでしょう。
STEP4:公正証書での契約
完成した契約書は、「公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人が個人や法人などの嘱託によって作成する公的な文書です。
公正証書にする理由は、契約書に証明力と執行力を持たせるためです。公正証書にしておくことで、あなたの死後、受任者(専門家)が業務をスムーズに進めることができます。
なお、この手続きは、原則として公証役場へ出向いて行います。
STEP5:費用の支払い・預託金の預け入れ
公正証書での契約が無事に完了したら、最後のステップです。
まず、契約書作成などにかかった費用を専門家に支払います。
公正証書での契約まで済んだら、契約書作成などにかかった費用を専門家に支払います。
また、葬儀代や遺品整理費用など、死後の手続きに必要となる「預託金」を、信託口口座を通して専門家に預け入れます。
口座の名義には「委託者」「受託者」の氏名が記載されるため、信託財産であることがわかるようになっています。
死後事務委任契約に関するよくある質問(Q&A)
ここからは、死後事務委任契約に関する「よくある質問」にお答えします。
認知症になってしまったら、契約は無効になりますか?
いいえ、契約は無効にはなりません。
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に効力が発生する契約です。したがって、契約を結んだ時の内容が有効であれば、契約自体が無効になることはありません。
この契約は「生きている間」のサポートはでないため、認知症への備えを万全にしたい場合は、生前の財産管理などを任せる「任意後見契約」を併せて結んでおくことをおすすめします。
契約した後に、内容を変更したり解約したりできますか?
はい、原則として可能です。
自身の意思能力がはっきりしている限り、契約を結んだ相手(受任者)との合意のもとで、契約内容の一部を変更したり、契約そのものを解約したりすることができます。
生活状況の変化や心境の変化によって、「やはり葬儀の形式を変えたい」「依頼したい項目が増えた」といったことが出てくるのは自然なことです。
変更や解約をしたい場合は、まずは契約した専門家に相談しましょう。
改めて合意書や変更契約書(公正証書)を作成する形で対応するのが一般的です。
依頼した専門家が自分より先に亡くなった場合はどうなりますか?
原則として委任契約は終了します。
対策としては、以下の2つが挙げられます。
- ①「法人」と契約する
- 個人の専門家ではなく、弁護士法人やNPO法人といった「法人格」のある組織と契約する方法です。組織として契約を引き継いでくれるため、最も安心な方法といえます。
- ②予備的な受任者を定めておく
- 契約書の中で、「万が一、Aさんが亡くなった場合は、Bさんが業務を引き継ぐ」といった形で、バックアップの受任者を指定しておくことも可能です。
契約前の相談時に、「万が一の際の継続性」について、どのような対策を取っているかを確認しておきましょう。
遠方に住む親のために契約を検討しています。注意点はありますか?
「契約は必ず本人の明確な意思に基づいて結ばなければならない」という点に注意しましょう。
子どもが代理で契約することはできません。
子どもは、あくまで「サポート役」です。
死後事務委任契約という選択肢があることを親に伝え、一緒に専門家を探したり、相談に同席したりすることは、親にとって大きな助けになります。
ただし最終的に「誰に」「何を」依頼するかを決めるのは、契約者である親自身です。本人の意思を最大限に尊重し、決して無理強いすることのないよう、丁寧に対話を進めることが大切です。
まとめ
死後事務委任契約は、死後の事務手続きを信頼できる第三者に託すための契約です。
「死後の備え」と聞くと、少しネガティブな気持ちになるかもしれません。
しかし、この契約は「これからの人生を、より安心して前向きに生きるためのポジティブな活動」です。
自身のもしもの時に備え、やるべきことを済ませておくことで得られる心の平穏は、何物にも代えがたいものです。
もし、あなたが少しでも将来に不安を感じているなら、当事務所は初回相談無料となっていますので、まずは私たちとお話してみませんか?