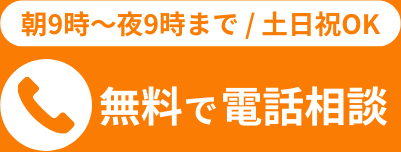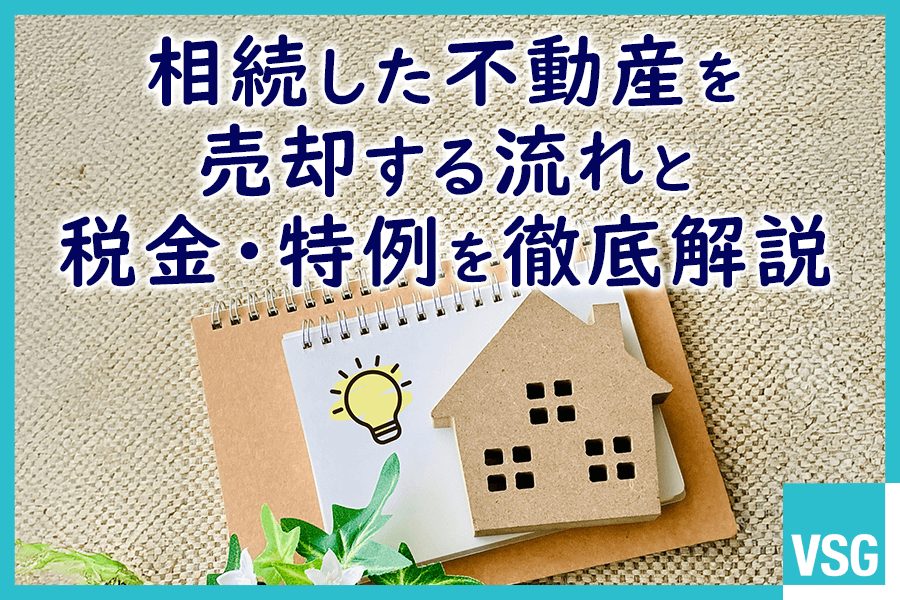記事の要約
- 相続不動産を売却するには相続登記が必須
- 2024年4月以降は義務化され、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 譲渡所得税が課税されるが、取得費加算や空き家特例の活用で節税可能
相続で実家や土地などの不動産を受け継いだとき、多くの方が直面するのは「相続した不動産を売却するには何から始めればよいのか」「売却すると税金はいくらかかるのか」「期限を守らないとどうなるのか」といった悩みです。
特に2024年4月からは相続登記の義務化がスタートし、期限を過ぎると過料の対象になるため注意が必要です。さらに相続不動産を売却するときには、譲渡所得税や空き家特例、取得費加算の特例など複雑な税制が関わるため、判断を誤ると数百万円単位の税負担が増えることもあります。
この記事では、相続不動産の売却に必要な手続きの流れ・税金の仕組み・利用できる特例や税額控除・トラブル回避のポイントを網羅的に解説します。読み終えたときには「何をいつまでに進めればよいか」が整理でき、安心して相続不動産の売却準備を始められるでしょう。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
ご自身の状況でどのように対応すべきか、少しでも不安を感じたら、お気軽にご連絡ください。
目次
相続した不動産を売却する前に知っておくべき基礎知識
売却には「相続登記」が必須(2024年4月~義務化)
相続で取得した不動産を売却するには、まず相続登記(所有者の名義変更)を行う必要があります。登記をしないままでは、不動産の名義が被相続人(亡くなった人)のままとなってしまい、買主と売買契約を結ぶことができません。つまり、相続不動産を売却する第一歩は相続登記の完了なのです。
さらに2024年4月からは相続登記が法律で義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことが求められます。もし申請期限までに正当な理由なく、登記の義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続不動産をスムーズに売却するためには、まず相続登記を早めに済ませ、売却の準備を整えることが大前提となります。
相続登記を怠るとどうなる?
相続登記を怠ると、名義が被相続人のまま残り、当然ながら売却契約を結ぶことはできません。さらに時間が経過すると、二次相続が発生して相続人が増えることで、権利関係が複雑化し売却が極めて困難になるリスクが高まります。
特に共有名義の不動産では、相続人のうち1人でも手続きを拒否すると売却が進まないため注意が必要です。
相続不動産を売却する際には、「相続登記をしていない=売却できない」と認識し、できるだけ早期に登記を完了させることが重要です。
不動産を売却できるのは「遺産分割協議」が終わってから
相続した不動産を売却するためには、まず相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成することが前提となります。遺産分割協議書がなければ、相続登記を行うことができず、結果として不動産の売却もできません。
つまり、「遺産分割協議の完了=相続不動産売却のスタートライン」といえます。
特に以下のようなケースでは、遺産分割協議が長期化する傾向があります。
- 相続人が多数いる場合
- 各相続人の持分割合で意見が対立する場合
- 相続人の一部が行方不明、または連絡が取れない場合
こうした状況では、話し合いだけで解決するのは難しく、売却が大幅に遅れる可能性があります。その場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用するのも一つの方法です。
相続不動産を売却するまでの流れ【完全フロー】
相続した不動産の売却は、以下の手順で進めるのが一般的です。全体の所要期間は、スムーズに進んでも6〜12カ月程度が目安です。
ここでは、相続不動産の売却を行う際の基本的な流れをステップごとに解説します。
- 遺言書の確認と相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記で名義変更
- 不動産会社に査定依頼(仲介か買取かを選択)
- 売却活動と契約・決済
- 確定申告で譲渡所得税を納付
ステップ1:遺言書の確認と相続人の確定
まずは、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書があるかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進めます。
遺言書がない場合は、戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定させます。
相続人調査は、後の遺産分割協議・相続登記・売却契約すべてに直結するため、漏れなく行うことが重要です。
ステップ2:遺産分割協議書の作成
相続人全員で不動産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
売却する場合、分割の方法としては、複数の相続人で相続した不動産を売却して得た代金を分ける「換価分割」がよく選ばれる方法です。
相続人の人数が多い場合や意見が対立している場合、遺産分割協議が長期化して売却に影響することがあります。その際は、家庭裁判所の調停や弁護士を交えた話し合いを検討するとよいでしょう。
ステップ3:相続登記で名義変更
遺産分割協議書をもとに、相続登記(所有権移転登記)を行います。
法務局で相続手続きをする際に必要となる一般的な書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の出生から死亡までの連続するすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 不動産の新たな所有者となる相続人の住民票
- 遺産分割協議書または遺言書
- 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書 など
登記申請書の作成方法や法務局への申請方法など、詳しくは下記の記事をご参照ください。
ステップ4:不動産会社に査定依頼
相続不動産を売却する際には、まず不動産会社に査定依頼を行いましょう。査定によって、売却価格の目安や売却方法の選択肢が見えてきます。
不動産の売却方法には「仲介」と「買取」があります。
- 仲介:不動産会社が買主を探し、売却をサポートする方法。時間はかかりますが、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、できるだけ高値で売りたい人に向いています。
- 買取:不動産会社や専門業者が直接購入する方法。市場価格よりも安くなることが多い一方で、短期間で現金化でき、相続税の納税資金や急な資金需要に対応しやすいメリットがあります。
相続不動産を「できるだけ高く売りたい」のか、「早く現金化したい」のか、目的によって仲介と買取のどちらを選ぶべきかが変わります。
ステップ5:売却活動と契約・決済
相続不動産を売却する方法として「仲介」を選んだ場合、不動産会社が広告を出したり内覧を実施したりして、購入希望者を探します。買主が見つかったら、売買契約を締結し、決済・引き渡しを行います。仲介の場合、売却価格は市場相場に近づく傾向がありますが、売却までに3〜6カ月程度かかることが一般的です。
一方、「買取」を選んだ場合は、不動産会社や専門業者と直接契約を結びます。価格は仲介に比べて低くなるものの、契約から数週間以内に現金化できるのが大きなメリットです。相続税の納付期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)に間に合わせたいケースや、早急に資金が必要な場合には有効な選択肢となります。
ステップ6:売却後の確定申告
相続不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行い、譲渡所得税を納付する必要があります。申告を怠ると延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。
譲渡所得は「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算し、不動産の所有期間に応じた税率(長期譲渡所得:20.315%/短期譲渡所得:39.63%)をかけて税額を求めます。
さらに、取得費加算の特例や空き家特例(相続した空き家の3,000万円特別控除)などを活用することで、税負担を大幅に軽減できるケースがあります。
相続不動産の売却では、「確定申告を忘れないこと」と「特例を正しく活用すること」がなによりも重要です。
相続不動産の売却にかかる税金
譲渡所得税の計算式
相続不動産の売却益(譲渡所得)は、次の式で求めます。
譲渡所得
取得費には、被相続人が不動産を購入したときの購入代金、仲介手数料、登記費用などが含まれます。取得費が不明な場合は、売却額の5%を概算取得費として計算することも可能です。
譲渡所得税は、所有期間によって「短期」と「長期」に分かれます。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
- 所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%(合計39.63%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超)
- 所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%(合計20.315%)
- ※
- マイホームを譲渡する場合、3,000万円の特別控除があります。また、所有期間が10年超であれば、税率10%を適用できます(租税特別措置法第31条の3)。復興特別所得税、住民税を合わせると14.21%となります。なお、6,000万円を超える部分は20.315%となります。
相続によって取得した不動産の場合、被相続人が所有していた期間も通算されます。
取得費加算の特例(3年10カ月ルール)
取得費加算の特例とは、相続税を支払った場合、譲渡所得税の計算において、その一部を不動産の取得費として加算できる制度です。
ただし、適用期限は「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(=3年10カ月以内)」に売却した場合に限られます。
期限を過ぎると特例が使えず、税額が数百万円単位で変わることもあります。相続不動産を売却する際は、この期限を意識したスケジュール管理が不可欠です。
空き家特例(相続した空き家の3,000万円特別控除)2024年改正
空き家特例とは、被相続人が一人暮らしで居住していた住宅を相続し、一定の条件を満たした上で売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。
この制度を利用できれば、譲渡所得が大きく圧縮され、税負担を数百万円単位で減らせる可能性があります。
ただし2024年以降は、相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2,000万円に縮小されているため注意が必要です。
また、耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修工事または取り壊しが必要になるなど、要件は細かく定められています。特例を活用できるかどうか、判断に迷ったときは相続専門の税理士にご相談ください。
小規模宅地等の特例との違い・注意点
相続した不動産を扱う際に混同しやすいのが、小規模宅地等の特例と、売却時に使える取得費加算の特例や空き家特例です。
小規模宅地等の特例は、相続税を軽減するための制度であり、譲渡所得税の軽減とは別物です。具体的には、被相続人が所有していた土地を相続した場合に、その相続税評価額を最大80%減額できます。
この点を混同している方が多いですが、
- 相続時の相続税を軽減 → 小規模宅地等の特例
- 売却時の譲渡所得税を軽減 → 取得費加算の特例・空き家特例
このように整理して、相続不動産の売却を検討する際は「どの税金に対して有効な制度か」を正しく理解しておくことが重要です。
さらに注意すべきなのは、被相続人の配偶者以外が土地を相続したケースです。この場合、相続税の申告期限よりも前に土地を売却すると、小規模宅地等の特例は適用できません。誤って早期に売却すると、相続税評価額の大幅な減額が受けられず、結果として相続税の負担が数百万円単位で増える可能性があります。
相続不動産の売却を検討する際は、必ず「相続税の特例」と「譲渡所得税の特例」を区別し、売却のタイミングを慎重に判断することが大切です。判断に迷う場合は、相続専門の税理士に早めに相談しましょう。
相続不動産売却でよくあるトラブルと解決策
共有名義で合意がまとまらない
相続した不動産が共有名義の場合、売却を進めるには相続人全員の同意が必要です。
そのため、1人でも反対する相続人がいれば売却できず、相続不動産の売却スケジュールが大幅に遅れることがあります。
解決策としては、
- 家庭裁判所での調停や審判を申し立てる
- 自分の持分のみを売却に反対している相続人又は第三者に売却する(持分売却)
といった方法があります。いずれにせよ、早い段階で専門家を交えることで、話し合いの行き詰まりを防げます。
相続人が行方不明
相続人の一部が行方不明のケースでは、売却がストップしてしまいます。この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで手続きを進めることが可能です。
財産管理人が選任されると、その相続人の代理として遺産分割協議に参加できるため、売却が進められるようになります。
なお、行方不明者が7年以上戻らない場合は利害関係人が家庭裁判所へ「失踪宣告」を申し立て、認められると法律上死亡とみなされます。戦争や災害・遭難などの場合は、危難が去ってから1年間以上経っても行方不明であれば失踪宣告の手続きを進められます。
境界確定・測量トラブル
不動産の境界が不明確なままでは、買主にとって不安要素となり、隣接地所有者とのトラブルを招く可能性があるため、売買契約が成立しないことがあります。
その場合は、土地家屋調査士に依頼して境界の確定測量を行い、隣接地所有者の立会い確認を得る必要があります。
境界確定には数十万円の費用と数カ月の期間がかかることもあるため、売却を見据えた早めの準備が重要です。
残置物が多い家の売却
相続した家に家具や家電などの残置物が大量に残っている場合、そのままでは買主がつきにくく、売却の大きなネックとなります。特に遠方に住んでいる相続人にとっては、片付けの手間やコストが大きな負担となりがちです。
一般的に、残置物の撤去費用は数十万円規模になることが多く、場合によっては売却価格や買主との交渉に影響することもあります。
解決策としては、次のような方法があります。
- 残置物を撤去して「空き家」として売却する方法
- 家屋を解体して更地にして売却する方法
特に古い家の場合、家屋を解体して更地にしたほうが買主の需要が高まり、結果的に売却価格が上がるケースもあります。
地方の空き家・再建築不可物件
地方の空き家や再建築不可物件は、市場での需要が低いため、仲介での売却が難航するケースが多く見られます。特に地方では、人口減少や空き家の増加により、買い手自体が少ないことも珍しくありません。
このような場合は、不動産買取業者に直接相談するのが現実的な解決策です。仲介に比べて価格は低めになりますが、短期間で現金化できるため、維持費や固定資産税の負担を軽減できるメリットがあります。
相続不動産を高く・スムーズに売却するためのポイント
ポイント1:売却のタイミングを見極める
相続不動産の売却では、特例などの適用期限と、市場動向を両方意識することが大切です。
ポイント2:仲介と買取を比較する
高値を狙うなら仲介、スピード重視なら買取。相続人同士で「高値を優先するか、スピードを優先するか」を事前に話し合っておくと、売却活動がスムーズに進みます。
ポイント3:専門家の専門分野を理解する
相続不動産の売却には、複数の専門分野が関わります。
- 司法書士:相続登記の手続き
- 税理士:譲渡所得税の計算、取得費加算の特例や空き家特例の適用判断
- 不動産会社:査定、売却活動、契約・決済の実務
ポイント4:ワンストップ対応の事務所を利用する
相続不動産の売却では、相続登記・税金の申告・不動産売却の実務と複数の専門分野が関わるため、それぞれ別の窓口に依頼すると手間やコストがかさみ、情報の行き違いからトラブルが生じやすくなります。
その点、ワンストップ対応の事務所に依頼すれば、相続登記から税金の申告、不動産売却までを一括で任せられるため、手続きがスムーズに進みます。複数の専門家にバラバラに依頼する必要がないので、効率的かつ安心して相続不動産の売却を進められるのが大きなメリットです。
VSG相続税理士法人でも、司法書士・不動産会社と連携したワンストップサービスを提供しています。実際にご依頼いただいた方からは、「相続登記から売却手続きまで一括で依頼でき、スムーズに進んで安心だった」「窓口が一本化されていて、余計なストレスがなかった」という声が多く寄せられています。
まとめ|相続不動産売却は「期限」と「特例」がカギ
相続不動産の売却を成功させるには、まず相続登記を3年以内に行うことが大前提です。さらに、譲渡所得税については、取得費加算の特例や空き家特例などを活用することで、数百万円単位の節税につながる可能性があります。
一方で、相続不動産の売却では、共有名義で合意がまとまらなかったり、境界が不明確で測量が必要になったりと、思わぬトラブルが発生することも少なくありません。こうした場合は、早めに税理士・司法書士・不動産会社といった専門家の力を借りることが不可欠です。
手続きの負担を減らし、効率的かつ安心して売却を進めるためにも、相続登記から税金の申告・不動産の売却手続きまでワンストップで依頼できる「VSG相続税理士法人」にご相談ください。