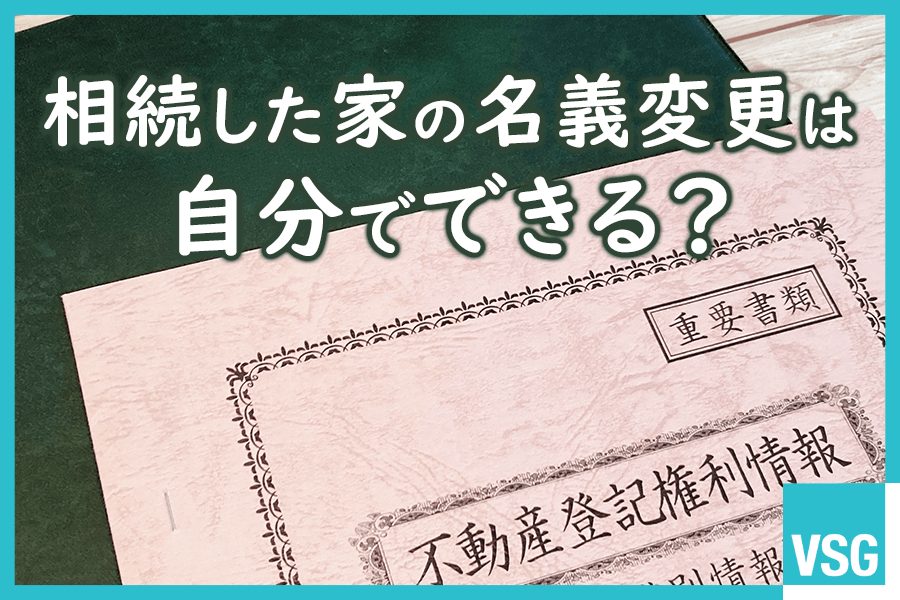この記事でわかること
- なぜ家の名義変更(相続登記)が義務になったのか
- 自分でできる?家の名義変更の具体的な手続きと流れ
- 総額いくら?自分でやる場合と専門家に頼む場合の費用
- どんな時に専門家に相談すべきかの判断基準
「親から実家を相続したけど、名義変更ってどうすればいいの?」
「手続きが面倒そうで、つい後回しにしてしまっている…」
もしあなたが今、そう考えているなら、少しだけ注意が必要です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)は、法律上の「義務」になりました。
この新ルールにより、これまで任意だった手続きに明確な期限が設けられました。重要なのは、この義務化が「法律が始まる前に相続した」という、過去のケースにも遡って適用される点です。知らずに放置してしまうと、思わぬ罰則の対象になる可能性があります。
ご安心ください。この記事では、家の名義変更を自分で行うための具体的な手順から、専門家に依頼する場合との費用比較、そして信頼できる専門家の選び方まで、あなたの疑問や不安がすべて解消されるように、一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたが次に何をすべきか、明確になっているはずです。
目次
家の名義変更とは?(まず基本と全体像を理解しよう)
家の名義変更とは、その不動産の持ち主(所有者)が誰であるかを、法務局の公式な記録(登記簿)上で書き換える手続きのことです。正式には「所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)」と呼ばれます。
この登記を行うことで、あなたがその家の新しい所有者であることを、国が公的に証明してくれるようになります。これにより、第三者に対して「この家は私のものです」と正当に主張できる(対抗できる)ようになるのです。
売買・贈与・離婚…そして「相続」で必要になります
家の名義変更が必要になるのは、主に以下のようなケースです。
| 具体例 | |
|---|---|
| 売買 | 家やマンション、土地などを購入したとき |
| 贈与 | 親から子へ、生きているうちに家を譲ったとき(生前贈与) |
| 財産分与 | 離婚に伴い、夫婦の共有財産だった家をどちらか一方の名義にするとき |
| 相続 | 親などが亡くなり、その方の不動産を引き継いだとき |
これまで、これらの手続きは、自分の権利を守るために行うものではあっても、法律上の義務ではありませんでした。しかし、ある一つのケースだけ、状況が大きく変わりました。それが「相続」です。
【最重要】相続だけは「義務」!知らないと損をする新ルール
不動産の名義変更(所有権移転登記)は、今でも売買や贈与などでは任意の手続きです。
しかし、相続によって不動産を取得した場合だけは、名義変更(相続登記)が法律で完全に義務化されました。
これは、2024年4月1日に施行された改正不動産登記法によるもので、日本国内の不動産すべてに適用される新しいルールです。もしあなたが相続で家を引き継いだのであれば、このルールを絶対に知っておく必要があります。
3年以内に手続きを!期限超過で10万円以下の罰則も
この新しいルールでは、相続登記の「期限」と「罰則」が明確に定められています。
- 手続きの期限
- 原則として「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請をしなければなりません。
- 罰則(ペナルティ)
- 正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料(かりょう)という行政上の罰則が科される可能性があります。
【要注意】過去の相続も「義務化」の対象です
この義務化は、「法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続」にも遡って適用されます。「何年も前に相続したけれど、まだ実家は亡くなった親の名義のまま…」というケースも、このルールの対象となるため、決して他人事ではありません。
ただし、過去の相続については猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。心当たりのある方は、早めに準備を始めましょう。
家の名義変更の流れ
「やるべきことは分かったけど、具体的に何から始めればいいの?」
ここからは、家の名義変更(相続登記)の具体的な手順を、4つのステップに分けて解説します。
一見すると複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを順番にこなしていけば、必ずゴールにたどり着けます。この章をガイドとして、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
ステップ0:手続きを自分で行うか専門家に依頼するか決める
具体的な作業を始める前に、まず最初に決めるべき最も重要なことがあります。それは、「この手続きを自分で行うか、それとも登記の専門家である司法書士に依頼するか」という方針です。
この最初の選択によって、時間のかかり方や手間が大きく変わってきます。
- 平日に役所や法務局へ行く時間を確保できる方
- 費用を少しでも安く抑えたい方
- 相続人の数が少なく、関係も良好な方
- 仕事などで忙しく、手続きに時間をかけられない方
- 書類集めや作成の正確性に少しでも不安がある方
- 相続人が多い、遠方に住んでいるなど、状況が複雑な方
費用は総額いくら?自分でやるvs専門家を徹底比較の項目で、それぞれのメリット・デメリットや費用を詳しく比較しますので、それを参考に最終判断しても問題ありません。
ステップ1:必要書類の収集
方針が決まったら、いよいよ具体的な作業の開始です。相続登記で最も時間と手間がかかるのが、このステップです。
ここでは最も一般的な「遺言書がなく、相続人全員の話し合いで不動産の取得者を決めるケース」を例に、必要書類を一覧にしました。
| 書類の種類 | 取得する場所 | |
|---|---|---|
| 亡くなった方(被相続人)の書類 | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本類 | 市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場(本籍地の市区町村役場) | |
| 相続人全員の書類 | 現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | |
| 不動産を相続する方の書類 | 住民票または戸籍の附票 | 住所地の市区町村役場 |
| 不動産に関する書類 | 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場・都税事務所 |
| 作成・準備する書類 | 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成し、実印を押印 |
| 登記申請書 | ご自身で作成 |
これらの書類、特に戸籍謄本類は、本籍地が遠方にある場合は郵送で取り寄せることも可能です。
ステップ2:登記申請書の作成
必要書類がすべて揃ったら、法務局へ提出する「登記申請書」を作成します。
申請書のひな形(テンプレート)や記載例は、法務局のホームページからダウンロードできますので、それを参考に作成を進めましょう。
主に記載するのは、「不動産の情報」「亡くなった方の情報」「新しく名義人になる方の情報」「登記の原因(相続)」「税金の計算根拠」などです。登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書に書かれている情報を、一字一句間違えずに正確に書き写すことが重要です。
ステップ3:法務局への申請
登記申請書が完成したら、ステップ1で集めた書類一式と合わせて管轄の法務局に提出します。
注意点として、申請先はどの法務局でも良いわけではなく、不動産の所在地を管轄する法務局に限られます。
申請方法は、主に以下の3つです。
- 窓口申請:直接法務局へ出向き、窓口で申請します。初めての方には最も安心な方法です。
- 郵送申請:書類一式を封筒に入れ、「書留郵便」で送付します。法務局へ行く時間がない場合に便利です。
- オンライン申請:パソコンで申請する方法ですが、専用ソフトやマイナンバーカードの読み取り機が必要なため、初心者にはややハードルが高いかもしれません。
申請後、書類に不備がなければ、1カ月半ほどで登記が完了します。完了すると、新しい名義人に対して「登記識別情報通知書」(権利証に代わる非常に大切な書類)が発行され、すべての手続きが終了となります。
取得方法別の必要書類の違いと注意点
家の名義変更は、その原因によって必要となる書類や、気を付けるべきポイントが大きく異なります。
前の章では、最も一般的な「相続(遺言書なし)」のケースを例に挙げましたが、この章では「遺言書がある相続」「贈与」「売買」のケースについて、必要書類の違いと特に注意すべき点を詳しく解説します。
相続による取得の場合
相続と一言でいっても、状況によって必要書類が変わります。
- ① 遺産分割協議で相続する場合(遺言書なし)
- これは前の章で解説した最も基本的なケースです。「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必須となります。
- ② 遺言書に基づいて相続する場合
- 法的に有効な遺言書がある場合、原則としてその内容が最優先されます。この場合、相続人全員の合意は不要なため、「遺産分割協議書」や「相続人全員の印鑑証明書」は原則として必要ありません。
その代わりに、「遺言書」そのものが登記の最も重要な書類となります。 - ③ 法定相続分で相続する場合
- 法律で定められた相続分(例:配偶者1/2、子1/2)の通りに共有名義で登記するケースです。この場合も「遺産分割協議書」は不要ですが、誰が法定相続人であるかを証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
相続手続きで最も大変なのは、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本類を集めることです。本籍地の変更が多い方ほど、複数の役所から取り寄せねばならず、時間と手間がかかることを覚えておきましょう。
贈与による取得の場合
親子間などで、生きているうちに不動産を無償で譲り渡す(生前贈与)ケースです。相続とは必要書類が全く異なります。
- 贈与契約書:いつ、誰が、誰に、どの不動産を贈与したかを証明する最も重要な書類です。
- 登記識別情報通知書(または登記済権利証):不動産をあげる側(贈与者)が持っている、いわゆる権利証です。
- 印鑑証明書:不動産をあげる側(贈与者)のものが必要です。
- 住民票:不動産をもらう側(受贈者)のものが必要です。
税金の負担が相続より格段に重い
贈与で最も注意すべきは税金です。
- 登録免許税:税率が2.0%と、相続(0.4%)の5倍になります。
- 贈与税:不動産のような高額な財産をもらうと、非常に高額な贈与税が課される可能性があります。
- 不動産取得税:相続ではかからない不動産取得税も、贈与の場合は課税対象となります。
安易に贈与を選ぶと、後で高額な税金に驚くことになりかねません。必ず税金のシミュレーションを行ってから判断しましょう。
売買による取得の場合
個人間で不動産を売り買いするケースです。
- 売買契約書:代金額や支払い条件などを定めた契約書です。
- 登記識別情報通知書(または登記済権利証):売主のものです。
- 印鑑証明書:売主のものです。
- 住民票:買主のものです。
- 固定資産評価証明書:売主に準備してもらいます。
親族間の売買は「みなし贈与」に注意
親族間で不動産を売買する場合、その売買価格に注意が必要です。市場価格と比べて著しく低い金額で取引すると、差額分が「贈与」とみなされ、買主側に贈与税が課される可能性があります(みなし贈与)。トラブルを避けるためにも、適正な時価で取引することが重要です。
自分で名義変更をするメリット・デメリット
家の名義変更を自分で行うか、専門家に依頼するかは大きな決断ですよね。費用を抑えられるという明確なメリットがある一方で、相応の手間やリスクも存在します。
両方の側面をしっかり理解して、ご自身の状況に合った最適な選択をしましょう。
メリット:最大の魅力は費用の節約
自分で名義変更を行う最大の、そしてほぼ唯一のメリットは費用の節約です。
- 専門家への報酬が不要になる
- 司法書士に依頼した場合、7万~15万円程度の報酬が発生します。自分で手続きをすれば、この費用をまるごと節約できます。もちろん、国に納める登録免許税などの実費はかかりますが、総額を大きく抑えられるのは非常に大きな魅力です。
- 手続きの知識が身につく
- 自ら書類を集め、申請書を作成する過程で、不動産登記や相続に関する一連の知識が身につきます。今後の人生で役立つ経験となるかもしれません。
デメリット:手間・時間・リスクが伴う
費用を節約できる一方で、自分で手続きを行う場合は、以下のようなデメリットを十分に理解しておく必要があります。
- 膨大な手間と時間がかかる
- 名義変更の手続きは、一度法務局に行けば終わるほど単純ではありません。亡くなった方の戸籍謄本を出生まで遡って集めるために複数の役所を巡ったり、慣れない登記申請書を作成したりと、多くの工程があります。特に、役所や法務局は平日の日中しか開いていないため、お仕事をされている方にとっては、手続きのために何度も休みを取る必要があるのが現実です。
- 専門的な知識が必要で、不備のリスクがある
- 登記申請書や添付書類には、法律で定められた厳格なルールがあります。もし書類に少しでも不備(記入ミス、書類の不足など)があると、法務局から修正(補正)を求められ、再度法務局へ出向かなければなりません。最悪の場合、申請が却下されて一からやり直しになる可能性もゼロではありません。
- 完了まで精神的な負担がかかる
- 「この書類で本当に合っているだろうか」「申請が受理されなかったらどうしよう」といった不安が、手続きが完了するまで常につきまといます。特に、ご家族が亡くなられて間もない時期に、こうした複雑で気を使う作業を行うことは、精神的にも大きな負担となる可能性があります。
費用は総額いくら?自分でやるvs専門家を徹底比較
家の名義変更手続きを進める上で、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面ではないでしょうか。
かかる費用は、「必ずかかる実費」と、専門家に依頼する場合にのみ発生する「司法書士への報酬」の2つに大きく分けられます。ここでは、それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。
必ずかかる費用①:登録免許税(計算シミュレーション付き)
登録免許税は、不動産の名義変更(登記)をする際に、国に納める税金です。これは自分でやっても専門家に依頼しても、必ず同額がかかります。
相続による名義変更の場合、税額は以下の式で計算します。
登録免許税
課税価格の基となる「固定資産税評価額」は、毎年春ごろに市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されています。もし手元にない場合は、不動産がある市区町村の役所(または都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取得すれば確認できます。
計算シミュレーション
2,000万円 × 0.4% = 8万円
この場合の登録免許税は8万円となります。
必ずかかる費用②:書類取得などの実費
手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを、市区町村役場で取得するための発行手数料です。
- 戸籍謄本:1通 450円
- 除籍・改製原戸籍謄本:1通 750円
- 住民票、印鑑証明書など:1通 300円前後
- 固定資産評価証明書:1通 300円前後
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を遡って取得する必要があるため、複数通になることがほとんどです。相続人の数にもよりますが、合計で5,000~15,000円程度を見ておくとよいでしょう。
司法書士の報酬相場はいくら?
司法書士に手続きの一切を依頼する場合に支払う費用です。報酬額は事務所によって異なりますが、一般的な相続登記の場合、報酬の相場は7万~15万円程度です。
相続人の数が多い、不動産が複数ある、数代にわたって相続登記がされていないなど、手続きが複雑になる場合は、報酬が加算されることもあります。多くの司法書士事務所では無料で見積もりを出してくれるので、依頼を検討する際は事前に確認しましょう。
【モデルケース】3,000万円の家を相続した場合の総額費用
それでは、ここまでの情報を元に、具体的なモデルケースで総額費用を比較してみましょう。
条件
- 登録免許税
3,000万円 × 0.4% = 120,000円 - 必要書類の取得費用
約 10,000円 (概算) - 司法書士報酬
0円
【合計費用】 約 130,000円
- 登録免許税
120,000円 - 必要書類の取得費用
約 10,000円 (概算) - 司法書士報酬
約 100,000円 (相場の中間値)
【合計費用】 約 230,000円
このケースでは、自分でやるか専門家に依頼するかで約10万円の差が出ることが分かります。この金額差と、手続きにかかる手間や時間を天秤にかけ、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
名義変更を専門家に依頼した方がいいケース
メリット・デメリットや費用を比較しても、「自分の場合はどうなんだろう?」と判断に迷うこともあるかと思います。
もし、これからご紹介するケースに一つでも当てはまるものがあれば、無理に自分で進めようとせず、専門家である司法書士に相談することを強くお勧めします。手続きを安全かつスムーズに完了させるための、賢明な判断です。
ケース1:平日に役所へ行く時間を確保できない
これは最も現実的で、多くの方が直面する問題です。
戸籍謄本などを集める市区町村役場や、登記申請を行う法務局は、いずれも平日の日中しか開庁していません。
書類の収集や申請、万が一の不備の修正(補正)のために、何度も仕事を休んで各所を回るのは、想像以上に大きな負担となります。平日に身動きが取りにくい方は、時間的コストを考えても専門家に任せる方が効率的です。
ケース2:相続関係が複雑で、手続きに不安がある
法律上の相続人が多ければ多いほど、手続きの難易度は格段に上がります。具体的には、以下のような状況です。
- 兄弟姉妹や甥・姪など、相続人が4人以上いる
- 相続人の中に、遠方に住んでいる人や連絡が取りにくい人がいる
- 長年疎遠にしており、関係性が良くない相続人がいる
相続登記には原則として相続人全員の協力(戸籍謄本や印鑑証明書の提出)が必要です。こうした関係者の調整や書類の取りまとめは非常に骨が折れる作業であり、専門家が中立的な立場で間に入ることでスムーズに進むことが多くあります。
ケース3:不動産の権利関係が難しい(未登記など)
相続した不動産そのものに、手続きを複雑にする要因が隠れているケースです。
- 相続した家が未登記だった
- 法務局に登記されていない建物の場合、まず建物の情報を登録する「建物表題登記」から始めねばならず、手続きが二段階になり非常に複雑です。
- 土地の登記簿が先代や先々代の名義のままになっている
- 「数次相続」と呼ばれ、現在の相続人がネズミ算式に増えている可能性があります。関係者全員を戸籍から調査するのは、個人ではほぼ不可能です。
- 土地を複数の人で共有している(共有名義)
- 共有者全員の協力が必要になるなど、権利関係が複雑になりがちです。
ケース4:その他、手続きに少しでも不安要素がある
上記以外にも、手続きに専門的な判断が必要な場合があります。
- 遺言書の内容が特殊、または有効性に疑問がある
- 相続人の中に行方不明者や未成年者がいる
- 住宅ローンが残っている不動産を相続した
もし一つでも当てはまる項目があれば、ぜひVSG相続税理士法人の無料相談を活用してください。登記経験の豊富な司法書士がそれぞれの状況に即したご提案をさせていただきます。
失敗しない!信頼できる司法書士の選び方3つのポイント
専門家に依頼しようと決めても、「どの司法書士に頼めばいいの?」という次の壁にぶつかりますよね。
司法書士は全国にたくさんいますが、それぞれに得意分野があります。あなたの大切な手続きを安心して任せるためには、いわば「相続のプロ」である司法書士をパートナーに選ぶことが重要です。
ここでは、信頼できる司法書士を見つけるための、3つのチェックポイントをご紹介します。
ポイント①:相続案件の実績が豊富か
これが最も重要なポイントです。お医者さんに内科や外科といった専門分野があるように、司法書士にも得意な業務分野があります。
あなたが依頼すべきなのは、ホームページなどで「相続手続き」や「不動産登記」を主要な業務として明確に掲げている司法書士です。
- 事務所のホームページで「取扱業務」や「実績紹介」のページを確認しましょう。
- 「相続登記の実績〇〇件以上」「相続専門チームが対応」といった具体的な記載がある事務所は、経験が豊富である可能性が高いです。
企業の登記がメインの事務所より、日頃から数多くの相続案件を手がけている事務所の方が、圧倒的に知識と経験が豊富で、スムーズな手続きが期待できます。
ポイント②:費用体系が明確か
手続きを依頼する上で、費用に関する不安はできるだけなくしたいものです。信頼できる司法書士は、必ず費用について透明性の高い説明をしてくれます。
- 事前に無料で見積書を出してくれるか
- しっかりとした事務所であれば、必ず正式な依頼の前に、詳細な見積書を提示してくれます。
- 見積書の内訳が分かりやすいか
- 見積書には、国に納める「登録免許税」などの実費と、事務所に支払う「司法書士報酬」が明確に区別して記載されているはずです。「一式〇〇円」といった曖昧な見積もりではなく、何にいくらかかるのかを丁寧に説明してくれる事務所を選びましょう。
契約前に総額と内訳をしっかりと確認することが、後のトラブルを防ぐ鍵です。
ポイント③:無料相談で親身に対応してくれるか
最終的には、人と人との相性も非常に大切です。相続手続きでは、ご家庭のプライベートな情報をお話しいただく場面も多くあります。あなたが「この先生になら安心して話せる」と感じられるかどうかは、重要な判断基準です。
多くの事務所では無料相談を実施しています。ぜひこれを活用し、実際に司法書士と話をして、以下の点を確認してみてください。
- こちらの話をじっくりと、親身になって聞いてくれるか
- 専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか
- 質問しやすい雰囲気を作ってくれるか
複数の事務所に相談してみて、最も「信頼できる」「話しやすい」と感じた司法書士に依頼するのが、後悔しないための最善の方法です。
まとめ
家の名義変更は自分でも可能ですが、専門的な知識と時間、そして手間がかかります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。
VSG相続税理士法人では、税理士と司法書士が連携し、登記手続きから相続税申告まで、ワンストップでサポートしています。お客様の手間とご負担を最小限に抑え、スムーズな手続きを実現します。お気軽にご相談ください。