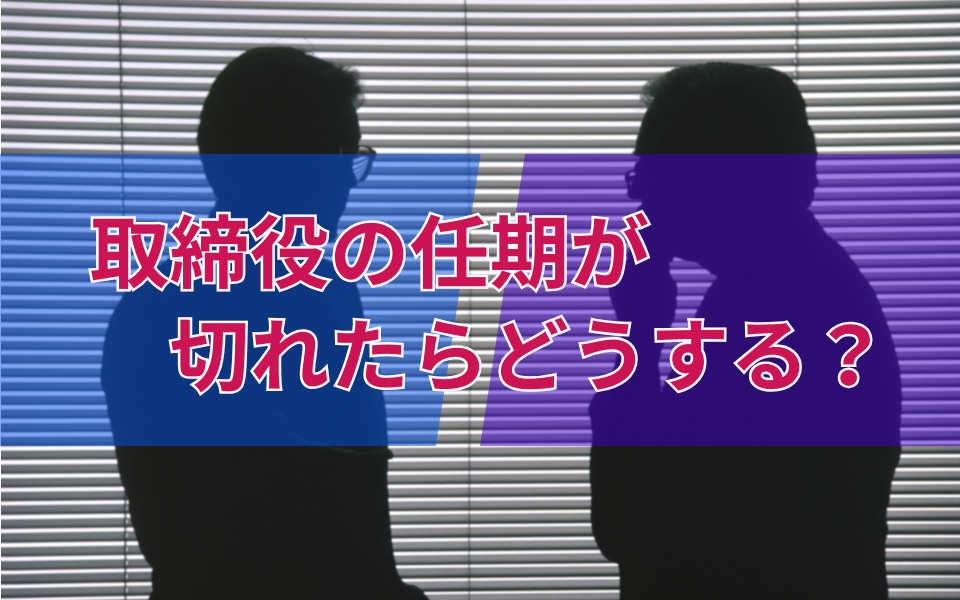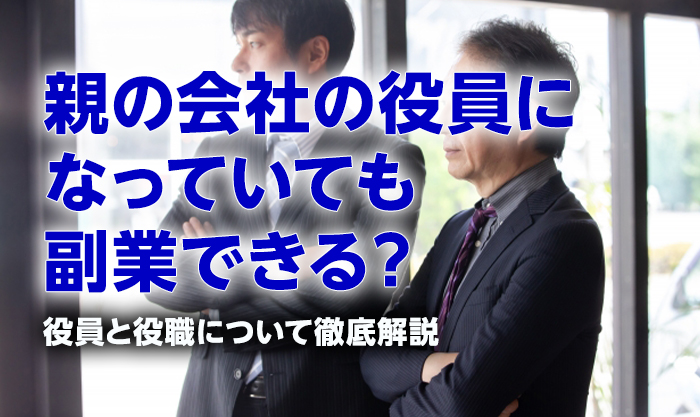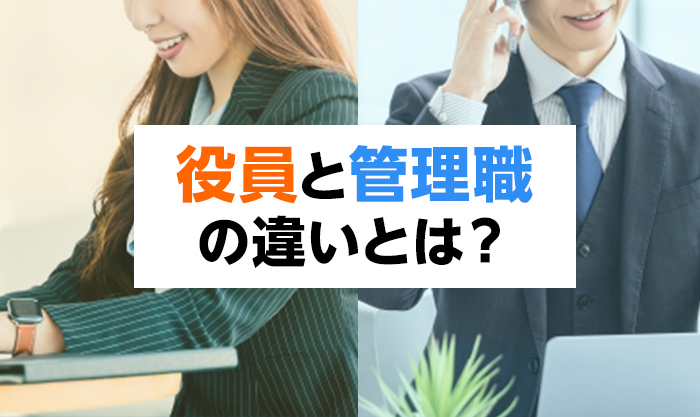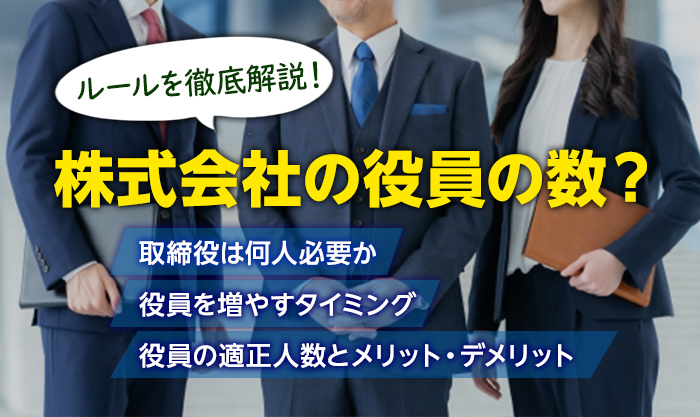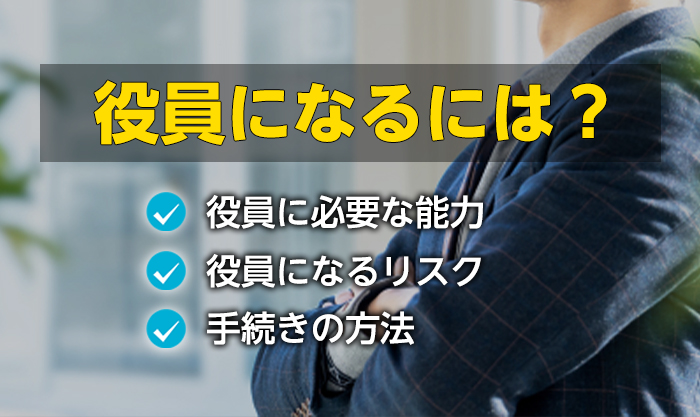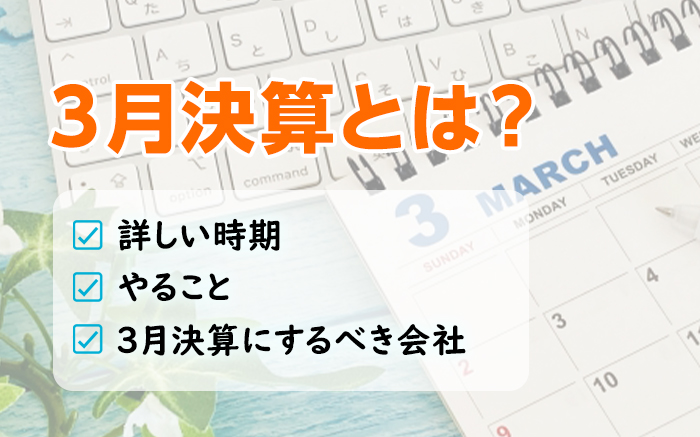最終更新日:2025/4/7
定款とは?作成・変更・紛失時の対応まで詳しく解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
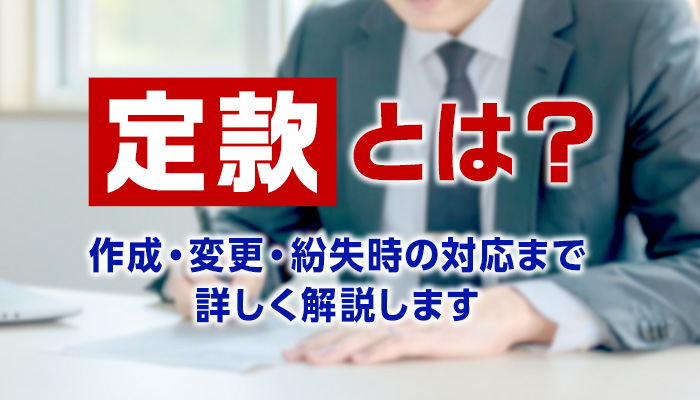
この記事でわかること
- 定款の基礎知識
- 定款変更について
- 定款の種類や記載事項
定款は、会社や法人の基本ルールを定める重要なものです。会社設立時の定款の作成方法から、変更や作り直しの手続き、紛失時の対応などの定款に関する知識は法人を運営していく上では欠かせません。この記事では、定款の基礎と、定款変更の際に必要な株主総会の決議や登記手続きの流れを詳しく解説します。
目次
定款は変更できる
会社の企業活動や運営方針が変わる場合には、定款の変更が必要になるケースがあります。例えば、事業目的の追加や、本店所在地の移転、役員変更などがあげられます。
これらの変更がある場合は、法的に認められる範囲で定款を修正できます。そして、役員の変更や所在地の移転の場合などは登記も行う必要があります。
定款は一度作成したら二度と変更できないものではなく、修正が可能です。
定款の変更が必要なのはどんなとき?
定款の変更が必要になるのは、法人の運営や方針が変化して、定款の内容が会社の実態と合わなくなっているときです。
- 事業目的の追加
- 本店所在地の移転
- 会社名の変更
- 役員の変更
- 株式の種類や発行数の変更
- 事業年度の変更
上記の場合は、定款の変更が必要です。変更の内容によっては登記も必要となります。
定款がすでにある人のためのガイド
定款をすでに所有している人のために、登記や変更手続き、紛失時の対応方法などをわかりやすく解説します。
登記の変更と定款の変更
定款の変更は株主総会の特別決議を経て行われる内部的な手続きです。
一方、登記の変更は、会社の基本ルールの変更点を公的に届け出る「外部的な手続き」で、法務局で行われます。
定款だけを変更すればいいというケースと、定款の変更と登記の両方が必要になるケースがあります。
下記は、登記が必要なケースと不要なケースをまとめた表です。
| 登記が必要な変更 | 会社名(商号)の変更 事業目的の変更 本店所在地の変更 支店の移転・設置・廃止 発行可能株式総数の変更 株式発行の定めの新設 取締役会の設置・廃止 株式の譲渡制限の変更 資本金の変更 |
|---|---|
| 登記が不要な変更 | 事業年度の変更 取締役の人数の変更 |
定款の変更が必要な場合でも、内容によって登記が必要になることがあります。
定款変更
定款は、あとから変更ができます。定款のなかでも特に重要な記載事項である「商号」や「事業目的」なども変更が可能です。
そのため、会社の方針に大きな変更がある場合でも、定款を作り直す必要はなく修正で対応できます。
定款の変更をする場合には、株主総会等を開いてその議事録を定款と一緒に保管します。ただし、何度も変更した場合は、最初の定款に議事録がいくつも重なってわかりにくくなることがあるため、一番新しい定款の内容を「現行の定款」として運用する方法もあります。この場合でも、最初の定款(原始定款)と議事録が正式な定款とその変更書類となります。
定款を作り直すこともできる
定款は何度でも変更できますが、作り直すこともできます。一般的には定款の変更で対応するケースが多いですが、作り直して新しい定款にすることも可能です。
定款を紛失した場合
定款を紛失した場合は、以下のような対応方法があります。
- 謄本の再発行
- 法務局で閲覧
- 作り直す
まず、公証役場で定款の謄本を再発行することができます。定款認証を受けていれば、公証役場で原始定款が20年保管されます。この原始定款のコピーまたはデータ(電子定款の場合)を再発行できます。
ただし、公証役場で保管されているのは会社設立時の原始定款なので、あとから変更した内容は反映されていません。
次に、法務局で定款を閲覧するという方法です。保存期間は10年と公証役場より短い上に、あくまでも閲覧ですのでコピーはできません。
続いて、新しく作り直すという方法です。これは、法務局で「登記事項証明書」を入手して定款を作り直し、さらに株主総会等の決議で「新しい定款を現行定款とする」という決議を経る流れになります。
なお、会社設立の際に司法書士に依頼していた場合、依頼していた司法書士が定款のデータを保管している可能性があります。依頼していた司法書士に連絡をすれば、定款のデータを複製してもらえるかもしれません。
定款を今から作る人のためのガイド
ここからは、定款の変更ではなく、新しく定款を作成する人に向けた内容です。
定款はどんなときに作るのか
定款は、法人を設立する際には必ず作る必要があります。株式会社や一般社団法人の場合は、定款認証という公的な手続きが必要です。
定款は会社の基本的なルールを定めたもので、その会社がどこにあって何をするために作られたのかが書かれている文書です。合同会社の場合、定款認証は不要です。ですが、定款は作る必要があります。
株式会社などの法人の設立登記を行う前には、必ず定款を作成します。
会社設立時の定款作成の流れ
会社設立の際に必ず作らなければならない定款ですが、作成は自分でしても構いません。定款作成時のポイントについてみていきましょう。
定款の作成
まずは定款を作成します。定款の記載事項にはルールがあります。具体的な内容については後述します。
定款の作成は、WordやGoogleドキュメントを使用して作成できます。もちろん、手書きでも問題はありません。
定款認証を受ける
株式会社の場合は、定款認証という手続きが必要です。これは、作成した定款を公的に認証してもらうことでお墨付きをもらうというものです。
登記申請書類の作成と申請
定款認証を終えてから、法務局で登記を行います。認証を受けた定款がなければ、株式会社の設立登記はできません。
定款とは?基本的な解説
そもそも定款とはどんなものなのでしょうか。定款についての基本的な知識を解説していきます。
定款は何のためにあるのか
日本国内にあるすべての会社は「会社法」という法律の範囲で運営されます。そして、各会社の定款は会社法の範囲内で作られます。この会社法はすべての会社に共通する全体的なルールですが、定款は個々の会社ごとに内容が異なります。
そして、株式会社の場合は「株主」という会社の持ち主がいます。株主は会社に出資している人のことですが、どんな会社で何をするために活動するのかを定款ではっきりさせておくことで、株主の誤解がなくなります。あとになって「そんな会社だったなんて知らなかった」というようなトラブルを回避できるのです。
また、会社や一般社団法人を「法人」といいます。この法人とは、人ではありません。人ではありませんが、会社の名前で契約をしたり銀行口座を持つことができます。
こうした、法律的な責任を負うことができるのが「法人」です。こうした責任を負うためには、その責任の範囲をはっきりと定める必要があるのです。
定款の読み方と英語表記
定款は「ていかん」と読みます。英語表記にすると「articles of incorporation」となります。
定款にありがちな失敗
定款を作成したものの、実際に会社を運営していくとトラブルや不具合が発生することもあります。
会社の事業内容が定款の目的に合っていないケースや、決算期の設定で失敗して設立後すぐに決算期が来てしまうケースもあります。
定款は自分でも作成できますが、内容に関しては会社の実情を理解した上で丁寧に作っていく必要があります。
定款の記載事項は?
定款には、必ず記載しなければならない項目があります。ここでは、定款の記載事項について解説します。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」です。これはどのような会社でも必ず記載します。
| 事業目的 | 会社の事業として具体的に何をするのか |
|---|---|
| 商号(法人名) | 会社の名前 |
| 本店所在地 | 会社の本店の住所 |
| 資本金 | 設立時の資本金の金額 |
| 発起人の氏名又は名称及び住所 | 発起人の情報 |
定款に記載する事業目的一覧とは?
定款には「事業目的」を記載しなければなりません。事業目的とは、会社が「何をするのか」を書いたもので、誰でも見ることができます。
事業目的をはっきりさせることで「取引の安定性」を提供できます。何をする会社なのかを定款に書くことでトラブルを防止するのです。何のために作られた会社なのかを明確にすることは、そのまま取引の安全性につながっているのです。
事業目的のサンプルとしてこちら(ベンチャーサポート税理士法人 事業目的一覧)をご覧ください。
もちろん、定款に記載したからといってすべての事業を必ずしなければならないということではありません。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に書かなければ効力を持たない項目のことです。絶対的記載事項とは違って、必ず記載しなければならないというものではありません。ですが、できるだけ記載しておくほうがいいでしょう。
| 現物出資 | 土地や車などの現物での出資 |
|---|---|
| 財産引受 | 会社が設立された場合に会社が受け取るor買う財産 |
| 発起人の報酬・特別利益 | 発起人の報酬・利益 |
| 設立費用 | 会社の設立費用 |
現金ではなく現物で出資したものや、設立後に会社が買い取る予定のものについては、金額が明確ではないため、出資者間の不公平感につながる可能性があります。定款に記載しておくことで、事前にトラブルを防止するという目的があります。
任意的記載事項
任意的記載事項も、必ず記載しなければならないものではありません。ですが、定款に記載しておくことで明確にしたいことがある場合は、書いておくほうがよい事項です。
簡単に言えば「記載しなくても定款としては成立するが、最初からはっきりさせておきたいこと」です。
定款の作り方と必要事項
ここからは、定款の作り方について解説します。自分でも作れる定款ですが、ルールがあるため作り方を確認しておきましょう。
定款に記載すべき項目
先述のとおり法律で定められている絶対的記載事項は必ず記載します。
そして、トラブル回避のために、可能な範囲で相対的記載事項や任意的記載事項についても記載するのが望ましいでしょう。
定款はあとから変更できますが、絶対的記載事項に関しては書かれていないと定款認証が受けられません。絶対的記載事項はすべての項目を必ず記載しなければなりません。
定款の雛形
定款を自分で作る場合に利用できるフォーマットがあります。いろいろなサイトで定款の雛形が配布されています。
信頼できる発信元として日本公証人連合会のフォーマットがあるので、参考にしてください。
定款認証の手続きと費用
定款を作成したら、株式会社や一般社団法人の場合は「定款認証」という手続きが必要です。ここでは、定款認証について解説します。
定款認証とは
定款認証とは、作成した定款を公証人によって「認証」してもらう手続きです。定款の内容に問題がないかをチェックしてもらって、公的なお墨付きをもらうのが定款認証です。
定款認証については、以下の記事で詳しく解説しています。
定款認証の流れと費用
定款認証は公証役場で行います。専門家に依頼することも、自分で定款を作って認証を受けることも可能です。定款認証の際には、電子定款と紙定款の2つの方法があります。どちらでも法的な効力は同じです。
下表は定款認証の費用をまとめたものです。
| 資本金の額等が100万円未満の法人の認証手数料 | 3万円 1万5,000円(発起人が3人以下、法人出資でない、出資者が発起人のみ、取締役会がない会社の場合) |
|---|---|
| 資本金の額等が100万円以上300万円未満の法人の認証手数料 | 4万円 |
| その他の場合の認証手数料 | 5万円 |
| 収入印紙(紙定款のみ) | 4万円 |
| データ保存手数料など(電子定款のみ) | データ保存手数料300円・提供手数料1通700円・書面交付手数料20円×枚数 |
定款認証の費用や必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
電子定款
電子定款の認証手続きは、定款を電子データで作成し、公証役場に送信した上で認証を受けるという流れです。電子定款を使えば、公証役場に足を運ばずに定款認証を済ませることもできます。
定款認証を受ける人の9割以上が電子定款を利用しています。
電子定款については以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてください。
紙定款
紙定款の認証手続きは、印刷した定款を公証役場に持参して認証を受けるという流れです。定款は紙で保管されるため、電子データに抵抗がある場合や、電子データを作る環境がない場合に利用されます。
ただし、紙定款の場合は収入印紙代がかかります。また、電子定款のようにオンラインで完結させることはできません。
定款変更の手続き
定款は、あとで変更ができます。
定款変更が必要なのはどんなとき?
定款を変更する必要があるのは、役員の員数の変更、事業目的の変更、本店所在地の移転などがあったときです。
絶対的記載事項の変更はもちろんですが、相対的記載事項であっても任意的記載事項であっても、定款に書かれていることを変更する場合は定款の変更を行います。
他にも、代表取締役の選任方法の変更や役員の任期の短縮・延長でも定款変更が必要です。
役員の員数の変更
会社の役員とは、取締役と監査役、会計参与のことです。執行役員は会社法上の役員ではありません。
役員に関しては、員数やどのような役員を置いているかが定款に記載されているため、変更が発生した場合は定款も変更しなければなりません。
事業目的の変更
会社の事業目的は絶対的記載事項であるため、追加したり削除したりする際には必ず定款変更が必要です。新しい事業を始めるときに、その事業が定款の事業目的に含まれていない場合は、必ず定款を変更します。
本店所在地の移転
定款に具体的な番地まで本店所在地が記載されている場合、移転に伴って必ず定款の変更が必要です。
ただ、定款の本店所在地は番地まで書く必要はなく、最小行政区画まででも良いとされているため、例えば「東京都渋谷区」でも定款として成立します。
このように一定のエリアを設定しているだけという場合は、そのエリア内の移転であれば定款変更は必要ありません。
定款変更手続きの流れ
定款の変更が必要になった場合でも、最初に作った原始定款を直接変更することはできません。原始定款を基準として、そこに議事録で変更を加えるという形になります。
株主総会の特別決議
定款を変更する際には、株主総会の特別決議が必要です。そして、この株主総会の議事録を作成します。
株主総会の特別決議では、決議に参加した株主の議決権の3分の2の賛成が必要です。
法務局の手続き
会社を運営するなかで登記の変更が必要になるのは以下の場合です。
- 事業目的の変更
- 商号(法人名)の変更
- 所在地の変更
- 株式総数の変更
- 株式発行についての変更
- 取締役会および監査役会の設置と廃止
- 株式の譲渡制限の変更
- 資本金の増額と減額
上記の変更をした場合は法務局で手続きを行います。法務局の手続きでは、変更登記申請書と株主総会の議事録を提出します。電子申請・紙の申請どちらでも手続きが可能です。
定款変更から2週間以内に法務局で手続きを行う必要があります。
定款の保存と管理方法
会社のとても重要な書類である定款の保管方法について解説します。
定款の保管方法
定款の保管方法としては、電子定款の場合は電子データとして保存します。複数の媒体に保存しバックアップを取っておくと安心です。
そして、紙定款の場合は火災や盗難に注意して保管します。社内の重要書類として厳重に保管されるのが一般的です。
定款の保存期間
定款は会社が存続する限り保管しなければなりません。また、定款を変更した場合は、定款変更を行った際の株主総会の議事録も一緒に保管します。
また、定款認証を受けた場合は公証役場に20年は原始定款が保管されます。
定款は記載事項が決められていて登記の変更が必要な場合もある
定款は会社の基本ルールを定めた重要な書類です。自分で作ることもできますが、作成にはルールがあり、必要な記載事項が定められています。定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、絶対的記載事項は必ず記載しなければなりません。
また、定款の内容はあとで変更することも可能で、事業目的や本店所在地などを変更する際には、定款変更の手続きを行います。定款変更をするときには、必ず株主総会の特別決議が必要です。内容によっては法務局での登記手続きが求められる場合もあります。
定款は会社が存続している限り社内で保管しなければなりません。紛失してしまった場合には、公証役場でデータを複製したり、場合によっては新たに作り直すこともあります。
定款に関する基本事項を知っておくことで、会社運営を円滑に進めることができます。