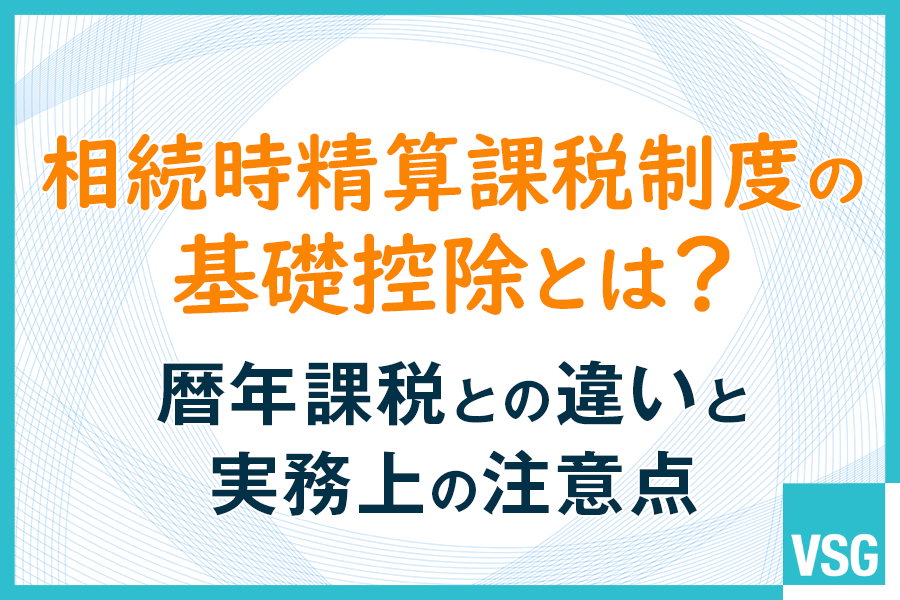国税庁が公表した「令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、相続時精算課税を適用した申告者数は、令和5年度の4万9,000人から令和6年度には7万8,000人へと大幅に増加しました。
この背景には、令和5年度税制改正により相続時精算課税に基礎控除110万円が創設され、制度が使いやすくなったことがあります。
今後も利用者が増えると予想されますが、暦年課税との違いや基礎控除額の按分・端数処理、期限後申告時の扱いなどいくつか注意すべき点があります。
この記事では、相続時精算課税の基礎控除に関連する重要なポイントを整理します。
目次
相続時精算課税制度に基礎控除が導入された背景
従来の相続時精算課税制度には基礎控除がなく、少額の贈与であっても申告が必要となり、利用ハードルが高いとされていました。
今回、令和5年度税制改正で「年間110万円の基礎控除」が創設され、基礎控除以下の贈与であっても相続開始前7年以内贈与は相続財産に持ち戻す暦年課税と異なり、相続時精算課税の基礎控除は持ち戻しは不要となったことで、利用者数が増加しています。
暦年課税と相続時精算課税の基礎控除の違い(比較表)
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 年110万円 | 年110万円 |
| 控除の適用対象 | 受贈者ごとに年110万円 | 贈与者ごとに累計2,500万円 別途、受贈者ごとに年110万円 |
| 届出の要否 | 不要 | 初年度は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要 |
| 相続時の扱い | 相続開始前7年以内の贈与は持ち戻し対象 | 年110万円の基礎控除後の残額のみ持ち戻し |
基礎控除のしくみと端数調整
相続時精算課税制度を選択して贈与した人を「特定贈与者」といいます。
相続時精算課税における基礎控除額110万円は、同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、それぞれの贈与額に応じて按分します。計算の結果、割り切れずに端数が生じることがありますが、その場合は、基礎控除の額の合計額が110万円となるようにその端数を調整します(相続税法基本通達21の11の2₋2)。
たとえば、特定贈与者である父から5,500,340円、同一年中に特定贈与者である祖父から8,439,580円の贈与を受けたとします。
この場合、基礎控除額110万円は以下のように計算します。
計算
- 父:110万円 × 5,500,340 /(5,500,340 + 8,439,580)= 434,032.189…円
→ 円未満切捨て 434,032円 - 祖父:110万円 × 8,439,580 /(5,500,340 + 8,439,580)= 665,967.810…円
→ 円未満切捨て 665,967円
合計すると1,099,999円となり、基礎控除額110万円に対して1円不足しますが、国税庁の通達により「⋯⋯計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に1円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が110万円になるようにその端数を調整して差し支えない。」とされています。
したがって、どちらか一方に1円を加算することで、基礎控除の合計額を110万円にすることができます。
期限後申告になった場合の特別控除
期限内申告の場合
たとえば、特定贈与者である父から5,500,340円の贈与を受け、その後、同年中に特定贈与者である祖父から8,439,580円の贈与を受けたものの、祖父からの贈与分の申告が漏れていたとします。
この場合、期限内申告では父からの贈与分のみを申告しているため、5,500,340円-1,100,000円=4,400,340円となります。相続時精算課税を初めて適用する贈与であれば、4,400,340円は特別控除の対象となるため、課税価格は0円となります。
期限内申告と基礎控除額が異なる場合
その後、祖父からの贈与分の申告漏れが判明した場合には、基礎控除を按分して再計算する必要があります。ただし、祖父からの贈与は期限後申告となるため、特別控除の適用はできません(相続税法第21条の12第2項)。その結果、祖父からの贈与額から基礎控除を差し引いた金額に対して、20%の贈与税が課税されることになります。
また、按分計算により、父からの贈与に対する基礎控除は665,967円減少します。正しい控除を受ける金額の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があると税務署長が認める場合、この減少部分について特別控除を適用できるとされています(相続税法第21条の12第3項)。
通常、税金の世界で「やむを得ない事情」と出てくると、自然災害や人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害があったことで申告や届出が期限までにできなかった、というようなケースが該当し、忘れてしまったという理由では認められないというイメージがあります。
ここでの「やむを得ない事情」はそこまで強いものではなく、当初申告はしていたものの、他の贈与の申告漏れにより基礎控除減少が発生した場合には、この基礎控除減少部分に対して特別控除の適用が認められます。これは、相続時精算課税が相続において精算されることが予定されており、租税回避に繋がらないからです。期限内に申告した財産について評価誤りがあった場合も同様です。
とはいえ、まったくの制限をかけずに修正申告であれば特別控除を適用できるとしてしまうと、税額に影響がないので修正申告をしないという選択をする納税者が出てくることも予想されます。それゆえ、やむを得ない事情があると税務署長が認める場合というように条件が付されているようです。
相続時精算課税の適用初年度に相続が発生した場合
相続時精算課税の適用初年度に基礎控除以下の贈与を受けた場合、申告書の提出義務はないものの、贈与を受けた年の翌年の贈与税申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
ところが、申告期限を待たずに特定贈与者が亡くなった場合には、提出期限および提出先は通常の場合とは異なります。次のイまたはロのいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
- イ 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
- ロ 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10カ月を経過する日)
この届出書を提出し忘れると、相続時精算課税の基礎控除額110万円は適用できず、暦年課税の扱いとなります。その結果、相続開始前7年以内の贈与として相続財産に加算される点にも注意が必要です。
相続時精算課税と暦年課税を併用した場合
同一年中に、相続時精算課税と暦年課税の両方の贈与を受ける場合は、以下のようになります。
- 相続時精算課税、暦年課税ともに基礎控除額以下の贈与の場合:贈与税の申告書の提出は不要
- 相続時精算課税に係る財産の価額が相続時精算課税の基礎控除額を超える場合:贈与税の申告書の提出が必要。また、同一年中に暦年課税に係る贈与があった場合、財産の価額が暦年課税の基礎控除額以下であっても暦年課税に係る財産について申告書に記載する必要あり
- 暦年課税に係る財産の価額が暦年課税の基礎控除額を超える場合:贈与税の申告書の提出が必要。また、同一年中に相続時精算課税に係る財産の価額が相続時精算課税の基礎控除額以下であっても相続時精算課税に係る財産について申告書に記載する必要あり
ポイントは、相続時精算課税と暦年課税のいずれかが基礎控除額を超えた場合には、もう一方も必ず申告書に記載しなければならないという点です。「基礎控除額以下なら申告不要」と誤解されやすく、申告漏れの典型的な原因となるため特に注意が必要です。
チェックリスト:相続時精算課税の基礎控除を正しく活用するために
相続時精算課税制度を利用する際は、以下のポイントを毎年確認することが大切です。
チェックを習慣化することで、思わぬ申告漏れや余計な課税リスクを未然に防ぎ、制度を安心して活用できます。
チェックリスト
□ 初年度の「相続時精算課税選択届出書」を提出したか?
□ 期限内申告を守り、申告漏れがないか確認したか?
□ 暦年課税との併用がある場合、双方の記載を忘れていないか?
相続時精算課税制度の基礎控除を正しく理解して安心の相続・贈与を
相続時精算課税に基礎控除が設けられたことで、制度はぐっと使いやすくなり、実際に利用する人も年々増えています。
一方で、基礎控除額の按分計算や申告期限、相続時精算課税選択届出書の提出、暦年課税との併用ルールなど、ちょっとした見落としが余計な税金につながることもあります。
実際の申告時に慌てないよう、この記事で紹介した比較表やチェックリストなどをぜひ参考にしてください。
そして、大切な相続や贈与を安心して進めるためにも、不安や疑問があれば、相続専門のVSG相続税理士法人へお気軽にご相談ください。