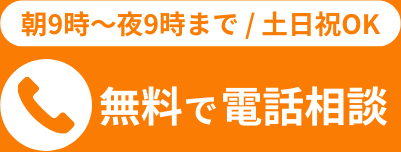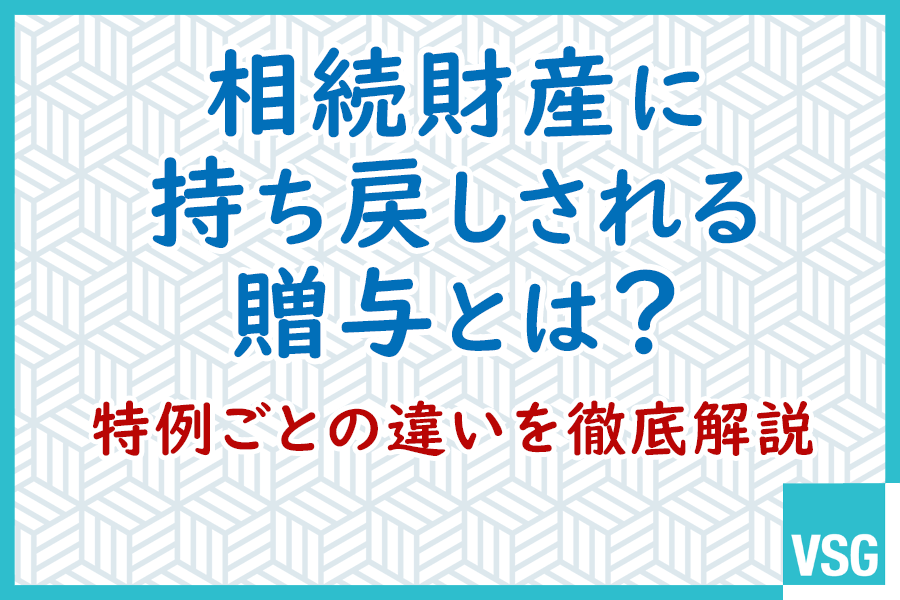生前贈与をした財産は、相続税を計算する際に「相続財産へ持ち戻す」必要があるケースがあります。
持ち戻しのルールは、暦年課税や相続時精算課税といった基本的な課税方法だけでなく、住宅取得等資金贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などの特例によっても異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、相続財産への持ち戻しの仕組みと最新の税制改正ポイント、さらに特例ごとの違いをわかりやすく整理して解説します。
目次
暦年課税と相続財産への持ち戻し
生前贈与の代表的な方法である暦年課税には、相続時に「持ち戻し」が発生するルールがあります。
これまでの制度では、暦年課税の場合は相続開始前3年以内の贈与が持ち戻し対象、相続時精算課税の場合は贈与額の全額が持ち戻し対象とされてきました。
しかし、令和5年度の税制改正で大きな見直しが行われ、次のように変わっています。
- 暦年課税
- 相続開始前7年以内の贈与が持ち戻し対象。ただし、延長された4~7年分については100万円を控除。
- 相続時精算課税
- 年110万円の基礎控除が新設され、この部分は持ち戻し不要に。
暦年課税の改正ポイント
相続または遺贈により財産を取得した人が暦年課税で贈与を受けていた場合、基礎控除110万円以下の贈与であっても、相続開始前7年以内であれば相続財産に持ち戻す必要があります。
- 改正前:相続開始前3年以内の贈与が持ち戻しの対象
- 改正後:2024年1月1日以降の贈与は、相続開始前7年以内が持ち戻しの対象
この改正により、7年間すべてが持ち戻し対象となるのは2031年1月1日以降に開始する相続からとなります。
なお、延長された4年分(相続開始前4~7年の贈与)については、納税者の事務負担を考慮し、100万円の控除が設けられています。
相続時精算課税と相続財産への持ち戻し
相続時精算課税を利用して贈与を受けた場合、これまでは「相続や遺贈で財産を取得していなくても、贈与額の全てが相続財産に持ち戻される」仕組みでした。
しかし、2024年1月1日以降の贈与からはルールが改正され、
- 年110万円の基礎控除が新設
- この基礎控除分については相続財産に持ち戻す必要がなくなった
という大きな変更が行われています。
暦年課税との大きな違い
- 暦年課税:相続開始前7年以内の贈与であれば、基礎控除110万円以下の贈与も持ち戻し対象
- 相続時精算課税:基礎控除110万円までの贈与は持ち戻し不要
この違いは実務上の大きなポイントです。「暦年課税は少額の贈与でも持ち戻しあり、相続時精算課税は一定額まで持ち戻し不要」と覚えておくと整理しやすいでしょう。
主な贈与特例と持ち戻しの要否
生前贈与にはさまざまな特例がありますが、相続時に「持ち戻しが必要かどうか」は特例ごとに異なります。ここでは代表的な4つの特例を確認しましょう。
おしどり贈与特例(配偶者控除)
被相続人(亡くなった人)から配偶者に贈与された財産について、おしどり贈与特例(贈与税の配偶者控除)を適用していた場合は、たとえその贈与が相続開始前7年以内であっても、非課税とされた部分は相続財産に持ち戻す必要がありません。
贈与税の配偶者控除は「老後の生活保障」を目的とした制度であり、相続時の持ち戻し対象から外れる仕組みになっています。
住宅取得等資金の贈与特例
被相続人からの贈与について、住宅取得等資金の贈与特例を適用していた場合も同様です。
たとえ、その贈与が相続開始前7年以内であっても、特例によって非課税とされた額は相続財産に持ち戻す必要がありません。
住宅取得等資金の贈与特例は、若い世代の住宅取得を支援する目的で設けられており、非課税の範囲については相続時に再度課税されない仕組みになっています。
教育資金の一括贈与特例
教育資金の一括贈与特例は、子や孫に教育資金をまとめて贈与できる制度です。当初は「契約期間中に贈与者が亡くなった場合でも、非課税枠内の管理残額は相続財産に持ち戻さなくてよい」という仕組みでした。
しかし、その後の制度改正により、ルールが段階的に変わっています。
2019年4月1日以降の贈与
相続開始前3年以内の贈与に該当する場合、以下①〜③のいずれにも当てはまらないときは、管理残額を相続財産に持ち戻す必要があります。
- ①受贈者が23歳未満である
- ②学校等に在学している
- ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている
2021年4月1日以降の贈与
上記の要件に加え、受贈者が贈与者の子以外(孫など)の場合は、相続税額が2割加算されます。
2023年4月1日以降の贈与
①〜③の条件を満たしていても、贈与者の相続税の課税価格の合計額(管理残額を除く)が5億円を超える場合には、管理残額を相続財産に持ち戻す必要があります。
ただし、管理残額以外に相続財産を取得していない場合には、たとえ暦年課税で相続開始前7年以内の贈与を受けていたとしても、相続財産に持ち戻す必要はありません。
結婚・子育て資金の一括贈与特例
結婚・子育て資金の一括贈与特例は、結婚や出産・育児にかかる費用を一括で贈与できる制度です。取り扱いは基本的に教育資金の一括贈与特例と同じです。
- 贈与者が亡くなった時点で管理残額がある場合
→ その残額は相続財産に持ち戻す必要があります。 - 例外的に持ち戻し不要となるケース
管理残額以外の相続財産を受け取っていない場合は、たとえ暦年課税による相続開始前7年以内の贈与を受けていても、相続財産に持ち戻す必要はありません。
相続税対策におすすめの贈与特例|持ち戻しの仕組みを正しく理解しよう
暦年課税による相続開始前7年以内の贈与は、基礎控除110万円以下であっても相続財産に持ち戻す必要がある点に注意が必要です。このルールを見落としてしまうケースは少なくありません。
暦年課税の場合、相続または遺贈で財産を取得した人は、相続開始前7年以内の贈与について必ず相続財産に持ち戻さなければなりません。
一方で、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与特例では、贈与者が亡くなったときに残っている管理残額が「相続等により取得したもの」とみなされる場合でも、租税特別措置法70条の2の2により除外されています。具体的には、管理残額以外に相続財産を受け取っていない場合には、他の贈与を受けていたとしても相続財産への持ち戻しは不要です。
こうした制度の違いを踏まえると、相続税対策として最も活用しやすいのは住宅取得等資金贈与特例といえます。その他の特例は、相続税の軽減というよりも、配偶者の老後の生活保障や子・孫への経済的支援といったライフプランの一環として利用するのが適切です。
「自分の場合は持ち戻しの対象になるのか?」「どの特例を使うのが有効か?」といった疑問がある方は、どうぞお気軽に相続専門の「VSG相続税理士法人」までご相談ください。