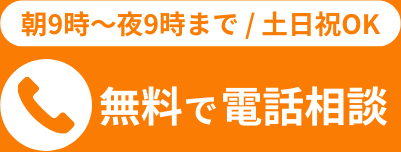記事の要約
- 借主・貸主が死亡した場合、使用貸借契約が相続されるのかどうか
- 使用貸借中の土地の相続税評価と小規模宅地等の特例の可否
- 相続が発生した際に必要となる登記手続きと実務上の注意点
使用貸借とは「無償で物を貸す」契約のことです。
親の土地に子どもが家を建てて住んでいるケースが典型的なケースでしょう。
ところが、貸している親や借りている子どもが亡くなったとき、「このまま住み続けられるの?」「契約は終わってしまうの?」と不安に思うことも少なくありません。
この記事では、使用貸借契約は相続されるのかどうかをはじめ、賃貸借契約との違いや土地の評価方法、小規模宅地等の特例が使えるかどうかを解説します。
相続が起きたときに慌てないために、ぜひ押さえておきましょう。
使用貸借とは?
まずは、使用貸借の概要や賃貸借との違いについて紹介します。
使用貸借の定義と特徴
使用貸借(しようたいしゃく)とは、ある人が自己の物を無償で相手に使用させ、その使用が終わったら返還を受ける契約のことです。
民法593条では「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。
つまり、賃料の支払いを伴う「賃貸借」と違い無償で利用させる点が、使用貸借最大の特徴です。
親が所有する土地に子どもが自宅を建てて住んでいるケースなど、親族間でよく利用される契約形態です。
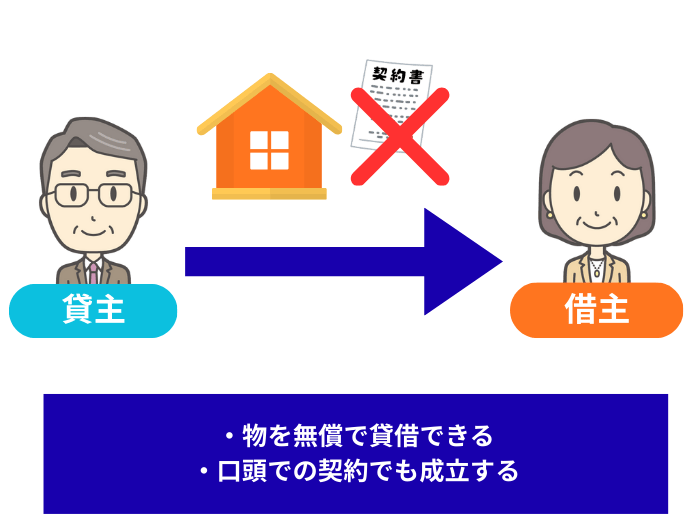
賃貸借との違い
使用貸借と賃貸借には、次のような違いがあります。
いずれも動産・不動産を対象にすることができますが、この記事では不動産の貸し借りを例に紹介します。
| 項目 | 使用貸借 | 賃貸借 |
|---|---|---|
| 対価 | 無償 | 有償(賃料あり) |
| 借主の権利の強さ | 弱い(原則として、借主の死亡や使用目的の達成、期間満了で契約は終了する。不動産を借りている場合でも、借地借家法が適用されない) | 強い(不動産の賃借権は、登記で保護される。登記がなくても、建物の引き渡しを受けていたり、借地上に登記された建物を所有していたりすれば第三者に権利を主張できる) |
| 税務評価 | 原則「自用地」として評価 | 「貸家建付地」など、減額評価が可能な場合あり |
不動産の賃貸借契約の場合、借主は借地借家法によって強力に保護されます。また、貸主は正当事由がなければ更新を拒絶できません。
これに対し、使用貸借契約の借主は、対価を支払わないため法律上の保護は弱く、特に契約期間が定められていない場合には、貸主の判断ひとつで利用を打ち切られるリスクが高いとされています。
使用貸借の借主は、賃貸借の借主に比べると権利の安定性が低いため、相続や贈与の場面でトラブルになることがあります。
相続場面で問題となる典型ケース
親(貸主)の土地を無償で借りて、その土地に子(借主)が住んでいる状態で相続が発生すると、以下のようなケースではどうなるのでしょうか。
- 子(借主)が亡くなったら子(借主)の家族は住み続けられるのか?
- 親(貸主)が亡くなったら子(借主)は住み続けられるのか?
- 土地の相続税評価はどうなるのか?
このように、「死亡による契約の継続可否」や「土地評価の扱い」は、使用貸借契約に特有の相続問題となります。
借主が死亡した場合の契約の取扱い
借主が亡くなった場合、契約はどうなるのでしょうか。
原則:契約は終了する
借主が亡くなった場合、使用貸借契約は原則として終了します。
これは民法597条3項において「使用貸借は借主の死亡によって終了する」と明記されているためです。
それでは、借主の配偶者や子どもがそのまま居住を続けることはできないのでしょうか。
特約・黙示の合意・権利濫用の法理による契約の継続
もっとも、以下のような場合には例外的に契約が継続することがあります。
- 1.特約がある場合
- 契約書や合意で「借主死亡後もその相続人が使用できる」と定めていたときは、その内容が優先されます。
- 2.黙示の合意がある場合
- 契約書はなくても、長年にわたり親子・親族間で無償使用が継続しており、死亡後も使わせることを当事者が当然の前提にしていたと判断されるケースです。
- 3.権利濫用にあたる場合
- 借主の家族が住み続けることを前提に自宅を建築していたのに、貸主側が急に「出ていけ」と主張するのは社会通念上不当とされ、継続を認めた判例もあります。
判例の紹介と解釈
代表的な判例として、東京地裁平成5年9月14日判決があります。
この事案では、敷地上に借主が建物を建てていたことから、借主が亡くなった後も、その借主の相続人が使用を継続できると認められました。
裁判所は貸主と借主の特別な関係から貸していることよりも、土地に関する使用貸借契約がその敷地上の建物を所有することを目的としていることを重視し、「借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借契約が当然に終了するということにはならない」と判示しました。
つまり、条文上は契約終了が原則であっても、実際には事情次第で使用継続が認められることがあるのです。
貸主が死亡した場合の契約の取扱い
それでは、貸主が亡くなった場合、契約はどうなるのでしょうか。
原則:貸主の地位は相続され契約は継続する
貸主が亡くなった場合、使用貸借契約は終了せず、貸主の地位は相続人に承継されます。
貸主(相続人)側の解除の可否
貸主の地位を承継した相続人が「使用貸借をやめたい」と思っても、契約期間が満了していなかったり、使用目的が達成されていなかったりするケースでは、原則として貸主側から契約を解除することはできません。
ただし、借主の重大な債務不履行など、特段の事情がある場合は例外となることがあります。
また、使用貸借時に取り交わしていた契約書に「貸主が亡くなった時点で契約を終了する」といった特約の記載があれば、新しい貸主は借主に対し、明け渡しを求めることができます。
相続税評価と小規模宅地等の特例について
被相続人(亡くなった人)が使用貸借により土地を貸していた場合でも、相続税を計算するうえで、その土地の評価額は、評価減のない更地状態の評価である「自用地評価」となります。
使用貸借中の土地評価
土地を有償で貸した場合、利用目的によっては「借地権」が発生しますが、使用貸借は無償で利用しているだけなので、借地権は認められません。
そのため、貸主が亡くなって相続税を計算する場合の土地の評価は、通常の自用地(所有者だけに使用権がある土地)と同じ評価額で算出されます。
例えば、時価1億円の土地を子が親から無償で借りて住んでいたのであれば、相続税の評価上は1億円そのままで計算されます。
賃貸借であれば、第三者に貸している土地の評価額は、借地権を差し引いて評価額を算出できます。しかし使用貸借では、賃貸借契約のように「借地権割合」による減額が使えない点が大きな違いです。
子が親から土地を無償で借り受け、その土地の上にアパートや賃貸住宅を建てて第三者に貸している場合も、貸家建付地として評価額が下がることはありません。
子と親との間ではあくまで使用貸借であり、親に利用制限がかかっているとはいえないのです。
小規模宅地等の特例の適用可否
使用貸借中の土地でも、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が利用できる可能性があります。
- 適用が認められる場合
同一生計の親族が自宅敷地・事業用敷地として使用していたケース
親族である貸主(敷地所有)と借主(家屋所有)が同居していたケース - 適用が認められない場合
単に親族に貸しているだけで、同一生計とはいえない場合
| 利用形態 | 評価方法 | 小規模宅地等の特例 |
|---|---|---|
| 親が所有する土地に子が自宅を建てて同居(生計一) | 自用地評価 | 適用○(同一生計なら可) |
| 親が所有する土地に子が自宅を建てて別居(生計別) | 自用地評価 | 適用× |
ケース別Q&A
ここでは、使用貸借についてよくある疑問にお答えします。
親の土地に子が家を建てたが、親が死亡した場合はどうなる?
親が貸主として自分の土地を子に無償で貸していた場合、親の死亡により貸主の地位は相続人である子に承継されます。
したがって子は直ちに住居を失うことなく、そのまま住み続けることができます。
また、相続人である子は「借主」と同時に「貸主」にもなります。
この状態を「混同」といい、混同の状態になると使用貸借契約自体が終了します。
相続人が複数いる場合は、土地は遺産共有の状態となり、遺産分割が確定するまで子はその家に住み続けることができます。
ただし、遺産分割確定後は、その土地を引き継いだ相続人が「居住継続を認めるかどうか」で引き続き住み続けられるかどうかが決まります
借主だった夫が死亡した場合、残された家族は住み続けられる?
原則として、使用貸借契約は借主の死亡により終了します。
例えば夫が死亡した場合、残された妻や子が自動的に借主の地位を引き継ぐわけではないため、当然に住み続けられるわけではありません。
ただし、「借主の死亡後も使用継続できる特約がある場合」や「貸主が黙示的に承認していると解される場合」、「明け渡し請求が権利濫用にあたると判断される場合」は、例外的に居住継続が認められることもあります。
なお、賃貸借の場合は、借主だった夫が亡くなっても相続人である妻や子に借主としての立場が相続されるため、引き続きその物件に住むことができます。
小規模宅地の特例を受けたいが、別居していると使えない?
小規模宅地の特例が適用されるには、相続開始直前にその宅地が被相続人または「被相続人と生計を一にする親族」の居住用に供されていたことが前提となります。
つまり、使用貸借中の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかは、「同一生計かどうか」が大きなポイントとなります。
- 同一生計の親族が居住・事業に使用している場合
→ 適用される可能性あり。相続開始直前に、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用であれば、特定居住用宅地等として検討できる。 - 別居していて生活が独立している場合
→ 適用されない。同居自体は要件ではないが、生活費等の継続的な送金などが確認できない場合は、生計を一にしていると認められにくい。
判断に迷うときは税理士に相談しましょう。
自用地評価ではなく貸宅地評価にするためには地代を払えばいいの?
個人間の場合、無償もしくは固定資産税程度の支払いであれば使用貸借とみなされ、借地権は発生しません。
一方、借地契約では、土地を借りる際に「権利金」(土地を借りる権利を得るため地主に支払う一時金)を支払うのが一般的です。
権利金を支払わずに通常の地代(他人同士の貸し借りで払う程度の地代)の授受を行う場合、貸主から借主へ借地権の贈与(認定課税)があったとみなされ、借主に贈与税が課税されます。
なお、権利金の代わりに通常の地代よりも高い相当の地代(更地価格の6%)の授受がある場合、権利金の認定課税は行われません。
ただし、相続での評価減を考えて長年相当の地代を払い続けたとしても、貸主は地代収入に対して所得税を払い続けることになり、結果として相続税の節税効果を上回る所得税の負担を抱える可能性もあります。
確かに、使用貸借の土地は自用地として評価されるため、賃貸借契約の土地に比べると相続税評価額は高くなる傾向があります。だからといって、相続直前に使用貸借から賃貸借に切り替えると租税回避として税務調査で問題になりかねません。
そのため、相続税評価の引き下げ対策として地代を支払う方法は、あまりおすすめできません。
使用貸借にも契約書は必要?
使用貸借は口約束でも成立します。
しかし、無償で貸していた実態や契約期間があいまいになりやすく、相続時に「言った・言わない」のトラブルが生じがちです。
例えば、契約期間が決まっていない場合において、借主が長年住み続けていると、時効取得(所有権を得ること)を主張されるケースもあります。
ただし、親子間など身内の使用貸借では、裁判例上時効取得が認められにくい傾向があります。
また、契約書がないと相続人間で解釈が割れやすく、相続後の処理が難航することもあります。
使用貸借は書面がなくても成立しますが、相続時の争いを防ぐためには契約書を残しておくことが望ましいです。
相続で「共有財産」になった使用貸借の土地に、住み続けることはできる?
相続が発生すると、被相続人が所有していた土地は相続人全員の共有財産になります。
そのため、一部の相続人が土地を使用貸借している場合、他の相続人から「土地を返してほしい」と求められる可能性があります。
ただし、その相続人も「貸主」としての地位を相続しているため、一方的に立ち退きを主張できるわけではなく、権利濫用と判断されるケースもあります。
例えば、親の土地に子ども2人のうち1人が自宅を建てて住んでいたとします。
親が亡くなると土地は兄弟2人の共有財産となります。
住んでいない側の子どもが「土地を自由に使えない」と不満を持つことがあり、遺産分割や立ち退きを巡る争いに発展する可能性があります。
このように、使用貸借をやめさせようにも、双方の事情が対立すると解約が難しい場合があります。
「親が有償で借りている土地」に、子どもが権利金や地代を親に支払わず無償で使っている状態(親の借地に子が建物を建てる)のことを「借地権の使用貸借」といいます。
借地権の使用貸借は子が親から借地権の対価分の経済的利益を受けたことになり、子に贈与税が課税されます。
ここで子に贈与税を課税されないようにするには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を、借地権者(親)と建物の所有者(子)、地主の三名連名で使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に対し、提出する必要があります。
この確認書は、あくまでも借地権者は親であることを税務署に通知するものであり、親の相続のとき、借地は借地権として相続財産となります。
まとめ
使用貸借は、親族間でよく利用される無償の貸し借りです。
使用貸借は、原則として自用地評価となり、賃貸借のような借地権割合による減額は認められませんが、小規模宅地等の特例は同一生計の親族が居住しているか事業の用に供していれば適用可能です。
別居で同一生計の場合は、「同一生計であることの証明」ができるようにしておきたいところです。
不動産の権利関係は複雑なうえに、使用貸借は両者の口約束で成り立っていることも多く、トラブルとなることもあります。
疑問に思ったことがあれば、早めに税理士や司法書士、弁護士といった専門家に相談しましょう。当事務所は、初回相談料無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。