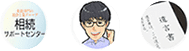「相続前にリフォームや建物修繕をしておくと相続税対策になるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。相続税対策の基本的な考え方のひとつに、「相続財産を減らす」というアプローチがあります。ただし、単に財産を使い切ってしまうのでは意味がなく、相続人にとってメリットのある形で財産を移転する、あるいは価値を有効に変換しておくことが重要です。
この観点から見ると、リフォームや建物修繕は、相続財産を現金から不動産の価値に移す手段として一定の効果が期待できます。また、もう一つの相続税対策として、「財産評価額を下げる」という考え方もあります。現金はそのままの金額で評価されますが、不動産の場合は土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されるため、現金に比べて評価額を抑えられる可能性があります。
しかし、リフォームや修繕によって不動産の評価額が上がってしまうケースもあるため、相続税対策として本当に有効かどうかは慎重に検討する必要があります。この記事では、リフォームや建物修繕が相続税対策に与える影響や注意点、評価額との関係などについて詳しく解説します。相続を見据えて資産を有効に活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
リフォーム・建物修繕による節税効果
では、具体的に家のリフォーム・の相続税対策としての2つの効果をみていきます。
相続財産の減少
建物の所有者がその所有建物をリフォーム・修繕した場合、通常、そのリフォーム・建物修繕を行うための工事費用などの支出が生じることになります。
その結果、現金や預金などが減少するという形で、相続財産の減少をもたらすことができます。
また、リフォーム費用をローンなどで調達した場合には、その分、借入金というマイナスが増えるため、それによっても相続財産の額は減少させることができます。
相続人へのメリット
被相続人が建物等をリフォーム・修繕しないままで亡くなった場合、その建物を相続によって取得した相続人は、その建物を利用するには自らリフォームや修繕等を行う必要が生じる可能性があります。
そうすると、せっかく建物を相続したのに、その修繕等のためにかえって費用の持ち出しになってしまうということも考えられます。
これに対して、被相続人が建物をリフォームして設備を最新のものにしたり、不具合を修繕・修復等しておいたりすると、将来的に相続が発生した場合に、相続人は設備が整い、また、修繕等の必要のない建物を相続によって取得することができます。
その結果、相続人はその建物に自ら居住するにしても、他人に賃貸等するにしても、その相続した建物を直ちに有効に活用することができることになり、相続人に対してのメリットが大きく、実質的にはリフォーム費用等を被相続人から相続人に贈与したのと類似した効果が得られることになります。
リフォームによる建物の評価額への影響
建物の床面積の増加や減少を伴うリフォーム、建物自体の価値が高くなるリフォームについては、評価額に影響がでてきます。
リフォームについての取り扱いは税制改正があった点になりますので必ず注意をしていただきたいと思います。
従来(平成25年の税制改正前)においては、リフォームを行った場合でも、建物の面積が増加した場合などを除いては、建物の評価額が上がるということは余りありませんでした。
そのため、建物のリフォームは、相続対策としてかなり有効な手段とされていました。
しかし、税制改正後には、リフォームをした場合、そのリフォームした部分の評価額を加算して物件の評価をすることとされました(国税庁が公表した「増改築にかかる家屋の状況に応じた固定資産評価額が付されていない家屋の評価」による)。
その増加額は、
- 「当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額」とされました。
- 類似した近隣物件がない場合には、リフォーム等に要した費用から償却費相当額を控除した額の70%相当額が増加額として判断されることになります。
仮に、リフォーム費用として1,000万円がかかった場合、その70%相当分(=700万円分)の建物の価値が増加したと評価されます。
例えば、5,000万円の建物に1,000万円をかけてリフォームした場合、全体の相続財産としては、かかったリフォーム費用の1,000万円が減少します。
一方で、かかったリフォーム費用の70%(=700万円分)が増加資産額となります。
この結果、実際にリフォームに要した費用の30%相当分だけ、相続財産を減少させることが可能となるわけです。
【税務署にはバレます】リフォーム費用は必ず加味して評価する
リフォーム後に相続が発生し、「リフォーム費用について建物評価に加味しなくてもバレないのでは?」と考える方もいらしゃるかもしれませんが、税務署は相続前の預貯金等の入出金を確認するため、この時点でハウスメーカーや工務店に振込の記録によりバレてしまうことになります。
維持修繕による建物の評価額への影響
なお、リフォームといっても通常の維持修繕費で、元の価値より高くなるような改修費でなければ、上記のような70%評価までの計算をする必要はないかと思います。質疑応答事例等にはリフォームの範囲が規定されてないので明言することができませんが、外壁の補修や屋根の雨漏り修復などは
- 「破損箇所の原状回復工事」
- 「建物を維持するために不可欠となる定期工事費」
- 「経年劣化した付帯設備の交換」
としてリフォームでなく現状維持のための修繕費として取り扱うことができます。
業者に依頼をする場合でも、リフォームと維持修繕をしっかり区分しておきましょう。
まとめ
以上、リフォームによる相続対策の方法と、実際について見てみました。
従来は、リフォームは相続対策の方法として、非常に有効性が高いとされていました、上記の通り、現在では、その効果は半減されていると言っていいでしょう。
逆に、税制改正後も、このことを知らずにリフォームによる増加額を相続財産として申告しなかった場合、税務調査などが入ったときに申告漏れを指摘される危険があります。
その場合、過少申告となり、加算税を課される可能性があります。
ですから、リフォームがなされてから新たな固定資産税評価がなされるまでの間に相続が発生した場合には、増加分の申告を忘れないようにする必要があります。
相続税対策を検討している方は、【厳選!相続税対策】22個の節税手法で相続税ゼロを目指す!の記事もあわせてご参考ください。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。