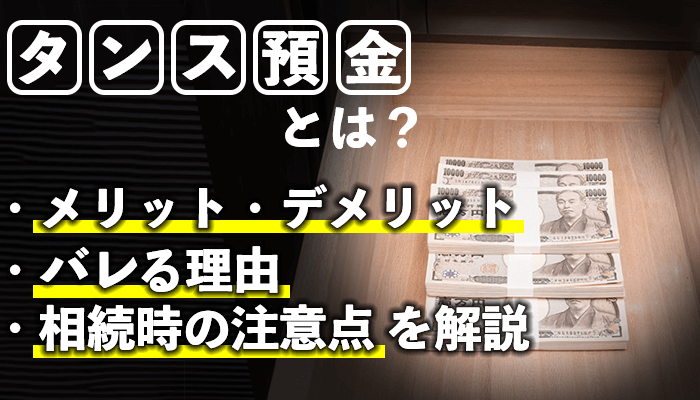この記事でわかること
- タンス預金の概要とメリット、デメリット
- タンス預金を相続時に隠した場合のリスク
- 相続時にタンス預金が見つかった場合の対処法
「タンス預金にしておけば相続税がかからないのでは?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。結論からお伝えすると、タンス預金を相続税対策として利用するのは間違いです。
タンス預金を隠そうとしても税務署にバレる可能性が高く、悪質な財産隠しには多額の追徴課税が課される恐れもあります。
この記事では、タンス預金のメリット・デメリット、タンス預金を隠すリスク、タンス預金が見つかったときの対処法などを解説します。
目次
タンス預金とは?
タンス預金とは、まとまった金額の現金を金融機関に預けず、自宅のような場所に資金移動の記録が残らない形で保管することを言います。
タンス預金の保管場所はタンスに限られません。保管場所が金庫や引き出し、クローゼット、屋根裏、軒下などであっても、現金のまま保管する行為を総じてタンス預金と呼んでいます。
日本銀行が令和6年に公表した資金循環統計の概要によると、家計の金融資産の合計額は2,211兆円で、そのうち約103兆円が現金のまま保管するタンス預金となっています(※1)。
タンス預金自体は法的に問題はない
多額の現金をタンス預金として保管しても、その行為自体は法的に問題ありません。ただし、「相続税対策として」タンス預金を利用することはできません。
タンス預金も、当然のことながら相続税や贈与税の課税対象です。
亡くなった被相続人の預金口座から現金を引き出して手元に保管し、相続税や贈与税の申告を誤魔化そうとすると、追徴課税などの重いペナルティを受ける可能性があります。
タンス預金のメリット
相続税対策ではなく手元に保管するだけなら、タンス預金にはいくつかメリットがあります。
タンス預金のメリット
- 相続発生時などの口座凍結に備えられる
- 都合の良いタイミングでお金を使用できる
- 金融機関の破綻から財産を守れる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
相続発生時などの口座凍結に備えられる
銀行口座の名義人が亡くなった場合には、銀行口座が凍結されます。凍結された銀行口座からは、入院費や相続発生時の葬儀代などを引き出すことはできません。
凍結された銀行口座からは公共料金やクレジットカードなどの引き落としもできなくなるため、親族が代わりに支払うことになります。
そのような場合でも、タンス預金で手元にいくばくかの現金を残しておくと安心です。
都合の良いタイミングでお金を使用できる
いつでも好きなタイミングで現金を使用できる点も、タンス預金の形で現金を保管するメリットと言えます。
銀行にお金を預けていると時間外でATMを利用できなかったり、ATMでの引き出し上限により現金の利用が制約されたりしてしまうことがあります。
怪我や病気などで急な出費が発生する可能性もあるため、タンス預金として手元に現金を残しておくと、そのような場合でも問題なく対応できます。
金融機関の破綻から財産を守れる
万が一金融機関が破綻した場合に備え、金融機関の預金には「預金保険制度」(ペイオフ)が設けられています。
預金保険制度で保証される預金は、一つの金融機関につき元本1,000万円までのため、それ以上の金額を預けている場合は、支払われない可能性が出てしまいます(※)。
一方、タンス預金であれば金額を気にすることなく、貯蓄をすることが可能です。銀行に預けた場合と比較して利息はつきませんが、金融機関の状況に左右されずにお金を保管できるのはメリットと言えます。
- ※
- 参考:預金保険制度:金融庁
タンス預金のデメリット
タンス預金にはメリットだけでなく、次のようなデメリットがあります。
タンス預金のデメリット
- 災害や盗難などで失われる可能性がある
- タンス預金の存在を保有者が失念してしまう可能性がある
- タンス預金の独占など相続時のトラブルに繋がりやすい
特に気をつけたいタンス預金のデメリットは、相続時にトラブルの火種となってしまう可能性がある点です。
相続人が被相続人が残したタンス預金の存在に気付かないまま、相続税の申告や遺産分割協議を終えてしまうかもしれません。
こうしたケースでは、修正申告や遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、注意が必要です。
災害や盗難などで失われる可能性がある
タンス預金で注意したいのは、災害や盗難などで失われてしまうリスクがある点です。
まとまった現金を自宅で保管するのは、セキュリティの観点から金融機関に預けておくよりも盗難の可能性が高いと言えます。
盗難だけでなく火災や自然災害で自宅が被害にあった場合も、一定額しか保険の補償とならないため、多くの現金が失われてしまうかもしれません。
親族の誰かが無断で持ち出す恐れもあるため、現金を安全に保管したいのであれば、タンス預金ではなく銀行に預けた方がリスクがより少ないでしょう。
タンス預金の存在を保有者が失念してしまう可能性がある
タンス預金でまとまった現金を保管するケースでは、保有者が保管場所を忘れてしまう可能性があります。
保有者が本人しか分からない場所に現金を保管していた場合、保有者が保管場所を忘れてしまうと誰もタンス預金の存在に気づくことはできません。
また、保有者がタンス預金の存在を親族に伝えずに亡くなった場合、相続時に財産から漏れてしまう恐れがあります。
相続税申告後にタンス預金の存在が発覚すると、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが親族に課されてしまうかもしれません。
タンス預金の独占など相続時のトラブルに繋がりやすい
タンス預金の存在が発覚すると、タンス預金の有無や金額をめぐる相続トラブルが起こりやすいです。
タンス預金は資金移動の記録が残らないからこそ、相続人の一人が先んじてタンス預金を見つけた場合、他の相続人に無断で持ち出してしまう可能性があります。
タンス預金の金額を正しく証明するのは簡単ではありません。
最初の発見者ではない相続人が「本当にこれで全額だったのか」と疑い、遺産分割協議を成立させるのが難しくなってしまう恐れもあります。
タンス預金を相続時に隠した場合のリスク
相続時にタンス預金が見つかったときには、隠さず申告してください。タンス預金を隠すことには、次のようなリスクがあります。
タンス預金を相続時に隠した場合のリスク
- 税務調査の対象となる恐れがある
- 相続税の申告漏れによる追徴課税を課される可能性が高い
特にタンス預金を相続時に隠した場合の大きなリスクが、税務調査の対象となる恐れがある点です。税務調査では、自宅を訪問しての実地調査が行われます。
税務署には、さまざまなデータを参照し、必要な調査を実施する強力な権限があるため、タンス預金を隠し通すことはできないと考えておくべきです。
税務調査の対象となる恐れがある
「どうせバレない」と考えタンス預金を隠したとしても、税務調査が入って相続財産の計上漏れを指摘される可能性は高いと言えます。
税務署には納税者の情報が集まる仕組みとなっており、被相続人の所得は過去の申告状況に関するデータで把握されています。
加えて、不動産を購入した場合は登記から、死亡保険金を受け取った場合は生命保険会社からの支払調書などから、被相続人のおおよその財産情報を税務署は掴んでいます。
そのため、相続税の申告書の内容と税務署が目星をつけている被相続人の財産額に大きな差がある場合は、税務調査の対象となる可能性が高くなるのです。
タンス預金が税務署に見つかる理由
税務署は、「KSK(国税庁総合管理)システム」で納税者の情報を管理しています。KSKシステムには、被相続人の生前における所得税をはじめとする納税データが蓄積されています。
金融機関は過去10年間のデータを保管しているうえに、税務署は被相続人や相続人などの預金口座の出入金記録を調査することも可能です。
KSKシステムのデータと預金口座の入出金記録を確認すると、被相続人にどのくらいの遺産があるかの予測をつけられます。
事例
税務署の調査対象に浮上する可能性がある例
仮に被相続人が亡くなる直前に1,000万円の引出しがあった場合、同時期に車を購入していたり、老人ホームの入居金を支払ったりしていたために費消したとわかるのであれば問題はありません。
しかしながら、預金が引き出されてその1,000万円分の財産が増えていない、何に使ったのかわからない場合、調査対象に浮上することになります。
新紙幣の発行によって見つかる可能性が上昇?
令和6年7月に新紙幣が発行されました。
旧紙幣はこのまま使用することができ、親券に交換する必要はありませんが、新紙幣の流通が進むにつれて、旧紙幣は新紙幣と両替できなくなったり、対応する機械が減少したりする可能性があります。
新紙幣に対応するためにタンス預金を新券に交換すると、銀行で手続きを行う際に履歴が残ります。税務署は、被相続人や相続人の銀行口座や利用履歴を確認できるため、税務署にタンス預金の存在が見つかる可能性は高くなるでしょう。
相続税の申告漏れによる追徴課税を課される可能性が高い
税務調査により相続税の申告漏れが発覚すると、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税などの追徴課税を課されることになります。
特に、意図的にタンス預金を隠していたときには悪質な財産隠しと認定されて、重加算税を課されます。
重加算税の対象となった場合には配偶者の税額軽減が使えない
配偶者には、配偶者の税額軽減という規定により、法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい額まで相続しても相続税はかかりません。
被相続人の財産形成に配偶者が大きく貢献していることと、配偶者は被相続人と年代が同じことが多く、近く相続が発生し課税されることが予測されることから、このように優遇されています。
しかしながら、重加算税の対象となった場合、配偶者の税額軽減が適用できなくなります。そのため、「タンス預金にしておいて、バレたら配偶者が相続すれば相続税はかからない」とはならないのです。
相続時にタンス預金が見つかった場合の対処法
相続時にタンス預金が見つかった場合は、見つかったタイミングに応じて次のように対応してください。
相続時にタンス預金が見つかった場合の対処法
- 相続人に共有して財産目録に含める
- 申告後に見つかった場合は速やかに修正申告をする
それぞれの対処法について詳しく解説します。
相続人に共有して財産目録に含める
タンス預金を発見したら、各相続人に金額を共有して相続財産の目録に追加しましょう。タンス預金を隠したり、嘘の金額を伝えたりすると他の相続人が不信感を抱いて相続トラブルに繋がってしまいます。
タンス預金が見つかったときには、すぐに正確な金額を相続人に共有してください。
なお、被相続人の生前からタンス預金の存在がわかっているときには、生前から保管場所や使用した額、時期を記録しておくと、相続トラブルになる可能性はより低くなるでしょう。
申告後に見つかった場合は速やかに修正申告をする
相続税の申告後にタンス預金が発見されたときは、速やかに修正申告をしてください。
タンス預金が見つかったのに修正申告をせずにいると、意図的にタンス預金を隠したと疑われて、過少申告加算税や無申告加算税の税率が高くなったり、重加算税が課されたりする可能性があります。
申告漏れによる負担増を最小限に抑えるには、できる限り早く修正申告を行うことが重要です。
タンス預金は相続税対策にはならない!相続税対策は相続専門の税理士に相談しよう
タンス預金は、緊急で現金が必要になった場合や口座が凍結された場合の備えとしては便利なものです。しかし、タンス預金を相続税対策として利用することはできません。
タンス預金を隠そうとしても、税務署にバレる可能性は極めて高くなっています。税務署にバレると多額の追徴課税を課されるため、相続税対策としてタンス預金をすることはリスクでしかありません。
相続税の節税をしたいのであれば、相続専門の税理士にするのがおすすめです。タンス預金ではなく、生前贈与や生命保険など、追徴課税の対象とならない方法で相続税対策を提案してもらえます。