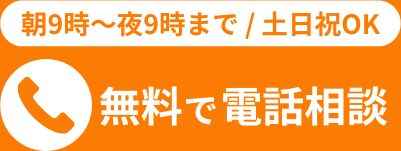記事の要約
- 生前贈与加算の対象期間延長で相続税が実質増税となる理由
- 生前贈与加算の延長による相続税増税の影響
- 過去に行われた相続税の増税
- 相続税の増税に向けてできること
2023年度税制改正では資産課税に大きな変更があり、相続税の増税につながる改正内容も含まれています。
相続税の税率や基礎控除などは変更されていませんが、贈与財産の扱いが変わるため、生前贈与を活用している人は注意しましょう。
この記事では、2023年度税制改正の内容や相続税が実質増税になるのかをわかりやすく解説します。
目次
生前贈与加算の対象期間延長で相続税が実質増税された
生前贈与加算は「相続財産への持ち戻し」とも呼ばれており、改正前の税制では、相続発生前3年以内に行われた贈与を相続財産に加算しなければなりませんでした。
本来、生前贈与したときは受贈者(受け取った人)へ財産が移転するため、贈与者(贈与した人)が死亡しても相続財産にはなりません。
しかし、生前贈与した額が相続財産に加算されると、相続税対策として贈与した意味がなくなってしまいます。
生前贈与加算は相続税対策の効果を打ち消すので、対象期間の延長は相続税の増税といえるでしょう。
では、2023年税制改正がどのような内容だったか、詳しく解説していきます。
生前贈与加算の対象期間を3年から7年に延長
2023年の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。
適用は2024年1月1日以降の贈与になるため、すでに生前贈与加算の期間延長がスタートしています。
ただし、いきなり7年間の延長ルールが適用されるわけではありません。贈与した年に応じて、4年や5年など段階的に生前贈与加算の対象期間が延長されます。
2031年1月1日以降に相続が発生したときは、過去7年間の贈与がすべて生前贈与加算の対象となります。
なお、相続財産への持ち戻し期間3年から7年への変更は影響が大きいため、延長された4年間に贈与があったときは、贈与額から100万円を控除できる経過措置があります。
生前贈与加算の延長による相続税増税の影響
生前贈与加算は暦年贈与が対象で、相続発生前の贈与を相続財産に持ち戻す計算のことです。
暦暦年贈与には年間110万円の基礎控除があるため、毎年110万円以下の贈与を長期的に続けると、1,000万円以上の非課税贈与も可能です。
ただし、生前贈与加算の対象期間中に贈与があったときは、基礎控除額以下の金額も含めて相続財産に加算しなければなりません。
では、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されると、相続税にどのような影響が出るのかみていきましょう。
生前贈与加算が3年だった場合の相続税
たとえば、生前贈与加算の対象期間が3年だった場合、以下の状況だと相続税はいくらになるのでしょうか。
- 相続発生時の課税財産:1億円
- 毎年の贈与:110万円ずつ
- 相続人:1人
相続発生前3年間の贈与(110万円×3年)は生前贈与加算するため、相続発生時の課税財産は1億330万円です。
また、相続税には以下の基礎控除があり、基礎控除額を超えた金額に対して相続税がかかります。
相続税の基礎控除
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
では、相続税がいくらになるか計算してみましょう。
- (1)基礎控除額:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
- (2)課税遺産総額:1億330万円-基礎控除3,600万円=6,730万円
- (3)相続税:6,730万円×税率30%-控除額700万円=1,319万円
相続税の税率と控除額については、国税庁ホームページで「相続税の速算表」を参照してください。
参考:相続税の税率(国税庁)
生前贈与加算が7年になった場合の相続税
生前贈与加算の対象期間が7年になると、770万円(110万円×7年)を相続財産に加算するため、相続発生時の課税財産は1億770万円です。 課税財産が1億770万円の場合、相続税は以下のようになります。
- (1)基礎控除:3,600万円
- (2)課税価格:1億770万円-3,600万円=7,170万円
- (3)相続税:7,170万円×税率30%-控除額700万円=1,451万円
生前贈与加算が3年ルールだったときと比べ、相続税は132万円(1,451万円-1,319万円)の増税となっています。
過去に行われた相続税の増税
過去の税制改正をみると、相続税率と基礎控除の改正が相続税の増税につながっています。
基礎控除の最低額はもともと2,400万円(抜本改正前)でしたが、「平成バブル」の時期に引き上げとなり、その後は以下のように引き下げられています。
- 抜本改正前:2,000万円+(400万円×法定相続人の数)
- 1988年1月1日以降:4,000万円+(800万円×法定相続人の数)
- 1992年1月1日以降:4,800万円+(950万円×法定相続人の数)
- 1994年1月1日以降:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
- 2015年1月1日以降:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
中でも2015年の改正は特に影響が大きく、相続税率も一部改正されています。当時から現在までの税制改正の歴史は以下のとおりです。
2015年の相続税率と基礎控除改正
2015年の税制改正では、相続税の基礎控除額が大きく引き下げられ、1994年の改正と比べて最低額が以下のように変わりました。
- 1994年改正の基礎控除額:5,000万円+(1,000万円×1人)=6,000万円
- 2015年改正の基礎控除額:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
基礎控除の引き下げにより、2015年の改正以降は相続税の申告件数が約2倍に増加しています。
また、2015年の改正前後では、相続税の税率も以下のように一部見直しとなっています。
- 課税価格が2億円超~3億円以下:改正前40%、改正後45%
- 課税価格が6億円超:改正前50%、改正後55%
相続税の基礎控除額の引き下げと税率の見直しによって、相続税申告の対象者が広がり、富裕層の納税額も増加しました。そのため、2015年改正は「相続税の大増税」といわれています。 社会情勢などが変われば、今後も基礎控除や税率が改正される可能性があります。
2022年の税制改正
2022年の税制改正大綱では、一部の非課税贈与の特例のみ期間延長となりました。
ただし、生前贈与加算の対象期間延長は2022年以前から議論されています。社会情勢などを考慮して実行されなかったものの、2023年改正の原型はすでにできていました。
政府は「相続税と贈与税の一体化」を目指しています。その点を踏まえると、2023年の税制改正は「増税の実行開始」とみるべきでしょう。
相続税と贈与税の一体化とは、贈与した時点では税金をかけず、相続時にまとめて課税する考え方です。
多くの諸外国の税制では、生前贈与加算の対象期間が10年や15年に設定されています。アメリカに至っては、生前に贈与されたすべての財産が相続財産へ持ち戻しとなります。
資産課税は諸外国の税制を参考にしているため、今後、生前贈与加算の対象期間が10年や15年になる可能性もあります。
相続税の増税に向けてできること

税制改正の流れをみると、相続税の増税は段階的に実行されています。
今後もさらに税負担が重くなる可能性があるので、以下の節税対策を検討してみましょう。
親が若いうちから少しずつ贈与する
暦年贈与の基礎控除は、近年の税制改正の影響を受けていません。親の年齢が若いうちから少しずつ贈与することで、贈与税や相続税を節税できます。
たとえば、50歳の親が毎年100万円ずつの贈与を70歳まで続けるとします。子どもは2,000万円を非課税で取得することになり、相続財産も2,000万円減少します。
もちろん70歳以降も非課税贈与は可能ですが、健康状態や平均寿命を考慮し見送る選択肢もあります。一定年齢に達した時点で贈与をやめると、生前贈与加算を回避できる可能性が高まります。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫への贈与を累計2,500万円まで非課税とし、贈与者が亡くなったときに制度を利用して行った贈与財産を相続税の課税対象とする制度です。
この相続時精算課税制度に、2024年1月1日から年間110万円の基礎控除が新設されました。
これまで、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、すべて相続財産に加算しなければなりませんでした。
基礎控除が新設されたことによって年間110万円以下の部分は生前贈与加算する必要はありません。
また、相続時精算課税制度は暦年贈与の課税方式と併用できないため、税制改正前は「まとまった資金を贈与したい人」など利用者が限定的でした。
しかしながら基礎控除の新設により、少額の贈与にも利用しやすくなったといえるでしょう。
推定相続人以外への生前贈与
生前贈与加算は、相続財産への持ち戻し期間内に法定相続人へ贈与した財産が対象となり、法定相続人以外への贈与は対象外です。 そのため、推定相続人以外の子どもの配偶者や孫への贈与は生前贈与加算する必要はありません。
推定相続人以外には暦年贈与で贈与し、推定相続人には相続時精算課税制度で贈与することで、効率的に相続財産を減らすことができます。
ただし、生前贈与した推定相続人以外へ遺贈によっても財産を渡す場合や、孫が代襲相続人になる場合は、生前贈与加算が適用されるので注意しましょう。
非課税贈与の特例の活用
直系尊属(父母や祖父母)が直系卑属(子どもや孫)へ贈与する場合、以下のように一定額まで非課税になる特例措置があります。 夫婦間の贈与にも特例措置があり、すべて生前贈与加算の対象外となっています。
- 教育資金の一括贈与の特例:1,500万円まで非課税(2026年3月31日まで)
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例:1,000万円まで非課税(2025年3月31日まで)
- 住宅取得資金の贈与の特例:最大1,000万円まで非課税(2026年12月31日まで)
- 贈与税の配偶者控除:2,000万円まで非課税
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、受贈者の専用口座に贈与者が入金し、その後、学費などの領収書と引き換えに出金するしくみです。
受贈者が一定年齢に達したときや、贈与者が亡くなったときに残額があると、贈与税や相続税がかかるので注意しましょう。
相続や遺贈による財産承継
相続発生後には以下の特例を利用できるので、生前贈与しなくてもよいケースがあります。
- 相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減):1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかからない制度
- 小規模宅地等の特例:自宅の敷地評価額を最大80%減額できる制度(限度面積330㎡)
十分な節税効果があれば、あえて贈与は行わず、相続や遺贈で財産を渡してもよいでしょう。
なお、小規模宅地等の特例は被相続人が事業を行っていた宅地や、賃貸アパートなどを建築している貸付事業用宅地にも適用できます。
専門家に相続税対策を相談する
専門家に相続税対策を相談すると、今後の税制改正にも柔軟対応してくれます。
生前対策は、ご本人や家族の意向に沿った適切な方針を立てることが難しい事柄です。相続税対策は税理士に提案してもらうとよいでしょう。
たとえば、一部の贈与税の特例は、たびたび税制改正によって適用要件が変わっています。従来の考え方で贈与すると、高額な贈与税を納めることになりかねません。
また、生前贈与加算の対象期間がさらに延長されると、まとまった資金をすぐにでも贈与しなければならない状況になります。
不動産を贈与するときは不動産取得税がかかるうえに、登録免許税の税率も高くなります。したがって、相続税や贈与税以外の税金もよく理解しておく必要があります。
相続税対策として生前贈与を活用する場合、いつ・誰に・何を・いくら贈与するかで節税効果が変わります。税理士のアドバイスを参考にすることをおすすめします。
相続税の増税の可能性に備えて専門家に相談しよう
2023年度税制改正により、生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたため、贈与してから7年経たなければ相続税対策の効果が出なくなっています。
相続財産への持ち戻しの7年ルールが完全に適用されるのは2031年1月1日以降ですが、経過措置の期間中に相続が発生すると、「4年6カ月」などの月単位で過去の贈与を遡らなければなりません。
効果的な生前贈与は今後さらに難しくなる可能性があります。VSG相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士、行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。生前贈与などの相続税対策についてお気軽にご相談ください。