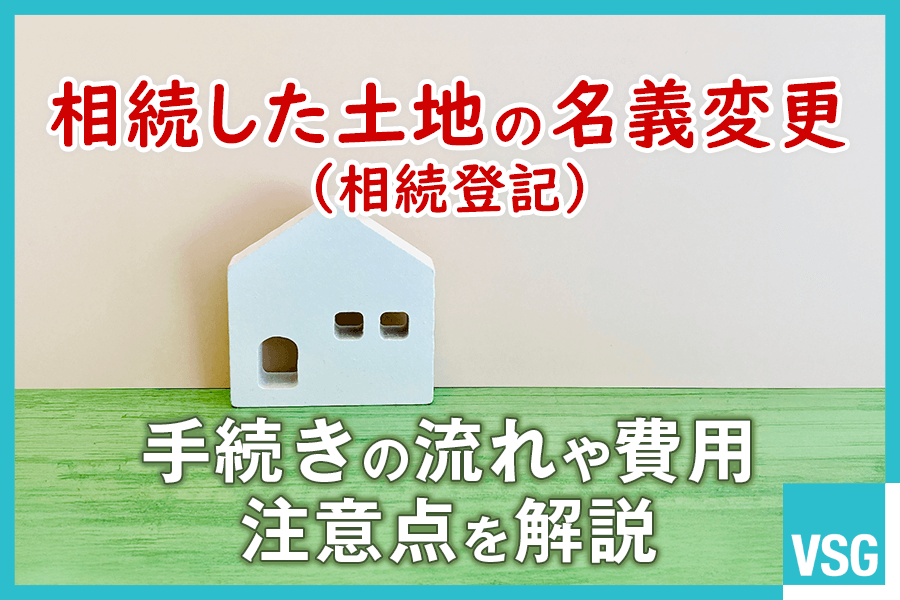この記事でわかること
- 相続した土地の名義変更の手続き期限
- 土地の名義変更の手続きの流れ
- 名義変更手続きをしなかったらどうなるか
土地の相続は、人生において何度もあることではありません。「何から始めれば良いのか」「どのような書類が必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、多くの疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。特に、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、より一層正確な知識と迅速な対応が求められるようになります。
この記事では、土地の相続が発生した際に必要な法務局での名義変更手続きの全体像から、必要となる書類、発生する費用、そして共有名義の場合の注意点まで、専門家でなくても理解できるよう丁寧に解説します。
目次
相続や遺贈による土地の取得には名義変更(相続登記)が必要
不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を被相続人(亡くなった人)から相続人に名義変更します。
名義変更の正式名称は「所有権移転登記」といい、法務局で所有権移転登記申請をすることで登記簿の所有者を変更します。
このような相続の発生をきっかけにして行う所有権移転登記のことを、「相続登記」と呼びます。
相続登記は2024年より手続きが義務化された
2024年より相続登記が義務化された背景には、人口減少や社会の高齢化、地方から都市部への人口移動等により、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加したことが挙げられます。
日本の所有者不明土地の面積を合わせると、約410ヘクタールに及ぶとされ、九州地方の面積よりも広いといわれています。
所有者不明土地には、所有者が分からないことで発生するデメリットが複数あります。たとえば、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者不明なことから工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまう恐れがあります。
また、公共事業や市街地開発などを目的とした用地買い取り交渉も所有者不明だと行えないため、土地の有効活用の妨げになってしまいます。
所有者不明土地が発生する要因の一つが相続登記が行われないことであるため、相続により不動産を取得した人は、2024年4月より、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う
相続登記は、相続したことを知った日から3年以内に行なわなければなりません。この「知った日」とは、「相続開始があったこと」と「該当する不動産の所有権を取得したこと」の両方を知った日のことを指します。
そのため「自身が相続人である」と認識している相続人であっても、被相続人がその不動産を所有している事実を知らなかった場合、登記義務は発生しません。
たとえば、遺産分割協議の成立によって不動産を取得した場合、被相続人がその不動産を保有していると知らなかったような場合を除き「相続開始を知った日から3年以内」に登記申請をする必要があります。
過去に相続した土地も2027年3月末までに名義変更が必要
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。早めに登記の申請をしましょう。
相続した土地の名義変更手続きの流れ
相続による土地の名義変更をするにあたって、まずは被相続人が所有していた不動産の洗い出しを行います。
不動産所有者の自宅に届く「固定資産税の課税明細書」などから、被相続人が所有していた不動産を確認しましょう。その後、「相続人が所有していた土地を誰が取得するのか」を決定したうえで、必要書類を準備し、法務局へ申請します。
- Step1:土地の取得者を決定する
- Step2:必要書類を収集する
- Step3:申請書を作成して管轄の法務局に提出する
- Step4:登記識別情報通知を受け取る
Step1:土地の取得者を決定する
被相続人が遺言書を残している場合、その通りに遺産分けを行います。
一方、遺言書を残していない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合い、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
なお、遺産分割協議書を作成して相続登記を行う場合、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
Step2:必要書類を収集する
相続による土地の名義変更では「登記申請書」と「不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)」を用意したうえで、以下の書類が必要となります。
- 戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
- 住民票の除票
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
なお、状況によっては他の書類も必要となります。法務局の「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」でより詳しく確認することができます。
Step3:申請書を作成して管轄の法務局に提出する
必要書類を揃えたら「登記申請書」を作成して、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
登記申請書は専用用紙があるわけではなく、自身で作成します。
法務局のウェブサイトから相続登記用のひな型をダウンロードすることができ、手書きでもパソコンでもかまいません。
Step4:登記識別情報通知を受け取る
相続登記が完了すると「登記識別情報通知」という書類が発行されます。
登記識別情報通知は、以前「権利書」「権利証」などと呼ばれた書類に代わるもので、土地や建物の登記名義人となった人ごとに定められ、登録名義人となった人にのみ通知されます。
この情報を知る人は不動産の登記名義人とみなされます。他人には絶対に内容を知られないようにしましょう。
なお、登記識別情報通知は登記完了から期限内に受領が必要となります。期限が過ぎると破棄されてしまう可能性があるため、注意してください。
相続した土地の名義変更をしていないとどうなるか
相続や遺贈で土地を取得したにもかかわらず、名義変更を放置し続けた場合、その土地を売却したり、担保として融資を受けることができないといった不都合が生じることもあります。
また、相続登記が義務化されたことから、正当な理由なく怠ると罰金が科せられます。
ここからは、「相続した土地の名義変更をしていないとどうなるか」について詳しく解説します。
- 10万円以下の過料が科される可能性がある
- 売却や担保の設定ができない
- 所有権を第三者に主張できない
- 共有者の死亡により権利関係が複雑になる
10万円以下の過料が科される可能性がある
相続登記が義務化されたことで、正当な理由なしに登記をしていない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月よりも前に相続が発生した場合であっても相続登記は義務ですので、早めに登記申請をしましょう。
なお、過料が科されたにもかかわらず支払いを無視し続けた場合は、不動産をはじめとする財産を差し押さえられる恐れもあります。
売却や担保の設定ができない
相続登記をしていない場合、その不動産の登記簿上の所有者が被相続人のままであることから、売却ができません。
不動産を売却する場合、買主側は購入代金を払う相手が本当に土地の所有者であるかどうかを確認してから支払うこととなります。このときに不動産の名義が売主と違うと、払うわけにはいかないでしょう。
また、土地を担保に入れてお金を借りることもできません。
土地を担保に融資を受ける場合など、法的な権利関係を明確にする必要があるケースでは、相続登記が済んでいないと手続きが進められないことがあります。
所有権を第三者に主張できない
たとえ遺産分割協議で合意していなくとも、相続人は自身の法定相続分であれば、単独で相続登記をすることが可能です。
登記の一般原則として、不動産の所有権を主張する人が2人現れた場合、権利主張の優劣は登記の先後で決められることになります。
このため、先に法定相続分で登記を済ませた相続人が所有権を第三者に売却した場合、仮に遺産分割協議で「その不動産の権利を単独取得したい」と他の相続人が主張したとしても、第三者である名義人にはそのように主張することができなくなってしまいます。
自己の権利を守るためにも登記は重要です。
共有者の死亡により権利関係が複雑になる
土地を複数人で共有している場合に相続登記を怠ると、共有者の一人が亡くなった場合に次の相続が発生し、相続人が増えてしまうことがあります。
共有者である相続人の一人が亡くなると、その相続人の次の相続人に共有持分の所有権が移るため、土地の権利者が増えることになります。
そのため、手続きに関係する人の人数が増え、必要な書類を揃えたり、処分するのか、活用するのかを決めることもままならなくなります。
相続した土地の名義変更にかかる費用
相続登記には、登記に必要な戸籍や住民票を収集するための費用と、登録免許税が必要となります。主な必要書類の取得費用の目安は、以下の通りです。(※発行する自治体によって異なります。)
- 戸籍謄本:1通 450円
- 除籍謄本:1通 750円
- 改製原戸籍:1通 750円
- 戸籍の附票:1通 300円
- 住民票:1通 300円
- 印鑑証明書:1通 300円
- 固定資産評価証明書:1通 300円
- 登記簿謄本(全部事項証明書):1通 600円
また、登記申請には登録免許税を納める必要があり、相続による所有権移転登記の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が税額です。
なお、相続登記の手続きの代行を司法書士に依頼すると、上記の他に司法書士への報酬が6万円から15万円ほど発生します。
相続登記の登録免許税の免税措置(時限措置)
2027年までの時限措置ですが、相続または遺贈により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に亡くなった場合には、2027年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。
相続した土地の名義変更のよくある質問
ここからは、相続した土地の名義変更に関する「よくある質問」にお答えします。
- 個人で名義変更はできる?
- 手続き期限までに所有者が決まらない場合はどうしたらいいの?
- 不動産の共有者を把握できない場合はどうしたらいいの?
個人で名義変更はできる?
可能ですが、登記申請までに法務局に出向く必要があります。
通常、1回から2回ですが、書類の不備などにより出向く回数が増えることがあります。お仕事をお持ちの方には少々きびしいかもしれません。
手続き期限までに所有者が決まらない場合はどうしたらいいの?
「遺産分割協議がまとまらず、所有者が決まらない場合」や、「相続人が極めて多数であり、戸籍謄本等の収集や相続人把握に時間が必要である場合」は「相続人申告登記」をすることで、簡易に義務を履行できます。
相続人申告登記をしたあとに遺産分割協議が成立するなど、権利者が明らかとなった場合には相続登記をする必要があります。
不動産の共有者を把握できない場合はどうしたらいいの?
「登記事項証明書」を取得し、現在登記されている共有者の戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を特定します。
ただし、相続人の人数が多いと書類の取得に手間がかかるなどして非常に大変です。司法書士に依頼した方がよいでしょう。
相続登記に不安がある場合は司法書士に相談しよう
相続登記は2024年4月から義務化され、怠ると過料が科されることもあります。土地を相続したら必ず相続登記を行いましょう。
相続登記は自分でも可能ですが、手続きに不安を感じたり、時間がないと感じる場合は、迷わず司法書士に相談してください。
あなたの状況に合わせた最適なサポートを受けることで、スムーズかつ確実に相続登記を完了させることができます。