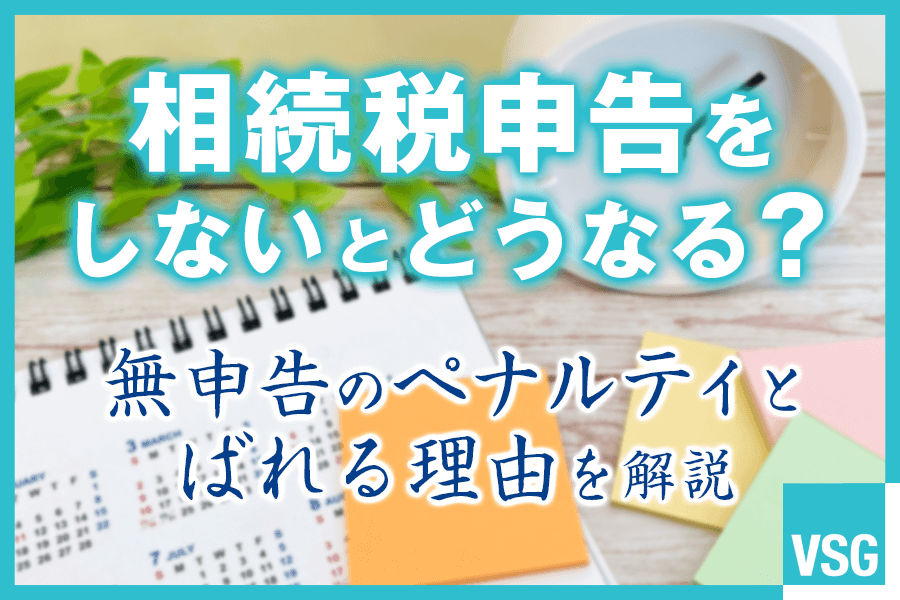この記事でわかること
- 相続税申告をしない場合に課されるペナルティの種類と内容
- なぜ相続税の無申告が税務署にバレてしまうのか
- もし無申告だった場合にどう対応すればよいのか
相続が発生し、被相続人の財産を受け継いだ際、誰もが相続税の申告が必要になるわけではありません。しかし、申告が必要なケースで無申告の場合、思わぬペナルティが課されるだけでなく、税務署からの厳しい調査を受けることになります。
「もしかして、うちも相続税の申告が必要だったの?」
「申告しなくても税務署にはバレないんじゃない?」
もしそう思われているのであれば、それは非常に危険な考えです。この記事では、相続税の無申告がなぜバレるのか、そして無申告が発覚した場合にどんなペナルティが課されるのかを詳しく解説します。
目次
相続税申告が必要なのに無申告だとどうなる?
相続税申告は、相続が発生したすべてのご家庭で必要となるわけではありません。しかし、もし申告義務があるにもかかわらず無申告だった場合、重いペナルティが課される可能性があります。
すべての家庭で相続税申告が必要となる訳ではない
相続が発生した際に、必ずしも相続税の申告が必要になるわけではありません。相続財産の総額が、相続税の基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額
例えば、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が基礎控除額となります。遺産総額がこの金額を超えないのであれば、相続税の申告は必要ありません。
申告期限を過ぎたことに対するペナルティが課される
相続税の申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告を行わなかった場合、さまざまなペナルティが課されることになります。
相続税申告の期限は相続発生から10カ月以内
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10カ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、後述する加算税や延滞税といったペナルティの対象となります。
税務調査が行われる可能性がある
相続税の無申告が税務署に発覚した場合、税務調査が行われる可能性が極めて高くなります。税務調査では、被相続人の財産状況や過去の資金の流れ、相続人の預金なども詳細に調べられ、隠れた財産がないか徹底的に確認されます。
無申告の場合に課されるペナルティの種類
相続税の申告を怠った場合、通常の相続税に加えて、以下の税金がペナルティとして課されます。
無申告加算税
無申告加算税は、相続税の申告期限までに申告を行わなかった場合に課される税金です。税務署からの指摘を受けて申告した場合と、自主的に期限後申告を行った場合とで税率が異なります。
- 税務調査通知前(自主的に期限後申告した場合):本来の税額の5%
- 税務調査通知後:本来の税額が50万円以下の部分は10%、50万円を超えて300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%
- 税務調査等で指摘された後:本来の税額が50万円以下の部分は15%、50万円を超えて300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%
延滞税
延滞税は、相続税の納付が期限に遅れた場合に課される利息のような性質を持つ税金です。申告期限の翌日から、実際に納税するまでの日数に応じて発生し、税率はその時の金融情勢などにより変動します(概ね数%から10%程度で推移)。
過少申告加算税(申告しているが漏れや評価間違いがある場合)
過少申告加算税は、相続税の申告はしたものの、申告した財産が実際よりも少なかった場合(一部の財産があとから出てきた、間違えて低い評価額で計算していたなど)に課される税金です。
無申告加算税と同様に、自主的に修正申告を行った場合と、税務調査で指摘された場合とで税率が異なります。
- 税務調査通知前(自主的に修正申告した場合):課されない
- 税務調査通知後:50万円以下の部分は不足税額の5%(期限内申告税額が50万円超であれば期限内申告税額以下)、50万円超の部分は10%(期限内申告税額が50万円超であれば期限内申告税額超の部分に対して)
- 税務調査等で指摘された後:50万円以下の部分は(期限内申告額が50万円超であれば期限内申告税額以下)不足税額の10%、50万円超の部分は(期限内申告税額が50万円超の場合期限内申告税額超の部分に対して)15%
重加算税(無申告であることが悪質な場合)
相続財産を意図的に隠したり、仮装したりするなど、悪質な手口で相続税を免れようとした場合に課される、最も重いペナルティです。通常の加算税に代わって課され、税率は非常に高くなります。
- 無申告の場合:本来の税額の40%
- 過少申告の場合:不足税額の35%
相続税の無申告は税務署にバレる可能性が高い
「申告しなくても、まさかバレないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、相続税の無申告は税務署にバレる可能性が極めて高いのが実情です。税務署は、その高い調査能力と多様な情報源を駆使して、相続税の申告漏れがないか常に目を光らせています。
税務署は調査能力が高い
税務署は、さまざまな機関から情報を収集し、その情報を分析する独自のシステムを持っています。
死亡情報と税務署の連携
役所に死亡届が提出されると、その情報は税務署にも連携されます。これにより、税務署は「相続が発生した」ことを把握します。また、被相続人の所有していた固定資産の内容、評価額も税務署に通知されます。
金融機関からの情報
銀行や証券会社などの金融機関は、税務署からの照会に対して、被相続人の預貯金口座や証券口座の履歴、高額な入出金といった情報を開示する義務があります。これにより、被相続人の生前の資金の流れや、相続発生時の残高が明らかになります。
不動産の登記情報
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記が行われた際にその情報が法務局から税務署に伝わります。
過去の申告情報との照合
被相続人が過去に提出した所得税の確定申告書や贈与税の申告書、会社に提出された扶養家族の情報など、税務署が持つあらゆる情報と照らし合わせることで、相続財産の全容や生前の資金移動を推測します。
KSK情報システム
税務署は「国税総合管理(KSK)システム」という情報システムを運用しています。このシステムは、国民の所得や資産に関する膨大な情報を一元的に管理・分析しており、過去の申告状況、金融資産の変動、不動産の取得・売却履歴など、さまざまな情報を把握することができます。
これにより、生前の所得や相続による財産形成を類推することが可能です。
周囲からの情報提供
税務署への情報提供は、何も公的な機関だけではありません。時には、周囲からの情報提供(いわゆるタレコミ)によって無申告が発覚するケースもあります。親族間のトラブルや、被相続人の財産状況を知る知人などから、税務署に情報が寄せられることも少なくありません。
無申告のまま申告期限が過ぎてしまった場合の対処方法
もし、相続税の申告期限が過ぎてしまっていても、諦める必要はありません。適切な対処をすることで、ペナルティを軽減できる可能性があります。
期限後申告は可能か?
相続税の申告期限が過ぎてしまった場合でも、期限後申告を行うことは可能です。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告を行うことで、ペナルティを抑えることができます。
税務署から指摘される前に自主的に申告するメリット
税務署からの指摘を受けてから申告するのと、自主的に期限後申告を行うのとでは、課されるペナルティに大きな違いがあります。
具体的には、無申告加算税の税率が大幅に軽減されます。 税務署からの連絡を待つよりも、ご自身で早めに動くことが、結果として納税額を抑えることに繋がります。
相続税に強い税理士に相談する
相続税の申告は非常に複雑であり、特に期限が過ぎてしまっている場合は、財産評価から申告書の作成、税務署との対応まで、専門的な知識が不可欠です。
もし無申告の状況にあるのであれば、相続税に強い税理士に早めに相談することをおすすめします。 税理士は、お客様の状況を正確に把握し、適切な期限後申告の手続きをサポートします。また、税務署からの問い合わせや税務調査にも、お客様の代理として対応することが可能です。
相続税申告が必要か迷う場合は、専門家に相談しよう
相続税の申告は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの経験です。そのため、「自分の場合は申告が必要なのか」「どのくらいの税金がかかるのか」など、判断に迷うことも多いでしょう。
もし少しでも不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。 私たち税理士は、お客様の状況に合わせて相続税の計算や申告の要否を判断し、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。