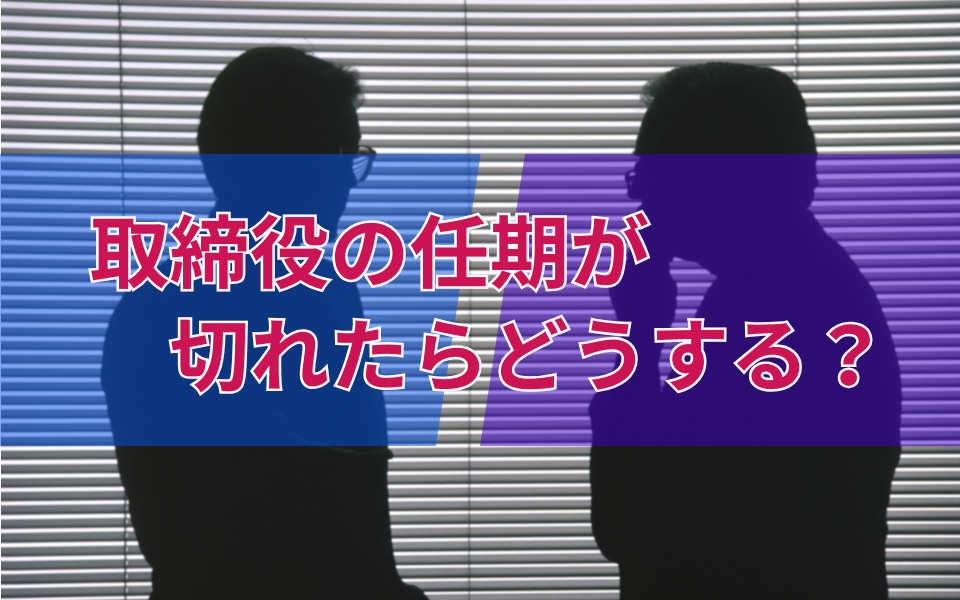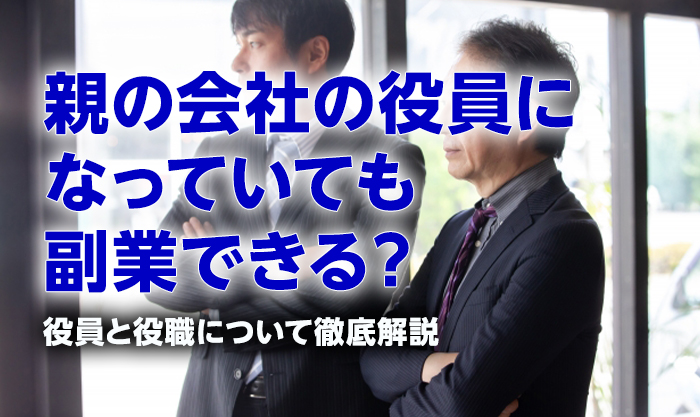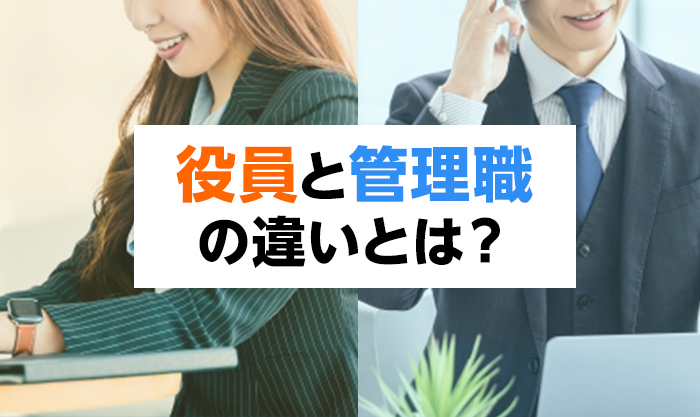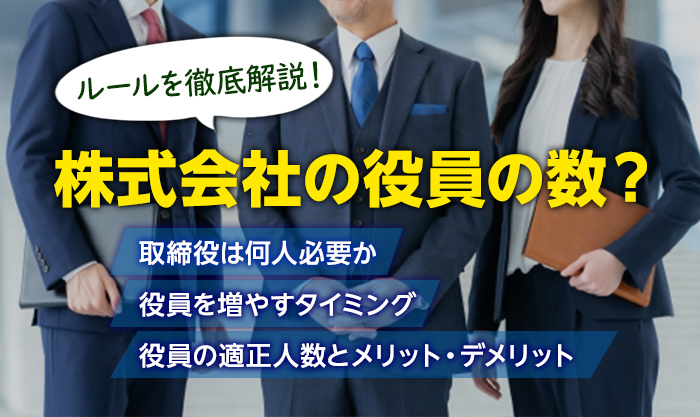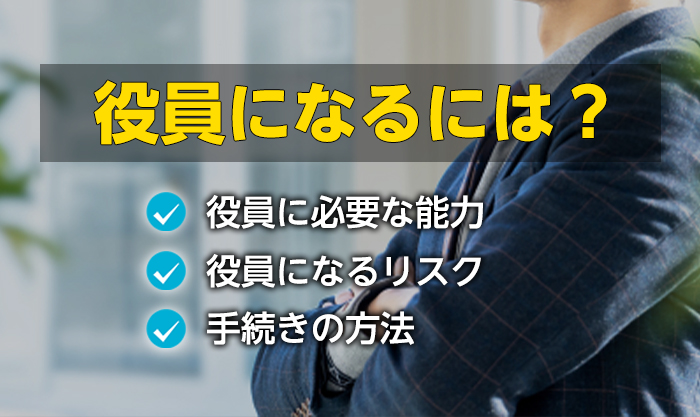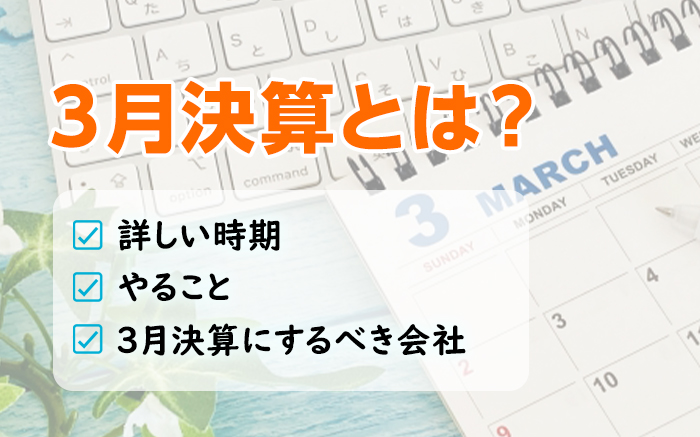最終更新日:2025/4/21
役員は失業保険がもらえない?役員と雇用保険の関係を解説します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
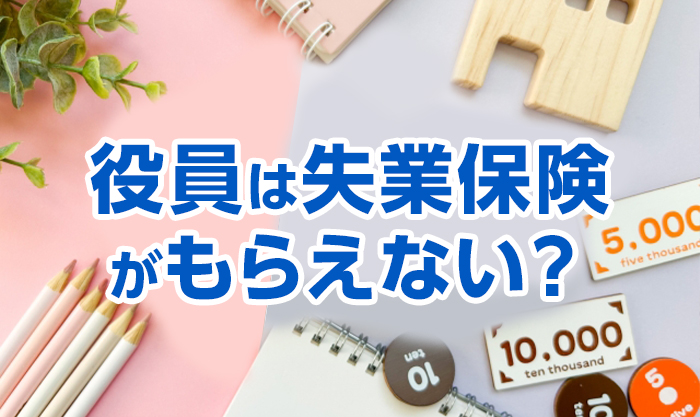
この記事でわかること
- 役員が失業保険をもらえない理由
- 例外的に失業保険をもらえるケース
- 労働者性について
労働者は、失業したときに失業保険(失業手当)を受け取ることができます。これは雇用保険に加入しているためです。しかし、役員は労働者ではなく、会社の経営に関わる立場にあるため原則として失業保険を受給することができません。
しかし、役員であっても「使用人兼務役員」としての労働実態が認められる場合などは、例外的に雇用保険に加入できるケースもあります。
この記事では、役員が失業保険を受け取れない理由や、受給できる条件について詳しく解説します。これから役員になる予定の人にも、いつか役員になりたいという人にも参考にしてほしい内容です。知っておいて損はない雇用保険のしくみを正しく理解しておきましょう。
目次
役員は原則として失業保険がもらえない
会社の役員は、一般の労働者とは異なり、原則として会社を辞めても失業保険を受け取ることはできません。
ここでは、役員が失業保険をもらえない理由について詳しく解説します。
雇用保険の対象にならない
失業保険は、一定の条件を満たす雇用保険加入者がもらえるものです。この雇用保険は、労働者が失業したときのためにつくられた制度です。
そのため、雇用保険の対象は「労働者」 に限られます。「雇用保険」という名前からもわかるとおり「雇用されて労働している人」のための保険制度なのです。
労働基準法では、労働者とは、事業主に使用され賃金を支払われる者とされています。雇用されていない役員は雇用保険の対象ではないため、失業保険ももらえないのです。
なぜ役員は失業保険がもらえないのか
会社のために業務を行なっているにもかかわらず、役員はなぜ失業保険をもらえないのでしょうか。
役員は会社に雇用されていない
役員は、委任契約を結んで業務をしています。つまり会社から雇用されていないのです。
一方で従業員は会社と雇用契約を結んで労働しており、労働基準法という法律で守られています。どちらの契約も会社のために業務を行うという目的は同じですが、契約の内容が異なります。
| 労働者 | 役員 | |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用契約 | 委任契約 |
| 所得の種類 | 労働の対価としての給与 | 株主総会で決められた報酬 |
| 解雇・解任 | 労働基準法に基づく | 株主総会の決議に基づく |
役員は会社の偉い人というイメージがあるため、従業員のトップだと勘違いしやすいのですが、従業員ではないのです。
失業保険などの雇用保険は労働者のための制度
失業保険は、雇用保険という保険制度の一部です。
失業してから再就職するまでの間の生活を支えるためのもので、雇用されている労働者を守るために作られました。雇用保険は「給与」を受け取っている労働者のためのものなのです。
委任契約のもとで会社を経営する役員は労働者ではないため、この制度の対象になっていないのです。
委任契約を結んでいる役員、代表権がある者は雇用保険には加入できません。
昇進して役員になった場合
社内で昇進して役員になった場合、今までの雇用契約から委任契約に変わることになります。
雇用契約は終了しますが、役員として委任契約に変わるため、失業状態になく、失業保険はもらえません。
「今まで支払ってきた失業保険がもったいない」と感じるかもしれませんが、失業保険は掛け捨ての保険に近いと認識するとよいかもしれません。もちろん、掛け捨ての保険とは異なる部分もありますが、「万が一、失業したときのための公的な保険」と考えることができます。
ただし、役員に昇進した後すぐに退職した場合など、失業保険がもらえるケースもあります。
例外!役員でも雇用保険に加入できるケース
前述のとおり、役員は失業保険を受け取ることができません。ですが、例外的に雇用保険に加入できることがあります。
労働者としての実態がある
役員でも、労働者としての実態があるケースがあります。
この場合、条件を満たせば、雇用保険に加入し、失業保険を受給できることがあります。
労働者性とは?
役員が雇用保険に加入するときにポイントとなるのが労働者性です。
会社との雇用契約があり労働者性があると判断されれば、雇用保険に加入できるケースがあります。
- 事業主の指揮命令に従っている
- 就業実態がある
- 他の労働者と同様に賃金が発生している
- 事業主と利益を一つにする地位(取締役等)にない
上記の条件を満たしている場合は、労働者性があると判断されて雇用保険に加入できるケースがあります。
役員でも雇用保険に入れる条件
社内で昇進して役員になった場合でも、原則として雇用保険には加入できません。ですが、例外的に加入できるケースがあります。「使用人兼務役員」などがこれに該当します。
例えば、役員として登記されているものの実際には現場の「管理職」として働いているということもあります。特に、中小企業などで多く見られるケースです。
役員という立場にあっても労働条件や給与が従業員と同様とされる場合「使用人兼務役員」となります。
役員報酬より給与が多い
役員報酬より労働の対価として得る給与の方が多い場合は、労働者の立場で働いている実態があるといえるでしょう。
- 役員報酬がない
- 役員報酬より給与が多い
- 一般の従業員と同じように労働者の対価として給与を受け取っている
- 給与の支払いが就業規則に基づいている
このような場合は、役員であっても「使用人兼務役員」として認められる可能性があります。
就業規則の適用がある
使用人兼務役員は労働者であるため、会社の就業規則を守って働いている実態が必要です。
委任契約のもとで働く役員の場合、会社の就業規則は適用されず働く場所や時間は制限されません。一方、雇用保険を結んでいる従業員は就業規則に従う必要があります。
勤務時間をタイムカードやシフト表などで管理している場合や、会社の勤務時間に合わせて働いている場合は、就業規則に従っているといえるでしょう。
役員が雇用保険に加入する場合の「労働者性」の根拠として就業規則の適用もポイントになります。
代表権と業務執行権がない
使用人兼務役員は、代表権や業務執行権を持っていません。
役員として会社の経営判断を行なっている人や、代表者とともに重要な意思決定を行なっている人は、労働者ではなく経営者です。
また、監査役も労働者と兼ねることはできません。
兼務役員が雇用保険に入るときの手続き
「使用人兼務役員」は、会社の役員でありながら、一般の従業員と同様に就業規則に従い労働し、給与を受け取っています。ここでは、そんな使用人兼務役員が雇用保険に加入する際の手続きを解説します。
通常、役員は雇用保険に加入できませんが、労働者としての実態があると認められた場合は雇用保険に加入できます。
このような場合、役員としての業務と労働者としての業務が明確に区別されているという書類が必要です。
労働者性を判断するための書類が必要
役員が例外的に雇用保険に加入するには、労働者としての実態を証明するために以下の書類を求められるケースがあります。
- 就業規則
- 賃金規定
- 資格取得届
- 取締役会議事録
- 定款
こうした書類を客観的な判断材料として、役員報酬と給与が明確に分かれているか、労働者としての地位があるかが判断されます。
役員報酬と給与の分け方
役員が例外的に雇用保険に加入するためには、役員報酬と給与が分かれていることが重要です。
役員報酬は、会社の経営判断を行う役員としての業務や成果に対する報酬です。一方で、給与は労働の対価として支払われる賃金です。
使用人兼務役員が役員報酬も給与も受け取っている場合は、労働者としての給与と役員報酬が明確に区別されている必要があります。役員報酬に関する株主総会の決定、委任契約の内容、そして就業規則と業務の範囲を明確にすることで、役員報酬と給与を区別できます。
みなし役員の場合
みなし役員とは、登記されていないものの、会長や副会長といった立場で「実質的に経営判断をしている人」のことです。
みなしであっても役員
みなしであっても、役員は労働者ではないため原則として雇用保険に加入できません。したがって、失業保険ももらえません。
みなし役員とされる条件としては、会社の経営判断をしているかや経営に従事しているか、社内での地位・役割がポイントとなります。
役員とは会社法上の役員
ここまで、役員の雇用保険や失業保険について解説してきましたが、そもそも「役員」とはどのような立場なのでしょうか。
会社法上の役員とは
誰が「役員なのか」については、会社法で決められています。会社法上の役員は「取締役・監査役・会計参与」です。会社法上の役員は、会社や第三者に対して法的な責任を負っています。
また、会社法上の役員は株主総会の決議で選任され、登記も必要です。
役員に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
執行役員
役員という名前の役職に「執行役員」があります。執行役員は、会社の上層部であることは間違いないのですが、会社法上の役員ではありません。
執行役員は、現場の管理職と経営陣である取締役の中間に位置するポジションであることが多く、株主総会の決議ではなく社内の人事によって昇進して与えられる役職です。
会社法上の役員ではないため登記の必要もなく、執行役員になったあとも雇用契約を維持したまま働くケースもあります。会社との契約が雇用契約であり、就業規則に従って働いている場合、社内の役職が「執行役員」であっても雇用保険に加入できます。
ただし、役職が執行役員であっても、会社の経営に関与していると、雇用保険の対象外となるケースもあります。
雇われ社長・役員
株を持っていない雇われ社長や役員、また、名前だけ登記されている役員であっても、原則として雇用保険には加入できず失業保険を受け取ることはできません。
雇用契約を結んで社長などの役職にある場合は「労働者としての実態」が雇用保険の適用を判断するポイント になります。
役員の失業保険以外の保険について
役員は、一般の労働者とは異なり雇用契約ではなく委任契約で働くため、雇用保険の対象外 となります。そのため、会社を辞めても失業保険を受け取ることはできません。
しかし、雇用保険以外の保険については、日本の法律で加入が義務付けられているものがあります。 ここでは、役員が必ず加入しなければならない健康保険、厚生年金保険、介護保険について詳しく解説します。
強制加入の保険
日本では、すべての国民が何らかの公的な健康保険に加入しなければならない制度(国民皆保険制度)が採用されています。そのため、会社の役員や代表者であっても健康保険の加入が義務付けられています。
また、介護保険についても40歳以上の人は必ず加入しなければなりません。さらに、役員でも年金制度に加入しなければならず、厚生年金保険または国民年金にも加入する必要があります。
健康保険に関しては、会社が健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している場合、役員もその健康保険に加入することとなります。また、厚生年金保険にも加入することとなります。
役員は原則として失業保険をもらえない
役員は、雇用保険で働く従業員とは異なり会社と委任契約を結んで業務を行うため、原則として雇用保険の対象外になります。そのため、失業したときにも失業保険を受給できません。
しかし「使用人兼務役員」としての労働実態がある場合や、雇用契約を維持している場合は、雇用保険の適用対象となるケースがあります。。また、委任契約であっても、健康保険や厚生年金保険については加入が義務付けられています。
役員が雇用保険に入れるかどうかの条件や例外を理解し、適切な保険制度の利用を検討しましょう。