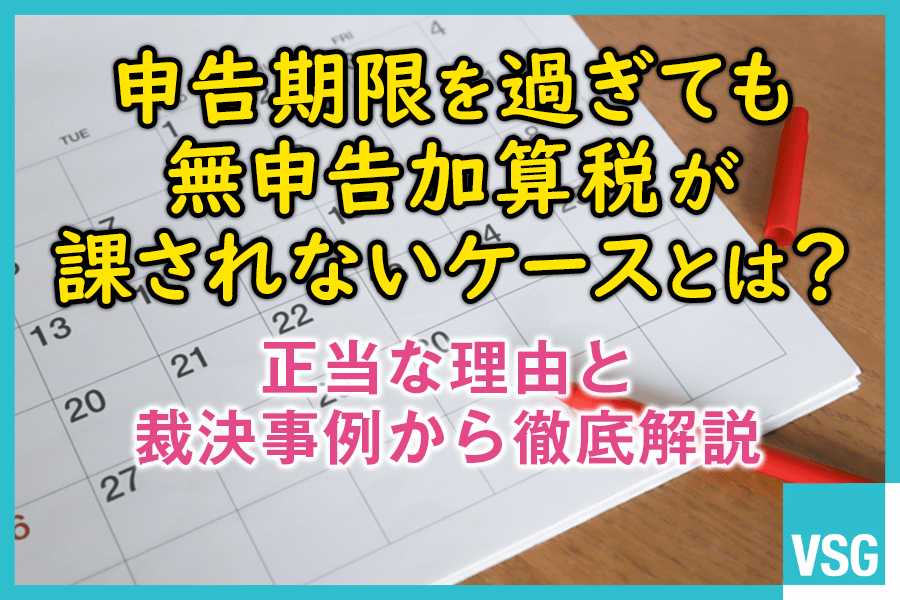目次
無申告加算税とは何か
無申告加算税とは、法定申告期限までに申告をしなかった場合に、本税(相続税や贈与税など)にペナルティとして加算される税金です。
この制度は、納税義務の履行を促すために設けられたもので、国税通則法第66条第1項に規定されており、法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は課されません。
加えて、同条ただし書きでは、「期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。」とされており、「正当な理由」がある場合には、無申告加算税が課されない可能性もあります。
この記事では、「期限を過ぎたが無申告加算税が課されないケース」 に焦点をあて、法令・通達・裁決・判例をもとに、実際の判断基準や対応策をわかりやすく整理します。
【令和7年1月17日裁決】相続税の期限後申告と無申告加算税の判断
令和7年1月17日に出された国税不服審判所の裁決では、相続税の期限後申告に対して無申告加算税が課された事案が争点となりました。
事案の概要
請求人は、原処分庁(税務署)の調査を受けて相続税の期限後申告書を提出しましたが、その後、無申告加算税の賦課決定を受けました。これに対し請求人は、「法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことには正当な理由がある」と主張し、当該賦課決定処分の取り消しを求めました。
請求人は、交際関係にあった勤務先の歯科医師から死因贈与を受けており、本来は相続税の申告義務がありました。しかし、被相続人の配偶者および息子といった相続人の協力を得られず、相続財産の総額を把握できなかったことから、法定申告期限内に申告書を提出できなかったとしています。結果として、税務署から無申告加算税の賦課決定を受けました。
請求人の主張
請求人は、相続人に対して相続財産の総額の開示を求めたものの、協力を得られず拒否されたため、基礎控除額を超える額の相続財産を把握できなかったと主張しました。
その結果、申告期限までに相続税の申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書きに定める「正当な理由」があるとして、無申告加算税の賦課決定処分の取り消しを求めました。
審判所の判断
審判所は、請求人が法定申告期限内に相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書きに定める「正当な理由」があるとは認められないと判断しました。
その理由として、請求人の主張は、請求人と相続人らとの人間関係に起因する主観的な事情であって、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情とはいえないと指摘しました。
さらに、被相続人は歯科医師として歯科医院を営んでいたことから、請求人が管理していた預金口座以外にも、多くの預貯金や不動産などの財産があったと認識できたと判断。したがって、相続財産に係る課税価格の合計額が基礎控除額を超えると認識できたにもかかわらず、法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、正当な理由があるとは認められないと結論づけました。
正当な理由とは?
国税通則法第66条第1項における「正当な理由」とは、申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、納税者の責めに帰することができない客観的な事情を指します。
国税庁が公表している「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」では、無申告加算税の取り扱いについて次のように定められています。
通則法第66条第1項の正当な理由があると認められる事実
(注)相続人間に争いがある等の理由により、相続財産の全容を知り得なかったこと又は遺産分割協議が行えなかったことは、正当な理由に当たらない。
つまり、自然災害や交通・通信の途絶など、物理的に申告書を提出できない事情があった場合、または行政庁の誤案内や誤証明により申告が不可能となった場合など、納税者に責任のない客観的な理由がある場合は、「正当な理由」として認められる可能性があります。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 地震や豪雨などの自然災害により、申告書を期限までに作成・提出できなかった
- 道路・鉄道などの交通の途絶により、申告書の提出が物理的に不可能だった
- 法務局が誤った法定相続情報一覧図の交付するなど、行政庁の誤証明により提出が困難となった
一方で、次のような事情は「正当な理由」には該当しません。
- 相続人間の不仲や対立により、財産の内容を把握できなかった
- 遺産分割協議がまとまらず、申告書を作成できなかった
- 体調不良・入院・多忙など、個人的・主観的な事情
- 税理士との意思疎通不足や依頼の遅れ
このように、「正当な理由」と認められるのは、法定申告期限までに申告書を提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情が存在する場合に限られるということです。
期限を延長できるケース
国税通則法第11条では、「災害その他やむを得ない理由」により申告期限までに申告できない場合、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、期限を延長できると定められています。
この場合、延長後の申告期限は、「災害等のやむを得ない理由のやんだ日から2カ月以内」とされており、一定の要件を満たすことで申告期限を過ぎても無申告加算税が課されない扱いとなります。
やむを得ない理由の具体例(相続税法基本通達27-5、27-6)
相続税の申告期限が、次のような事由が生じた日から1カ月以内に到来する場合には、「災害その他やむを得ない理由」に該当します。
- 認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続回復請求権による相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じた
- 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定した
- 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があった
- 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があった
- 相続の開始後に新たに子と推定された者又は認知された者への弁済すべき額が確定した
- 相続開始後において相続人となるべき者について失踪の宣告に関する審判の確定があった
- 法定代理人が民法第886条の規定により、相続について既に生まれたものとみなされる胎児の生まれたことを知った
- 退職手当金等の支給額が確定した
相続財産の総額がわからなくても申告は必要
もし日本の相続税制度が「遺産取得課税方式」であれば、今回のような問題は生じにくいでしょう。
しかし、現行の日本の相続税は「法定相続分課税方式」で計算されるため、被相続人の遺産総額を把握しなければ正確な相続税額を算出することができません。
とはいえ、たとえ相続人同士の関係が悪く、財産の全容を把握できない状態であっても、相続税の申告をしなくてよい理由にはなりません。
家族関係が複雑化する昨今、このようなケースは今後も増えていくと考えられます。
被相続人の財産の全体像が把握できない場合でも、ある程度の財産を有していたことが推認されるのであれば、相続または遺贈によって自分が取得した財産額や、被相続人が所有していたことが明らかな不動産などを基に、単独で相続税の申告を行っておくことで、無申告加算税の賦課を避け、税率の低い過少申告加算税の対象とすることが可能です。正確な申告は難しい状態だとしても、出来る限りの対応をすることが望ましいでしょう。