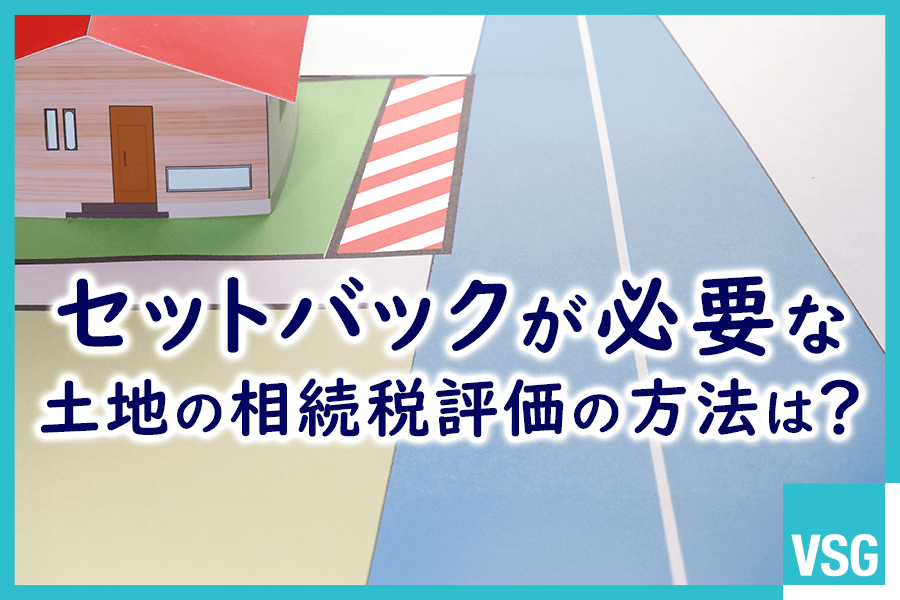記事の要約
- セットバックとは、幅員4m未満の道路(2項道路)を拡幅するために敷地を後退させること
- セットバック済みの土地は私道扱いとなり、相続税評価額は0円または30%評価になる
- 未セットバックの土地でも、将来後退が必要な部分は宅地評価額から70%控除できる
相続した土地の前面道路が狭い場合、「セットバック」という聞きなれない言葉を耳にする機会があるでしょう。
これは、将来的に道路の幅を確保するために、自分の敷地を一部後退(セットバック)させて、道路として提供しなければならないというルールのことです。
「土地が減ってしまう」と聞くと、損をした気分になるかもしれません。しかし、実は相続税の評価において、このセットバック部分は土地の評価額を大幅に下げ、相続税を安くできる重要なポイントとなります。
この記事では、そもそもセットバックとは何かという基礎知識から、状況によって変わる相続税評価額の計算方法、自身の土地が対象かどうかの調べ方までをわかりやすく解説します。
目次
そもそもセットバックとは?
セットバックとは、建築基準法上の「接道義務」を満たすために、敷地の一部を道路として後退させることを指します。
建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接している」必要があります。これを接道義務といいます。
しかし、古くからの市街地などでは、幅員が4m未満の狭い道路も多く存在します。このような道路に接している土地で建物を建てる(または建て替える)場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させなければならない、というルールが定められています。
これは、将来的に道路の幅員を4m確保し、緊急車両の通行や日照・通風を確保するなど、安全で住みやすい街づくりを目的としています。
第四十三条(敷地等と道路との関係) 二項
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2項道路に接する土地はセットバックが必要
セットバックが必要になるのは、主に「2項道路(にこうどうろ)」に接している土地です。
2項道路とは、建築基準法第42条第2項に定められている道路のことで、「みなし道路」とも呼ばれます。これは、建築基準法が施行された(または都市計画区域に指定された)時点で、すでに人々が生活道路として使用しており、建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道を指します。
将来的に道路の幅員を4m確保することを前提として、例外的に「道路」として扱われているため、新たに建物を建てる際にはセットバックが義務付けられています。
第四十二条(道路の定義) 二項
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
セットバック部分の土地は利用が制限される
セットバックした部分は、法律上「道路」として扱われるため、さまざまな利用制限がかかります。
たとえ登記上の所有権が自分にあったとしても、その土地(セットバック部分)には、建物はもちろん、門や塀、擁壁などを建築・設置することはできません。
あくまで道路として、人や車両が通行できる状態を維持する必要があります。このように私有地でありながら利用が大幅に制限される点が、相続税評価において重要なポイントとなります。
現に道路幅を確保できていない土地も建て替え時にセットバックが必要になる
2項道路に面している土地で、現にセットバックがされておらず道路幅が4m未満であっても、建築基準法が適用される前から建っている建物(既存不適格建築物)をそのまま使用し続ける場合は、直ちにセットバックを強制されるわけではありません。
しかし、重要なのは、その建物を「建て替える」(新築、増改築)際です。建て替えのタイミングで現行の建築基準法が適用されるため、必ずセットバックをしなければ建築確認申請が許可されません。
このように、相続の時点でまだセットバックされていなくても、将来的に建て替えを行う際にはセットバックが必要となる土地(つまり、まだセットバックしていない土地)は、相続税評価において特別な考慮が必要となります。
2項道路に接している土地の相続税評価の方法はセットバックの有無で変わる
2項道路に接する土地の相続税評価は、相続開始時点で、すでにセットバックが完了しているか(セットバック済みか)、まだセットバックされていないかによって、計算方法が大きく異なります。
セットバック部分は、建築ができないなど利用価値が著しく制限されるため、その制限の度合いに応じて評価額を減額するルールが定められています。
セットバックがある土地は対象部分を私道としての評価(0円または30%評価)
すでにセットバックが完了しており、その部分が(見た目上も機能上も)道路として使われている土地は、「私道(しどう)」として評価します。
私道は、その利用状況によって評価が2パターンに分かれます。
- 評価額0円(非課税)となるケース:その道路が、近隣住民など不特定多数の人の通行に使われている「通り抜け道路」などの場合、公共性が非常に高いとみなされます。この場合、セットバック部分の評価額は0円として扱われます。
- 宅地評価額の30%で評価するケース:その道路が、袋小路(行き止まり)になっており、特定の居住者(その道路に面した家の人)だけが利用している場合。この場合は、公共性が限定的であるため、通常の宅地として評価した価額の30%相当額で評価します※。
- ※
- 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合や、私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用しているなどの場合、不特定多数の者の通行の用に供されていることになり、評価額は0円となる
セットバックがない土地は対象部分を宅地評価額から70%控除
相続開始時点で、まだセットバックがされておらず、宅地の一部として利用されている土地(例:庭や駐車スペースとして使っている)の場合、その土地は「私道」とは評価できません。
しかし、将来的に建物を建て替える際には必ずセットバックしなければならないという、法的な利用制限がかかっています。
この将来的な制限を考慮するため、セットバックが必要となる部分(セットバック部分)については、通常の宅地として評価した価額から70%を控除して評価します。
計算イメージ
結果として、前述の「特定の人のみが利用する私道」と同じく30%評価になりますが、計算のプロセス(まだ宅地であるため70%を「控除」する、という考え方)が異なります。
セットバックがある土地の相続税評価額の計算例
相続開始時点ですでにセットバックが完了している土地(私道として利用されている土地)の具体的な計算例を見ていきましょう。
ここでは、以下の土地を例に計算します。
- 土地全体の面積:200㎡
- 宅地部分の面積:190㎡
- セットバック部分(私道)の面積:10㎡
- 相続税評価額(路線価):1㎡あたり20万円
不特定多数が利用している場合
セットバック部分が、近隣住民など不特定多数の人が通行する「通り抜け道路」の一部となっているケースです。
この場合、セットバック部分は公共性が非常に高いとみなされ、公共用道路として評価し、評価額は0円となります。
計算例
- 宅地部分(190㎡)の評価額:190㎡ × 20万円/㎡ = 3,800万円
- セットバック部分(10㎡)の評価額:10㎡ × 20万円/㎡ × 0% = 0円
- 土地全体の相続税評価額:3,800万円 + 0円 = 3,800万円
特定の人のみが利用している場合
セットバック部分が「袋小路(行き止まり)」のようになっており、その道路に面した居住者など、特定の人のみが利用しているケースです。
この場合、セットバック部分(私道)は、通常の宅地の30%相当額で評価します。
計算例
- 宅地部分(190㎡)の評価額:190㎡ × 20万円/㎡ = 3,800万円
- セットバック部分(10㎡)の評価額:(10㎡ × 20万円/㎡) × 30% = 60万円
- 土地全体の相続税評価額:3,800万円 + 60万円 = 3,860万円
このように、セットバック部分がどのように利用されているかによって、相続税評価額が変わってきます。
セットバックがない土地の相続税評価額の計算例
相続開始時点でまだセットバックが完了しておらず、宅地の一部として利用されている(例:庭や駐車場になっている)ものの、将来的に建て替える際にはセットバックが義務付けられている土地の計算例です。
この場合、宅地全体を一体として評価した価額から、「セットバックが必要となる部分」の価額の70%相当額を控除して計算します。
- 土地全体の面積:200㎡
- このうちセットバックが必要な面積:10㎡
- 相続税評価額(路線価):1㎡あたり20万円
計算例
- 土地全体の評価額(控除前)を計算:まず、土地全体(200㎡)が宅地であるとして評価額を計算します。 200㎡ × 20万円/㎡ = 4,000万円
- セットバック部分の控除額(70%)を計算:次に、セットバックが必要となる部分(10㎡)の評価額を計算し、その70%(控除額)を求めます。 (10㎡ × 20万円/㎡) × 70% = 140万円(控除額)
- 土地全体の相続税評価額を計算:最後に、土地全体の評価額から控除額を差し引きます。 4,000万円(全体評価額) – 140万円(控除額) = 3,860万円
計算結果としては、「セットバックがある土地(特定の人のみが利用)」の場合と同じ評価額になります。
セットバックが必要な土地の確認方法
相続した土地(あるいは将来相続する土地)にセットバックが必要かどうかを正確に把握するには、複数の方法で調査する必要があります。
役所で確認
最も確実な方法は、その土地が所在する市区町村の役所(建築指導課、道路課など)で確認することです。
役所では、土地に接している道路が建築基準法上のどの道路に該当するのかを管理しています。
- 土地に接している道路が「2項道路」に指定されているか。
- 「指定道路図」や「道路台帳」を閲覧し、道路の幅員や中心線がどこに設定されているか。
ここで「2項道路」であると確認できれば、その道路の幅員が4m未満である限り、建て替え時にはセットバックが必要な土地であると判断できます。
法務局(登記)で確認
法務局では、土地の登記情報(登記簿)や、土地の形状・隣地との境界を示す地図(公図、地積測量図)を取得し、登記上の土地の面積や形状、道路との境界線を確認できます。
ただし、登記簿上の面積(公簿面積)は、セットバックが必要な部分を含んだままになっているケースがほとんどです。登記簿を見ただけではセットバックの要否は判断できないため、必ず役所での調査と組み合わせて確認する必要があります。
現地(実測)で確認
実際に現地を訪れて道路の状況を確認することでも、セットバックが必要かどうかの目星をつけることができます。
メジャーなどを持参し、土地に接している道路の幅員を測ってみて、明らかに4m未満であれば、2項道路である可能性が高いです。
ただし、これらはあくまで簡易的な確認のため、相続税申告などで正確なセットバック部分の面積が必要な場合は、境界の専門家である「土地家屋調査士」に依頼し、測量(実測)を行ってもらうのが最も確実です。これにより、道路の中心線や境界線を法的に確定させることができます。
セットバックの相続に関するQ&A
最後に、セットバックに関して相続時によくある質問とその回答をまとめます。
Q.固定資産税が非課税なら、相続税評価も0円になりますか?
いいえ、必ずしも「0円」になるとは限りません。
固定資産税と相続税は、根拠となる法律や評価のルールが異なるためです。
市区町村は、公共性の高い私道(セットバック部分)について、所有者が申請(固定資産税の非課税申告)をすれば、固定資産税を非課税とする運用を行っていることが多くあります。
しかし、相続税の評価では、あくまでその私道が「不特定多数の通行に使われているか(評価額0円)」か「特定の人のみが利用しているか(30%評価)」という実態で判断します。
たとえ固定資産税が0円であっても、それが袋小路などで特定の人しか使っていない私道であれば、相続税評価では30%評価となるため注意が必要です。
Q.セットバック部分に小規模宅地等の特例は適用できる?
はい、セットバック部分も含めて特例の適用対象となります。
小規模宅地等の特例(被相続人が居住していた土地などの評価額を最大80%減額できる制度)は、セットバック部分を除外して計算する必要はありません。
セットバック評価減と小規模宅地等の特例は、両方を適用することが可能です。
Q.セットバック部分を自治体に寄付することはできる?
自治体によりますが、断られるケースも多いのが実情です。
セットバックした部分の所有権を自治体(市区町村)に寄付(採納)し、公道として管理してもらう制度は存在します。
しかし、寄付を受け入れると、その後の舗装や維持管理の費用が自治体側に発生するため、受け入れに消極的な自治体も少なくありません。
また、寄付を受け入れる場合でも、「土地の分筆登記(測量して登記簿を分けること)費用は所有者負担」「抵当権などが設定されていないこと」「隣地との境界が確定していること」など、厳しい条件が定められていることが一般的です。
寄付を検討する場合は、まず役所の道路管理課などに相談してみましょう。
まとめ:セットバック評価の判断で迷ったら税理士に相談しよう
この記事では、セットバックが必要な土地(2項道路に面した土地)の相続税評価について解説しました。
建築基準法上の2項道路に接しており、セットバックが必要となる土地(またはセットバック済みの土地)は、その利用が制限されるため、相続税評価において大幅な減額が認められています。
しかし、その評価方法は、
- すでにセットバック済みか、まだセットバックされていないか
- セットバック部分が不特定多数の通行用か、特定の人専用か
- そもそもセットバックが必要な土地かどうかの調査
など、非常に専門的な判断を伴います。
とくに、相続開始時点でまだセットバックされていない土地(70%控除の対象)を見落としてしまうと、本来よりも高い評価額で相続税を計算してしまい、税金を払いすぎてしまうことになりかねません。
もし、ご自身での判断に少しでも不安がある場合や、相続した土地の評価を正確に行いたい場合は、土地評価や相続税申告に強い「相続専門の税理士」に相談することをおすすめします。
VSG相続税理士法人でも土地の評価についてのご相談を受け付けております。初回相談は無料のため、ぜひお気軽にご連絡ください。