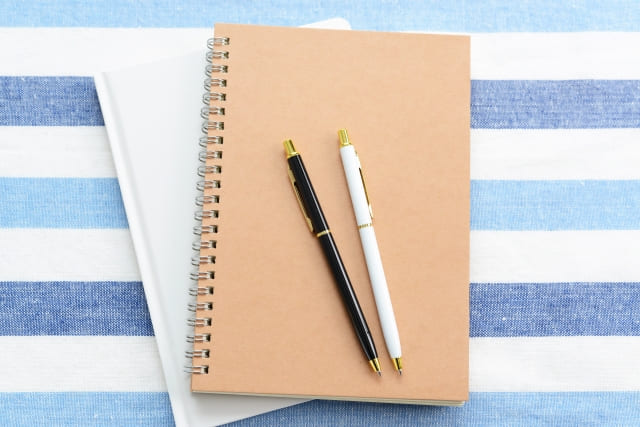最終更新日:2025/3/5
創業融資の返済期間は何年にすべき?返済計画の考え方と据え置き活用

創業融資を受けることが決まったら、次に考えなければならないのが返済期間です。
「長く設定すると負担が減るのか?」
「短期間で返したほうが経営に良いのか?」
融資を受けるとき、多くの人がこのバランスに悩みます。返済期間を長くすれば月々の負担は軽くなりますが、利息の総額が増える可能性があります。逆に短く設定しすぎると、資金繰りが厳しくなり、追加の借入が必要になることも…。
では、どのように返済期間を設定するのがベストなのでしょうか?
この記事では、創業融資の返済計画を立てる際のポイントと、「据え置き期間」を活用する方法についてわかりやすく解説します。
返済期間
まずは返済期間について見ていきましょう。
返済期間は文字どおりいつまでに支払うというものです。
日本政策金融公庫の創業時の融資では、返済期間は5年以上となります。
運転資金は5年~7年、設備資金では5年~10年といったところです。
返済期間は長い方がいいのか?短い方がいいのか?
先ほど返済期間は5年以上ということがわかりました。
では、5年~10年位の間でどれくらいに設定すればいいのでしょうか?返済期間が短ければ月々の返済負担は重くなりますが、その期間を過ぎれば重い負担がなくなります。
他方、返済期間が長ければ毎回の返済は低く抑えられますが、返済期間が長くなるので固定負担が重くのしかかってきます。
月並みなことですが、無理な返済期間を設定しないことです。
それでは返済のために借金をする悪循環に陥りかねないからです。
もし、支払いを長めに設定したいと考えるならば、設備資金を増やすことで最長10年の期間を設定しましょう。
これですと、毎回の返済は低く抑えられます。
他方、長く拘束されることになりますし、より魅力的な融資も途中で出てくるかもしれません。
具体的には、約30%以上の返済をした方には追加融資の話が来るようになります。
金融機関からの追加融資を考えている方であれば、返済期間はある程度短くしておくべきです。
据置期間
これまで返済期間について見てきました。
それでは次に据置期間について見ていきます。
そもそも据置期間とはどのようなものなのでしょうか?
(1)据置期間とは?
据置期間とは融資を受けた場合に、元金の返済が猶予される期間のことです。
本来元金と利息は両方支払うのが原則ですが、開業時の特殊性を考慮して利息のみを支払う期間のことを指します。
(2)開業時の特殊性
事業を始めるとわかりますが、開業当初というのはよほどのことがない限り、経費は発生すれど安定的な利益が発生することはまずありません。
それこそ荒波に揉まれるような状態が続くといってもいいでしょう。
(3)据置期間の決め方
(2)で述べたような状態を考慮して据置期間を決める必要があります。
具体的には、創業して3ヵ月ほどは売上の目処も立ちにくいですので、半年後から元金の返済をスタートさせるなどです。
また、業界的に最終的な入金が遅いというのであれば、その特殊性をも加味して考えるべきでしょう。
気をつけたいのは知り合いの話です。
同業種の方の話であれば参考になりますが、別の業種の方の話ですと入金のスパンが異なりますので、非現実的な据置期間を作ってしまうかもしれません。
ご注意ください。
まとめ
ここまで返済期間と据置期間について見てきました。
いずれにせよ、長い返済をしていく上で大切な期間となります。
「そんなのわからないよ」「知り合いがこうしてうまくいったから、自分も同じようにしよう」という安易なフィーリングでこの2つを決めてしまうと、後で自分の首を絞めることになりかねません。
何となくではなく、きちんと見通しを立てて、この期間を決めておきたいところです。
創業融資 関連記事