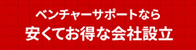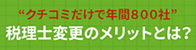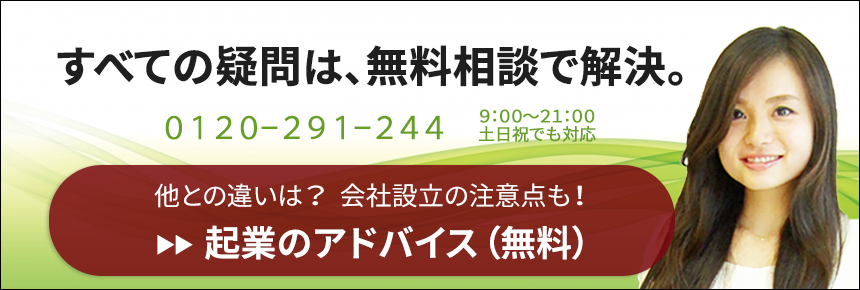- TOP|会社設立
- ›
- 会社設立前に確認したい 48項目徹底検討
- ›
- 役員報酬はいくらが得?節税・社会保険・融資・相場から見る適正額とは
役員報酬はいくらが得?節税・社会保険・融資・相場から見る適正額とは

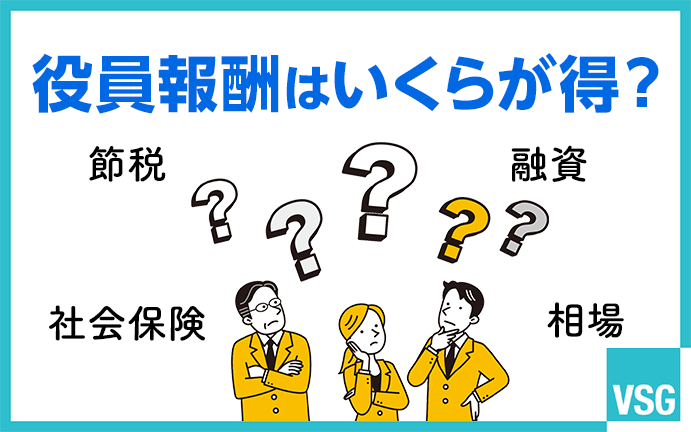
この記事でわかること
- 役員報酬はいくらが得か
- 役員報酬の相場と平均データ
- 役員報酬の適正額を決めるポイント
- 役員報酬の注意すべきデメリットとルール
役員報酬をいくらに設定するかは、非常に重要な経営判断です。設定額によって、会社の法人税、個人の所得税・住民税や社会保険料、さらには将来受け取れる退職金や融資の可否までに影響を与えます。
単なる給料ではないので、役員報酬はさまざまな要因を考慮して設定する必要があります。
この記事では、2025年の最新税制に基づき、役員報酬の最適な金額を判断するためのポイントをわかりやすく解説していきます。
▼目次
- 役員報酬はいくらが得?【結論
- 役員報酬の相場データ
- 会社の利益別・報酬額別の手取り比較
- 年間利益500万円の会社
- 年間利益1,000万円の会社
- 年間利益2,000万円の会社
- 役員報酬の適正額を決める3つのポイント
- 社会保険料の負担軽減を考慮
- 所得税の累進税率を活用
- 会社の法人税負担とのバランス
- 役員報酬の適正額を決めるときの注意点
- 退職金を考慮した準備
- 融資やローンへの影響
- 役員貸付金は絶対に避ける
- 役員報酬を決める際のポイント
- 役員報酬を決める際のルール
- 1. 定期同額給与
- 2. 事前確定届出給与
- 3. 利益連動給与
- 役員報酬は年に1度だけ変更できる
- まとめ:役員報酬がいくらが得かは税理士に相談しよう
役員報酬はいくらが得?【結論】
結論からいくと、「得」な役員報酬は会社の利益・生活水準・社会保険加入状況によって異なります。
一般的な目安としては以下のようになります。
| 会社の利益 | 最適役員報酬 | 最適化のポイント |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 300万~400万円 | 最低限の生活費確保を優先 |
| 500万円以上3,000万円未満 | 600万円前後 | 税負担バランスが最良 |
| 3,000万円以上 | 段階的設定 | 累進税率と法人税のバランス調整 |
役員報酬の相場データ
役員報酬の相場は、会社の規模、業種、設立からの年数、役員の役割などによって大きく変動します。国税庁や中小企業庁の統計によると、中小企業の役員報酬の平均は以下のとおりです。
資本金別の役員報酬の年間平均額
| 資本金 | 役員報酬の年間平均額 | ||
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男女合計 | |
| 2,000万円未満 | 755万4,000円 | 437万7,000円 | 661万1,000円 |
| 2,000万円以上 | 1,130万円 | 518万円 | 999万8,000円 |
| 5,000万円以上 | 1,425万1,000円 | 709万8,000円 | 1,323万5,000円 |
| 1億円以上 | 1,570万9,000円 | 645万円 | 1,458万円 |
| 10億円以上 | 2,260万円 | 798万6,000円 | 2,092万8,000円 |
このデータから、資本金が大きい会社ほど役員報酬も高くなる傾向があるとわかります。
会社の利益別・報酬額別の手取り比較
役員報酬 をいくらに設定するかで、会社に残るお金と手取りの合計がどのように変わるか、会社の利益別に役員報酬額をシミュレーションしてみました。
年間利益500万円の会社
| 役員報酬 | 個人手取り | 会社手取り | 合計手取り |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 168万円 | 207万円 | 375万円 |
| 300万円 | 242万円 | 138万円 | 380万円 |
| 400万円 | 316万円 | 69万円 | 385万円 |
年間利益1,000万円の会社
| 役員報酬 | 個人手取り | 会社手取り | 合計手取り |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 316万円 | 414万円 | 730万円 |
| 600万円 | 468万円 | 276万円 | 744万円 |
| 800万円 | 614万円 | 138万円 | 752万円 |
年間利益2,000万円の会社
| 役員報酬 | 個人手取り | 会社手取り | 合計手取り |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 468万円 | 966万円 | 1,434万円 |
| 1,000万円 | 699万円 | 678万円 | 1,442万円 |
| 1,400万円 | 1,016万円 | 414万円 | 1,430万円 |
この表からわかるように、利益額ごとに最適な役員報酬額が存在し、その金額で合計手取り額が最大化されます。
役員報酬の適正額を決める3つのポイント
役員報酬の適正額を決めるポイントはいくつかあります。
ポイントを押さえてご自身の一番しっくりくる金額を見つけてみてください。
社会保険料の負担軽減を考慮
役員報酬を決める際に、社会保険料は重要なポイントです。
社会保険料は、報酬額に応じて負担額が決まります。特に一定の報酬額を超えると、それ以上の増額分によっては社会保険料の負担額は変わりません。この上限を活用することで、社会保険料の負担を抑えつつ、手取り額を増やすことができます。
役員報酬にかかる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料です。
・健康保険料:報酬月額の約5.0%(会社負担分含む約10.0%)
・厚生年金保険料:報酬月額の約9.15%(会社負担分含む約18.3%)
参考:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
所得税の累進税率を活用
所得税は累進課税制度のため、役員報酬が増えれば増えるほど、税率も高くなっていきます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
この表にあるとおり、課税所得が900万円(役員報酬額面:約1,100万円)を超えると33%、1,800万円(役員報酬額面:約2,400万円)を超えると40%と、税率は高くなります。
このラインを目安にして役員報酬を設定していくとよいでしょう。
参考:所得税の税率|国税庁
会社の法人税負担とのバランス
会社にかかる税金は、法人税です。
また、社会保険料も個人と会社が折半して支払うので、会社からも同額を支払います。
役員報酬を上げた場合と下げた場合で、それぞれの税金・費用がどう変わるのか見てみましょう。
| 役員報酬を上げる場合 | 役員報酬を下げる場合 | |
|---|---|---|
| 会社の利益 | 減る | 増える |
| 法人税 | 安くなる | 高くなる |
| 個人の所得 | 増える | 減る |
| 所得税・住民税 | 高くなる | 安くなる |
| 個人の社会保険料 | 高くなる | 安くなる |
| 会社負担の社会保険料 | 高くなる | 安くなる |
役員報酬を増やせば、会社の利益が減り、法人税の負担は軽くなります。逆に、役員報酬を減らせば、会社の利益が増え、法人税の負担が重くなります。
法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料の合計額が最も少なくなるバランスを見つけることが、全体の手取り額を最大化するポイントです。
役員報酬の適正額を決めるときの注意点
役員報酬の適正額を決めるときに、注意すべき点がいくつかあります。以下の3つの注意点を考慮して総合的に判断しましょう。
- 退職金を考慮した準備
- 融資やローンへの影響
- 役員貸付金は絶対に避ける
退職金を考慮した準備
役員報酬を考える上で、将来の退職金を見据えた準備も重要です。
退職金は支給額が多額でも税制上の優遇措置が大きいため、所得税の負担を抑えられます。
- 生命保険
- 小規模企業共済
生命保険の活用
法人が契約する生命保険の一部は損金として計上でき、退職金の資金としても準備できます。
小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の役員が加入できる共済制度で、掛け金は全額が所得控除の対象となります。将来の退職金や廃業時の資金として活用でき、節税にもつながります。
融資やローンへの影響
金融機関は、会社の決算書や個人の年収を審査して融資を決定します。
役員報酬を低く設定しすぎると、個人の年収が低く見られ、融資や住宅ローンなどの審査に通りにくくなります。
将来的に大きな借入れを予定している場合は、税負担の最適化よりも報酬額を優先することも必要です。
役員貸付金は絶対に避ける
役員報酬の税負担を考え、報酬額を低く設定した場合、生活費が不足し、会社から個人への貸付(役員貸付金)が発生するケースがあります。
役員貸付金には以下のデメリットがあります。
- 税務署から認定利息課税のリスクを負う
- 融資の審査でマイナス評価を受ける
- 会社の財務内容悪化の印象を与える
- 個人の債務として相続税の課税対象になる
- 会社を清算しようと思ってもできない
このように、役員貸付金にはデメリットはたくさんありますが、メリットはありません。
役員報酬は、役員貸付金が発生しないよう最低限の生活費を考慮して決定したほうがよいです。


役員報酬を決める際のポイント
役員報酬を決めるポイントとして、「逆算」の考え方があります。
例えば、会社には源泉所得税を納付する義務があります。「納期の特例」というものがあり、1年に2回、半年ごとにまとめて納付することができます。
このときに「役員報酬をこれくらいに設定したら、所得税の納付は〇〇万円となるが、支払うことが可能か?」と考えます。
また、社会保険料も会社と個人の折半なので、会社も社会保険料を支払うことになりますが、「社会保険料は毎月〇〇万円だが、これくらいなら支払えるか?」と逆算して考えてみます。
税金や社会保険料の支払額から逆算した上で無理のない報酬額を決定すれば、資金繰りの悪化を防ぐことができます。
役員報酬を決める際のルール
役員報酬は、原則として1年に1回しか変更できません。変更できるのは、事業年度開始から3カ月以内と定められています。
もちろん、社長がオーナーでもある場合には会社のお金をどれだけ取っても文句は言われないかもしれませんが、そのお金を会社の経費として処理できなくなってしまうことがあるということです。
役員報酬の支給の仕方としては、以下の3つから選択する必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
1. 定期同額給与
定期同額給与とは、「1カ月以下の一定期間ごとに支給される給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」のことです。
端的に言えば、毎月の固定給という形での報酬ということになります。
2. 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは「固定給とは別のボーナスを支給する際に、事前に税務署へ届出をしておくことで損金計上を認められたボーナス」のことです。
その届出の期限は、以下のどちらか早いほうとなっています。
・株主総会などでその旨を定めた日から1カ月以内
・その会計期間開始から4カ月以内
事前の届出がなかったり、金額と期日を勝手に変更してしまうとその全額が損金不算入となってしまうので注意しましょう。
3. 利益連動給与
利益連動給与とは「利益に関する指標、または売上高に関する指標に基づいて支給される給与」、つまり成果報酬型の給与ということです。
ただし、利益連動給与には「同族会社ではない法人が業務執行役員に対して、利益に関する指標を基礎として算定して支給される給与であること」という条件があるため、同族会社であることが多い中小企業ではあまり有効な方法ではないといえるでしょう。
役員報酬は年に1度だけ変更できる
役員報酬は1年に1回、事業年度開始の月から3カ月以内のタイミングでのみ変更できるというルールになっています。
これは法人税の脱税行為を防止するためのルールで、例えば「今期はたくさん利益が出たから、決算直前に役員報酬を一気に増やす」というようなことはできないということです。
1年に1回のタイミングで変更した役員報酬については、形式上は定時株主総会を開いて決めたということになりますから、その議事録を作成して保管しておきましょう。
まとめ:役員報酬がいくらが得かは税理士に相談しよう
役員報酬がいくらが得かは、会社の利益、個人のライフプラン、税金、社会保険料、将来の資金計画など、多くの要素を総合的に判断して決める必要があります。
この記事で解説したポイントをもとに、会社にとって最適な役員報酬額を検討してみてください。
役員報酬額の決定に不安がある場合、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、最適な節税対策を講じながら、会社や個人の将来に備えることができます。
- 個人事業と法人はどちらが税金で有利か
- 株式会社か合同会社かどちらにすべきか
- 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】
- 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!
- 助成金で取得できるものとは?
- 補助金で取得できるものとは?
- 設立後の創業融資を視野に入れた設立とは?
- 許認可について
- 銀行口座開設を視野に入れた設立スケジュールについて
- 許認可申請を視野に入れた設立スケジュールについて
- 商標権登録されている会社名でないかの調べ方
- 会社名で使える記号や文字とは?
- 会社名で使えない言葉とは?
- 会社名と同じドメインの取得ができるかの確認について
- 同名の会社名の会社がネット検索で上位にでないかは確認しましょう
- レンタルオフィスで設立をするときの注意点
- 商号に英語表記を入れるかどうか?
- 資本金は消費税の免税を考えているか?
- 会社設立に必要な資本金は借入でもよいのか?資金調達方法と注意点を解説
- 資本金を使える時期とは?
- 資本金の振り込み方を詳しく説明
- 現物出資のメリット・デメリット
- 納税時期を考えて何月決算が最適か?
- 消費税の免税期間を考えて何月決算が一番得?
- 消費税の特定期間を考えて何月決算が一番得!?
- 定期的に売上のあがる時期を考えて何月決算かを決めよう
- 事業計画の立てやすさから考えて何月決算が最適か検討しよう
- 本店所在地は銀行通帳が作りやすい場所になっている?
- 本店所在地を自宅にする際のメリット・デメリット
- 部屋番号まで登記する場合のメリット・デメリット
- 定款の本店所在地を市町村で止めるメリット・デメリット
- 役員の構成は節税上有利になるようになっているか確認しましょう
- 役員報酬をいくらにすべきか検討しているか
- 非常勤役員を置くメリットと注意点について
- 安定経営を考えた資本政策とは?
- 他社に過半数出資している株主の確認
- 事業目的は許可申請を取得することを念頭に置けている?
- 事業目的はわかりやすさが重要
- 事業目的には将来予定している内容も盛り込むといいの?
- 公告の方法について
- 発行可能株式総数とは?
- 設立日におすすめの六曜の縁起とは?
- 設立予定日とは?
- 取締役会の設置、非設置について
- 種類株式について
- 株式の譲渡制限について
- 1株当たりの金額は展開を視野に検討しましょう
- 取締役の任期について
- 設立後の社会保険の加入の手続きの流れを詳しく説明
≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!