

東京弁護士会所属。東京都出身。
弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。
立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。
複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。
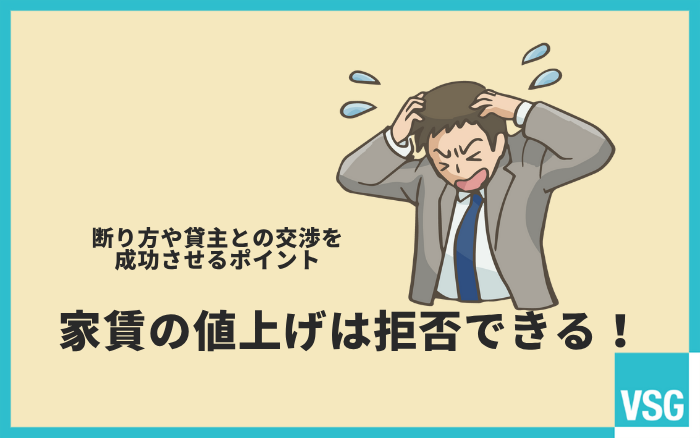
大家さんから突然家賃を値上げを要求され、「拒否できるか」「退去させられてしまう可能性はないか」と不安に思う方もいるでしょう。
貸主からの一方的な家賃の値上げは、借主が同意しなければ成立しません。
正当な理由がなければ、値上げの拒否が可能です。
本記事では、家賃の値上げを拒否できる条件や、貸主との交渉を成功させるポイントをお伝えします。
万が一交渉がうまくいかなかった場合の対処法も、あわせて解説します。
目次
借主は、正当な理由がない家賃の値上げを拒否できます(借地借家法第32条)。
これは、借主の居住権を保護する法律上の権利です。
賃貸借契約は双方の合意が原則で、貸主が一方的に家賃を決定できません。
貸主は、借主による値上げの拒否を理由に、契約解除や立ち退きを要求できません。
ただし、貸主側に税負担の増加や相場の上昇など正当な理由がある場合は、協議や調停を経て値上げが認められる可能性があります。
家賃の値上げは、借地借家法に以下3つのケースで認められると定められています。
それぞれのケースについて解説します。
賃貸物件の取得や保有を続けるには以下の税金を納付しなければなりません。
税金の負担額は、主に賃貸物件の評価額によって変わります。
3年に1回は固定資産の評価替えがあり、納付金額が増える場合もあります。
都市計画法の指定する市街化区域内に不動産を保有する大家さんは、都市計画税の納付も必要です。
税金の負担が増えた場合、増加分を家賃に上乗せして負担を回避するケースもあるでしょう。
税負担の増加は、借地借家法上の家賃値上げの正当事由として認められています。
賃貸物件を運営するには、前述した税金の他にさまざまな維持管理費用がかかります。
一般的には、賃貸物件の取得費用のほか、次のような維持管理費用を負担しなければなりません。
物価があがった場合、これらの維持管理にかかる費用も増加します。
特に建物が老朽化して数年後にリフォームが必要な状況などでは、費用が高額になるケースもあるでしょう。
維持費用が増えた場合、賃貸物件の運営を継続するために増加分の家賃値上げを行わなければならない場合もあります。
必要な維持管理費用の増加も、借地借家法上の家賃値上げの正当事由として認められています。
家賃相場は、その地域にある物件の賃貸需要が上がると値上がりします。
次のようなケースで「その地域に住みたい」と考える人が増えた場合、家賃相場があがります。
物件周辺の家賃相場があがった場合、大家さんは家賃をあげなければ本来得られるはずの収入を得られない機会損失を受けます。
賃貸需要があれば退去後の空き家リスクも少なくなるため、入居中であっても家賃値上げをしたいと考える大家さんもいるでしょう。
賃貸借契約は貸主と借主の双方合意によって成立する契約で、家賃のような重要な契約条件を変更するには、借主の同意が不可欠です。
借地借家法第32条第1項では、貸主からの値上げ請求権が認められていますが、あくまで請求する権利にすぎません。
借主が同意しなければ、自動的に値上げが確定するわけではありません。
貸主が一方的に値上げを通知しても、借主が同意しない限り、これまでの家賃額での支払いが継続されます。
家賃の値上げを伝えられたときは、以下の対処をしましょう。
ここからは、家賃の値上げを伝えられたときの対処法について紹介します。
家賃の値上げを伝えられたときは、まず根拠を確認しましょう。
賃貸借契約書に、家賃の値上げをする条件が記載されているケースがあります。
値上げの根拠を質問し、賃貸借契約書に定めた条件と合致しているか確認してください。
賃貸借契約書に記載されている条件は、家賃相場の上昇や大家さんの納税額上昇によるケースが大半です。
家賃の値上げの根拠とともに、家賃の値上げ幅を確認します。
詳しくは後述しますが、家賃金額の上げ幅を確認するのは、家賃が近隣相場に合っているか確認するためです。
値上げされた家賃が近隣相場と合っていなければ、大家さんとの交渉のときに家賃の値上げが正当ではない根拠として主張できるでしょう。
大家さんから家賃の値上げ通知が来ても、まずは感情的にならないように気を付けましょう。
家賃の値上げは生活に関わるため、焦りや怒りを感じやすいです。
感情的になると話し合いで解決するのが難しくなり、裁判上の手続きに進んでしまうケースもあるため、冷静に対処してください。
家賃値上げの交渉では、証拠として書面を残す行為が重要です。
口頭のやり取りだけでは、万が一、調停や裁判となった場合に不利になる可能性があります。
残す書面は、貸主からの値上げ通知書、借主からの回答書、交渉経緯を記録したメールや内容証明郵便などです。
話し合いについても、日時・場所・発言内容を記録しておきましょう。
これらの証拠は、値上げの正当性を争う際や不当な扱いを受けた場合、自身の主張を裏付ける重要な材料となります。
家賃の値上げを拒否したい場合は、家賃交渉を行います。
家賃交渉を円滑に進めるためのポイントは、以下の通りです。
ここからは、家賃の値上げ交渉へのポイントを紹介します。
周辺の家賃相場を確認し、家賃の値上げ幅が適正なのか確認します。
家賃の値上げ幅が周辺家賃の相場からかけ離れている場合は、家賃の値上げ幅を下げられる可能性があります。
周辺家賃の相場は、賃貸物件のポータルサイトで確認しましょう。
賃貸物件と同じ地域で、築年数や間取り、階数、広さなど似た賃貸物件の家賃を調べ、その情報を基に交渉を進めていきます。
大家さんから家賃の値上げを伝えられたときには、周辺家賃だけでなく、物価のデータを取得しましょう。
データがあると、値上げの根拠がより正確にわかります。
値上げを拒否する前提であれば、交渉の準備としてなるべく多くの情報を集めましょう。
家賃の値上げを条件付きで承諾するのも、値段交渉の1つです。
たとえば、以下のような別条件を提示しましょう。
家賃は上がりますが、その他の項目で得ができる可能性があります。
当事者同士での話し合いが難しいと感じたら、専門家の意見を聞くのも有効です。
家賃の値上げ交渉のような不動産トラブルは、弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士は、法律や過去の判例に基づき、大家さんの主張する値上げ理由や金額が妥当かどうかを客観的に判断します。
また、交渉の進め方や、有利な条件を引き出すための具体的なアドバイスも受けられるでしょう。
専門家の意見を後ろ盾にすると、冷静かつ有利に交渉を進めやすくなります。
値上げ交渉に失敗した場合は、以下の対処をしましょう。
それぞれの対処法について詳しく解説します。
交渉が決裂すると、大家さんが裁判所に調停を申し立てる場合があります。
調停とは、裁判所で調停委員を交え、中立な立場で話し合い解決を目指す手続きです。
調停では法的な主張や証拠が重要となるため、弁護士に相談するのが賢明です。
弁護士はあなたの代理人として、有利な解決に向けた主張を組み立ててくれるでしょう。
弁護士法人VSGは、家賃問題の解決実績が豊富です。
交渉から調停まで一貫してサポートします。
お困りの際はご相談ください。
もし今の入居物件にどうしても住み続けなければならない理由がない場合、思い切って別の物件に引っ越すのも一つの方法です。
新しい物件を探す手間や引っ越し費用などもかかりますが、場合によっては今よりも良い物件が見つかる可能性もあるでしょう。
特に大家さんと争ってまで今の物件に住み続けたいとは思わない場合、新しい賃貸物件で生活をスタートするのもおすすめです。
家賃の値上げは、家計に直結する重要な問題です。
大家さんとの今後の関係を考えると、どう対応するか悩んでしまうでしょう。
しかし、借主の立場は法律によって守られており、理不尽な要求に応じる必要はありません。
弁護士法人VSGでは、豊富な実績をもとに法的な観点から最適な解決策を提示します。
一人で抱え込まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。