

立ち退きを求められたとき、まず気になるのは「立ち退き料」のことではないでしょうか。
「提示された金額が妥当なのか」「どうすれば立ち退き料を増額できるのか」など、不安や疑問を感じる方も多いでしょう。
立ち退き料は、借主の権利を守るための重要な補償であり、交渉次第で金額を増やすことも可能です。
しかし、そのためには立ち退き料の相場や、交渉のポイントを押さえておく必要があります。
本記事では、立ち退き料の基礎知識から、具体的な交渉術、注意点までを詳しく解説します。
目次
立ち退き料の金額は、法律で明確に定められているわけではありません。
建物の種類や立地、契約内容、立ち退きの理由など、様々な要素を考慮して個別に決定されます。
立ち退き料とは、貸主の都合で賃貸借契約を解除する場合に、借主に対して支払われる金銭のことです。
借主の経済的な損失や精神的な苦痛を補償する意味合いを持ちます。
借地借家法では借主の権利が強く保護されており、貸主が一方的に賃貸借契約を解除することは原則としてできません。
貸主からの立ち退き要求が正当と認められるためには、相応の立ち退き料の支払いが求められることが一般的です。
立ち退き料の相場は、建物の種類や用途によって大きく異なります。
居住用物件の場合の立ち退き料の目安は、次のとおりです。
店舗や事務所の場合の立ち退き料の目安は、次のとおりです。
ただし、これらの金額はあくまで目安であり、実際の立ち退き料は個別の状況によって大きく異なります。
飲食店などの店舗の場合、立ち退きによって営業を継続できなくなるため、居住用物件よりも高額な立ち退き料が認められる傾向にあります。
店舗の立ち退き料は、以下の要素も考慮して算出されます。
再開発による立ち退きの場合は、公共性の高さから、立ち退き料が比較的低く抑えられる傾向があります。
再開発による立ち退き料は、以下の要素などを考慮して算出されます。
立ち退き料は、貸主の都合や借主の不利益、移転にかかるコストなどを具体的に示すことで増額交渉が可能です。
特に、正当事由が弱い場合や移転コストが高額な場合、立ち退き料の増額が期待できます。
以下のようなケースでは、立ち退き料の増額が期待できます。
貸主側の事情で立ち退きを求められる場合、借主には居住や営業を続ける権利があり、貸主の都合でその権利を奪うことになるため、相応の補償が必要です。
この場合、立ち退き料の増額交渉がしやすくなります。
貸主側の事情の具体例としては、次のものがあります。
借地借家法は、借主の権利を強く保護しており、立ち退き料の増額交渉に有利に働くことがあります。
特に、長期間にわたって居住している場合、借主の生活基盤が確立されているため、退去による影響が大きくなります。
そのため、立ち退きに伴う補償が必要とされるケースが多く、交渉の余地が広がります。
また、貸主が契約の更新を拒絶するためには「正当事由」が必要とされます。
正当事由には、建物の老朽化や貸主自身の使用目的などが考慮されます。
しかし、それらの事情が十分に立ち退きを正当化できるものでない場合、借主が退去に応じる義務はなく、交渉を有利に進めることができます。
こうした状況では、貸主が立ち退きを実現するために立ち退き料を増額するケースも少なくありません。
店舗や事務所が立ち退きを求められた場合、移転によって売上の減少が見込まれることがあります。
特に、顧客の多くが立地に依存している業態では、新しい場所への移転によって固定客を失うリスクが高まります。
また、新規顧客を獲得するための広告費やマーケティング費用も発生するため、営業損失の補償を求める理由になります。
さらに、移転準備や新たな店舗の設営には時間がかかるため、その間の休業による売上減少も無視できません。
特に、飲食店や小売業などの業種では、一時的な閉店が長引くほど経済的な影響が大きくなります。
このように、移転による営業損失が見込まれる場合には、立ち退き料の増額を交渉する根拠となります。
上記以外にも、立ち退き料を増額できるケースには様々なものがあります。
立ち退きによって借主側が被る損失が大きいほど、立ち退き料を増額できる可能性が高まります。
これらのケースでは、借主が不利な状況に置かれていると判断され、立ち退き料が増額される可能性があります。
立ち退き料の増額には、貸主との交渉が欠かせません。
単に「もっと補償を増やしてほしい」と主張するだけではなく、合理的な根拠を示し、戦略的に交渉を進めることが重要です。
ここでは、具体的な増額の方法について解説します。
立ち退きに伴う費用を明確にし、それを根拠として貸主に提示することで、増額交渉をスムーズに進めることができます。
たとえば、以下の費用が該当します。
事業者の場合は、内装の撤去・再施工費、休業による売上減少分、広告・販促費用なども考慮しなくてはなりません。
具体的な見積もりを取得し、数字を示すことで貸主に納得してもらう材料となり得ます。
借地借家法では、貸主が契約の更新を拒絶したり、立ち退きを求めたりする場合、「正当事由」が必要です。
この正当事由が十分でない場合、借主には強い交渉権があり、立ち退き料を増額させる余地が生まれます。
たとえば、「建物の老朽化を理由にしているが、まだ十分に使用可能」「貸主の自己使用とされているが、本当に必要なのか不明」というケースでは、貸主側の理由は立ち退きを求めるには主張が弱いといえるでしょう。
このような場合には、借主は立ち退きを拒否するか、より高額な補償を求めることが可能です。
貸主が早期解決を望むなら、立ち退き料の増額に応じる可能性が高まります。
立ち退き交渉では、貸主側が提示する最初の立ち退き料をそのまま受け入れず、粘り強く交渉を続けることが重要です。
貸主としては、できるだけ少ない補償で解決したいと考えますが、交渉が長引くと物件の再開発や売却計画に支障が出るため、妥協点を探ろうとします。
この状況を利用し、交渉の長期化を避けるために立ち退き料の増額を引き出すことができるでしょう。
特に、弁護士を介して交渉することで、法的な裏付けを持った主張ができるため、貸主側も簡単には譲歩を求めにくくなります。
交渉をスムーズに進めるためにも、法律の専門家と連携することが有効です。
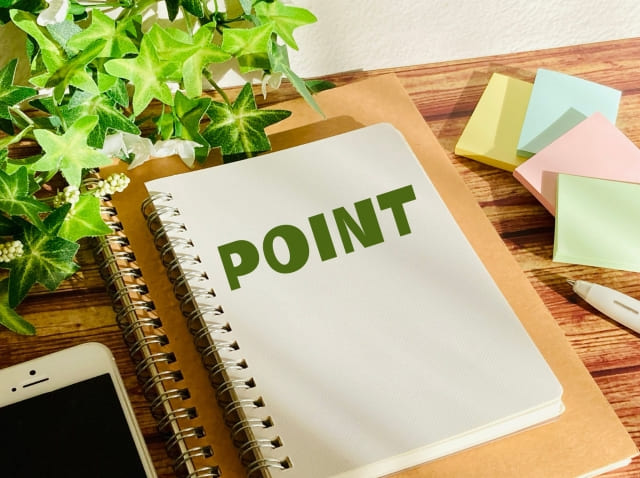
立ち退き交渉では、貸主と対等な立場で話し合いを進めることが重要です。
感情的にならず、冷静かつ戦略的に対応することでより有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
ここでは、立ち退き交渉のポイントについて詳しく解説します。
立ち退き交渉では、貸主とのやり取りを記録に残すことが後々のトラブルを防ぐ上で重要になります。
口頭での話し合いは貸主側の都合で解釈される恐れがあるため、可能な限りメールや書面でのやり取りを心掛けましょう。
たとえば、貸主が提示した立ち退き料の額や、立ち退きを求める理由について文書化しておくことで、交渉内容を明確にし、後で条件を変更されることを防ぐことができます。
また、賃貸借契約書や建物の修繕履歴、営業実績(店舗の場合)など、交渉をスムーズに進めるための資料も交渉前に整理しておくとよいでしょう。
特に、建物がまだ十分に使用可能であることを示す写真や修繕記録、借主の営業に影響が出ることを示す売上データなどがあると、貸主の「正当事由」の弱さを指摘しやすくなります。
立ち退きを求められた際、貸主側はできるだけ早く話をまとめたいと考えていることが多いです。
そのため、借主が即答せずに慎重な姿勢を取ることで、交渉の主導権を握ることができます。
貸主は時間が経つにつれて再開発や売却計画に影響が出るため、焦りが生じる可能性があります。
この状況を利用し、よりよい条件を引き出すことが戦略的な交渉のポイントです。
また、貸主が最初に提示する立ち退き料は、ほとんどの場合、最低限の金額になっています。
そのため、すぐに受け入れず、「この条件では難しい」と伝えた上で、追加の補償を求めるとよいでしょう。
たとえば、「移転にかかる費用を考慮すると、この金額では対応できません」「新たな物件を見つけるまでの期間が必要です」といった形で、具体的な理由を示しながら交渉を進めると、貸主側も譲歩しやすくなります。
立ち退き交渉では、法律や契約に関する知識が求められるため、専門家のサポートを受けることで、よりよい条件で交渉を進めることができます。
特に、弁護士や不動産コンサルタントに相談することで、貸主の主張の妥当性を判断し、適切な反論や要求を行うことが可能になります。
さらに、弁護士を通じて交渉を行うことで、貸主側も慎重な対応を取らざるを得なくなります。
貸主としても、法的なトラブルに発展することを避けたいと考えるため、交渉をスムーズに進めやすくなります。
費用はかかりますが、最終的に得られる立ち退き料の増額を考慮すれば、十分にメリットがあると言えるでしょう。
立ち退き料は、あなたの生活や事業を守るために重要なものです。
相場や交渉のポイントを理解し、適切な準備と対応を行うことで、納得のいく結果が得られる可能性が高まります。
しかし、立ち退きに関する法律や手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場面も多いです。
少しでも不安を感じたら、一人で悩まず弁護士や不動産鑑定士などの専門家へ相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、あなたの権利を守り、よりよい条件で立ち退きを実現できるでしょう。