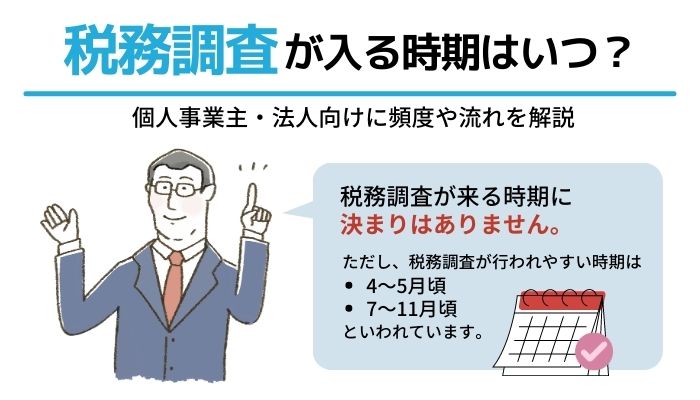最終更新日:2025/5/8
税務調査の期間は何年?対象年数と追徴課税の仕組みをわかりやすく解説

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

税務調査とは、申告された内容に誤りや不正がないかを確認するために、税務署が法人や個人事業主に対して実施する調査です。帳簿や申告書の内容が正しく記載されているか、経費や売上に不自然な点がないかなどをチェックするために、ある日突然調査が入ることもあります。
従来は企業が主な対象とされてきましたが、近年では副業やフリーランスとして収入を得ている個人も増えており、税務調査は誰にとっても他人事ではありません。
では、税務調査ではどこまで過去にさかのぼって調査されるのでしょうか。また、もし脱税と判断された場合には、どのような税金やペナルティが課されるのでしょうか。
本記事では、税務調査の対象となる期間やその理由、調査で不備が見つかった際の対応について詳しく解説します。
税務調査の基本的な対象期間は3年である
税務調査では、申告に使った帳簿や領収書などの資料をチェックされることになります。
資料を準備して、チェックできるように整えておくことが重要です。
あまりにも古い資料は廃棄しているケースも少なくありません。
だからこそ、過去何年分チェックされるのかは大切なポイントになります。
税務調査では、過去何年分の資料を準備しておけばいいのでしょうか。
基本的な税務調査では、3年分の資料をチェックすることになります。
税務調査において「過去何年分の資料をチェックしなければならない」という法律上の決まりはありません。
税務調査によっては、3年分の資料をチェックする前に終了することもあります。
3年分の資料を整えておいても、2年分の資料をチェックした段階で「もういいですよ」と言われることがあるのです。
基本は3年分の資料がチェック対象になると覚えておきましょう。
ただし、税務調査で問題が見つかった場合は、さらに長い期間が調査対象になります。
税務調査で問題や不正が見つかった場合の対象期間
税務調査で不正や問題が見つかった場合は、対象期間が伸びます。
伸びる期間はケースによって変化しますが、5年ないしは7年になります。
税務調査の対象期間が5年になるケース
問題が見つかった場合は、対象期間が5年になります。
税務調査の対象期間が5年に遡る代表的なケースは、申告のミスが見つかったり、否認があったりした場合。
税務調査の対象期間は基本的に3年ですが、ミスや否認を税務署側が発見した場合は、3年で留まらずさらに資料を確認することになります。
調査対象期間の基本は3年。
税務署側が「これは大丈夫そうだな」と思ったら、裁量で1年や2年の資料をチェックするだけで終了する可能性あり。
ちょっとしたミスや税務署側が気になるポイントを見つけたら資料の調査対象期間が5年になる。
こんなふうに覚えておけばわかりやすいはずです。
税務調査の対象期間が7年になるケース
悪質な問題が見つかった場合は、税務調査の対象期間が7年になります。
悪質な問題とは、明らかな脱税など。
対象期間が5年のケースは、問題が見つかった場合でした。
対して対象期間が7年になるのは、悪質な問題が見つかった場合です。
ちょっとしたミスで済まないからこそ、さらに調査されることになります。
税務調査の対象になる期間は最長7年です。
不正の疑いがある場合や、事実の隠蔽がある可能性がある場合は、最長で過去7年分の税務調査ができるという決まりがあるのです。
最長で過去7年という期間は、国税通則法第70条第4項に定められています。
7年という期間はかなり長いもの。
小学校1年生が中学生になるほどの期間です。
最悪のケースでは、それだけ長い期間の資料を徹底的に調べられることに。
ただ、最長で過去7年なので、それより過去を調べられることはないと解釈することも可能です。
税務調査で申告ミスが見つかったらどうなるのか
税務調査で税金の申告ミスが発覚した場合や、悪質な脱税などが見つかった場合は、ペナルティを課されることになります。
ペナルティは税金の加算。
要するに、罰金のようなものです。
悪質さやケースによってペナルティの重さや種類が変わってくるという特徴があります。
税務調査で問題が見つかった場合にかかる税金
税務調査で問題が見つかった場合は、次のような税金がかかります。
- 1.過少申告加算税
- 2.無申告加算税
- 3.重加算税
- 4.不納付加算税
- 5.延滞税
この他にも、税務調査で嘘をついたり、税務調査に非協力的であったりする場合もペナルティの可能性があります。
税務調査での対応によってはさらに痛い結果になって頭を抱えることも。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告ミスなどのために本来より少ない税額を申告してしまったと判断された場合に課される税金(ペナルティ)です。
加算される税率は10%から15%、ただし、税務調査前において自主的に「間違っていました」と修正申告をした場合は課されません。
無申告加算税
無申告加算税とは、申告すべき期限までに申告の手続きをしなかった場合に課される税金(ペナルティ)です。
申告しなければならないのに、しなかった。よって、15%~20%の税金が加算されます。
自分から「期限に送れてしまいました」と素直に申し出て手続きした場合にはペナルティが5%に軽減。
重加算税
税金を過少申告した場合に課される税金(ペナルティ)です。
過少申告加算税との大きな違いは悪質さです。
科重加算税の場合は、過少申告でも特に悪質なケースや意図的に過少申告したケース、事実や資料を隠蔽したケースに課される重いペナルティになります。
重加算税が課される代表的なケースこそが脱税です。
加算される税率は35%~40%、悪質だからこそ、加算も大きくなっています。
不納付加算税
源泉所得税を所定の期限まで納めなかった場合に加算される税金(ペナルティ)です。
基本的な加算は10%、税務署に指摘される前に自主的に納めた場合はペナルティが軽減され、5%になります。
延滞税
納付期限まで税金を納付しなかったことに対する税金(ペナルティ)が、この延滞税です。
ミスなどで納めなかった場合もこのペナルティがあります。
利息のようなものだと解釈すればわかりやすいことでしょう。
税務調査で脱税が見つかったらかかる税金
1つの例として、税務調査で脱税が見つかったケースについて考えてみましょう。
脱税の場合は、まずは本来納めるべき税金をしっかり納めなければいけません。
税金が1,000万円なのに500万円で申告していた場合は、足りない分の税金を納めることになります。
500万円しか払っていないなら、差額は500万円です。
さらに、ペナルティ分の税金が課されます。
脱税という悪質なケースなので、重加算税が加算。
税金の支払いが遅れた分の延滞税も加算されることになります。
延滞税は利息のような存在なので、支払いが遅れるとそれだけペナルティが重くなる結果に。
まとめ
税務調査は唐突にやってきます。
基本は3年。
問題点があればさらに長い期間が調査対象になります。
ミスや問題がないように、「税務調査は自分のところにも来る可能性がある」という意識を持ちたいもの。
申告や資料に不備がなければ、税務調査にびくびくする必要はありません。
いざ税務調査という時に慌てずに済むように、税理士にアドバイスを受けられる体制を整えておきましょう。
税務調査 関連記事
- 税務調査の対象になる会社の特徴とは?選ばれやすい理由を解説
- 税務調査の流れと対応のポイント!調査対象にされやすい特徴とは?
- 税務調査では何年分調べるの?脱税が見つかった場合にかかるお金とは
- 税務調査では何が行われるのか?調査対象になりやすい会社と備え方
- 税務調査で見られるポイントや注意点とは?
- 税務調査が来る頻度や確率|特に警戒が必要な業種や事業者は?
- 税務調査の頻度とは?
- 税務調査の対象になりやすい会社や業種とは?
- 税務調査の対象期間は何年?脱税が見つかった場合にかかる税金など詳しく解説
- 税務調査に入られる個人事業主の特徴4つ!事前に対策を考えよう
- これで怖くない!税務調査が行われる日の実際の流れと対策について
- 税務調査の不安を解消する税務調査の真実 パーフェクトガイド