

東京弁護士会所属。東京都出身。
弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。
立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。
複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。
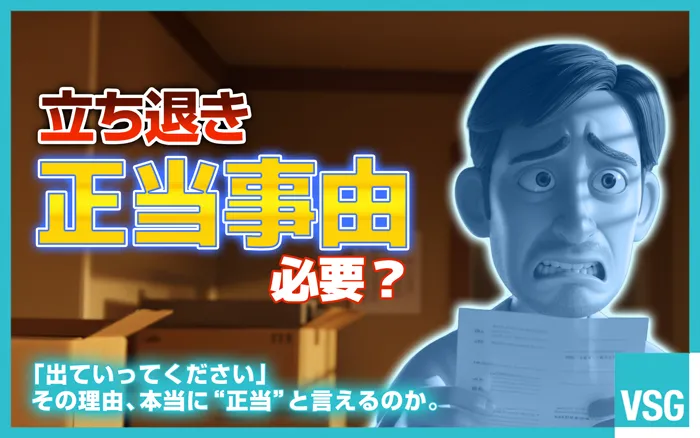
「突然、大家から立ち退きを求められた」「建物を取り壊すから契約を終了すると一方的に通知された」——賃貸住宅に住んでいる方にとって、こうした状況は非常に大きな不安を伴うものです。
しかし、貸主が一方的に契約の更新を拒んだり、退去を求めたりすることは、法律上そう簡単には認められていません。借主の住まいを守るため、借地借家法では「正当事由」がなければ立ち退きや更新拒絶ができないと規定しています。
とはいえ、どんなケースであれば正当事由に該当するのか、自分のケースが正当事由に該当するのかがわからない人も多いと思います。立ち退き交渉で不利な立場に立たないためにも、立ち退きが認められる「正当事由」について正しい知識をつけましょう。
この記事では、借地借家法28条における「正当事由」の判断基準や、正当事由に納得できない場合の対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
貸主が借主に立ち退きを求めるには、法律上、一定の要件を満たす必要があります。とくに普通借家契約では、「正当事由」がなければ立ち退きや更新拒絶は認められません。
普通借家契約では、貸主が一方的に契約の更新を拒んだり、契約途中で解約を申し入れたりすることは原則認められていません。借地借家法28条では、借主の居住を保護するため、「正当事由」がある場合にのみ立ち退きや更新拒絶が認められると定めています。
「正当事由」とは、貸主・借主それぞれの事情を総合的に見て、契約終了に妥当性があるかを判断する基準です。たとえば、貸主が「建物を自分で使いたい」「建て替えを検討している」と主張しても、借主の生活状況や転居の困難さなどを考慮した結果、正当事由が認められないケースもあります。
契約を終了するという通知を受けたとしても、借主が直ちに退去しなければならないとは限りません。まずは契約の種類や状況を確認し、冷静に対応することが大切です。
定期借家契約では、契約期間が満了すると、正当事由がなくても貸主は契約を終了できます。更新を前提としない契約形態であるため、貸主は期間満了後に借主へ退去を求めることができます。
この契約は、契約時に「これは定期借家契約である」という旨を書面で説明しなければ無効とされています。借主が内容を十分に理解したうえで契約を結んでいることが前提となるため、貸主は契約終了時に正当事由を主張する必要がありません。
たとえば「2年間の定期借家契約」が終了した場合、貸主が「建物を取り壊したい」などの理由を示さずとも、借主に退去を求めることが可能です。
ただし、契約書の説明不足や、普通借家契約と誤認されていた場合などは、貸主側の主張が通らないケースもあります。契約内容や正当事由について疑問があれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
借地借家法第28条では、契約の更新拒絶や解約が認められるための判断基準として、「正当事由」に関する要素をいくつか挙げています。建物の使用目的や契約の経過、建物の状況、立ち退き料などを総合的に見て判断されるのが特徴です。
以下では、主な5つの判断要素について具体的に解説します。
建物の使用目的と必要性は、正当事由を判断するうえで重要な要素の一つです。
たとえば、貸主が建物を自分や家族の居住に使いたい、あるいは売却や建て替えを予定している場合は、使用の必要性があると評価されやすくなります。特に、高齢の親と同居する必要があるなど、現実的かつ差し迫った事情があれば、正当事由として認められる可能性は高まります。
一方で、貸主が多数の不動産を所有しており、当該建物を使わなくても支障がないと判断される場合は、使用の必要性が低いとみなされ、正当事由が否定されやすくなります。
借主側も、建物の必要性を主張できます。たとえば、病気の家族と居住している、長年営業に使用しているといった事情があれば、退去により生活や事業に深刻な影響が出ると判断され、借主側が保護されることもあります。
裁判所は、貸主と借主の双方の事情を比較し、どちらがより切実に建物を必要としているかを総合的に判断します。
どのように契約して、どのようなやり取りを経て立ち退きに至っているか――こうした経緯も、正当事由の有無を見極めるうえで重要な判断材料になります。契約の締結から立ち退きを求めるに至るまでの経緯を総合的に見て、契約関係が円滑だったかどうかを判断します。
賃料や更新料の支払い状況、契約期間の長さ、信頼関係が維持されていたかなどが、主な判断材料になります。借主が家賃を繰り返し滞納していたり、更新料を支払っていない場合には、貸主との関係が悪化していたと見なされ、正当事由を補強する事情とされることがあります。
また、契約締結時にどのような約束があったのか、過去の更新時に貸主がどのように対応してきたかといったやり取りも考慮されます。急な通知や一方的な態度があった場合には、貸主の信頼性が疑問視されることもあります。
このように、契約当初から立ち退きを求めるまでの流れや、貸主・借主間の信頼関係の変化が、正当事由の判断に大きく影響します。
借主が建物をどの程度活用しているか、契約上の義務を守っているかなども、正当事由の判断では重要なポイントとなります。
たとえば、借主が契約に違反して無断転貸をしていたり、禁止されている用途で使用していたりする場合は、契約違反と見なされ、正当事由を補強する事情として扱われることがあります。とくに、貸主が再三注意しても改善が見られない場合は、信頼関係が破綻していると判断される可能性もあります。
また、建物を借りていてもほとんど使っていない場合や、長期間空き家状態になっているケースでは、借主の使用の必要性が低いと評価されることがあります。生活や事業の拠点としての実態が乏しいと、建物を使用する意義が薄いと判断され、貸主の事情が優先されやすくなるのです。
このように、建物の使われ方や契約の遵守状況は、実質的な利用の有無を示すものとして、裁判所の判断に大きく影響します。
建物の安全性や居住環境の問題から、建て替えを検討せざるを得ない状況もあります。そうしたケースでは、老朽化の程度や耐震性、設備の損傷状況などをふまえて、契約終了が認められるかどうかが判断されます。
たとえば、築年数が古く耐震基準を満たしていない、配管や給排水設備の破損がひどく修繕も困難といった事情があれば、建物の使用継続が現実的ではないと見なされやすくなります。とくに過去の地震によって構造的なダメージが蓄積している場合などは、安全面の観点からも建て替えの必要性が認められる傾向にあります。
貸主側が新築アパートなどの建築を予定している場合、老朽化や耐震性の問題を理由に立ち退きを求めることが増えています。ただし、建て替えの具体的な計画や安全上の理由が伴わない限り、正当事由として認められない場合もあります。
築年数に明確な基準はないものの、一般的には築30年を超えると建て替え時期とされることも多いです。そうした建物に住んでいる場合は、立ち退きを求められる可能性を認識しておくとよいでしょう。
貸主からの立ち退き要求に対して、「財産上の給付」があったかどうかも、正当事由の判断に影響します。ここでいう財産上の給付とは、立ち退き料の支払いや代替物件の提供を指します。これらは借主に対する補償として、立ち退きによる不利益を軽減する役割を果たします。
とくに立ち退き料は、正当事由を補完する要素とされることが多く、貸主からどのような補償の申し出があったかが重視されます。たとえば、借主が近隣へ引っ越す場合、転居費用・新居の礼金・仲介手数料などを立ち退き料として貸主が負担することがあります。事業用物件であれば、内装工事費や営業損失への補填も含まれることがあります。
立ち退き料に明確な基準はありませんが、居住用なら通常は6カ月〜1年分程度の賃料相当が相場とされ、事業用では交渉によりさらに高額となる場合もあります。
また、代替物件の紹介や確保があったかどうかも、正当事由の有無を判断するうえで重要です。反対に、ほかの要素(たとえば建物の老朽化や貸主の使用目的)が非常に強ければ、立ち退き料の支払いがなくても退去が認められるケースもあります。
立ち退き料や補償内容は物件の状況や契約形態によって大きく異なるため、安易に応じず、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応することが大切です。
正当事由が実際にどのような事情で認められるかは、裁判例を見ることで具体的にイメージしやすくなります。ここでは、立ち退きに際して実際にどのような要素が評価されて契約終了が認められたのか、裁判例を基に解説していきます。
2階建て木造アパートについて、貸主の相続人Xが、建物の老朽化と過去の契約における更新終了合意を根拠に、唯一の入居者である借主Yに立ち退きを求めた事案です。
アパートは築50年を超え、耐震診断の結果「倒壊の可能性がある」とされており、Xは近隣の建物と合わせて解体し、駐車場や低層マンションを計画していました。
また、Yは更新終了合意後も10年以上居住を続けており、Xは立ち退き料として賃料6か月分(27万円)の支払いも申し出ていました。
東京地方裁判所は、Xの明渡し請求を認め、Yに立ち退きを命じました。
裁判所は、築年数が50年を超え、耐震性にも問題があり倒壊の危険があること、入居者がY1人のみで収益性が著しく低下していることなどから、貸主Xにとって明渡しを求める必要性は相当程度高いと認定しました。
他方で、借主Yは30年以上居住し、70歳を超える高齢者であるため、引き続き住み続ける必要性も一定程度認められると判断しました。
しかし、Y自身が過去に「更新は今回限り」との特約付き契約に署名押印していたことや、その後も10年以上居住を継続していたことなどを踏まえ、居住の必要性は相対的に低下していると評価。最終的には、貸主が申し出た立ち退き料(賃料および共益費6か月分)が借主の不利益を補完するものとして、正当事由を認めています。
築57年の木造平屋戸建て住宅について、貸主Xが老朽化と建替えの必要性を理由に、借主である高齢女性Y1およびその娘Y2に対して、賃貸借契約の解約と建物明渡しを求めた事案です。Xは倒壊の危険性を強調し、立ち退き料として840万円の支払いも申し出ましたが、借主側は建物の安全性やY1の健康状態を主張して立ち退きを拒否しました。
東京地方裁判所は、Xの明渡し請求を棄却し、正当事由を否定しました。
裁判所は、建物が旧耐震基準で築後57年を経過している点について、「比較的簡易な補強で十分対応可能であり、早急な建替えや補強の必要はない」とする専門家の意見書につき、不合理な点はないと判断しました。
また、借主Y1については、肺気腫など重篤な健康問題を抱えており、長年慣れ親しんだ住宅からの転居が生命に関わるリスクを伴うとし、「極めて高い自己使用の必要性がある」と認定。
一方で、貸主Xの建替計画は自身の使用目的ではなく、正当事由としての必要性も乏しいと判断されました。
その結果、立ち退き料による正当事由の補完を検討するまでもなく、解約告知に正当事由はないと結論付けられました。
築後45年以上が経過し老朽化したアパートの1室を巡って、賃貸人Xらが賃借人Yに対して契約の解約と建物の明渡しを請求した事案です。Xらは、アパートの倒壊リスクや耐震補強に必要な高額費用を理由に建物の取壊しを主張し、補完的事情として立ち退き料100万円の支払いを申し出ました。これに対し、Yは老朽化の原因は賃貸人の修繕義務違反であるとして争いました。
東京地方裁判所は、Xらの請求を認容し、立ち退き料100万円をもって正当事由を補完できると判断しました。
裁判所は、アパートが築45年を超えており、全体として老朽化が著しく、耐震性にも問題があることから、Xらに建物を取壊す必要性があると認めました。加えて、耐震補強や修繕に多額の費用がかかる点からも、現実的に建替えが妥当とされました。
一方で、Yは当該建物を住居として利用しており、賃料の滞納もないことから、一定の保護が必要とされました。「直ちに正当事由があるとまではいえないが、正当事由を基礎づける事実が相当程度認められる」と判断しています。
そこで裁判所は、賃料の20か月分以上に相当する100万円の立ち退き料支払いが補完的事情として十分であると判断し、Xらの請求を認容しました。
貸主からの立ち退き要求に対して、「正当事由があるのか疑問だ」と感じることは少なくありません。納得できないまま退去に応じてしまうと、不利益を被るおそれがあります。ここでは、借主としてとるべき具体的な対応策を3つの視点から紹介します。
貸主から立ち退きを求められても、すぐに応じる必要はありません。「正当事由がある」と一方的に主張されたとしても、その内容が法律的に妥当であるかどうかは慎重に判断されます。たとえば、建物の老朽化や自己使用の必要性といった理由があっても、それが本当に正当性のある事情かどうかはケースバイケースです。
借主としては、自身の生活実態や契約の状況などを整理し、「正当事由には該当しない」と具体的な根拠をもって反論する姿勢が大切です。長期間その建物に居住していた場合や、家賃を滞納せず誠実に契約を履行している場合などは、借主の保護が優先されることもあります。
反論の際は、感情的にならず、事実と証拠をもとに冷静に主張することがポイントです。不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらうと安心です。
たとえ正当事由の一部が認められたとしても、貸主が提示する補償条件が妥当でなければ、借主としては補償の増額や代替物件の提供を求めることができます。立ち退きにより新しい住居を探す手間や費用、営業を行っている場合には移転コストや営業損失など、多くの負担が発生するためです。
立ち退き料には、引っ越し費用、新居の礼金・仲介手数料、家賃差額などが含まれるのが一般的で、場合によっては新居の内装費用や営業損害の補填なども対象になります。
貸主から一方的に提示された内容に納得できない場合は、その場で即答せず、内容を十分に吟味して交渉を行いましょう。無理に立ち退きに応じる必要はなく、正当な補償を求めることは借主として当然の権利です。
立ち退き交渉が難航している場合や、貸主から強く退去を迫られて精神的に負担を感じている場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、正当事由の有無や補償内容の妥当性について法的観点からアドバイスを受けられます。
また、弁護士が窓口となることで、貸主との直接交渉を避けられるため、精神的なストレスが大きく軽減されるのも大きなメリットです。仮に裁判に発展した場合でも、弁護士が代理人として対応してくれるため、不利な立場に立たされるリスクを回避できます。
立ち退きにくわしい弁護士に依頼すれば、過去の判例などに基づいた実践的なアドバイスも受けられます。初回相談無料の事務所もあるため、無理に一人で解決しようとせず、早めに専門家の力を借りるとよいでしょう。
貸主が立ち退きを求めても、借主が応じない限りすぐに強制退去にはなりません。退去を実現するには、貸主が裁判で正当事由を立証し、明け渡し判決を得たうえで強制執行の手続きが必要です。ただし、家賃の滞納が続いている場合は「契約違反」と判断され、立ち退きに正当性が認められやすくなるため注意が必要です。
正当事由がない限り、借主が立ち退きに応じる義務はありません。借地借家法では、貸主が契約の終了や更新拒絶をするには正当な理由が必要とされています。納得できる理由や補償がない場合は、退去に同意する必要はありません。
立ち退き料を増額してもらうためには、以下のポイントを意識することが重要です。
立ち退き料の増額を目指すには、まず貸主の「正当事由」がどれほど強いかを冷静に分析しましょう。事情が弱ければ交渉の余地が広がります。また、「いつまでに退去してほしいのか」を確認することで、期限に応じる代わりに補償を引き上げる交渉も可能です。交渉の記録は書面や録音などで残しておけば、トラブルを避けることや、訴訟の証拠として役立ちます。
注意点として、家賃滞納や感情的な言動は逆効果です。信頼関係を損ねれば、補償を受けるどころか契約解除の理由にもなり得ます。誠実かつ冷静な対応を心がけましょう。
賃貸物件の立ち退きを求められたときは、まずその要求に「正当事由」があるかどうかを確認することが重要です。正当事由の有無は、建物の使用目的や老朽化の状況、借主への補償内容など、複数の要素を総合的に考慮して判断されます。貸主からの一方的な要求に従う必要はなく、不当と思われる請求には根拠をもって冷静に対応しましょう。
立ち退き料や代替物件の提供条件も、借主が不利益を被らないようしっかりと確認し、必要に応じて交渉する姿勢が求められます。不安がある場合や話し合いが難航する場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
相談先に迷ったら、立ち退き案件に豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」にお気軽にご相談ください。