
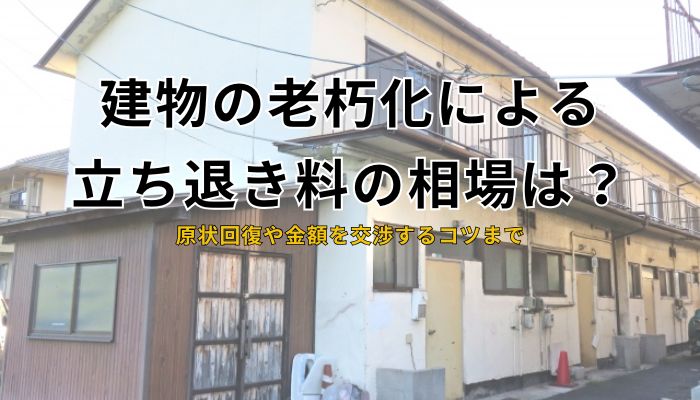
老朽化した建物の改修は、賃借人に立ち退きを求めるための正当事由として認められる可能性があります。
正当事由とは、賃借人に退去を求めるためのやむを得ない事情であり、老朽化の程度や立ち退き料の額などから総合的に判断されます。
立ち退き料の相場は、マンションやアパートは数十万円〜200万円ほど、店舗では数百万円〜数千万円を超えるケースもあるでしょう。
ここでは、建物の老朽化を理由に退去を求められた場合の立ち退き料やその相場などを解説します。
目次
建物が倒壊する恐れがあるほど老朽化している場合、賃借人に立ち退きを求めるための正当事由になる可能性があります。
正当事由とは、賃借人へ退去を求めるための相当な理由です。
たとえば、以下のようなケースで認められる可能性があります。
建物の老朽化だけでなく、家主の事情や賃借人の生活状況、立ち退き料の額などから総合的に判断されます。
建物の老朽化を理由として立ち退きを求める場合は、多くのケースで立ち退き料が必要です。
立ち退き料には、退去に伴う賃借人の損失補填や慰謝料としての意味があります。
例外的に、契約時にあらかじめ建物の取り壊しの予定や時期が定められているときは立ち退き料が認められない可能性があるでしょう。
賃借人に契約違反がある場合など、契約が解除される事由があるときも立ち退き料はもらえません。
建物の老朽化に加えて、耐震性能が不十分であったために正当事由が認められた判例があります。
該当の建物は、昭和49年に建設された9階建ての鉄筋鉄骨コンクリート造りでした。
建物にはひび割れや雨漏りなどの経年劣化が見られ、耐審診断では「十分な耐震性を有していない」と判定されています。
しかし、耐震補強工事費用を行うと新築工事費用の半額程度に達すると判明しました。
建物を取り壊して新築工事を行ったほうが、経済合理性を有すると認定されています。
つまり、耐震補強工事を行ったとしても経年劣化した建物の寿命は短く、建て替えを行ったほうが合理的で社会通念上無駄がないと判断されました。
上記のように正当事由が認められるのは、老朽化に加えて建物の安全性を脅かす危険性があるときや社会通念上合理的ではないときです。
老朽化+αで複合的な要因が重なると家主側の正当事由が認められる可能性が高まります。
正当事由は、裁判所がさまざまな状況を鑑み総合的に判断を下します。
参照元:東京地裁平成22年12月27日/建物の耐震強度不足による立ち退きの判例
立ち退き料の相場はケースによって異なりますが、家主の退去を求める正当事由の強さや賃借人の受ける損害などが考慮されます。
たとえば賃借人が店舗営業をしている場合は、立ち退きによって休業補償も必要になるため一般的に立ち退き料は高額になります。
ここからは、賃貸マンション・アパートと店舗の場合で立ち退き料の相場がどのように算定されるのかを確認していきましょう。
賃貸マンションやアパートの立ち退き料は、数十万円〜200万円ほどになるケースが多いです。
立ち退き料は以下の費用などが含まれます。
新居は現在の住宅と同程度の生活が可能な物件であり、より広い新居に引っ越すときは増額分が認められない可能性があります。
要介護者がいるなど、賃借人に引っ越しが困難な事情があるときは立ち退き料に慰謝料や迷惑料が加算されるケースもあるでしょう。
飲食店や美容室など、事業を営んでいる店舗の立ち退き料は数百万円〜数千万円を越える場合もあります。
前述の家賃差額や引っ越しの初期費用に加え、以下の費用などが立ち退き料として必要です。
休業補償は、営業を休止する期間の収益や発生し続ける固定費などから計算します。
店舗の移転によって顧客を失うリスクが高い場合、売上の減少に応じた補償や広告費用などを上乗せするケースもあるでしょう。
建物の老朽化による立ち退きで、立ち退き料を交渉するには以下のコツがあります。
ここからは、立ち退き交渉のコツについてご紹介していきます。
家主側に立ち退きが必要な理由を聞き、正当事由の有無を確認します。
一般的に正当事由と立ち退き料には以下のような関係性があります。
| 正当事由の必然性 | 立ち退き料の金額 |
|---|---|
| 強い | 低くなる |
| 弱い | 高くなる |
仮に立ち退き料が低く設定されていれば、賃借人側は提示された金額に即座に納得せず、立ち退きの意思がない旨を伝えましょう。
一度、家主側には立ち退きの意思がないと伝え、物件の必要性をアピールしましょう。
たとえば、経済的に他の賃貸への転居はできない、重い病気を患う親の介護のため実家に近い家が必要などです。
家主側もできるだけ早く立ち退き交渉をまとめたいと考えています。
賃借人側に立ち退きの意思がないと伝えられれば、早急に交渉をまとめようと立ち退き料の増額を検討するでしょう。
家主側の再度の提示を待って、交渉を進めていきます。
あらかじめ立ち退きによる引っ越し代などの実費や、損害をまとめておきます。
賃借人が立ち退きにかかる主な実費は以下の通りです。
損害額は引っ越し先との差額家賃だけでなく、店舗運営であれば休業中の営業収入などが該当します。
計算の根拠となる見積書や契約書などを準備しておきましょう。
立ち退き交渉は法的知識が必要になるため、弁護士に依頼するのが原則です。
特に正当事由の判断は、借地借家法に詳しい専門家の意見が必要となります。
弁護士に依頼すれば、正当事由を適切に判断し、スムーズに交渉を進められるでしょう。
立ち退き交渉から立ち退き料を受け取るまでの流れは以下の通りです。
立ち退き料が支払われるタイミングは、部屋を引き払い、鍵を家主側に返却する当日に振り込まれるのが一般的です。
賃貸物件から退去するときは、原則として借りる前と同じ状態に戻す原状回復が必要です。
賃借人の故意や過失による損壊は、賃借人が修繕費などの原状回復費用を負担します。
ただし、老朽化による取り壊しなどを理由とした立ち退きの場合、原状回復は不要となるケースが多いでしょう。
取り壊し予定の建物は、原状回復をする必要がないケースがほとんどであるためです。
原状回復費用の要否は賃借人だけで判断せず、家主側に確認をしましょう。
建物の老朽化は賃借人に危険が及ぶと判断され、正当事由として認められる可能性があります。
一方で、賃借人の生活や事業に大きな影響を与えるため、立ち退き料が必要となるケースがほとんどです。
立ち退き料の交渉では、家主から不当に低い金額を提示されるケースがあります。
立ち退き料の交渉は専門的な知見が必要となるため、弁護士に交渉の代行を依頼するとよいでしょう。
弁護士は過去の判例や相場を根拠に交渉してくれるため、もらえる立ち退き料が大幅に増える可能性があります。