

東京弁護士会所属。東京都出身。
弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。
立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。
複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。
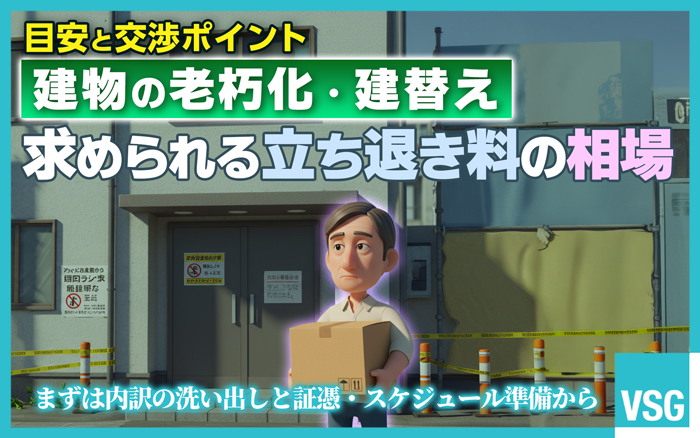
目次
建物の安全性や再開発等の事情で退去を求める場合、貸主側の必要性・代替可能性・提供条件などを
総合考慮して正当事由が判断されるのが一般です。通知のタイミング・書式、説明の具体性、代替案の有無、
そして提示条件(立ち退き料や猶予期間等)が評価に影響します。
定期借家と普通借家では要件や手続が異なるため、契約書・覚書・更新の経緯を確認しましょう。
住居では一般に家賃の3〜6か月程度が語られることはありますが、建替え工程・工期・仮住まいの確保、
転居時期の制約、地域相場、原状回復の範囲などで変動します(事案により)。定額ではないため、
根拠資料(見積や相場)で積み上げるのが実務的です。
安全確保は最優先ですが、通知の形式・内容・代替案を含めた協議が必要です。医師の通院・就学等の事情は配慮要素になります。
定型ルールはありませんが、工期や入居制約が大きい場合は調整項目になり得ます(事案により)。
合意書に工程変更時の連絡・負担調整の条項を設け、変更時の協議プロセスを明記しておくとトラブル防止に有効です。
老朽化・建替えを理由とする退去要請では、正当事由・通知の適法性・工程の妥当性を踏まえつつ、
立ち退き料は転居負担の実費+調整要素を積み上げる形で協議されます。一般に住居は家賃の3〜6か月程度と
語られることはあるものの、工期・地域相場・仮住まいの確保で大きく振れます。見積・相場・スケジュール
の根拠を揃え、金額と明渡日のセット合意を目指しましょう。契約類型や条項により手続が異なるため、
書面と経緯を前提に弁護士へ早期に相談するのが確実です。