

東京弁護士会所属。埼玉県出身。
建物の老朽化や売却に伴う「立ち退き」は、これまで大切にしてきた生活やビジネスの基盤を揺るがす大きな出来事です。突然の通告に対し、「いつまでに、いくらで立ち退くのが正当なのか」という不安を抱えるのは当然のことです。
立ち退き交渉を円滑に進めることは、いわば「目的地へ向かうための線路を、専門家と一緒に安全に敷き直すこと」に似ています。脱線(法的なトラブル)を防ぎつつ、適正な「立ち退き料」という切符を手に入れ、安心して次の場所へ移動できるようサポートするのが私の役割です。
私はこれまで不動産問題を中心に、数多くの交渉現場で依頼者様の権利を守ってきました。法律の壁は高く感じるかもしれませんが、難しい言葉を使わずに、一つひとつ丁寧に進むべき道をお示しします。まずはあなたの今の状況をお聞かせください。最善の解決策を共に導き出しましょう。
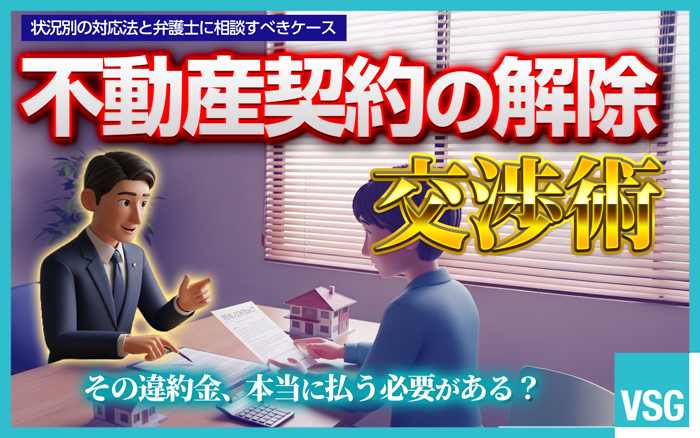
不動産の契約は高額なうえ、売買や賃貸に伴う準備や調整が広範囲に及ぶため、いったん締結すると簡単に取り消せるものではありません。とはいえ、契約後に住宅ローンの審査に通らなかったり、転勤・離婚・病気など予期せぬ事情が生じたりと、やむを得ない理由から契約の解除を考えざるを得ない状況も現実には起こり得ます。
こうした場面では、契約書の内容、関連する法律の規定、そして当事者間の交渉状況が、「契約を解除できるかどうか」や「どのような方法で解決を図るべきか」を判断するうえで重要な材料となります。
本記事では、不動産契約を解除したいときに誰に相談すべきか、状況に応じてどのように交渉を進めるべきかについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
不動産会社や都道府県宅建協会(全宅連)、消費生活センター、市区町村の無料法律相談窓口などは、不動産契約に関する相談先として利用できます。契約内容の確認や軽微なトラブルであれば、これらの窓口でも十分対応可能です。
しかし、契約の解除をめぐって金銭のトラブルが発生している場合や、解除の正当性について争いがある場合には、はじめから弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、契約書や法律を踏まえて適切な対応策を提示し、交渉や訴訟にも対応できます。トラブルが深刻化する前に、専門的な判断を仰ぐことが解決への近道です。
ここでは、弁護士に相談する主なメリットを3つご紹介します。
適切に不動産契約を解除するには、法律知識だけでなく、状況に応じた柔軟な判断力が欠かせません。弁護士に相談すれば、解除の可否やリスクを法的根拠に基づいて明確に示してくれるほか、必要に応じて相手方との交渉、通知書の作成、損害賠償請求まで一貫して対応してもらえます。
たとえば、買主が住宅ローンの審査に落ちて契約解除を希望する場合でも、ローン特約の条項や契約書の記載によって、解除が認められるかや金銭負担の有無は変わります。自己判断では見落としや誤解が生じやすく、結果的に不利な条件を受け入れてしまうおそれもあります。
法的判断と実務対応を一体で任せられることが、弁護士に相談する最大の強みです。トラブルを最小限に抑え、確実に契約解除を進めるためにも、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、不動産会社との交渉を有利に進められます。不動産会社は契約書の条項や宅建業法などの法律に基づいて対応するため、専門知識に乏しい個人が一人で交渉を行うのは容易ではありません。弁護士が関与することで、不動産会社の対応が慎重になり、交渉の主導権を握りやすくなります。
たとえば、売買契約の解除を希望する買主が「手付金を返してほしい」と求めても、不動産会社が「契約上返還義務はない」と主張することがあります。しかし、契約書の条文やローン特約の条件次第では返還が認められるケースもあります。弁護士が間に入れば、法的根拠に基づく主張ができ、感情論や一方的な説明に流されず、冷静かつ合理的に話を進められます。
さらに、弁護士名義で作成する通知書や意見書には「いざとなったら法的に争う意思がある」というメッセージが込められるため、不動産会社に慎重な対応を促します。裁判に発展することなく、スムーズにトラブルを収束させやすくなるでしょう。
契約解除をめぐるトラブルが深刻化すると、当事者間の交渉では解決できず、最終的に裁判に発展することもあります。そのような場合でも、弁護士に依頼していれば、訴訟対応を含めて一貫して任せることができます。これが、ほかの相談窓口では得られない、弁護士ならではの強みです。
裁判では契約書の内容だけでなく、交渉経緯、証拠資料、法律の解釈などが重視されるため、個人での対応には限界があります。弁護士であれば、訴状や答弁書の作成、証拠の整理、法的主張の構築まで全て対応できます。裁判所での主張立証や口頭弁論も代理人として行ってもらえるため、依頼者の心理的負担を大幅に軽減できます。
また、弁護士は法的な争点や過去の判例を踏まえて戦略的に主張できるため、裁判の結果や和解条件にも大きな影響を与えます。不確実性の高い裁判だからこそ、経験と知識を備えた弁護士の存在が欠かせません。
不動産契約は、金額が大きく関係者も多いため、原則として一度締結すると簡単には解除できません。しかし、法律や契約書で定められた条件に当てはまる場合は、契約を解除できるケースもあります。
解除の可否は、契約の種類や締結時の条件、当事者間の事情によって異なります。ここでは、まず契約解除の基本的な仕組みを確認していきましょう。
不動産契約における「解除」と「解約」は似ているようで意味が異なります。
契約解除は、契約成立後にさかのぼって契約をなかったことにすることです。解除が成立すると、原則として当事者は元の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。
契約解約は、将来に向かって契約を終了させることです。すでに履行した部分は有効なままとなり、それ以降の義務だけが消滅します。
たとえば、売買契約で手付金を支払い済みの場合、解除なら手付金は返還される可能性がありますが、解約の場合すでに受け渡した代金や物件には影響しないため、支払い済みの手付金も返ってこないことが多いです。この違いを理解していないと、思わぬ金銭トラブルにつながるため注意が必要です。
契約解除のルールは、大きく分けて「民法」と「宅建業法」という二つの法律で定められています。
民法はすべての契約に適用される一般法で、債務不履行解除(契約違反による解除)や合意解除、手付解除などが規定されています。
宅建業法は宅地建物取引業者(不動産会社)を規制する特別法で、クーリングオフ制度や手付金保全措置、違約金の上限など、不動産取引特有のルールを定めています。
たとえば、宅建業者の事務所等以外で契約した場合は宅建業法上のクーリングオフ制度が適用され、8日以内であれば理由を問わず解除できます。一方、民法上の解除は契約違反や特約条項の存在が必要です。
このように、どちらの法律が適用されるかで解除の可否や条件が変わるため、まずは契約の形態と関係する法律を確認することが重要です。
契約解除が可能かどうかは、契約書に記載された解除条項の内容が大きな判断材料になります。解除条項には、手付解除の条件、ローン特約、債務不履行による解除、不可抗力による解除などが盛り込まれていることが多いです。
確認すべきポイントとしては、以下のようなものがあります。
文言が抽象的な場合は、解釈をめぐって相手方と争いになることもあります。契約書を確認するときは、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、あいまいな点を事前に明確にしておくと安心です。
買主や借主が不動産契約を解除したいと考える理由はさまざまです。ここでは、代表的な4つの事例とそのポイントを解説します。
不動産の購入では、ほとんどの買主が住宅ローンを利用します。契約後にローンの本審査に落ちた場合、ローン特約が契約に含まれていれば、一定の条件下で契約を無条件で解除できます。
ローン特約とは、「融資が受けられなかった場合、手付金を返還して契約を白紙に戻す」という条項です。これがない場合、解除には違約金や損害賠償が発生する可能性があります。
契約後に家族構成の変化、転勤、病気、介護など予測できない事情が生じることがあります。これらは「やむを得ない事情」として考慮される場合がありますが、契約解除が無条件で認められるとは限りません。
解除が可能かは、契約書の特約や当事者間の合意によります。たとえば、賃貸契約で「転勤の場合は違約金なしで解約可能」と明記されていれば、その条件で解除できます。記載がなければ、違約金や残り期間分の賃料を求められることもあります。
事情を正直に説明し、証明できる書類(転勤辞令、診断書など)を用意することで、相手方の理解を得られる可能性が高まります。
引渡し前に物件の構造や設備に重大な欠陥が発覚した場合、契約解除が認められることがあります。民法の契約不適合責任に基づき、契約内容に適合しない物件を引き渡そうとした場合、買主は解除や修補請求が可能です。
重大な欠陥の例としては、雨漏り、シロアリ被害、基礎部分のひび割れなどがあります。解除が認められるかどうかは、欠陥の程度や生活への影響の大きさが判断基準となるため、専門家による調査報告書が有力な証拠になります。
また、契約前の内覧や建物状況調査(インスペクション)を活用して状態を確認しておくことは、後々のトラブルを防ぐ有効な手段です。購入前に細かく内容を確認することで、契約後の大きな損失や紛争を避けられます。
不動産取引では、売主や貸主には契約前に重要事項を正確に説明する義務があります。これを怠ったり、虚偽の説明を行った場合、契約解除や損害賠償請求の対象となります。
たとえば、過去に雨漏りがあった事実や、近隣との境界トラブル、再建築不可物件であることなどを告げずに契約した場合です。これらは宅建業法上の説明義務違反にあたり、契約の根本に関わる情報であれば解除が可能です。
売主や貸主が契約を解除する場合、単なる気持ちの変化では認められず、法律や契約書で定められた正当な理由が必要です。ここでは、解除が検討される典型的なケースを3つ紹介します。
代金や家賃などの支払いが滞った場合、売主や貸主は契約解除を検討できます。民法上、支払い義務は契約の根幹であり、履行しない状態が続けば債務不履行解除が可能です。
たとえば、売買契約で残代金の支払い期限を過ぎても入金がない場合や、賃貸契約で家賃を何か月も滞納している場合が該当します。契約書に「○か月以上滞納した場合は契約解除できる」と定められていれば、その条件を満たすことで解除が有効になります。
解除にあたっては、まず催告(支払いを求める通知)を行い、それでも改善がない場合に手続きを進めるのが一般的です。
契約当事者と連絡が取れない状態が長期化すると、契約内容の履行が事実上不可能、または極めて困難になります。このような場合も契約解除の対象となります。
たとえば、買主が引渡し日の調整に応じず音信不通になる、借主が無断で退去して連絡がつかないなどが典型例です。支払いの有無にかかわらず、契約上の義務全般が果たされていないと判断されます。
なお、解除を進める際は、あらかじめ「内容証明郵便での通知」や「公示送達」といった法的に有効な手段で意思表示を促すことになります。適切な手続きを踏むことで、後々の紛争や無効主張を防ぎやすくなります。
契約で定められた使用方法に反する行為や、許可のない転貸、不法な改造は、重大な契約違反として解除の対象になります。
たとえば、賃貸契約で「住居専用」と定められている物件を無断で事務所として使用する、無断で第三者に又貸しする、あるいは建物を勝手に改造して構造や安全性に影響を与えるといったケースです。これらの行為は契約の根本を損なうため、解除理由として認められやすくなります。
多くの契約書には、こうした違反があった場合に解除できる旨が明記されています。実際に解除を進めるには、違反を裏付ける証拠(写真、近隣住民の証言、契約書の条項など)を確保することが重要です。また、解除の前には事実確認を行い、是正を求める催告を経てから手続きを進めるのが望ましいです。
不動産契約を解除する際は、感情的に動くのではなく、契約書と法律に基づいた手順を踏むことが大切です。誤った進め方をすると、解除そのものが無効になったり、相手から損害賠償を請求されるおそれがあります。
まず、契約書や重要事項説明書を確認し、解除条件や違約金、手付金の扱い、期限などを把握します。解除理由を整理し、必要に応じて関連する資料を集めます。住宅ローンの不承認通知、欠陥を証明する調査報告書、相手の説明義務違反を示す資料などが該当します。
次に、解除の意思を相手方に伝えます。口頭だけでなく、内容証明郵便など記録が残る方法を使うのが望ましいです。当事者間で合意が得られれば、解除合意書を作成して終了です。合意できない場合は、契約条項や法律に基づき一方的に解除することになりますが、この場合は後の紛争を想定し、弁護士の関与が望まれます。
解除後は、手付金の返還や、違約金・損害賠償などの精算を行います。交渉で解決できない場合は、調停や裁判に進むこともあります。こうした段階では証拠や主張の整理が結果を大きく左右するため、早めに専門家の助言を受けて進めることが安全です。
不動産契約を解除する際は、必ず書面を取り交わしましょう。合意解除を口頭だけで済ませると、あとになって「言った」「言わない」の水掛け論になりやすく、不必要なトラブルを招きかねません。解除条件や精算内容、解除日などを明記した契約解除合意書を作成し、当事者双方が署名捺印することが重要です。
また、不動産取得税の課税についても確認しておくことが重要です。不動産売買契約を合意解除した場合、法律上は契約前にさかのぼって元の状態に戻るのが原則です。しかし課税上は、一度買主に移った所有権が再び売主に戻ったとみなされ、売主が改めて不動産を取得したとして取得税が課される場合があります。
ただし、このような不動産取得税については必ず課税されるわけではなく、自治体の運用によっても異なるため、事前に不動産取得税の担当部署へ確認しておくことが安心です。
契約解除の意思表示は、内容証明郵便やメールなど記録が残る方法で行いましょう。電話や口頭だけでの契約解除は避けるべきです。法律上は意思表示の方法に制限はありませんが、あとで「言った」「言わない」のトラブルになる可能性が高くなります。解除を行う際には、解除合意書を作成しておくことが望ましいです。
借主の一方的な理由で途中解約すると、家賃のほかに違約金や原状回復費を請求される可能性があります。とくに定期借家契約では、原則として期間途中の解約はできず、特約や法律で定められた事由に限られます。トラブルを避けるためにも、契約書の条件はあらかじめ必ず確認しておきましょう。
手付解除とは、売買契約時に授受した手付金を放棄、または倍返しすることで契約を解除する制度です。買主は支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで、契約を一方的に解除できます。
ただし、これは相手が履行に着手する前までに限られます。たとえば、売主が登記の準備を始めた、買主が融資の実行を進めたなど、契約履行に向けた行為があると手付解除できません。解除できる期限や条件は契約書でも定められているため、必ず確認しましょう。
契約後に自己都合で解除する場合、契約書で定められた違約金やキャンセル料を支払う必要があります。売買契約では手付金の放棄や倍返しがこれにあたり、賃貸契約では解約予告期間内の家賃や違約金が発生する場合があります。
たとえば、引渡し前に買主が「やっぱり購入をやめたい」と申し出た場合、ローン特約など正当な解除事由がなければ、契約書に基づいて手付金を失う可能性が高いです。
クーリングオフとは、一定期間内であれば理由を問わず契約を解除できる制度です。不動産の場合、宅建業者が売主となる取引で、事務所以外の場所で契約した場合に限り適用されます。期間は契約書を受領してから8日以内です。
ただし、自己所有物件の売買や、宅建業者の事務所内で締結した契約には適用されません。条件に該当するかどうかは契約場所や相手方の立場によるため、契約直後に解除を考える場合は早急に確認が必要です。
不動産契約の解除は、契約書の条項や法律の規定などによって可否や条件が大きく変わります。住宅ローンの不承認や物件の重大な欠陥、説明義務違反など、正当な理由があれば解除が可能な場合もありますが、自己都合での解除は違約金や損害賠償が発生することもあります。
スムーズかつ安全に契約解除を行うためには、契約書の確認と関連資料の準備、相手方への適切な通知、そして必要に応じた専門家への相談が欠かせません。とくに合意解除の場合は書面を交わすこと、不動産取得税の課税の有無を事前に確認することが重要です。
不動産契約の解除は、大きな金額と生活への影響が伴う重大な手続きです。少しでも不安や疑問がある場合は、不動産や契約にくわしい弁護士などの専門家に早めに相談し、後悔のない判断を下しましょう。相談先に迷ったら、賃貸トラブルに豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」にお気軽にご相談ください。