

東京弁護士会所属。千葉県習志野市出身。
立ち退きの通告は、多くの方にとって予期せぬ大きな不安を伴うものです。法的な手続きが不明透明なまま進んでしまうと、本来受け取れるはずの正当な権利(立ち退き料や代替物件の確保など)が損なわれてしまうリスクがあります。
私は、東証一部上場メーカーの法務部門にて、契約交渉やコンプライアンス遵守といった実務の最前線に立ってきました。そこで培った「ビジネスの実態に即した交渉力」と「緻密な法的分析力」は、賃貸人との利害調整が必要な立ち退き問題においても非常に強力な武器となります。
弁護士は単なる代弁者ではなく、良質なサービスを提供するパートナーであるべきだと考えています。依頼者様が抱える不安を一つひとつ解消し、法律の専門家として、最大限の利益を確保するために尽力いたします。まずは今抱えているお悩みをお聞かせください。
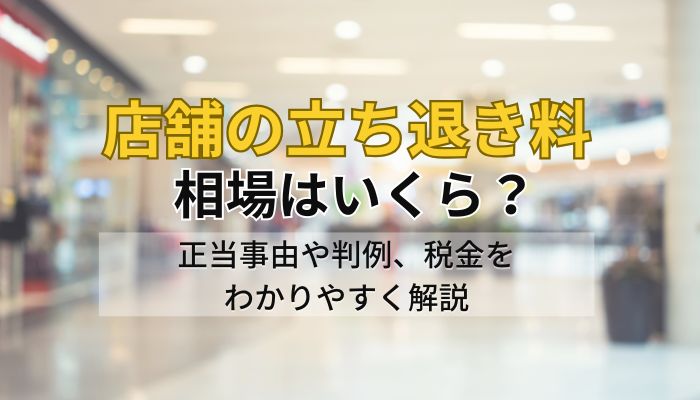
目次
立ち退き料は法律で金額が決まっているわけではなく、個別事情(建替えの必要性、契約内容、テナントの損失範囲など)を総合考慮して合意形成します(原則)。
「正当事由」の基礎や一般論は総合解説ページも参照してください:立ち退き料の相場はどのくらい?(総合) / 正当事由とは
店舗は、改装・造作・集客の再構築コストが高くなりやすいため、賃料の2〜3年分程度が目安とされることがあります(一般に/幅)。
住居・事務所の相場比較は総合ページへ誘導し、本ページは店舗の内訳にフォーカスします。
準備チェックリスト
立ち退き料は所得税・法人税の対象となる場合があります。
また、移転補償・営業補償は消費税の課税対象外となる取扱いが一般的ですが、賃借権の譲渡対価等は課税となる場合があります(一般に)。
詳細な判断・申告は税理士に確認してください。
居抜きは第三者へ設備等を一括譲渡するもので、賃貸人の承諾や賃貸借の扱いに注意が必要です。造作買取は賃貸人側が設備等を買い取るイメージで、いずれも価格は評価・交渉次第です。
契約条項と建物の状態を確認し、費用見積と明渡時期を含めて総額で協議します。原状回復の範囲は事案により大きく変わります。
滞納等があると交渉上の不利要素になり得ます。まずは滞納清算計画を整理し、退去条件と併せて協議しましょう。
店舗の立ち退き料は、法律で金額が決まっているわけではなく、原状回復・造作(買取/撤去)・移転費・広告費・在庫ロス・休業(営業)補償などを積み上げて協議するのが一般です
目安としては賃料の2〜3年分と語られることもありますが、業種・商圏・工期・契約条項によって幅が生じます(一般に/事案により)。
交渉では、過去の売上・粗利や固定費、相見積、機器リスト、工期見込みといった数値根拠と証拠を揃え、金額とスケジュールをセットで提示することが近道です。
住居・事務所向けの一般論は総合ガイドに委ね、本ページのポイントはあくまで“店舗特有の内訳と準備”。
税務の詳細判断は税理士の領域ですが、合意書の条項整理・説明文書の評価・交渉/調停対応は弁護士が伴走できます。迷ったら早期にご相談いただき、感情的対立や手戻りを避けつつ、実務的に妥当な着地点を一緒に設計しましょう。