

土地と建物の名義人が異なる場合、現在の関係は良好でも、将来的に相続などのタイミングでトラブルが起きる可能性があります。
トラブルが発生すると、建物の名義人は土地の名義人から立ち退きや代償金の支払いなどを要求されるかもしれません。
もし立ち退きを要求された場合、名義の統一や建物の解体など、名義人同士で話し合って解決方法を決める必要があります。
ここでは、土地と建物の名義が違う場合のトラブルや立ち退きの要件、トラブルを解決するための対処法などをご紹介します。
土地と建物の名義人が異なる場合に発生するトラブルは、主に以下のものが挙げられます。
どのようなケースが考えられるのか、それぞれ確認していきましょう。
たとえば以下のようなケースでは、建物の名義人が土地の名義人から立ち退きを要求される可能性があります。
建物の名義人が土地の名義人から土地を賃借しており、契約期間の満了を迎えた場合です。
たとえば土地の名義人が事業を開始するなどの理由で土地を使用したい場合、立ち退きを要求されるかもしれません。
建物の名義人は、土地の利用権に基づいて建物を使用しています。
土地の利用権が通常の賃貸借契約のとき、契約期間満了後に建物の名義人が期間を更新したい場合は、土地の名義人は更新を拒否できません。
ただし、使用貸借契約の場合は土地の名義人からの立ち退き要求が優先されるため、注意が必要です。
たとえば、建物の名義人が親族の土地に自宅を建てた場合です。
親族が亡くなると、土地の名義は親族の配偶者や子どもなどに承継されます。
土地の相続人が自宅を建てたい場合など、相続人の事情によっては立ち退きを要求される可能性があるでしょう。
たとえば以下のようなケースでは、建物の名義人が代償金の支払いを請求される可能性があります。
親の土地に子どもが家を建てた後、親が亡くなって下表のように複数の子どもが土地を相続した場合です。
| 相続開始前 | 相続開始後 | |
|---|---|---|
| 建物の名義人 | A(子ども) | A(子ども) |
| 土地の名義人 | X(親) | A・B(子ども) |
土地の共有者であるBは土地を利用できないため、遺産分割協議でBからAに代償金を支払うよう請求される可能性があります。
建物の名義人が土地の名義人から立ち退きを要求された場合、立ち退きをしなければならないケースがあります。
ここからは、建物の名義人が立ち退かなければならないケースと、立ち退かなくてもよいケースについて確認をしていきましょう。
以下の場合、建物の名義人は土地から立ち退かなければなりません。
定期賃貸借とは、50年などの期間を定めて不動産を使用する契約です。
期間満了後、合意があれば継続も可能ですが、立ち退きの要求があるときは建物の名義人は原則として応じなければなりません。
使用貸借は、賃貸借と同様に不動産を使用するための権利です。
原則として賃料の支払いは不要ですが、期間満了後に要求があるときは立ち退きが必要になります。
土地の共同相続人などから請求された代償金を支払えない場合、分割払いや他の資産を譲渡する方法もあります。
共同相続人へ支払う方法がない場合、最終的には土地の明け渡しを求めて訴訟を提起される可能性もあるでしょう。
訴訟が認められた場合、建物の名義人は土地から立ち退きをしなければなりません。
以下のケースでは、建物の名義人は土地から立ち退かずに使用を継続できます。
普通賃貸借契約に基づいて土地を使用している場合、土地の名義人は正当な事由がなければ建物の名義人からの契約更新を拒絶できません。
ただし、賃料の滞納や使用方法の違反などがある場合、土地の名義人の更新拒絶が認められる可能性があります。
前述の親が亡くなって、複数の子どもが土地を相続した事例で考えてみましょう。
| 相続開始前 | 相続開始後 | |
|---|---|---|
| 建物の名義人 | A(子ども) | A(子ども) |
| 土地の名義人 | X(親) | A・B(子ども) |
AからBの共有分を取得するための代償金を支払えない場合、建物部分に相当する土地をA、残りの土地をBに分筆する方法もあります。
分筆が完了すると、建物と土地の名義は両方ともAになります。
土地の広さによっては、分筆ができない場合や一部の代償金をBに支払う場合がある点に注意しましょう。
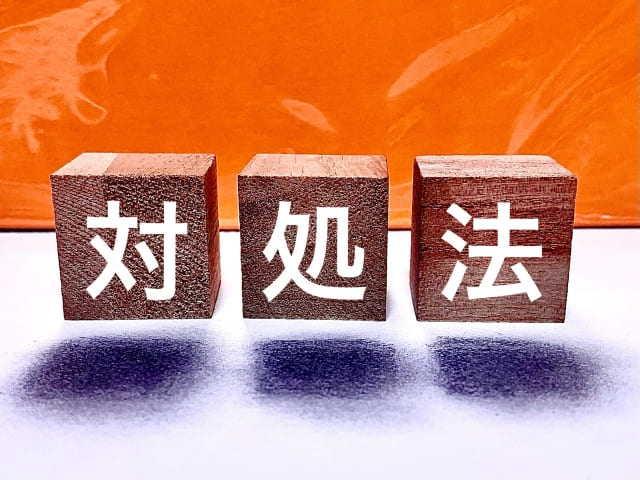
土地と建物の名義が違う場合、対処法として以下の方法があります。
それぞれの方法を確認していきましょう。
土地と建物の名義を同一にするのは、たとえば以下のようなケースです。
建物の名義人が土地を買い取って名義を同一にすれば、将来的な立ち退きや代償金の支払いなどは必要ありません。
前提として、土地の名義人が売却に同意しており、建物の名義人に土地の購入代金を支払うための資力が必要です。
土地と建物を第三者に売却したい場合、通常は名義を同一にしてから売却します。
名義が別々のままでは、買い手を見つけるのが難しいでしょう。
買い手を見つけたとしても、相場よりも低い売却価格になる恐れがあります。
なお、不動産会社の介入によって名義が異なる土地と建物を同時売却できる場合もあるため、不動産会社に相談しましょう。
以下のように、名義を別々にしたまま建物を解体するケースもあります。
建物の解体は原則として名義人同士の合意が必要であるため、まずは解体について名義人同士で話し合いましょう。
建物の名義人に普通賃借権があり、土地の名義人に更新を拒絶された場合、建物の名義人は土地の名義人に建物の買い取りを請求できます。
契約期間の満了前に解約する場合や、定期借地権の場合は建物の買い取りを請求できません。
建物の名義人に土地を購入する資力はないが、建物に住み続けたい場合、賃料を払いながら土地を利用する方法もあります。
ただし、将来的に前述の立ち退き要求などのリスクがある点に注意しましょう。
土地と建物の名義が異なる場合、相続や借地権の期間満了のタイミングで立ち退き要求などを受けるリスクがあります。
名義人同士の関係が悪化すると話し合いが難しくなるため、事前に名義の統一や建物の解体などをしておくのが望ましいでしょう。
名義人同士での話し合いが難しい場合、弁護士に交渉を依頼するのもよい方法です。
当事者同士では感情的になって交渉が進まないケースもありますが、弁護士が介入すると円滑に交渉が進む可能性が高くなるでしょう。