この記事でわかること
- 夫の死亡で妻が全部相続できるか
- 夫が死亡したときの妻の相続割合
- 配偶者に有益な相続税の控除や特例
- 夫が死亡した場合も生命保険の扱い
夫の死亡後、妻がすべての財産を相続できるかどうかは、様々な状況に左右されます。
遺言書の有無、他の相続人の存在、遺留分の問題など、複雑な要素が絡み合います。
また、相続税の配偶者控除や特例、生命保険金の取り扱いなど、知っておかなければならない重要なポイントがあります。
この記事では、妻の立場から見た相続の仕組みや、相続割合、税金の問題について、わかりやすく解説します。
目次
夫が死亡したら妻が全部相続できますか?
夫が死亡した際、妻が全財産を相続できるかどうかは、遺言書の有無や他の相続人がいるかどうかにより異なります。
ここでは、遺言書や他の相続人の存在が相続にどのように影響するかを詳しく解説します。
遺言書の有無
遺言書の有無は、相続の行方を大きく左右します。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産が分配されます。
一方、遺言書がない場合は法定相続分に基づき、最終的には相続人全員の協議によって遺産が分割されます。
このため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言の場合、法務局に保管されている場合があります。
公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場に問い合わせることで、遺言書の存在を調べることが可能です。
法務局や公証役場に問い合わせても遺言書が見つからない場合は、自宅に保管されている可能性もあります。
ただし、自筆証書遺言が自宅で見つかった場合は、その場で開封してはいけません。
検認手続きを行う必要があるため、家庭裁判所に持参しましょう。
妻以外に相続人がいる場合
夫が死亡し、妻のみが相続人の場合は、妻が全財産を相続します。
一方、他に相続人がいる場合は、法定相続分を考慮の上、相続人全員が話し合って相続分を決めます。
これを遺産分割協議といいます。
以下は、法定相続人と法定相続分をまとめた表です。
この割合に従って遺産分割を進めましょう。
| 法定相続人の 組み合わせ |
配偶者の 法定相続分 |
子の 法定相続分 |
父母の 法定相続分 |
兄弟姉妹の 法定相続分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全部 | – | – | – |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 配偶者と父母 | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
遺言書より優先される遺留分
遺留分は遺言よりも優先され、法定相続人が最低限受け取れる遺産の割合を保障するものです。
たとえば、夫が妻に全財産を相続させる旨の遺言を残したとしても、他の相続人が不満な場合は、遺留分の請求をすることができます。
遺留分は以下の表の割合になります。
| 法定相続人の組み合わせ | 相続財産に対する遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 遺産の1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者:遺産の1/4 子:遺産の1/4(子が複数の場合は均等に分割) |
| 配偶者と父母 | 配偶者:遺産の1/3 父母:遺産の1/6(父母それぞれ1/12ずつ) |
なお、兄弟姉妹や相続放棄者などは遺留分を主張することができません。
遺留分が請求できる期限は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内または相続開始から10年以内であることにも注意しましょう。
【ケース別】夫が死亡したときの妻の相続割合
夫が亡くなった場合、妻の相続割合は家族構成によって大きく変わります。
子どもの有無、義理の親や兄弟姉妹の存在などが相続の分配に影響を与えます。
ここでは、3つのケースについて詳しく説明します。
子どもがいる場合
夫との間に子どもがいる場合、相続人は妻と子どもです。
法定相続分として、妻は遺産の1/2、子どもは残りの1/2を相続する権利があります。
遺産分割は、相続人全員の合意があれば自由に決めることができるため、妻がすべてを相続することも問題ありません。
相続人全員が納得していれば、どのような分割方法も可能です。
ただし、子どもが未成年で法定相続分以外の割合で遺産を分割する場合は、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立て、審判によって決定されます。
また、遺言書がある場合は遺言書が優先されます。
ただ、遺言書で遺留分を侵害されている場合は、遺留分を請求することが可能です。
子どもがなく夫の親(義理の親)がいる場合
夫との間に子どもがなく、夫の親(義理の親)が生存している場合、妻と義理の親が相続人となります。
法定相続分は、妻が遺産の2/3、義理の親は1/3です。
たとえば、相続財産が9,000万円の場合の相続割合は、妻が6,000万円、義理の親は3,000万円です。
義理の親が両親とも健在な場合は、3,000万円を両親で分けて、それぞれ1,500万円ずつ相続します。
もちろん、相続人全員が同意していれば、法定相続分以外の割合で分けることもできます。
つまり、義理の親が納得していれば、妻が遺産を全部受け取ることも問題ありません。
また、遺言書があれば遺言書が優先し、遺留分を侵害されている場合は遺留分を請求できます。
子どもも夫の親もいない場合で夫の兄弟姉妹がいる場合
夫婦に子どもがなく、夫の親も既に亡くなっていて、夫の兄弟姉妹が生存している場合、相続人は妻と兄弟姉妹です。
法定相続分は、妻の遺産の3/4で、夫の兄弟姉妹は1/4となります。
たとえば、相続財産が1億円の場合、妻は7,500万円、夫の兄弟姉妹で2,500万円を相続することができます。
夫の兄弟姉妹が複数いる場合は、2,500万円を人数で均等に分割します。
この場合も、夫の兄弟姉妹全員が納得すれば、遺産分割協議により妻が全部を相続することもできます。
また、遺言書があれば遺言を優先しますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、夫が生前に遺言書を作成することで、妻に全財産を相続させることも可能です。
夫が死亡したときの相続税
夫が亡くなった際、妻が相続する財産には相続税がかかる可能性があります。
しかし、配偶者には特別な控除や特例が適用されるため、多くの場合、相続税の負担を軽減できます。
ここでは、配偶者の相続税について詳しく解説します。
配偶者の税額の軽減と小規模宅地等の特例
配偶者が相続する際には、「配偶者の税額の軽減」という特別な制度が適用されます。
引用:
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この制度により、配偶者は「1億6,000万円まで」または「配偶者の法定相続分」のいずれか大きい額まで、相続税がかかりません。
たとえば、相続した遺産が2億円の場合でも、法定相続分であれば、配偶者は全額相続税なしで相続できます。
「配偶者の税額の軽減」(以下、配偶者控除)を受けるには相続税の申告が必要で、申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
注意点は、申告期限までに遺産分割されていない財産は対象にならないことです。
遺産分割が遅れる場合は、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、申告期限後3年以内に分割した財産も対象になります。
また、夫が住んでいた自宅の敷地について「小規模宅地等の特例」を利用すると、評価額を最大80%減額できます。
この特例の適用も、相続税の申告期限までに申告する必要があります。
配偶者の相続税の計算例
配偶者控除により配偶者は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで相続税がかかりませんが、それを超える分には相続税がかかります。
以下の例で計算してみましょう。
- 正味の遺産総額:3億円
- 相続人:配偶者と子1人
- 相続割合:配偶者2億円、子1億円
まず、基礎控除額を計算します。
基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
計算式
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
課税対象となる遺産総額は、正味の遺産総額から基礎控除額を引いて求めます。
計算式
3億円-4,200万円=2億5,800万円
ここで配偶者控除を適用します。
配偶者の法定相続分は1億5,000万円(3億円の1/2)で、1億6,000万円を下回るため、1億6,000万円が控除の上限となります。
結果として、配偶者の課税対象額は2億円-1億6,000万円=4,000万円となります。
配偶者の相続税の計算式
- 4,000万円×20%(税率)-200万円=600万円
子の相続税の計算式
- 1億円×30%(税率)-700万円=2,300万円
よって、相続税額は以下の通りです。
- 配偶者:600万円
- 子:2,300万円
- 合計相続税額:2,900万円
このように、配偶者控除により、配偶者の相続税が大幅に軽減されます。
死亡した夫が加入していた生命保険はどうなる?
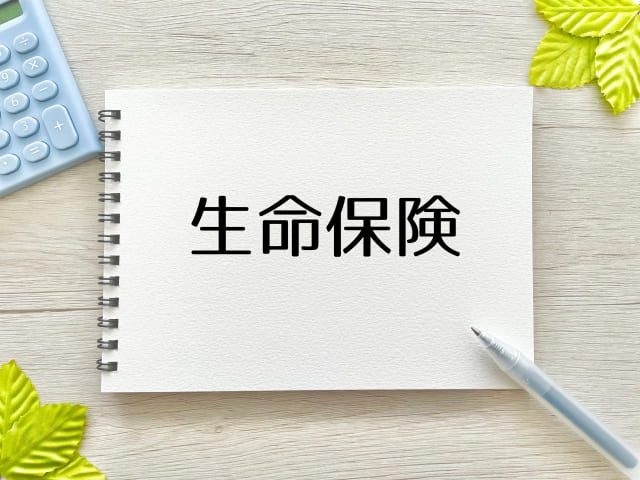
夫が死亡した場合、生命保険金は通常、受取人として指定された人に直接支払われます。
この保険金は原則として相続財産には含まれませんが、金額によっては相続に影響を与える可能性があります。
詳しく見ていきましょう。
生命保険は相続の対象か
生命保険金は、受取人が指定されている場合、受取人の固有の財産となります。
つまり、夫が妻を受取人に指定していれば、保険金は妻の固有財産となり、相続財産には含まれません。
これは、生命保険が保険契約に基づいて支払われるものであり、遺産とは別に扱われるためです。
そのため、原則として他の相続人に分配する必要はなく、妻は保険金を単独で受け取ることができます。
ただし、生命保険金も一定額を超えると相続税の課税対象となる場合があるため、注意が必要です。
保険金が高額な場合の注意点
生命保険金が非常に高額な場合は、注意が必要です。
保険金額が大きく、他の相続人と比べて著しく多くの利益を得ると、相続の公平性が問題視されることがあります。
著しく不公平といえるかは、たとえば以下の要素が考慮されます。
- 生命保険金の額
- 生命保険金が遺産総額に占める割合
- 被相続人の関係(同居の有無や貢献度など)
- 各相続人の生活状況(健康や経済状況など)
原則として生命保険金は特別受益には該当しませんが、上記のような特段の事情がある場合、例外的に特別受益に準じて扱われることがあります。
特別受益とみなされると、遺産総額に生命保険金が加算され「みなし相続財産」として計算されます。
計算式
- 相続財産+生命保険金=みなし相続財産
- (みなし相続財産×法定相続分)-特別受益の価額=各相続人の相続分
生命保険金が特別受益と判断されるかはケースによって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
夫の死亡による相続は、遺言書の有無や相続人の状況、遺産の規模などによって、複雑化する可能性があります。
配偶者の税制上の優遇措置や特例など、専門的な知識が求められます。
そのため、相続手続きを適切に進めるためには、個々の状況に応じた法的知識が不可欠です。
不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、法律や税制の観点から最適な相続方法が見つかるでしょう。

























