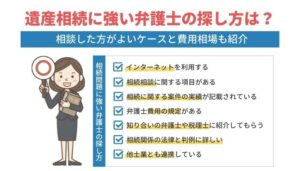この記事でわかること
- 生前と死後それぞれに現金を渡す税法上の扱い
- 生前にお金を渡す方法と死後にお金を渡す方法
- 相続税や贈与税を軽減できる制度
相続を控えている方にとって、家族にどうやってお金を渡したらよいか、悩むことも多いのではないでしょうか。
本記事では、生前と死後のお金の渡し方、税法上の扱いや非課税枠、具体的な手続き方法などを解説します。
また、現金手渡しや口座振込、遺言書作成など、様々な方法のメリットとデメリットを比較し、相続税や贈与税を軽減する方法も紹介します。
相続を控えてお金の渡し方に悩む方は、ぜひ参考にしてください。
目次
お金を渡すタイミングごとの相続での扱い
お金の渡し方は、生前に渡すか死後に渡すかで大きく異なります。
生前贈与の場合は贈与税が、相続の場合は相続税の課税対象となります。
それぞれのタイミングで税法上の扱いが異なるため、状況に応じた適切な方法を選択することが重要です。
ここでは、生前と死後のお金の渡し方について、税法上の扱いや非課税枠について、詳しく解説します。
生前に現金を渡す場合の税法上の扱いと非課税枠
生前に現金を渡す場合、税法上は「贈与」として扱われます。
贈与税の基礎控除額は年間110万円で、これを超える贈与には贈与税が課税されます。
これは、お金を渡す側(贈与者)にとってではなく、お金をもらう側(受贈者)にとって年間110万円なので注意してください。
たとえば、両親それぞれから年間110万贈与された受贈者は、110万円を超えた額に贈与税がかかります。
一方、父親が子どもたち3人それぞれに年間110万円ずつ贈与した場合は、受贈者であるそれぞれの子どもたちに贈与税はかかりません。
また、現金を渡す場合は、家族であっても贈与契約書を書いておくのがよいでしょう。
そうすることで、後に税務署から指摘があった場合も証拠を提出することができます。
さらに、親子や孫あるいは夫婦の場合は、以下の特例制度が利用できる場合があります。
- 30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)
- 親から子への住宅取得資金の贈与(最大1,000万円まで非課税)
- 配偶者間での居住用不動産や金銭の贈与(2,000万円まで非課税)
これらの特例制度は期限や条件などが複雑なため、専門家への相談をおすすめします。
死後に現金を渡す場合の税法上の扱い
死後に現金を渡す場合は相続となり、相続税の対象となります。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、この額を超えた財産にのみ課税されます。
たとえば、配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円となります。
配偶者は1億6,000万円まで非課税となる特例があり、税負担が大幅に軽減されます。
また、相続時精算課税制度を利用する場合は、合計2,500万円までの贈与が非課税となります。
2024年の法改正により、年間110万円の贈与非課税枠も併用可能になっています。
相続や税法に関して法改正が頻繁に行われていますので、最新情報を知っておくことも大切になるでしょう。
生前にお金を渡す方法
生前にお金を渡す方法には、「現金での手渡し」「口座振込」そして「家族信託契約」があります。
それぞれの特徴があり、税務上の扱いや法的な注意点が異なります。
ここでは、税法上の視点や法的な解説を交え、わかりやすく説明します。
現金手渡しの方法と注意点
現金手渡しは、最もシンプルで直接的な贈与方法ですが、記録が残りにくく不透明なことがデメリットです。
現金手渡しは税務署に発覚しないと考える人もいますが、これは誤った認識です。
受け取った側の預金残高の増加や買い物などから、税務調査が入る可能性があります。
贈与の事実を隠蔽すると重加算税が課されるため、隠れて贈与するのは控えましょう。
適切な方法としては、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことです。
そうすることで、たとえ税務調査が入っても対応しやすくなります。
年間110万の基礎控除の範囲内なら贈与税もかからず、税金を気にせずに現金手渡しができます。
それ以上の贈与をした場合は、翌年の2月1日から3月15日までの期限内に贈与税の申告を行いましょう。
口座振込による贈与の特徴と注意点
口座振込による贈与は、記録が残るため透明性が高く、税務上も適切な方法です。
記録がしっかりと残ることで、後々のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
振込で贈与する場合も、贈与契約書を作成すると確実です。
また、振込時には「贈与」という名目を明示しておくと、さらに明確になるでしょう。
贈与税の基礎控除額である年間110万円を意識することも大切です。
複数回に分けて振り込んだ場合でも、受け取る側の年間合計額が基礎控除額を超えれば贈与税の申告が必要となるため、注意しましょう。
口座振込は管理もしやすく、現金を贈与する際にはおすすめの方法といえるでしょう。
家族信託契約の活用
家族信託契約は、生前の財産管理と死後の相続対策を兼ねた方法で、特に高齢者や認知症対策として利用されます。
家族信託契約は、財産所有者が信頼できる家族などに財産管理を委託し、その利益を受益者(多くは委託した人自身)が受け取る契約です。
たとえば、親が子に財産管理を委託し、子は親のために財産管理をする場合などです。
認知症などで意思能力を失った場合、資産が凍結されることがありますが、家族信託を利用することで、そのリスクを回避できます。
また、二次相続以降の財産承継も指定できるため、長期的な相続対策としても有効です。
手続きは、公正証書による信託契約の作成が一般的です。
信託財産の受益権は相続開始時に評価され、その評価額が相続税の対象となりますが、複雑な計算が伴うため、専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。
家族信託は柔軟な設計が可能ですが、複雑な仕組みのため、専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
死後にお金を渡す方法
死後にお金を渡す方法として、生前に書く遺言書、死後に行われる遺産分割協議、そして生命保険を活用した相続対策があります。
これらの方法を適切に活用することで、自身や家族の意向を尊重しつつ、円滑な財産移転を実現できます。
ここでは、各方法の特徴や手続きについて解説します。
遺言書による財産分配の指定
遺言書には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽な方法ですが、法的要件を満たさない場合は無効になるため、慎重に作成しましょう。
なお、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると家庭裁判所での検認が不要となりますが、法的有効性については専門家の確認を受けると安心です。
一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、法的安定性が高く、確実性が高い方法です。
ただし、作成や更新には費用や手間がかかる点を考慮する必要があります。
それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、最適な遺言書の種類を選択しましょう。
また、遺言書を作成する際には遺留分に配慮し、遺言執行者を指定することで、遺言内容が確実に実行される体制を整えるとよいでしょう。
遺産分割協議による分配
遺言書がない場合には、すべての相続財産について相続人全員で話し合い、遺産分割協議によって財産を分配します。
話し合いで相続人全員の合意に至った際は、遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。
この協議書は、金融機関での相続手続きや不動産登記など、相続に関わる様々な手続きで必要になる重要な書類です。
また、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となるため、専門家に依頼して効率よく準備を進めることも検討しましょう。
協議が難航した場合は、調停や審判の申立ても可能ですが、これらは時間がかかるため、できる限り話し合いでの解決が望ましいです。
生命保険を活用した相続対策
生命保険は、相続税対策と円滑な財産移転を同時に実現できる有効な手段です。
死亡保険金は通常、相続財産に含まれず、指定された受取人に直接支払われるため、遺産分割協議前でも迅速に資金を移転することが可能です。
一方、保険料の支払者と被保険者が同一の場合は「みなし相続財産」となるため、注意が必要です。
みなし相続財産で受取人が相続人の場合は、非課税枠(法定相続人1人につき500万円)が設定されているため、相続税の負担軽減が期待できるでしょう。
生命保険を活用する際には、被保険者の年齢や健康状態、保険料の負担能力、受取人の指定などを総合的に検討しましょう。
既存の保険契約の見直しや、新たに保険契約を検討することも有効な対策となるでしょう。
相続税・贈与税を軽減できる特例

相続税や贈与税の負担を軽減するためには、様々な特例制度を活用することが有効です。
これらの制度を上手に利用することで、資産を効果的に移転し、税金の節約につなげましょう。
ここでは、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「配偶者居住権」の3つの制度について解説します。
それぞれの制度を理解し、状況に合わせて適切に活用することで、相続や贈与の際の税負担を軽減し、円滑な資産移転が実現できるでしょう。
暦年贈与の活用
暦年贈与は、毎年110万円までの贈与を非課税で行える制度です。
1月1日から12月31日までの1年間を単位とし、この期間内の贈与額が基礎控除額以下であれば贈与税がかかりません。
この制度を活用することで、長期的かつ計画的な資産移転が可能になるでしょう。
暦年贈与は相続税対策として有効ですが、相続開始前3年から7年以内の贈与は相続財産に加算される可能性があるため、注意が必要です。
税制改正により、持ち戻し期間が段階的に延長されるため、どの期間までの贈与が加算対象になるか確認しておくとよいでしょう。
効果的な活用には、贈与者の資産状況や受贈者の将来的な資金需要を考慮し、長期的な視点で計画を立てることが重要です。
また、贈与契約書の作成など、適切な手続きを行うことで贈与の証明を明確にすることで、トラブルを防ぐことができるでしょう。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与に利用できる制度で、2,500万円までの特別控除が設けられています。
この控除額を超える部分には、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年1月からは、この制度に年間110万円の基礎控除も追加され、さらに利用しやすくなりました。
この制度の大きな特徴は、贈与時に支払った贈与税が将来の相続税から控除される点です。
つまり、生前贈与と相続を一体的に捉えた課税方式となっています。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、以降は暦年課税に戻すことができなくなるため、慎重に判断しなければなりません。
また、一度選択すると撤回できない点にも注意しましょう。
この制度は、まとまった資産を早期に移転したい場合や、将来の相続税負担が大きくなると予想される場合に特に有効です。
配偶者居住権の活用
配偶者居住権は、2020年4月の民法改正により新設された制度です。
配偶者居住権は、相続発生時に残された配偶者が亡くなった配偶者の自宅に住み続ける権利を法的に保護するものです。
これにより、配偶者の生活基盤が維持され、安心して住み続けることができます。
しかし、配偶者居住権には譲渡や賃貸ができないといった制限があるため、活用は慎重に検討しましょう。
また、配偶者居住権を設定する場合は、遺言書や遺産分割協議書で明確に指定する必要があり、これは登記にも反映されます。
配偶者居住権の評価額は、通常、不動産の完全な所有権の評価額よりも低くなる傾向があり、二次相続時の節税効果もあります。
配偶者の生活基盤を守りつつ、相続税の負担を軽減できる有効な方法といえるでしょう。
見まとめ
相続でのお金の渡し方には様々な選択肢があり、それぞれに税法上の取り扱いや手続きが異なります。
税法は複雑なため、最適な方法を選ぶには、個々の状況や目的に応じた専門的な判断が必要です。
早めに相談することで、効果的な相続対策を立てられ、将来のトラブルを防ぐことができます。
専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った相続プランを作成しましょう。