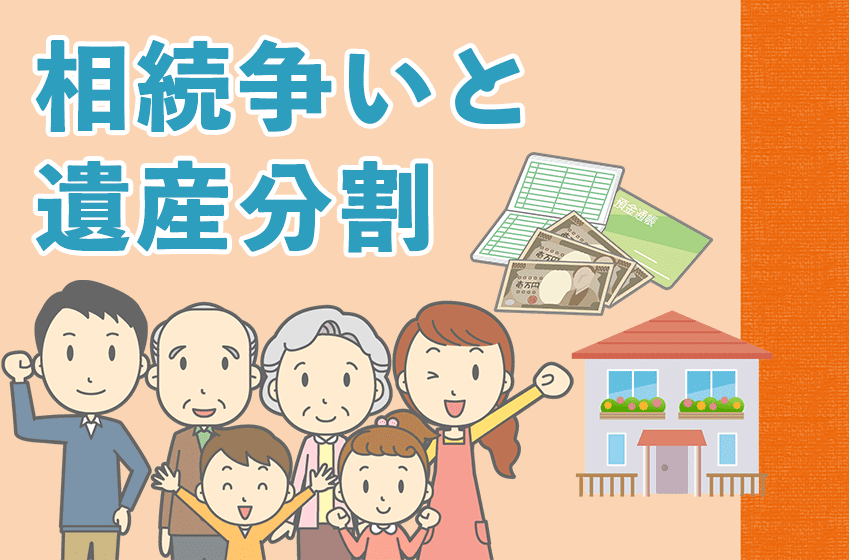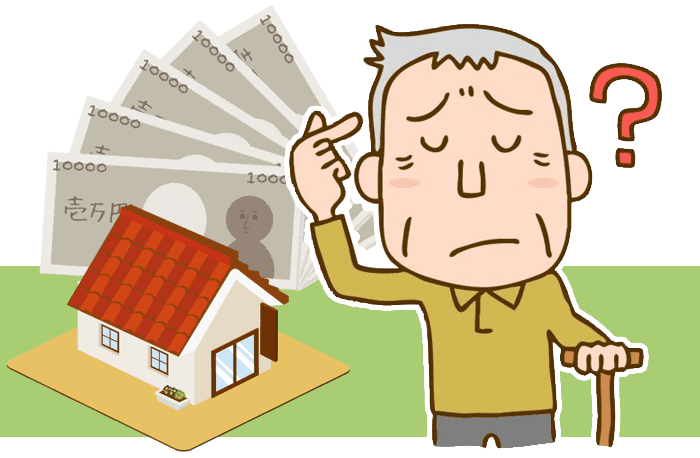これまで仲良くやってきた親族が、遺産相続をきっかけに財産を取り合うようになり、骨肉の争いを演じる…。
こんな話は決してテレビドラマの中だけの話ではありません。
遺産相続を円満に済ませるためには、当事者となる人がトラブルとなりやすい事例について知識を持っておき、解決方法について適切な対処を行うことが必要です。
今回は、遺産相続でトラブルが起こりやすい具体的な事例について紹介させていただきますので、遺産相続の問題に対処する必要があるという状況の方はぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
- 遺産相続でトラブルが生じるのはどんなとき?
- 相続財産の中に不動産がある場合
- 愛人が相続人となる場合
- 愛人との子(非嫡出子)がいる場合
- 被相続人の介護をしていた相続人とそうでない相続人がいる場合
- 相続人の一部と連絡がとれない場合
- 相続財産のほとんどが借金であるという場合
- 養子が相続人となる場合
- 過去に離婚した妻子や、再婚相手の連れ子がいる場合
- 相続分を譲渡したい人がいる場合
- 相続に当たって事業承継を行う場合
- 相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合の対処
- 相続人の廃除や相続欠格が問題となる場合
- 相続人の一部だけが生命保険金を受け取っている場合の対処
- 遺言の執行者が指定される場合
- 遺産相続の原則的な形
- 相続トラブルについては弁護士に相談しよう
- 弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に依頼するデメリット
- 司法書士や税理士、行政書士との違いとは?
- 遺産分割をスムーズに完了させることが重要ならば税理士や司法書士に
- 遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場
- まとめ
遺産相続でトラブルが生じるのはどんなとき?
例えば「1000万円の現金を5人の相続人で200万円ずつ均等に分ける」というような単純かつシンプルな遺産分割を行うことができれば理想的ですよね。
しかし、実際には相続人に誰がなるのか?や、分割できない財産を誰が相続することになるのか?…などなど、相続に関しては法律関係が非常に複雑となってしまうことがむしろ自然です。
具体的には、遺産相続をめぐるトラブルが生じやすいケースとしては、以下のような場合があります。
- 相続財産の中に不動産がある場合
- 愛人が相続人となる場合
- 愛人との子(非嫡出子)がいる場合
- 相続人の一部と連絡がとれない場合
- 相続財産のほとんどが借金であるという場合
- 被相続人の介護をしていた相続人とそうでない相続人がいる場合
- 養子が相続人となる場合
- 過去に離婚した妻子や、再婚相手の連れ子がいる場合
- 相続分を譲渡したい人がいる場合
- 相続に当たって事業承継を行う場合
- 相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合の対処
- 相続人の廃除や相続欠格が問題となる場合
- 相続人の一部だけが生命保険金を受け取っている場合の対処
- 遺言の執行者が指定される場合
以下、それぞれのケースの状況や対処方法について、順番に解説させていただきます。
相続財産の中に不動産がある場合

相続財産の中に土地や建物といった不動産がある場合、現預金のように「2分の1ずつ」といったようなシンプルな遺産分割を行うのが難しいケースがあります。
以下、相続財産に不動産が含まれる場合の問題点や解決方法についてみておきましょう。
不動産を共有とすることの問題点
不動産の分割には共有という方法がありますが、1個の不動産を複数の相続人で共有とした場合には、不動産の管理や処分をめぐる法律関係が複雑になってしまうというデメリットがあります。
具体的には、不動産を共有とした場合、その処分や収益化にあたっては共有持ち分の全員の同意や、過半数の持ち分を持つ人の同意という形で法律行為をすることになります。
例えば、被相続人が住宅を建てて居住していた土地を長男と次男で共有としたけれど、長男は賃貸アパートに建て替えて収益を得たいけれど次男は親の家にそのまま居住したい…といったような場合、将来的に兄弟間でトラブルが生じる可能性があります。
共有で問題が生じた場合の解決策
このような場合、長男が次男の共有部分を買い取るという解決方法も考えられますが、親族間で共有している不動産の持ち分を売買する場合には時価で取引を行う必要があるため、譲渡益が生じる場合にはその分の所得税を負担しなくてはならない可能性があります。
そうなると最初から共有ではなく、遺産分割で分け合っていればよかった…と後悔するケースも珍しくありません。
このように、将来的にトラブルが生じる可能性が高いことから、遺産相続の解決方法として共有という方法はあまり選択されない傾向があります。
共有以外の不動産の遺産分割方法
共有以外の不動産分割の方法としては、ほかには以下のような選択肢があります。
- 1 現物分割
- 2 代償分割
- 3 換価分割
以下、順番に見ていきましょう。
1 現物分割
不動産を複数に分けて、相続人がそれぞれ独立した不動産を相続する方法です。
例えば、1000㎡の土地を兄弟4人で250㎡ずつ(1000㎡÷4人)相続するといった形が現物分割です。
共有と異なるのは、それぞれが取得する不動産については単独の意思表示で処分や収益化を行うことができる点です。
土地については分筆という形で分け合うことも合理的なことが多いですが、建物については分割を行うことが難しいケースが多いです。
また、土地は細分化することで収益化による利益が少なくなってしまうことも少なくありませんから慎重に判断する必要があります。
2 代償分割
1人の相続人が不動産を相続する代わりに、その他の相続人に対しては不動産を相続した相続人がお金を払うというような形が代償分割です。
不動産を相続した相続人が問題なく代償となるお金を準備できる場合には問題ありませんが、必ずしもそうでない場合には対策を考えておく必要があります(生命保険金を原資に充てたり、分割払いにすることなどが考えられます)
また、相続後に負担する必要がある相続税についてもあらかじめ考慮しておくことが大切です。
3 換価分割
相続財産に含まれる不動産を第三者に売却し、その代金を相続人間で分け合うという方法が換価分割です。
財産を現預金の形に換えることができれば割合に応じて分割することが容易になりますから、不動産を手放すことそのものに問題がない場合であればメリットの大きい方法といえます。
ただし、不動産は売却して現金化するのが難しいことや、早期に売却しようと考えた場合には売価が著しく下がってしまうというケースが少なくないのがデメリットです(不動産の売却には不動産屋に支払う仲介手数料が必要になります)
また、先祖代々の土地であるから手放すことは避けたいという場合や、相続した不動産に居住している相続人がいるというような場合には採用するのが難しい方法であることにも注意が必要です。
愛人が相続人となる場合
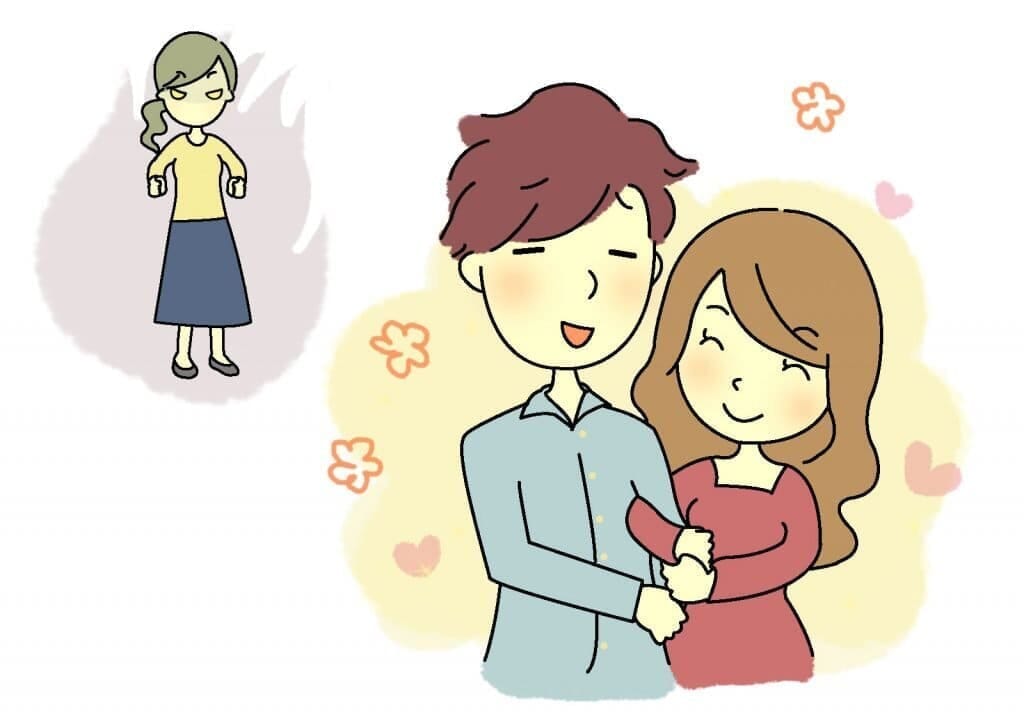
亡くなった人に愛人がおり、遺言によってその人に財産を相続させるとなっている場合も問題となりやすいケースです。
「正式に結婚していなかったのだから、遺産相続をする権利なんてないんじゃないの?」と思われる方もひょっとしたらおられるかもしれませんが、遺言による方法をとった場合には愛人であったとしても遺産を相続する権利があります。
民法の規定によって相続人となるのは法律上の婚姻関係にあった配偶者か、亡くなった人と血縁関係のあった人だけですが、遺言は民法の規定に優先するため愛人であっても相続人となることができるのです。
近しい親族には遺留分が認められる
ただし、遺言によって愛人に財産を相続させるとしたとしても、「全財産を愛人に相続させる」といったような遺言に対しては異議を唱えることが可能です。
亡くなった方と特に近しい親族関係にあった人(法律上の配偶者・子・親)には遺留分という権利が認められているためです。
遺留分というのはいわば「遺言によっても侵すことのできない親族が相続をする権利」のことで、相続財産のうち以下の割合については遺言でも別の人に渡すことはできないとされています。
直系尊属(親や祖父母)が相続人となる場合:全相続財産の3分の1
それ以外の人(配偶者や子)が相続人となる場合:全相続財産の2分の1
ただし、被相続人の兄弟姉妹については遺留分は認められないので注意しておきましょう。
遺言がない場合

上記では愛人が相続人となれるケース(遺言による指定がある場合)について解説させていただきましたが、逆に言うとこれ以外のケースでは愛人には相続人となる権利はないことになります。
遺言がなく、民法のルールによって遺産相続が行われる場合には、法定相続人となることができるのはあくまでも法律上の配偶者だけです。
内縁関係者と事業の共同経営などを行っていた場合
遺言がない場合には内縁の夫や妻は相続人となることができないのが原則ですが、共同経営のような形で事業を行ってきたというようなケースでは残された財産については「共有財産」という扱いになる可能性があります。
この場合は形式的には相続人ではありませんが、実質的には相続人と同じような立場を得ることになります(事業が共同経営といえるか、内縁者の寄与がどの程度なのか、については家庭裁判所が実際の状況をみながら判断します)
愛人との子(非嫡出子)がいる場合
法律上の婚姻関係になかった人との間にできた子供のことを「非嫡出子」といいますが、相続をめぐっては非嫡出子に相続分が認められるかどうかが問題となるケースは少なくありません。
結論から言うと、非嫡出子が相続人となるのは、亡くなった人がその非嫡出子を認知している場合だけです。
非嫡出子であっても認知されている場合には、法律上の配偶者との間に生まれた子(嫡出子)と同じように相続をする権利が認められます。
相続できる割合についても、近年法改正によって嫡出子と非嫡出子の相続分はまったく同じということになりましたので注意しましょう(数年前までは非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、このルールを定めていた民法の規定は改正されました)
遺言によって非嫡出子が認知されるケースもある
被相続人が遺言によって「非嫡出子を自分の子と認める(認知する)」という意思表示を行っている場合には、その非嫡出子は認知されたものとみなされます。
この場合、非嫡出子であっても嫡出子と全く同じ相続人としての権利が認められることになります。
生前には愛人や愛人との子の存在を明らかにすることができないような場合に遺言による認知が行われるケースは少なからずあります。
遺言による認知が行われている場合、その非嫡出子を参加させない形で遺産分割協議を行っても、その協議は無効となってしまいますので注意が必要です。
非嫡出子の側から認知を求めるケース
認知は親の側からだけではなく、子やその母親、さらにその子の子(被相続人からみて孫)の側からも求めることが可能です。
被相続人の死後の場合、認知の訴えは国(検察官)を相手に対して行われますが、被相続人の死亡から3年間が経過した場合には訴えを提起する権利が失効します。
被相続人の介護をしていた相続人とそうでない相続人がいる場合
被相続人の生前に介護を行っていた人と、そうでない人がいる場合、介護を行っていた人が何らかの形で見返りを得たいと考えることは自然なことです。
このようなケースでは、「寄与分」という主張を行うことによって介護を行っていた人は他の相続人よりも多くの相続財産を得られる可能性があります。
寄与分の主張
寄与分とは、簡単に言うと「亡くなった人の生前に特別な貢献をした人には、その分だけ多く遺産相続が認められる」というルールのことです。
ただし、実際には寄与分を認めてもらうためには「特別な寄与」があったものと家庭裁判所に認定してもらうことが必要です。
具体的には単純に介護をしていたというだけでは足りないことがほとんどです(裁判所は、子供が親の介護をするのは当然のことという判断をする傾向があります)
亡くなった人の財産を運用してその価値を増やすのに貢献したといったように、目に見える形で経済的な利益をもたらしたことが寄与分を認めてもらうための条件となることが多いです。
相続人以外の人に寄与分は認められる?
例えば長男の嫁が義理の親の介護をするといった場合のように、血縁関係はなく、法律上は相続人となる権利のない人が被相続人の介護を担当するというケースも少なくないでしょう。
このような場合、何らかの形で介護を担当した人に財産を取得させることができないか?が問題となります。
亡くなった方が遺言で「介護を担当してくれた人に一定額の財産を渡す」という意思表示をしてくれていればもっとも問題は少なく済みます。
しかし、このような遺言がない場合には、相続人となる権利のない人は寄与分を認めてもらうことは難しいというのが実際のところです。
「長男の嫁の寄与分」は長男が受け取ることも
ただし、上記の例のように長男の嫁が介護を担当していたというような場合であれば、長男の嫁には寄与分は認められなくとも、その夫である長男に対して寄与分を認めるという形が認められる可能性はあります。
しかし、例えば介護施設の職員のように、亡くなった人とまったく関係がない人の場合はやはり寄与分を認めてもらうことは難しいですから、遺言の形で被相続人自身に生前の意思表示をしておいてもらうのが先決ということになるでしょう。
特別受益者についてのルール
上では家族などがなくなった人に対して貢献をしたケース(寄与分)について解説させていただきました。
一方で、亡くなった人の側から、一部の相続人に対して生前特別扱いのような形で金銭その他が渡されていたような場合にはどうなるでしょうか。
このようなかたちで生前贈与を受けた人を「特別受益者」と呼びます。
相続人となる人の中に特別受益者がいる場合、その人が他の相続人と同じように遺産を相続できるとした場合には、相続人間で不公平感が生じる可能性があります。
持ち戻し計算
そのため、特別受益者が生前贈与を受けた財産の評価額を、相続財産に足し戻し、その合計額からそれぞれの相続人が相続する財産の価額を計算するということが行われます(持ち戻し計算とよびます)
持ち戻し計算の結果、特別受益者の相続分からすでに受け取っている生前贈与の分を差し引きした金額が、特別受益者の相続分ということになります。
もしこの計算方法によって特別受益者の相続分がマイナス以下となる(持ち戻し計算によって計算した相続分<生前贈与を受けた価額)場合には、特別受益者は相続財産の分割を受けることができなくなります。
持ち戻しを免除する意思表示がある場合
ただし、このような場合にも被相続人が遺言によって「生前贈与分については相続財産の分割において考慮しない」といったような意思表示をしている場合には、持ち戻し計算は行われないことになります。
そのため、生前贈与によって得た財産の金額が大きかったとしても、その人が他の相続人と同様の相続分を得るという扱いになる可能性は考えられます。
なお、その場合にも他の相続人の遺留分については侵害することはできません。
遺留分を害している状況が認められる場合には、特別受益者以外の相続人は遺留分減殺請求によって相続財産を確保することができます。
相続人の一部と連絡がとれない場合
遺産相続は、最終的には相続人となる人全員が遺産分割協議を行い、相続の内容を定めた遺産分割協議書に署名捺印を行うことによって完了します。
遺産分割協議書には必ず相続人全員の署名捺印が必要になりますので、相続人の中に連絡が取れない人がいるような場合には問題となります。
また、遺産相続については遺言が残されていたものの、相続財産のすべてについては遺言が定められておらず、一部については被相続人の意思が不明となっているような場合にも相続人全員が集まっての遺産分割協議が必要となります。
例えば、遺産のうち土地や建物については遺言が定められていたものの、現預金については遺言では何も定めていないというような場合、この現預金については相続人全員が集まって遺産分割協議を行う必要があるのです。
まずは連絡を試みるのが先決
相続人のうち音信不通となっている人がいる場合にも、なんとか連絡をとって遺産分割協議に参加してもらうのが大原則となります。
具体的には戸籍謄本ををたどって音信不通者の現在の本籍地を探したり、戸籍の附票を取得して現在の居住地を突き止める方法が考えられます(戸籍の附票には本籍地に関する手続きを行った後の住所移転の履歴が記載されます)
どうしても連絡を取ることができない場合の処置
上記のような手段をとっても音信不通者と連絡を取ることができない場合には、次のような方法によって遺産分割協議を開始する方法があります。
1 家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう
当分帰来する見込みがない音信不通者の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
この「当分帰来する見込みがない」というのは数日間の音信不通などでは認められない可能性が高く、数か月~数年以上にわたって音信不通の状態が続いていることが条件となることが多いです(ただし、生死不明であることは必要ではありません)
不在者財産管理人は音信不通となっている人の財産権を確保するために選任されますから、相続人となる別の親族が不在者財産管理人となることはできません(音信不通となっている人と利害が対立するためです)
親族が不在者財産管理人に選任される可能性もありますが、その場合の親族は相続人となる資格がない人に限られます。
2 家庭裁判所に失踪宣告を出してもらう
すでに何年間も音信不通の状態が続いている…というような場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことも一つの手です。
失踪宣告の条件は2種類あり、1つは「7年間以上音信不通の状態が続いていること」です(これを普通失踪といいます)
もう1つは災害などで音信不通になった後、1年以上が経過した場合です(特別失踪といいます)
利害関係人(相続の場合は別の相続人)が家庭裁判所に対して申し立てを行い、失踪宣告が出た場合には、その音信不通となっている人は法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告後には音信不通となっている人を欠いた状態でも相続財産について遺産分割協議を行うことが可能になります。
ただし、失踪宣告を受けた人に子供がいる場合には、その子に相続権が認められることになりますから、その子を遺産部活協議に参加させなくてはなりません(代襲相続といいます)
相続財産のほとんどが借金であるという場合
「親の借金は子供が返さないといけない」というようなことがいわれることもありますが、相続財産として残されているのは借金だけ…という場合についても見ておきましょう。
相続は負債(借金)についても生じますから、法律上のルールに従って相続人となる人がその借金を引き継ぐことになるのが原則です。
ただし、相続人は自分が相続にかかわるかどうかを自由に決めることができますから、自らの意思で相続にはいっさい関与したくないという意思表示をした場合には借金を相続することから逃れることが可能です。
具体的には、以下のような方法によって「自分は相続にはかかわらない」という法律上の意思表示を行います。
相続によるメリットが何もない場合は相続放棄
相続財産が借金などのマイナスの資産だけで、相続をしたとしても相続人になんのメリットもない…というような場合には相続放棄を行うのが適切です。
相続放棄とは、家庭裁判所を通して「自分は相続にはいっさいかかわらない」という意思表示をすることで、それぞれの相続人が独立して行うことができます。
相続放棄を行うと、相続財産に含まれるプラスの財産(現預金や不動産など)を受け取ることができなくなりますが、マイナスの財産(借金など)についても関わらないとすることができます。
具体的には「相続放棄の申述書」という書類(家庭裁判所にひな形が備え付けられてあります)を相続開始から3か月以内に作成し、亡くなった人の最終の住所を管轄している家庭裁判所に対して提出すればOKです。
相続人が未成年である場合は?
相続人が未成年者である場合、その人は単独では相続放棄を行うことができません。
未成年者にはその保護者が法定代理人となっているはずですから、その人が相続人の代理として相続放棄を行うことになります。
ただし、法定代理人自身が未成年者である相続人と利害関係がある場合(ともに同一の相続案件について相続人となっているような場合)には、法定代理人であっても本人に代わって相続放棄を行うことはできません。
このような場合には家庭裁判所に特別代理人(その相続に関してのみ代理人となる人)を選任してもらい、相続放棄の意思表示を行うことになります。
相続放棄をやっぱり辞めたい場合は?
一度相続放棄を家庭裁判所に対して行うと、その意思表示を取り消すことはできません。
借金しか残されていないと思っていたら後から資産があることがわかった…というような場合でも相続放棄を取り消すことはできません。
相続放棄を行うまでには3か月間の財産調査期間が設けられていますから、その間にどのような財産が残されているのかについて入念に調査を行うことが必要です。
相続放棄をしたら生命保険金はどうなる?

被相続人が亡くなったことによって保険会社から相続人に対して支払われる生命保険金については、相続放棄をした場合であっても問題なく受け取ることが可能です。
ただし、相続放棄をした場合にも受け取れる生命保険金は、「相続人となる予定の人が名宛人となっている保険金」に限られます。
もし亡くなった人が保険金の受取人となっているような場合には、その保険金は相続財産の一部ということになりますから、これを受け取ると遺産相続を認めたことになってしまいます。
このような形でお金を受け取った場合、すでに相続放棄を行っていたとしてもその相続放棄が取り消されてしまう可能性もありますから注意が必要です。
相続放棄をした人に子供がいる場合は?
相続放棄をすると、その人は最初から相続をする権利がなかったものとみなされますから、その人の子についても相続権は生じません。(代襲相続のような形は生じません)
借金を残して亡くなった人に子と、さらにその子(亡くなった人から見て孫)がいるというような場合には、子だけが遺産相続をすればOKということになります。
ただし、相続放棄を行うことによって、相続放棄を行った人よりも下位の相続順位の人が相続人となるケースもありますので注意を要します。
相続財産に資産も含まれている場合には限定承認
相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方があり、トータルで見るとプラスの財産の方が多い…という場合には、限定承認という形で相続を行うのが適しています。
限定承認を行うとプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も相続するという扱いにしてもらうことが可能になります。
例えば、3000万円の不動産があるけれど、5000万円のローンが残っているというような場合には、不動産の評価額の範囲内でのみローンも負担するという形を取ることができます。
ただし、限定承認は相続人となる人全員が共同して手続きを行う必要があるほか、清算手続きや準確定申告といった手続きを行う必要がありますから、多くの場合は専門家にアドバイスを受ける必要があることを知っておきましょう。
何も意思表示をしないと「単純承認」とみなされてしまう
相続が発生したこと(つまり親族が亡くなったこと)を知ってから3か月間は「熟慮期間」といわれ、この間に相続放棄や限定承認を行った場合には借金を相続しないという扱いにしてもらうことができます。
一方で、この3か月間に何ら手続きを行わず、漫然と時間が経過してしまったという場合には「単純承認」として財産を相続することを認めたものとみなされてしまいます。
ただし、上記の熟慮期間は「相続が発生したことを知ったとき」から起算しますから、遠方に住んでいたり、音信不通となっていたりして親族がなくなったことを知らなかったような場合には3か月間が経過した後にも相続放棄や限定承認を行うことが可能です。
養子が相続人となる場合
血のつながりはなくても、被相続人と生前に養子縁組を行っている人は、相続に関しては血縁関係のある子と同じように扱われます。
相続人となる順位についても同一ですし、遺産分割を受ける割合、さらに遺留分が認められる割合についても同じ扱いを受けることができます。
養子は実方の親との関係はどうなる?
養子となった人の立場で考えると、養子としてもらった親と、血のつながりのある実の親(実方の親)の2つの親族関係が考えられます。
もし、この実方の親に相続が生じた場合、養子となった人は実方の親の相続財産について相続分を主張することができるでしょうか。
結論から言うと、すでに行われた養子縁組が「普通養子縁組」であれば実方の親の相続人となることができますが、養子縁組が「特別養子縁組」である場合には相続人となることができません。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組とは養子縁組を行った後も、実方の親との関係が切れない形の養子縁組のことをいいます。
この場合、実方の親に相続が生じた場合には他者の養子となった後も、その実方の親の相続について相続人となることができます。
特別養子縁組の場合
特別養子縁組とは、養子縁組を行った後には、実方の親との法律的関係が断ち切られる形の養子縁組を言います。
特別養子縁組を行っている場合、実方の親との法律関係がすでに失効しているわけですから、実方の親に相続が生じたとしても養子となった人はその相続に関しては相続人となることができません。
養子に子がいる場合
被相続人が養子とした人に子がいる場合、その子には代襲相続の権利が認められるかが問題となることがあります。(養子となった人が被相続人の死亡時にすでに死亡している場合)
この場合、養子縁組が行われる前の段階ですでにその子が生まれていた場合には代襲相続の権利が生じますが、養子縁組を行った後に生まれた養子の子は代襲相続の権利を持たないことになります。
ただし、このような場合(養子に養子縁組前に生まれた子がいる場合)にはその子についても養子縁組の時点で被相続人と養子縁組を行うことが普通ですから、実際にはそれほど大きな問題とはならないことが多いでしょう。
養子縁組は相続税対策に有効?
相続税の計算は、相続財産から「基礎控除」と呼ばれる金額を差し引きした金額を課税標準として計算されます。
※計算式にすると以下の通りです。
相続税の課税標準額=相続財産の合計-基礎控除
そのため、この基礎控除の金額が大きくなればなるほど相続税の負担は小さくなることになります。
基礎控除は以下の計算式で計算します。
基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
相続税法上、基礎控除の計算に含む養子は1人または2人まで
この「法定相続人」には養子も含みますから、養子の数が増えることによって相続税の節税につながると考える方もひょっとしたら多いかもしれません。
しかし、この点で相続税法上は制限があり、実子がある人の場合は養子は1人まで、実子がいない人の場合には養子は2人までとして基礎控除を計算することになっています。
例えば、実子が3人いる人が、2人の養子もいるという場合、相続税の基礎控除は以下のように計算することになります。
基礎控除=3000万円+(実子3人+養子1人)×600万円=5400万円
民法上は養子にする人数に制限はありませんが、税金の計算上は上のような制限があることを理解しておきましょう。
過去に離婚した妻子や、再婚相手の連れ子がいる場合
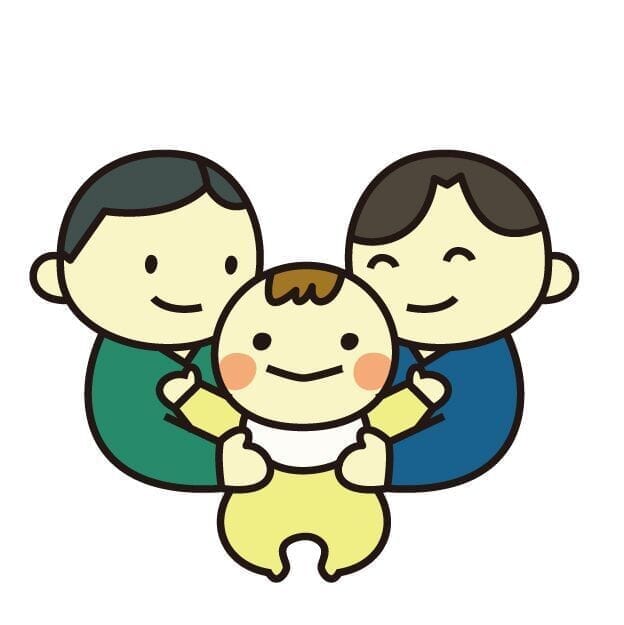
亡くなった方が過去に離婚をしており、前妻(前夫)との間に子供がいるという場合には遺産相続はどうなるでしょうか。
前妻、前妻との子、再婚後の連れ子についてそれぞれ相続人としての権利があるかどうかについて解説させていただきます。
前妻は相続人となれない
まず、別れた前妻は法律上の親族関係が終了していることになりますので、相続人となることはできません。
前妻との間の子は相続人となれる
前妻との間にできた子は、被相続人と血縁関係があるということになりますから、当然相続人となれます。
ただし、前妻が別の人と再婚しているような場合で、その人と前妻との子が特別養子縁組(実親との関係を終了する形の養子縁組)を行っている場合には、相続人とはなれません。
再婚相手の連れ子を相続人とするためには養子縁組が必要
被相続人が再婚しており、その再婚相手に連れ子がいるという場合、その子は当然には相続人とはなりません。
この子を相続人とするためには養子縁組を行う必要があるためです。
相続分を譲渡したい人がいる場合
相続放棄と少し似ていますが、相続人の中に「自分は相続にはかかわりたくはないので、自分の相続人となる権利を誰かに譲渡(売却)したい」と考える人がいるケースもあります。
このようなケースを「相続分の譲渡」といいますが、この場合には相続放棄とはまた違った問題が生じる可能性があります。
以下では相続分の譲渡に関して問題となりやすい点についてみておきましょう。
相続分の譲渡とは
例えば、遺産として残された不動産の相続人として被相続人の子供3人(長男、次男、三男)がいるという場合に、三男は「不動産の相続に関しては関わりたくはないが、自分が相続放棄をすることによって、仲の悪い次男の相続分が増えるのはくやしい」と考えたとします。
このような場合に三男が長男に対して相続分の譲渡を行うと、次男の相続分をは増やすことなく、三男は自分の相続分を別の人に譲り渡すことが可能になります。
通常は相続分を譲渡する代わりに金銭等で代金を受け取ることができますから、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合、早期に現金などを手元に受け取りたい人は相続分の譲渡を行うメリットがあるでしょう。
ただし、相続分の譲渡では次のような点に気を付けておく必要があります。
相続分の譲渡では、相続人としての身分は引き継ぐ
相続分の譲渡では、相続放棄とは違って「相続人としての身分」は引き継ぐ必要があります。
そのため、相続財産にマイナスの財産(借金)などが含まれている場合には第三者に対してその負債を支払う義務引き継がなくてはなりません。
ただし、相続分の譲渡を行う際に、譲渡を行う相手方に対して相続財産に含まれる負債については譲渡を受けたものが一切負担するというような取り決めを行っておけば、負債についての引継ぎは免れることができる可能性があります。
相続分の譲渡は遺産分割協議が開始する前に書面で行い、トラブルを未然に防ぐためにも事前に相続人全員に対して、特定の人に対して相続分の譲渡を行った旨を通知しておくのが良いでしょう。
相続分の譲渡は相続人以外の第三者に対しても行える
上では相続人となれる人が、自分以外の相続人に対して自分の相続分を譲渡するケースを紹介しましたが、相続分を譲渡する相手は親族とは無関係の第三者であっても有効です。
相続分を譲渡された第三者は、自らの名前で遺産分割協議に参加することが可能となります。
相続分の取戻し
しかし、全くの他人である第三者が遺産分割協議に参加してくることによって、事務が円滑に進まなくなってしまうことも考えられます。
そのような場合に備えて、法律上「相続分の取戻し」という方法が認められています。
相続分の取戻しとは、すでに行われた相続分の譲渡について、対価を支払って第三者から取り戻すことができる制度です(取り戻した相続分は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員に帰属することになります)
ただし、相続分の取戻しは相続分の譲渡が行われてから1か月以内に相手方に通知して行う必要がありますから注意が必要です。
相続に当たって事業承継を行う場合

亡くなった人が企業経営者(法人のオーナー社長)として事業を営んでいたという場合には、相続と同時に後継者を誰にするか?という問題が生じます。
具体的には亡くなった人が所有していた企業の株式を誰が相続するのかということが問題になりますが、経営権そのものである会社の株式を複数の人が分け合って引き継ぐというのは適切ではないことが多いです。
そのため、多くは後継者となる特定の一人に対して贈与や相続の形で株式を移転することになりますが、その対価を被相続人の生前に被相続人に対して支払っていない場合には、移転した株式には贈与税や相続税が問題となります。
事業承継税制によって相続税や贈与税の負担が猶予される
しかし、結論から言うとこういった事業承継に際して発生する見込みの贈与税や相続税については「事業承継税制」という特別のルールが適用されるため、相続税や贈与税の負担が猶予されるということになります。
従来は事業承継に関連する贈与税や相続税のすべてが猶予されるというわけではなく、一部は負担しなくてはならないとされていたのですが、平成30年の税制改正大綱ではさらに進んでこの事業承継に関する相続税や贈与税のすべてを猶予してもらえる仕組みに改正される見込みです(平成30年1月以降に実施される事業承継について適用されます)
ただし、事業承継税制を適用してもらうためには、以下のような条件を満たす必要があります。
従業員雇用の確保
事業承継が行われた後、5年以内に従業員の数が従来の80%未満となる場合には、都道府県に対して報告を行い、認定支援機関による指導助言を受けなくてはならないものとされています。
従来は事業承継後5年間は80%の従業員雇用を維持しなくてはならないというルールがあったのですが、今回の改正によって条件が大幅に緩和されたことになります。
都道府県に特例承継計画書を提出する
事業承継税制の適用をしてもらうためには、都道府県に対して「特例承継計画(事業承継後の事業計画書のようなもの)」を作成して提出しなくてはなりません。
この書類の作成に当たっては、中小企業庁が認定している「認定経営革新支援機関」に該当する業者(多くは税理士事務所です)から助言をしてもらうことができます。
事業承継についてのアドバイスは税理士に依頼しよう

このように、事業承継に関連する税金や今後の企業戦略に関する相談は、前の経営者の代から顧問となってもらっている税理士に相談するほか、相続事務を専門としている税理士に依頼するのが適切です。
遺産分割協議や遺言書内容の執行といった法律面に関する相談は弁護士や司法書士にするのが良いですが、税金については税理士でないと解決できない問題も多くありますから注意してください。
相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合の対処
相続が発生した後は、相続人となる人たちが集まって遺産分割協議を行い、だれがどの財産を相続するのかを確定します。
相続する財産が確定したら、その財産の金額からそれぞれが負担する相続税を計算し、期限までに相続税の申告と納付を行わなくてはなりません。
相続税の申告期限は相続が発生してから10か月以内ですが、もしこの間に遺産分割協議がまとまらない場合にはどうなるでしょうか。
遺産分割協議がまとまっていなくても相続税の期限はやってくる

結論から言うと、遺産分割協議の問題は誰がどれだけの相続税の納付を行わなくてはならないのか?ですが、遺産分割協議がまだ完了していない場合には、「民法のルールで遺産分割が行われた場合の相続割合」で遺産分割が行われたものと仮定して相続税を計算し、各自が自分の負担部分を納付することになります。
もちろん、まだ遺産分割は正式に行われていませんから、残された遺産に手をつけるわけにはいきません。
なので、各自の相続税負担部分については各々がポケットマネーで納税し、後で遺産分割協議が完了してから少なく納付していた人は追加納付、多く納付していた人は還付を受けるという形になります。
相続税の負担の具体例
例えば、相続人が長男と次男の2人で、相続税の合計額は3000万円とわかってはいるものの、遺産分割協議がなかなか整わないという場合を考えます。
この場合、相続税の納税期限においてはとりあえず各自が法定相続分である2分の1の金額(1500万円)を税務署に納付しなくてはなりません。
その後の遺産分割協議によって、結果として遺産のうち3分の2を長男が、3分の1を次男が相続したといった場合には、本来納付するべき相続税は長男が2000万円、次男が1000万円ということになります。
この場合は長男は500万円を追加納付し、次男は500万円を税務署から還付してもらえるというわけです。
なお、税務署としては納付される金額に変わりはありませんから、税務署に対しては特に何もせず、兄弟の間でお金を清算するという形で解決をしても問題ないことになっています。
相続税の負担が必要ないケース
なお、相続税には「非課税部分」に該当する部分があるため、必ずしもすべての遺産相続について相続税が発生するというわけではありません。
具体的には、以下の計算式で計算する金額までであれば相続税は非課税ということになります。
相続税の非課税部分=3000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、法定相続人となる人(被相続人の配偶者や子供)が合計で10人いるという場合であれば、相続税の非課税部分は9000万円ということになりますから、これを超える金額の遺産が残されていない場合には、相続税は1円もかからないということになります。
遺産分割協議が完了していない場合、各種の相続税減免措置が受けられない
ところで、相続税の納税については各種の減免措置が認められています。
例えば、亡くなった人の配偶者の方は相続税の負担をとても小さくしてもらえますし、遺産が居住用の宅地等で会った場合には相続税の課税標準額を大幅に小さくしてもらうことができる「小規模宅地の特例」といった特別措置を適用してもらうことができます。
しかし、遺産分割協議が相続税の納税期限において完了していない場合には、これらの減免措置を受けることもできないことになっています。
場合によっては、本来は負担する必要がない税金の負担をしなくてはならなくなるようなケースも考えられますから、遺産分割協議は相続税の申告期限を考慮しながら早期に完了しておくことが重要です。
親族だけではどうも遺産分割協議がまとまらない…という場合や、相続人の中に連絡が取れない人がいるというような場合には、弁護士などの法律の専門家に相談することで早期に問題を解決する手段を検討しなくてはなりません。
相続人の廃除や相続欠格が問題となる場合
亡くなった人の親族は相続人として財産を引き継ぐことができますが、例外的に相続人となる資格を失ってしまう場合があります。以下、該当するケースについて解説させていただきます。
相続人の廃除とは
日本は私有財産制の国ですから、自分が築いた財産については、自分の死後に誰に引き継ぐかは自由に決めることができるというのが大原則です(例外として遺留分などのルールはありますが)そのため、被相続人が生前において相続人から虐待などを受け、「この人は自分を虐待していたので、相続人となる権利を認めない」という意思表示を行った場合には、その人は相続人となる権利を失います(相続人の廃除)
ただし、この意思表示は生前に家庭裁判所に対して申し立てを行うか、遺言執行人を指定する形で遺言を残しておくことが必要になります。
また、相続人の廃除は被相続人本人しか行うことができませんから、被相続人の死後になってから別の相続人が「この人は被相続人を生前虐待していたから、相続人になることは認めない」という主張をすることは基本的に認められないことになります。
ただし、さらに深刻な事情がある場合には次の「相続欠格」に該当し、該当者は相続人となる資格を失うことになります。
相続欠格とは

相続人となる人が次のような行為をした場合には、相続人となる権利を失います(相続欠格)
・被相続人や、自分以外の相続人となる予定の人を故意に殺害したり、殺害しようとしたりした場合
・被相続人が犯罪に巻き込まれ、殺害されたことを知っているのに告訴などをしなかった場合
・遺言を被相続人への詐欺や脅迫によって変更させたり、偽造したりした場合
なお、相続人の廃除では厳格な手続き(遺言や家庭裁判所への申し立て)が必要でしたが、相続欠格については特別な手続きは必要なく、これらの事実が確定すれば当然に相続人となる資格が失われます。
そのため、遺産分割協議が行われた後になって相続欠格となる事実が判明したような場合には、その遺産分割協議は無効となるものと考えられます。
相続人の一部だけが生命保険金を受け取っている場合の対処
生命保険金の受取人は、被相続人の生前にどのような形で保険に加入していたかによって決まります。
そのため、相続人の間で不公平感のある形で生命保険金の支給がされるケースも珍しくありません(例えば、相続人が長男と次男の2人で、次男だけが生命保険金の受取人となるような場合)
生命保険金は相続財産ではありませんから、この場合、次男は遺産分割協議を経なくとも自分の名前で生命保険金を受け取ることが可能になります。
ただし、生命保険金の受け取りによって、相続人間で遺産分割にいちじるしい不公平が生じるような場合には、生命保険金については「特別受益」として扱われる可能性があります。
特別受益があったとされた場合、生命保険金を受け取った人はその分だけ受け取れる相続財産の割合を少なくするという形で解決が図ることが考えられます。
遺言の執行者が指定される場合
亡くなった人が生前に遺言を残している場合には、その遺言の内容通りに相続財産が分割されるのが原則です。
そのため、遺言の内容によってはすんなりと承諾できない相続人が出てくる可能性もあるでしょう。
そのような場合に備えて、遺言の内容には遺言執行者を定めておくことが有効です。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、相続が発生したら遺産目録を作成し、遺産に関する権利書や銀行通帳を保管して相続人となる人が勝手に遺産に触れることができないようにします。
その上で、遺言の内容通りに財産の名義変更や分配を行います。
遺言執行者がいない場合にはこうした手続きは相続人全体が共同して行う必要がありますが、遺言執行者が指定されていればその人がすべての事務を1人で行うことができますから、各段にスムーズに遺産分割の事務を完了することが可能になります。
遺言執行者の報酬や諸経費
なお、遺言執行者の報酬や、遺言執行のために必要になった諸費用については、相続財産の中から支払われるのが普通です(生前に契約で金額などは決まっていることが多いです)
もし報酬に関する定めがない場合には、家庭裁判所が決めることもあります。
なお、相続人の1人を遺言執行者に指定しておくことも可能ですが、通常は資格を持った専門家(弁護士や司法書士)に遺言執行者となってもらうケースが多いです。
遺産相続の原則的な形
ここまで説明させていただいたような複雑な遺産相続の対処を考える際には、まずは原則的な遺産相続の形(遺産相続の基礎知識)について理解しておくことが大切です。
遺産相続の基礎知識としては、以下のようなことを理解しておくと良いでしょう。
遺言がある場合には、その内容が最優先で適用される
遺産相続に関して、亡くなった人(被相続人)が遺言を残している場合には、その遺言の内容を最優先に相続財産の分割協議が行われます。
愛人を相続人に含めるようにという遺言があったり、遺産の一部を慈善団体に寄付するようにという遺言があったりする場合には、被相続人の意思通りに財産を処理するのが原則ということになります。
ただし、被相続人と特に近しい関係にあった親族には、遺言によっても侵害されない「遺留分」という権利が認められています。
例えば、被相続人の子供には遺留分として相続財産の2分の1を受け取る権利が認められます。
「自分が死んだあとは全財産を愛人に渡す」という内容の遺言が残されていたとしても、遺留分を持つ子供は2分の1を自分に渡すよう請求することができるということになります。
遺留分減殺請求
遺言の内容通りに相続財産の分割を行った場合には自分の遺留分が侵害されてしまうというような場合には、「遺留分減殺請求」という意思表示を別の相続人に対して行う必要があります。
逆に言うと、もし遺留分を侵害する形の遺言が残されていたとしても、この遺留分減殺請求が行われない場合にはその遺言に基づく遺産相続は有効という扱いになってしまうのです。
相続が発生してから一定期間が経過して時効が成立すると、遺留分減殺請求を行う権利も失効してしまいますから注意が必要です。
遺言がない場合には法律のルールによって遺産相続が行われる
もし亡くなった人が遺言を残していない場合には、法律(民法)のルールに従って相続財産を相続人が分け合うことになります。
法律上、相続人となるのは被相続人の配偶者と、その他の人に分けられます。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の人は相続順位に従い、順位が上の人のみが相続人となります。
(順位が上の相続人と、順位が下の相続人とがいる場合には、順位が下の相続人は相続することができません)
相続順位とは
配偶者以外の相続人の相続順位は以下のように決められています(配偶者は常に相続人となりますので、順位という概念はありません)
第1順位:被相続人の直系卑属(子供や孫)
第2順位:被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
なお、同順位の相続人が複数人いる場合には、同順位者間では平等の割合で財産を分け合うことになります。
例えば、被相続人に妻(配偶者)と子供3人(第1順位)、さらに父親(第2順位)がいるという場合には、妻が2分の1、子供がそれぞれ6分の1ずつ(配偶者の分を差し引きした2分の1÷3で計算します)という形で財産を分け合います。
父親は第2順位の相続人ですから、第1順位の相続人である子供がいる上記のような場合には相続人となりません。
遺産分割協議を行うことによって遺産相続は完了する
遺言や法律によって相続人となる人やそれぞれの相続財産は決められますが、実際には「遺産分割協議」という相続人間の話し合いによって遺産相続の手続きは完了します。
通常は話し合いの結果を遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人すべてが署名捺印することで完了しますが、当事者間の話し合いではまとまならないという場合には家庭裁判所に調停や審判を依頼するという方法もあります。
遺産分割協議とは別に、相続税の申告を行う必要がある
遺産として残されている財産の金額が一定額を超える場合には、相続開始から10か月以内に相続税の申告と納付を行わなくてはなりません。
相続税の申告と納付を行う時点ですでに遺産分割協議が完了しているのが理想的です。
遺産を相続した人は、それぞれ相続した財産の割合に応じて相続税を負担することになります。
一方で、もし遺産分割協議が完了していない状態であったとしても、相続税の申告と納付は期限までに行わなければならない点に注意が必要です。この場合には、法律上のルールにしたがって遺産分割をしたと仮定した場合の相続税負担分を、各相続人が期限までに納付しなくてはなりません。
もし期限までに相続税の申告と納付が行われない場合、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられてしまい、税負担がさらに大きくなってしまう可能性がありますから注意しましょう。
相続トラブルについては弁護士に相談しよう

「もともと仲の良い親族だから、相続に関しては多少のことは話し合いでなんとかなるだろう…。親族どうしでお金のことについてやかましく言うのはちょっと…」
多くの方がこのような期待のもとに相続に関する話し合いを開始しますが、ことお金の問題がからむと仲の良い親族であったとしてもなかなかうまく話がまとまらないものです。
親しい者同士であるからこそ、自分の主張が思うようにできずに結局はうやむやな形で遺産分割協議書にサインをしてしまった(しかもなんだか損しているらしい…)というようなことは決して珍しくないのです。
遺産分割協議は親族だけで行うより、専門知識を持った他人である専門家に間に入ってもらうことでスムーズにまとまる可能性がより高くなります。
弁護士に依頼するメリット

交渉の煩わしさから解放される
突然に家族の不幸が訪れ、遺産相続の話し合いをしなければなくなった場合の精神的負荷はかなりのものです。
ただでさえ親族が亡くなって悲しみに暮れる中、普段の仕事等も並行して行わなければならないわけです。
これに加えて、遺産相続に関する話し合いの煩わしさは大変大きなものです。 この煩わしい作業を、専門家に安心して依頼できることは非常に大きなメリットであります。
また、今まで親しくしてきた身内と突然お金の話をしなければならない状況に陥ります。 例えば、兄弟同士で父親の財産を分ける場合など、お互いの利益は相反することになります。
今後の関係性なども考えて、言いにくいようなことも多くあると思います。
このようなことに思いを巡らせること自体が大変に煩わしいことです。 弁護士に遺産相続を依頼した場合には、代理人として言いにくいことも言ってくれますので、非常に大きなメリットとなります。
手続きの煩わしさから解放される。
相続が発生して、自ら手続きを行おうとすると、その量の多さに驚きます。 戸籍謄本を一つとるだけでも、平日の仕事を休んで市役所へいく時間などないと考えてしまう人は少なくありません。
亡くなった人の代わりにお財産に関する証明書類も取得しなければなりません。
すでに本人はなくなっているわけですから、どこにどんな財産があるのかを把握するのも一苦労です。
例えば、銀行残高を確認するためには、それぞれの金融機関の窓口に赴き残高証明書を取得する必要があります。
また、生前の口座の動きに調整すべき項目があるかどうかを確認するために取引履歴を照会しなければなりません。 これらをすべての金融機関の種類ごとに行う必要があります。 最も財産の状況の確認作業が容易な銀行口座の預貯金でさえ、このように面倒な手続きが生じます。 不動産であれば謄本や権利書の確認等も必要になります。 また、金額において現在の相場を調べる必要があります。
非常に専門的な作業になりますので、普通の人が取り組もうとすると煩雑極まりない作業になります。
また、手続きの代行に関しては他の専門家と連携しているかも非常に重要なポイントです。
公証役場などの行政機関とのやりとりに関する書類の代理作成の専門家として行政書士があります。
また、不動産などの相続を受けた場合には、法務局へ登記を行う必要がありますが、この領域の専門家は司法書士になります。
この様な他の専門家とやり取りをする際に、いちいち事情を一から伝えるのは手間になります。
また、各手続きは複雑に関係していますから、他の専門家と連携している弁護士に依頼することによって、依頼者にとって総合的にもっとも有利な内容で外部と連携し手続きを進めることができるのです。
弁護士に依頼する際には、外部専門家との連携体制について確認するとよいでしょう。
知らないと損をする可能性を減らす
相続の局面においては、期限や取り扱いが非常に複雑なルールが多くあります。 財産の分割の方法や申告の期限の問題、相続税の支払方法等、数をあげればきりがありません。 しかも、金額が比較的大きなものになることが多く、うっかりミスをしてしまった場合の被害も大きくなりがちです。
弁護士は法律の専門家ですから、専門知識を駆使して、依頼者の利益が最大になるように提案・調整をしてくれます。
また、遺留分の考え方一つをとってみても、関係者の人数が多い場合や亡くなっている場合、離婚再婚などがあった場合は非常に複雑になります。
自分がもらう権利がある財産についても、ルールを知らないがゆえに主張する機会を逸してしまい、損をしてしまうというようなことにもなりかねません。 だれでも身内とあえてもめるようなことしたくはないはずです。 しかしながら、正当な権利があるのならば主張すべきと考えている人も多いのではないでしょうか。 相続はそのケースに応じて、まったく内容が違うものになります。 相続の事例を解説本などで調べてみても、まったくもって同じ状況ではないとうことがほとんどだと思います。
それぞれの家族にはいろいろな歴史があり、人間関係も異なります。
亡くなった方が築きあげてきた財産の内容もそれぞれ異なります。
すべての財産が銀行の預金であれば、相続に人で分けるのは簡単かもしれません。
しかし、現実には自宅などの不動産も財産として存在するケースも多くあります。
誰が相続して、だれが済み続けるのによって相続税法上の評価が異なることが多くあります。 不動産を相続した場合においては、お金は一銭ももらっていないのにもかかわらず、莫大な金額の相続税が発生することもあります。 この様なときの納税方法などの相談にも乗ってくれるはずです。
遺産相続の専門家である弁護士に依頼することによって、自分の状況にあった最適なプランを提案してくれるはずです。
相続の得意な弁護士に依頼すれば、知らずに損したというようなことはありません。
一生のうちに、多くても数回ていどしか直面しないのが相続です。是非、専門家に依頼するとよいでしょう。
そもそもトラブルが発生しないようにまとめてくれる
お金が絡むと誰でも欲が出て、感情的になってしまうことがあるものです。 時には、感情に任せて常識を外れた主張をしてしまうこともあるかもしれません。
そのようなことで、一度関係性に溝が入ると修復が難しいこともあります。 今まで仲の良かった兄弟同士にもかかわらず、相続をきっかけに絶縁状態になるなどといった話も残念ながら良く聞きます。 法律に熟知した弁護士を通して話し合いをすることによって、話し合いも自然と法律にのっとった建設的な内容になっていくものです。
この結果、スムーズに話し合いが進行し、トラブルが発生することなく無事に完了することもあります。
また、結果として正しいことを主張していたとしても、それが感情的になっている局面で話したことであれば、相手に受け入れてもらえないこともあります。
また、主張された相手側にとっても、それは本当に法的に正しいことなのかの判断がつかず、話し合いがうまくまとまらないこともあります。
こんな時、傍らに法律の専門家である弁護士がいた場合、すぐにその場で法律的な解釈を補ってくれます。
法律に詳しくない一般の人が発言した内容よりも、弁護士という裏付けのある人が発言することによってその信憑性は非常に高くなります。 特に、相続に関する話し合いを行う時は、緊張感が高まりますから、法律的に正しいという裏付けをもって話し合いを進めることができるというのは非常に大きなメリットになります。
相続にトラブルが生じた時に裁判の代理のため弁護士を依頼するという方法の他に、話し合いに一緒に参加してもらい、冷静な立場での交渉のまとめ役としても機能します。
話し合いがもつれる前から弁護士に依頼することにより、よりスムーズに話がまとまる可能性があります。 トラブルの予防のために弁護士に依頼することは、非常に大きなメリットです。
弁護士に依頼するデメリット

金銭的負担が必要
弁護士に遺産相続を依頼するときに、一番のデメリットとして思い浮かぶのが依頼費用ではないでしょうか。
一般の人が普通に生活するうえで、弁護士にお仕事を依頼する機会などはまずありません。
いざ、遺産相続について弁護士に依頼しようとすると高額の報酬を請求されるかもと、二の足を踏んでしまう人も多いのではないでしょうか。
大まかに分けると活動費と報酬に分けることができます。
活動経費
弁護士が依頼された遺産相続の案件について手続きを行う際の移動費が代表的なものです。
管轄の裁判所などに赴いて行う必要のある手続きも多く存在します。
また、資料作成の過程で、どうしても必要になる戸籍や謄本を取得する際にも、印紙代などの費用が掛かります。
また、土地の評価額の計算など、他の専門家に手続きを一部依頼する必要がある場合もあります。その場合には、不動産鑑定士への報酬費用などが発生します。
報酬
基本的に、弁護士費用の中心となるのが依頼報酬です。 多くの場合、導入時の相談料金、正式に手続きを依頼した際の着手金、完全に業務が完了した段階で支払う最終報酬に分かれます。
それぞれの弁護士事務所により異なりますが、まずは初回の相談料を無料としているところも最近は多いようです。
実際に案件に着手する際に支払う着手金についての計算方法は様々です。
全体の見積もり報酬額の2割と計算するところもあれば、一律に10万円等とするところも少なくないようです。
最終報酬については、成功報酬とする場合も多いようです。依頼した手続きが、完全に遂行された際に請求することが多いようです。
弁護士のスタンスによる違い
法律の世界と私たちの日常生活の感覚が異なることは多くあります。 たとえば、人間関係において、相手の性格や関係性に斟酌して、法律論に従って厳密に得られた結論とは違う内容で合意することはよくあることです。
ビジネスの世界において、取引先との関係上、この様な場面は多くあります。
それが親族の間となると、今までの関係性もあり、また、これから先も長く付き合うことを考えて、法律論とは違った合意がなされることがさらに多くあります。
相続の局面でも、まさに、金額の重要性や、相手の立場に配慮して、また、トラブルに発展するのを嫌って、この様な取引がされることが非常に多くあります。
外部の目から見れば、多少不自然に感じる部分があっても、当人同士では非常に整合性の高い結論であることもあるのです。
人間らしい話し合いがされることは決して悪いことではありません。
一方、弁護士は法律に関する豊富な知識を武器に、依頼者の利益を守る職業です。
また、弁護士によっては、法律的に正しいことが、正義であるとの信念を持ったひともいます。 遺産分割を円滑に進めるために弁護士に依頼したのにもかかわらず、当人同士が問題としていないような些細な点について、検討を始め、反対に話し合いがもつれる原因を作るということもあります。 もちろん、この様な弁護士ばかりではありませんが、個人の性格によるところも少なからずあることは確かです。
また、遺産分割について話し合いがこじれて裁判等になり、期間が長引くとそれ相応の追加報酬が発生します。
この意味においては、依頼者と利益が一致しない場合もあるでしょう。
司法書士や税理士、行政書士との違いとは?

弁護士以外で私たちが遺産相続について相談しようとした時に思い浮かぶ専門家として、司法書士、税理士、行政書士があります。
それぞれ専門分野が異なり下記のような特徴があります。
司法書士
司法書士も法律の専門家です。 不動産登記や遺言書の作成、遺産分割協議書の作成等が専門業務です。 これらは、弁護士も行える業務になります。
ただし、遺産分割協議や、調停等において代理人となることはできない点がポイントです。法律問題に対して代理人として対応できるのは弁護士だけです。
税理士
相続税の申告、準確定申告、相続財産の評価、節税スキームの提案等を行うことができます。
相続を考えたときに、実際の納税額が少しでも少なくなるような手法の提案を受けることができる点においては、非常に頼もしい専門家ということができます。 ただし、相続が実際に発生してしまった場合には、取るべき対策も限られます。
節税対策の手法は、基本的に数年単位の事前計画に基づくものが多いです。
行政書士
遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成を依頼することができます。
ただし、これらについては弁護士や司法書士にも依頼することのできる業務になります。
しかも、遺産分割の過程において問題が発生した際には、弁護士や司法書士に依頼することになります。
従って、よほど単純な案件で費用を安価に抑えたい場合以外は、相談しにくいというのが実情です。
遺産分割をスムーズに完了させることが重要ならば税理士や司法書士に

遺産相続を相談する専門家には税理士や司法書士も当てはまりますが、彼らにとって、相続を長引かせても良いことはりません。
確定した内容に基づいて相続税の申告を代理で行うことや、遺産分割協議の結論に基づいて各種登記等を行うことが業務になります。
そのため、遺産分割をスムーズに完了させることが重要になります。 この意味においては、弁護士と比較した場合に、スムーズに遺産相続を完了させたい相続人とより利益が一致するのかもしれません。
遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場
上記のメリットやデメリットを考慮して弁護士に遺産相続を依頼する場合、具体的にいくらの金額が必要になるのでしょうか。
遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を確認していきましょう。
相続の案件の特徴として、個別に内容が全く異なるということが挙げられます。
相続する財産についても、評価の簡単な現預金だけである場合や、多くの不動産や取引相場のない株式等、金額的評価を算定するのにも手間を有する財産を保有している場合があります。
相続人同士で、おおむね内容がまとまっているような場合や、完全にお互いが対立していて弁護士同士の交渉が必要な場合もあります。
また、弁護士報酬については、具体的な法律による規定が存在しません。
各弁護士が自由に報酬を決定しています。
しかも、上記のように案件ごとにも内容は様々ですから、一律に相場を決めることはもともと難しい問題があります。
遺産相続に関して報酬を決定する際には、上記のような相続案件の特殊性を理解した上で、考慮すべき事項があります。
それは、「経済的利益」の概念です。
言葉にすると少々かたくるしくなりますが、要は依頼者が、その弁護士に依頼することによっていくら(現金の形だけでなくその他の財産の形式を含めて)得をしたのかということです。
この経済的利益の金額が大きいほど、報酬の金額も大きくなると考えられます。
この点、現在撤廃されていますが、弁護士費用の報酬規定を参考までに記載いたします。
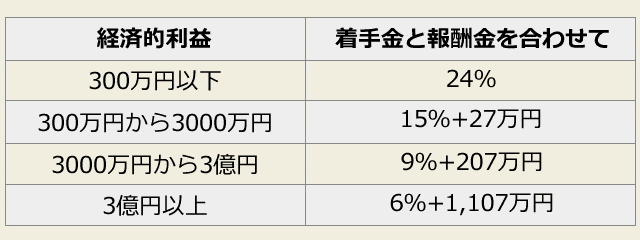
これによれば、
300万円以下の部分については、着手金と報酬金を合わせて24%と規定されていました。
300万円から3,000万円の部分については15%+27万円です。
3,000万円から3億円までの部分については9%+207万円、それ以上の部分については6%+1,107万円です。
金額が大きくなると、報酬も同様に比例して大きくなるのは実情に合いませんので、相対的に金額が大きい場合は報酬の割合は小さくなります。
それでも、この金額については現在の感覚のなじまないとの考え方もあって、2/3くらいのラインで決定しているところが多いようです。
報酬の金額について具体的に交渉する際には、上記の計算結果と比べてみると、交渉がスムーズに進むでしょう。
相続事件についての経験が豊富な専門家に相談するのが大切
相続に関しては弁護士や司法書士といった法律の専門家にアドバイスをしてもらうことができますが、相談する際には「相続に関する実務経験が豊富にある法律家なのか?」については事前にチェックしておく必要があります。
法律家といってもいろんな専門分野がありますから、相談する前にその専門家がこれまでにどのような事件をメインで扱ってきた人なのか?についてはしっかりとチェックするようにしてください。
性格的にも相性が良い専門家を見極めよう
また、相続に関する手続きは短くとも数か月、長ければ一年以上かけて遺産分割に関する協議が行われるというようなことも珍しくありません。
相続に関する事務を依頼する法律家とは長い付き合いになることもありますから、性格的な相性も思いのほか大切です。
多くの法律家の事務所では初回の相談は無料という形で気軽に受けてくれますから、相続に関する現状を相談してみて信頼できそうな人かどうかを見極めるようにしてください。
まとめ
今回は、遺産相続でトラブルが生じやすい事例や、その場合の対処法について具体的な例を挙げながら解説させていただきました。
相続をめぐっては親族間の日ごろの感情のもつれが原因となって「まとまるものもまとまらない…」というような状況になってしまうことも決して珍しくありません。
そのような場合には、弁護士や司法書士、税理士といった相続に関する専門家に遺産分割協議に参加してもらうことが解決の助けになることがあります。
現在、遺産相続をめぐってトラブルが生じてしまっているという方や、近い将来に生じる相続が円満に済むか心配…という方は、専門家からアドバイスを受けることも選択肢に入れてみてくださいね。