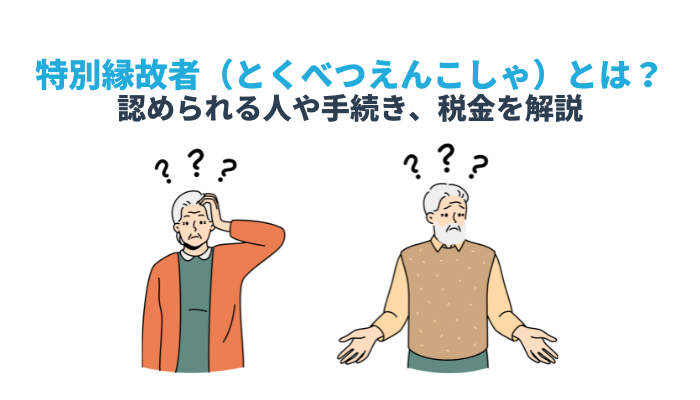この記事でわかること
- 特別縁故者とは
- 特別縁故者と縁故者の違いとは
- 特別縁故者に該当する人は誰か
法定相続人がいない場合、被相続人の生前に近しい関係にあった特別縁故者に遺産の承継が認められるケースがあります。
血縁関係などの縁やゆかりのある人を縁故者といいますが、相続で特別な関係を理由に遺産の承継が認められる人を特別縁故者といいます。
たとえば、生計を同一にしていた内縁の配偶者や事実上の養親子などは特別縁故者となる可能性があるでしょう。
特別縁故者になるには、家庭裁判所に遺産分与の申立てをして相続人の不存在や被相続人との関係を認められなくてはなりません。
法定相続人や特別縁故者がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属します。
ここでは、特別縁故者に該当する場合や家庭裁判所に遺産分与の申立てをするための手続きなどを解説します。
目次
特別縁故者とは
相続が発生すると、遺言など特別な指定がなければ、法定相続人が遺産を相続します。
ただし、被相続人の中には結婚していない、あるいは子がいないために法定相続人がいない人も珍しくありません。
亡くなるまで被相続人の面倒をみていた人が、被相続人の残した財産を相続するケースがあります。
法定相続人がいないときに、被相続人の遺産について特別に相続できる人を特別縁故者といいます。
生前に遺言や死因贈与などの方法で、被相続人の死後に遺産を譲り受けると定められている場合は、特別縁故者になる必要はありません。
上記のような方法がとられていない場合には、遺産を譲り受けるために特別縁故者となる必要があります。
特別縁故者と縁故者の違いとは
縁故者とは、一般的に近親者や親族などの血縁関係がある人をさす言葉です。
長年生活を共にしている親族など、縁やゆかりのある人を幅広く含みます。
一方で、特別縁故者は相続手続きで使用される用語です。
親族などの血縁関係に限らず、被相続人との特別な関係を理由として遺産を承継する権利を認められた人を特別縁故者といいます。
たとえば、被相続人の療養看護に勤めていた人や事実上の内縁関係の配偶者などが特別縁故者として認められる可能性があります。
相続人・特別縁故者がいない場合は国庫に帰属
法定相続人や遺言による財産の承継人、特別縁故者がいない場合の遺産は、最終的に国庫へ帰属します。
遺産が国庫に帰属するまでの流れとして、まず相続人を探すために相続人捜索の公告が行われます。
もし相続人が見つかった場合、遺産は特別縁故者や国庫には帰属しません。
催告期間が過ぎると、相続人の相続権や相続債権者などの権利は消滅し、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定した後、特別縁故者からも遺産分与の申立てがなければ遺産は国庫に帰属します。
国庫に帰属すると、原則として特別縁故者からの財産分与の申立てはできません。
国庫に帰属した遺産は売却により現金化され、相続財産管理人の報酬など関係者へ分配された後、国の歳入として扱われます。
特別縁故者として認められる人
特別縁故者となれば遺産を相続できますが、誰でもなれるわけではありません。
ここからは特別縁故者として認められる人について見ていきましょう。
被相続人と同一生計にあった人
被相続人と同居していた人や、被相続人により生計を維持されていた人は、特別縁故者になれます。
たとえば、被相続人の内縁の配偶者や、法律上の養子縁組はしていないが、事実上の養子・養親にあたる人などです。
実の子ではないが、甥や姪を自身の子のように育ててきた場合などは、特別縁故者になる可能性があります。
過去の裁判では、亡くなった子の配偶者が特別縁故者と認められた事例もあります。
被相続人の療養看護を行った人
被相続人が亡くなる前に、その被相続人の病気療養や介護に貢献した人は、特別縁故者になれます。
被相続人が自宅で過ごした場合に対象となるケースは、被相続人と一緒に生活する、あるいは頻繁に通って療養介護を行った場合です。
被相続人が入院していた場合や介護施設で生活していた場合、施設に定期的に通い、被相続人の世話をすると特別縁故者になる可能性があります。
療養看護を行った人は親族である必要はありませんが、看護師や介護士など業務として看護を行った人は、原則として特別縁故者にはなりません。
その他被相続人と特別の縁故があった人
被相続人から「自分が死んだら土地を譲る」といった約束を遺言書でしていた場合は、遺言書にしたがって財産を譲り受けられます。
遺言書がない場合でも、上記のような約束があったとが明らかになれば、特別縁故者となるケースがあります。
さらに、被相続人と特別に密接な関係にあった人は、特別縁故者になるかもしれません。
友人や知人、生前に被相続人から金銭援助を受けていた人などは、特別縁故者として認められる可能性があります。
法人も特別縁故者になれる
相続が発生した場合に法定相続人は個人に限られ、法人は対象となりません。
一方で、特別縁故者となるのは個人に限らず、法人なども含まれます。
法人の中で、地方公共団体や学校法人、宗教法人、公益法人、社会福祉法人などは特別縁故者と認められるケースがあります。
ただ、被相続人が経営や設立に深く関わっていなければなりません。
特別縁故者の申し立ての流れ

ここからは、どのような手続きをどのような流れで行うのか、解説していきます。
相続財産管理人を選任する
亡くなった人がいて相続が発生した場合のうち、相続人がいない場合、あるいは相続人がいるかどうかわからない場合があります。
このような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行います。
相続財産管理人の選任の申立ては、家庭裁判所に対して相続人の不存在を申告する手続きです。
特別縁故者のほか、被相続人にお金を貸していたが返してもらう前に亡くなった場合に、債権者が申し立てるケースもあります。
相続人を捜索する
相続人がいないと思っていても、実際に法定相続人がいないとは限りません。
中には、生き別れの兄弟や、隠し子がいる可能性もあります。
本当に相続人となる人がいないのか、相続人の捜索が行われます。
相続人の調査は、官報公告により行われます。
官報広告の内容は、被相続人に遺産相続が発生しているため、相続人は申し出るように通告する旨です。
もし官報公告で見つかった法定相続人は、すべての遺産についての相続権を有するため、特別縁故者を選任する手続きは必要なくなります。
債務の支払い・受遺者への遺贈を行う
被相続人が債務を抱えたまま亡くなった場合、相続財産管理人となった人は遺産から債務を支払います。
また、被相続人が遺言書を作成しており、特定の人に対する遺贈が発生している場合も同様です。
相続人の不存在が確定する
相続人を捜索するための官報公告は、6カ月間の期間にわたって行われます。
一方、名乗り出る人がいないまま公告期間の6カ月間が経過すると、相続人の不存在が確定します。
特別縁故者への遺産分与の申立てを行う
相続人の不存在が確定すると、遺産に対して相続権を有する人はいなくなります。
この場合、特別縁故者となる要件を満たす人がいれば、申立てにより遺産を分与してもらえるかもしれません。
特別縁故者となった人は、相続人の不存在が確定してから3カ月以内に、特別縁故者への遺産分与の申立てができます。
3カ月の期限を超えてしまうと、どのような状況にあった人でも特別縁故者としての遺産の分与を受けられません。
行方がわからない相続人がいる場合は申し立てできない
本来、法定相続人になる人と連絡がつかず、生死不明になっているケースもあるでしょう。
戸籍を調査した結果、兄弟など法定相続人になる人が見つかったが、生死や行方がわからないケースもあるかもしれません。
行方がわからない相続人がいる場合、相続人の不存在が確定していないとみなされるため、特別縁故者への遺産分与は認められません。
この場合、失踪宣告の手続きをすると行方不明の相続人は法律上死亡したとみなされます。
特別縁故者の申し立ての必要書類
被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に以下の書類を提出し、相続財産管理人選任の申立てをします。
- 申立書(裁判所HPから取得)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(役場で取得)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(役場で取得)
- 財産目録(預金通帳や不動産登記簿など)
- 被相続人と申立人の関係を証明する資料(被相続人が生前に残したメモなど)
相続人捜索の公告期間満了後、3カ月以内に以下の書類を家庭裁判所に提出して遺産分与を申し立てます。
- 申立書(裁判所HPから取得)
- 申立人の住民票(役場で取得)
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本(役場で取得)
- 財産目録(預金通帳や不動産登記簿など)
特別縁故者の申し立ての費用
相続財産管理人の選任や遺産分与の申立てをするときは、主に以下の費用が発生します。
- 予納金:10万円~100万円ほど
- 官報公告料:4,000円ほど
- 戸籍の取得費用:数千円ほど
- その他の諸費用(収入印紙や連絡用の郵便切手代など):数千円ほど
予納金は、遺産の総額が相続財産管理人の報酬等より不足する可能性がある場合に必要です。
遺産が少ないときは申立人の負担となるため、あらかじめ予納金を10万〜100万円ほど納付しなければなりません。
官報公告料は相続人を捜索するための費用であり、家庭裁判所の指示があってから納付します。
特別縁故者の申し立てを弁護士に依頼する費用
弁護士に依頼すると、家庭裁判所への申立ての手続きなどをすべて代行してもらえます。
弁護士報酬としては、主に以下の費用が発生します。
- 相談料:1時間5,000円ほど
- 着手金:40万円ほど(相続財産管理人の選任の申立に20万円、特別縁故者の遺産分与の申立に20万円)
- 報酬金:分与財産価額の15%ほど
報酬は事前の着手金と遺産分与後の成功報酬金にわかれます。
着手金は固定額、成功報酬は分与された財産に15%前後を乗じた額になるケースが多いです。
特別縁故者が相続するときの税金に関する注意点
特別縁故者になった人が、被相続人の遺産を受け取ると相続税がかかります。
特別縁故者は一般的な相続と異なる点があり、以下の注意点を押さえましょう。
- 基礎控除は3,000万円になる
- 相続税の2割加算が適用される
- 適用されない特例が数多くある
- 相続税以外に不動産取得税がかかる
- 審判確定日の翌日から10カ月以内に相続税を申告する
特別縁故者が注意する必要がある税金について、解説していきます。
基礎控除は3,000万円になる
相続税の計算を行う際は、すべての相続財産の評価額の合計から基礎控除額を差し引いた後の金額が、課税対象となります。
- 相続税の課税対象=すべての相続財産の合計額-基礎控除額
したがって、基礎控除額が相続財産の評価額を上回る場合には、課税対象となる金額は発生しません。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
ただし、特別縁故者が遺産を引き継ぐ場合は、法定相続人はおらず、また特別縁故者は法定相続人ではありません。
特別縁故者が遺産を引き継ぐ場合は基礎控除額は必ず3,000万円になり、相続財産の合計額が3,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の2割加算が適用される
被相続人の一親等の血族や配偶者以外の人が遺産を受け取り相続税が発生した場合、その税額は2割加算されます。
その結果、本来の税額の1.2倍の相続税額となり、特別縁故者の負担はより大きくなります。
適用されない特例が数多くある
相続税の計算を行う際には、相続人の負担が少しでも小さくなるよう、さまざまな特例があります。
ただし、特例の多くは法定相続人が相続した場合を想定して作られており、特別縁故者には適用されません。
特別縁故者が遺産を引き継いでも適用されない相続税の特例は以下のとおりです。
- 配偶者の税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 小規模宅地等の特例
- 相次相続控除
相続税以外に不動産取得税がかかる
法定相続人が不動産を相続した場合、不動産取得税は発生しません。
しかし、特別縁故者として遺産を引き継いだ場合、相続税以外に不動産取得税がかかります。
審判確定日の翌日から10カ月以内に相続税を申告する
特別縁故者が遺産を承継する場合、審判確定によって財産分与を知った日の翌日から10カ月以内に相続税を申告しなければなりません。
審判の確定日とは、申立人が家庭裁判所から審判書を受領した日から2週間が経過した日です。
相続税の申告先は、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する税務署です。
相続税の申告を忘れてしまった場合、通常の相続税に加え、延滞税が加算されます。
意図的な脱税行為など、悪質なケースとみなされると加算税が課せられる場合もあるため注意しましょう。
まとめ
被相続人と生前に特別な関係にあった特別縁故者は、法定相続人がいない場合に遺産を承継できる可能性があります。
特別縁故者として認められるのは、被相続人と生計を同一にしていた人や被相続人の療養看護をしていた人などです。
特別縁故者に該当する可能性があり、遺産の承継を望む人は、まず弁護士など相続の専門家に相談しましょう。
特別縁故者が遺産を承継するためには、裁判所への申立てや税務署への申告など複雑な手続きが多く、時間や労力がかかります。
手続きの方法を間違えてしまうと進められなくなってしまう可能性もあるため、弁護士などの専門家に代行してもらうのがおすすめです。
弁護士事務所によっては初回無料相談を実施しているため、積極的に利用するとよいでしょう。