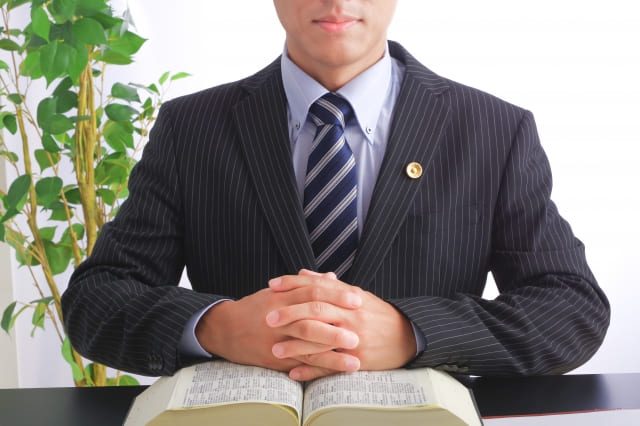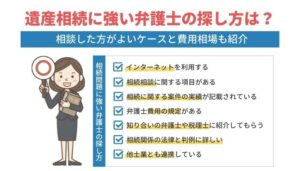この記事でわかること
- 相続の弁護士費用は誰が払う?相場はいくら?
- 弁護士費用は相続税から経費として控除されるか?
- 相続の弁護士費用を抑える方法とコツ
相続手続きを弁護士に依頼する際、気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。
また、弁護士費用が相続税から経費として控除できるか、気になる人も多いでしょう。
本記事では、相続手続きにかかる弁護士費用の相場や相続税との関係、さらに費用を抑えるための工夫について解説します。
相続手続きを検討している方が費用面での不安を少しでも解消し、安心して手続きを進められるよう、わかりやすい情報をお届けします。
目次
弁護士費用は誰が払う?相場はいくら?
弁護士費用は、依頼する事案の複雑さや、遺産の規模によって大きく変動します。
費用の内訳は主に、相談料、着手金、報酬金などがあり、実費や日当が別途かかります。
ここでは、相続手続きにかかる弁護士費用の相場や、誰がどのように支払うのかについて詳しく見ていきましょう。
相続の弁護士費用はいくら?相場は?
相続にかかる弁護士費用は、個々の事務所や事案によって異なりますが、主な費用項目には相談料、着手金、報酬金があります。
相談料は30分5,000円~1万円程度が一般的です。
初回無料相談を実施している事務所や、依頼によって初回相談料無料になる事務所もあります。
着手金の相場は20万円~50万円程度で、事務所ごとに異なるほか、遺産の総額によっても変動します。
また、着手金や報酬金は、手続きを通じて得られる経済的利益に応じて設定されるため、以下の表を参考にしてください。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
| 300万円~3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
日本弁護士連合会の報酬基準は、2004年4月1日に廃止されましたが、現在も多くの法律事務所がこの旧基準を参考にしています。
実際には、ケースによって大きく異なり、最終的には弁護士と相談の上で決定されます。
また、出張にかかる日当の相場は、半日で3万円~5万円、1日で5万円~10万円が相場です。
実費は郵便料金や行政手数料などで、一般的に数万円程度は発生するでしょう。
これらの費用は、遺産の総額や事案の内容によって大きく変わるため、事前に複数の弁護士に見積もりを依頼することをおすすめします。
相続の弁護士費用は誰が払う?
相続手続きにかかる弁護士費用は、原則として依頼者が負担します。
相続人が個別に弁護士へ依頼した場合、それぞれの相続人が費用を全額支払うことになります。
一方で、相続人全員で共同で弁護士に依頼する場合には、費用を分担するのが一般的です。
分担方法としては、相続人の人数で均等に分ける方法や、各自の相続割合に応じて分担する方法などがあります。
ただし、遺産分割協議が難航し、調停や裁判に発展した場合、申し立てた相続人が弁護士費用を負担することになります。
弁護士費用は相続税から経費として控除されない
相続に関する弁護士費用は、相続税の計算において経費として控除することはできません。
これは多くの人が誤解しやすい点です。
相続税法では、債務控除の対象は被相続人の債務や葬式費用などに限られており、相続手続きにかかる弁護士費用は含まれません。
また、相続税申告の際に発生する税理士費用も同様に、控除の対象外となっています。
弁護士費用が相続税の控除に含まれないことを踏まえ、費用対効果を検討した上で依頼を決めましょう。
相続の弁護士費用を安く抑える方法

相続手続きの弁護士費用は、いくつかの方法を組み合わせて活用することで、費用を抑えることが可能です。
ここでは、弁護士費用を安く抑える方法やコツを紹介します。
初回無料相談や法テラスの利用
多くの法律事務所では、初回無料相談を実施しています。
この機会を利用し、事案の概要や今後の見通し、おおよその費用を把握しましょう。
複数の事務所に相談することで、より適切な選択ができるでしょう。
経済的に費用負担が難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討しましょう。
法テラスでは、一定の収入条件を満たせば、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え、分割払いが利用可能です。
また、弁護士保険を活用するという選択肢もあります。
この保険は、保険会社と日本弁護士連合会が連携して提供しているサービスです。
すでに加入している場合は、保険を適用して弁護士費用をカバーできることもあるため、契約内容を確認してみましょう。
これらのサービスを活用し、費用負担を軽減して必要な法的支援を受けましょう。
自分でできることは自分でする
弁護士費用を抑えるには、自分でできる作業を積極的に行うことが効果的です。
たとえば、戸籍謄本や登記簿謄本の取得、相続財産の調査や整理などは自分でも進められる作業です。
また、相続人同士で話し合いが可能な部分は自分たちで進め、弁護士には専門的なアドバイスや交渉が必要な部分のみを依頼する方法もあります。
ただし、法的に複雑な問題や相続人同士で対立が生じている場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
自分でできる範囲を見極め、適切なタイミングで専門家の助言を得ることで、費用対効果の高い相続手続きが実現できるでしょう。
弁護士費用の比較検討や他の相続人との費用分担
弁護士費用を抑えるには、複数の法律事務所から見積もりを取り、比較検討することがおすすめです。
比較検討する際は、費用だけでなく、サービスの質とのバランスも考慮し、料金体系が明確であるかどうかも確認しておくと安心です。
その際、分割払いの可否を尋ねておくと、支払い計画を立てやすくなるでしょう。
相続人が共同で弁護士を依頼する場合、費用を分担することで個人の負担を減らせます。
ただし、相続人間で利害が対立する場合は別々の弁護士に依頼する必要があります。
また、遺産から弁護士費用を支払うことも可能ですが、相続人全員の同意を得ていない場合、トラブルになる可能性があるため注意しましょう。
まとめ
相続を弁護士に依頼する際は、まず初回の相談を通してしっかりとコミュニケーションが取れることが重要です。
費用が曖昧だと予期しない追加費用が発生し、トラブルにつながることもあります。
そのため、費用が明確で丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
弁護士との良好な関係が、スムーズな手続き進行を助けるため、初回相談時にしっかりと意見交換を行うことが大切です。
信頼できる弁護士を選び、安心して手続きを進めましょう。