この記事でわかること
- 相続廃除の定義と相続人が廃除される理由
- 相続廃除と遺留分や代襲相続の関係性
- 相続廃除の要件と家庭裁判所での立証方法
- 生前廃除と遺言廃除の手続きの違いと流れ
- 相続廃除が認められる事例と認められない事例
相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立て、相続する予定の人を相続から除外する制度です。
本記事では、相続廃除の定義や要件、具体的な事例を詳しく解説します。
遺留分や代襲相続との関係、相続欠格との違いにも触れ、生前廃除と遺言廃除それぞれの手続きの流れや必要書類についても説明します。
相続廃除が認められるケースや取り消しができるかどうかなど、相続廃除について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
目次
相続廃除とは
相続廃除は、被相続人が特定の相続人に対して相続権を剥奪する制度です。
その理由は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行があった場合に限られます。
手続きは家庭裁判所への申立てから始まり、具体的な証拠が必要です。
相続廃除が認められると、その相続人は遺留分も含めて一切の相続権を失います。
ここでは、相続廃除の定義や廃除される理由などについて、詳しく見ていきましょう。
相続廃除の定義と相続人が廃除される理由
相続廃除とは、民法第892条に基づき、被相続人が特定の相続人を相続から除外するために家庭裁判所へ申立てを行う制度です。
引用:
民法第892条第1項
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
被相続人が推定相続人(相続する予定の人)に特定の理由で相続させたくない場合、家庭裁判所にその旨を申し立てることができます。
相続廃除の主な理由は、以下が該当します。
- 被相続人に対する虐待:長年の身体的暴力や日常的な暴言など
- 被相続人への重大な侮辱:名誉毀損、秘密の暴露、度重なる不貞行為など
- その他の著しい非行:被相続人に借金の返済を強要、財産を無断で処分、重大な犯罪による有罪判決など
廃除が認められるには、家庭裁判所が正当と判断する理由がなければなりません。
そのため、申立ての際は十分な証拠を準備することが重要です。
相続廃除と遺留分や代襲相続の関係
相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する相続人、具体的には配偶者、子、親などに限定されます。
一方で、遺留分を持たない兄弟姉妹は、相続廃除の対象外です。
その理由として、兄弟姉妹については相続廃除の手続きを経なくとも、遺言書にその旨を記載することで相続人から除外することができるためです。
相続廃除が認められると、対象となった相続人は遺留分を含むすべての相続権を失います。
しかし、廃除された相続人に子や孫がいる場合は代襲相続が適用され、その子や孫が相続人となります。
たとえば、長男が廃除された場合でも、長男の子である孫が代わりに相続人となります。
このため、相続廃除によって廃除された相続人の家族全員を相続から完全に排除することはできません。
相続廃除と相続欠格の違い
相続廃除と相続欠格は、ともに相続権を失わせる制度ですが、これらには大きな違いがあります。
相続人の欠格事由は、民法891条に規定されています。
引用:
民法第891条
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除は、被相続人の意思に基づき家庭裁判所の審判で決定されますが、相続欠格は法律で定められた欠格事由に該当すれば、自動的に相続権が失われます。
以下に、相続廃除と相続欠格の違いを表にしていますので、参考にしてください。
相続廃除と相続欠格の違い
| 相続廃除(民法892条) | 相続欠格(民法891条) | |
|---|---|---|
| 概要 | 被相続人の意思により相続人の相続権を剥奪する制度 | 法律の欠格事由により自動的に相続権を失わせる制度 |
| 対象者 | 遺留分を有する推定相続人 | すべての相続人 |
| 発生要件 | ・被相続人に対する虐待 ・被相続人に対する重大な侮辱 ・推定相続人の著しい非行 |
民法891条の欠格事由に該当する殺人、詐欺強迫による遺言妨害、遺言書の偽造や隠匿など |
| 手続き | 被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる | 自動的に権利を失う |
| 被相続人の意思 | 必要 | 不要 |
| 遺留分 | 遺留分を請求できない | 遺留分がない |
| 取り消し | 可能 | 不可 |
| 効力発生時期 | 家庭裁判所の審判確定時 | 相続開始時 |
| 代襲相続 | 可能 | 可能 |
| 戸籍の記載 | あり | なし |
相続廃除の要件
相続廃除は、特定の相続人の相続権を剥奪する重大な法的手続きです。
民法で定められた厳格な要件を満たす必要があり、家庭裁判所の審判で認められなければなりません。
単なる不仲や意見の相違や音信不通などでは認められず、家庭裁判所は慎重かつ公平な判断を行います。
相続廃除の認容率は低く、立証のハードルは高いとされています。
ここでは、申立ての要件や立証方法などを解説します。
相続廃除申立ての要件
相続廃除の申立ては、民法第892条に基づき、以下の3つの要件のいずれかを満たす必要があります。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- 推定相続人の著しい非行
これらの要件は、一時的な行為ではなく、継続的または重大な影響を及ぼすものである必要があります。
暴力や暴言や不貞行為があっても、軽度なものや一時的な場合は、廃除は認められにくいのが実情です。
たとえば、以下のような場合が該当します。
- 被相続人に対して日常的に暴力を振るい、身体的な傷害を負わせた
- 被相続人に対して公然と重大な侮辱を行い、人格を否定し、精神的苦痛を与えた
- 被相続人の財産を無断で処分し、返還を求めても応じなかった
- 多額の借金を作り、被相続人に返済を強要した
- 被相続人が病気の際に無視し、必要な介護を怠った
- 長期間にわたり不貞行為を繰り返し、家庭を顧みなかった配偶者
- 罪を犯し、被相続人に重大な影響を与え、財産的損害や精神的苦痛を与えた
- 被相続人に対し、繰り返し脅迫や威圧的な行動で精神的な恐怖を与えた
これらに該当する場合でも、事実を客観的に証明できない場合は認められない可能性が高いため、立証できるかどうかが鍵となるでしょう。
家庭裁判所での立証方法
相続廃除の申立ては、具体的で客観的な証拠を家庭裁判所に提出することで、認められる可能性が高まります。
主な立証方法には、以下のものが挙げられます。
- 証人の証言:虐待や侮辱行為を目撃した第三者の証言
- 医療記録:虐待による傷害の診断書や治療記録
- 警察への通報記録:暴力事件などの通報履歴
- 音声や映像の記録:虐待や侮辱の様子を記録したもの
- 金銭的記録:財産の不正使用を示す銀行取引履歴など
申立人は、これらの証拠を用いて廃除の必要性を説明し、家庭裁判所の判断を仰ぎます。
家庭裁判所では、提出された証拠を総合的に評価し、相続廃除の可否を決定します。
立証が不十分な場合は認められないため、弁護士に相談の上、入念な準備が必要になるでしょう。
【生前廃除】相続廃除の手続き
生前廃除は、被相続人が生前に行う相続廃除の手続きです。
被相続人への虐待や重大な侮辱、推定相続人の著しい非行がある場合に申立てが可能です。
生前廃除は、遺言廃除に比べて認められやすいとされますが、手続きの段階で注意すべき点があります。
ここでは、生前廃除の具体的な流れと必要書類について解説します。
生前廃除の必要書類と手数料
生前廃除は、被相続人が家庭裁判所への申立てによって行います。
以下の書類や手数料が必要です。
- 申立人(被相続人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 推定相続人廃除の審判申立書:廃除の理由や対象者を具体的に記載
- 廃除の理由を裏付ける証拠資料:虐待や侮辱の事実を示す診断書、警察への届出書類、証人の陳述書など
- 申立手数料:推定相続人1名につき収入印紙800円分
- 郵便切手:裁判所からの書類郵送費
「推定相続人廃除の審判申立書」は、家庭裁判所で入手できます。
申立書には、廃除を求める理由を具体的かつ詳細に記載し、それを立証する証拠資料を添えて提出します。
家庭裁判所によっては追加の書類を求められる場合もあるため、事前に確認しましょう。
生前廃除の手続きの流れ
生前廃除の手続きは、以下の流れで進みます。
被相続人とは申立人本人を指し、対象者は廃除したい推定相続人を指します。
生前廃除の手続きの流れ
1)必要書類の準備:推定相続人廃除の審判申立書、被相続人と対象者の戸籍、立証のための証拠資料
2)推定相続人廃除の審判申立書の作成:対象者や廃除の理由を具体的に記載
3)家庭裁判所へ申立て:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
4)家庭裁判所の審判:家庭裁判所が申立ての内容を審理し、結果を被相続人に通知
5)家庭裁判所の審判確定:告知から2週間以内に即時抗告がなければ確定
6)審判書謄本と確定証明書の交付
7)市区町村への届出:10日以内に、被相続人の戸籍がある市区町村役場で推定相続人の廃除を届出(推定相続人廃除届、審判書謄本、審判確定証明書)
8)推定相続人の戸籍に廃除された旨が記載される
この過程で家庭裁判所は、必要に応じて関係者からの事情聴取や、証拠の提出を求めることがあります。
その際は、被相続人は廃除の理由を具体的に説明し、立証しなくてはなりません。
【遺言廃除】相続廃除の手続き
遺言廃除は、被相続人が自分の遺言を通じて特定の相続人の相続権を剥奪することができる制度です。
この制度は、遺言書を作成することで意思を示すものです。
被相続人の相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行うことで手続きできます。
ここでは、遺言廃除の必要書類と手続きの流れを説明します。
遺言廃除の必要書類と手数料
遺言書による遺言廃除の申立ては、被相続人の相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に行います。
申立てには、以下の書類や手数料が必要です。
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 推定相続人廃除の審判申立書:廃除の理由や対象者を具体的に記載
- 廃除の理由を裏付ける証拠資料:虐待や侮辱の事実を示す診断書、警察への届出書類、証人の陳述書など
- 遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺言執行者選任の審判書謄本:家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合
- 申立手数料:推定相続人1名につき収入印紙800円分
- 郵便切手:裁判所からの書類郵送費
なお、遺言書に記載された遺言執行者が申立てする場合は、遺言執行者選任の審判書謄本は不要です。
また、個々のケースにより追加書類を求められた場合は、裁判所の指示に従って手続きを進めてください。
遺言廃除の手続きの流れ
遺言廃除の手続きは、遺言書に記載された遺言執行人によって申し立てます。
以下は、遺言廃除に係る手続きの流れです。
遺言廃除の手続きの流れ
1)被相続人が生前に遺言書を作成し、以下について明記する
- 相続廃除する意思、廃除する推定相続人、その具体的な理由
- 遺言執行者の指定(指定がない場合は、死後に家庭裁判所が選任)
2)被相続人の相続開始後、遺言執行者が相続廃除の申立てのための必要書類を準備
3)家庭裁判所へ申立て:遺言執行者が被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
4)家庭裁判所の審判:家庭裁判所が申立ての内容を審理し、結果を遺言執行者に通知
5)家庭裁判所の審判確定:告知から2週間以内に即時抗告がなければ確定
6)審判書謄本と確定証明書の交付
7)市区町村への届出:10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場で廃除を届出(推定相続人廃除届、審判書謄本、審判確定証明書)
8)推定相続人の戸籍に廃除された旨が記載される
なお、遺言者は遺言書に遺言執行者を記載するのが望ましいです。
記載されていない場合は、相続人または利害関係者が家庭裁判所に遺言施行者選任の申立てをします。
遺言執行者が決まり次第、相続廃除の申立てをする、という流れとなります。
相続廃除や遺言書の作成は法的要件を満たす必要があり、専門知識が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。
相続廃除の事例
相続廃除は、判断基準が厳しく、単なる感情的対立や一時的な言動では認められません。
ここでは、認められた事例と認められなかった事例を紹介します。
実際の裁判例を通じて、適用範囲をより具体的に理解しましょう。
相続廃除が認められた事例
相続廃除が認められた事例として、以下の裁判例を紹介します。
事例相続廃除が認められた事例
- 長年にわたる虐待:末期がんで手術後、自宅療養中の妻に対し、不適切な環境での生活を強制し、人格否定する発言をした夫について、相続廃除が認められた。
(釧路家裁北見支部平成17年1月26日審判) - 重大な経済的損害:借金を繰り返し、2,000万以上を被相続人に返済させ、押しかけた債権者対応をさせるなど、約20年間にわたり経済的および精神的に苦痛を与えた長男に対し、相続廃除が認められた。
(神戸家裁伊丹支部平成20年10月17日審判) - 継続的な重大な侮辱:病気がちの被相続人を介護せず無視し、「80まで生きれば十分だ。早く死んでしまえ」などの罵倒を繰り返した息子について、相続廃除が認められた。
(東京高裁平成4年10月14日決定)
これらの事例に共通するのは、行為の継続性や重大性、被相続人への影響の大きさです。
一時的な感情の対立ではなく、長期間にわたる深刻な問題行動が相続廃除の認定につながっています。
相続廃除が認められなかった事例
相続廃除の申立ては、審理に進んでも認められない場合があります。
ここでは、相続廃除が認められなかった事例を紹介します。
事例相続廃除が認められなかった事例
- 継続的でない暴行:長男が60歳を超えた父に対して短期間に3回暴行を加え、1回は全治3週間を要する両側肋骨骨折等の傷害を負わせたケースで、長男の相続廃除は認められなかった。
(大阪高裁令和元年8月21日決定) - 被相続人の落ち度がある場合:父親(被相続人)が息子(推定相続人)から暴行を受けたケースで、父親に愛人がいたなどの事情があり、相続廃除は認められなかった。
(名古屋高裁金沢支部昭和61年11月4日決定) - 被相続人以外への非行:被相続人の同族会社で5億円を超える横領を行い、懲役5年の判決を受けた推定相続人に対して、相続廃除は認められなかった。
(東京高裁昭和59年10月18日決定)
一時的な行為や被相続人側にも問題がある場合、相続廃除が認められていません。
裁判所は相続人の権利を不当に奪わないよう、慎重に判断を行っているといえるでしょう。
相続廃除に関するよくある質問
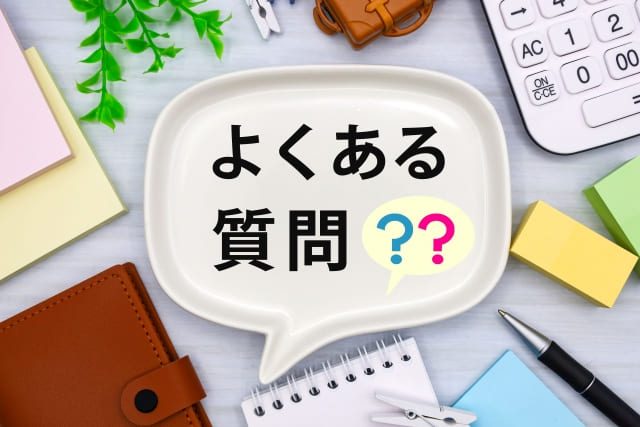
相続廃除に関して、多くの人が疑問を持っていることのひとつは、「一度決定した相続廃除は取り消しができるのか?」というものです。
また、「実際にどのくらいの確率で相続廃除が認められるか?」という質問も多く見られます。
ここでは、この2つの疑問について説明します。
相続廃除は取り消し可能か?
相続廃除は被相続人の意思を反映する制度であるため、気持ちが変わったときはいつでも取り消すことが可能です。
取り消しの手続きは、相続廃除の申立てと同様に家庭裁判所の審判で行います。
被相続人が生存中の場合は、本人が直接「相続人廃除の審判の取消し」を申し立てます。
遺言による取り消しの場合は、遺言書で廃除を取り消す旨を記載し、相続開始後に遺言執行者が申立てを行います。
取り消しの審判が確定すると、廃除されていた推定相続人は相続権を回復します。
この効果は過去にさかのぼり、相続発生時から相続権を有していたものとして扱われます。
相続廃除の取り消しは、被相続人の意思を反映し、家族関係の修復や状況の変化に対応できる柔軟な制度といえるでしょう。
相続廃除が認められる確率
裁判所の司法統計によると、相続廃除が認められるハードルは高く、廃除される確率は低いことがわかります。
2023年に家庭裁判所で受理された「推定相続人の廃除及びその取消し」308件のうち、認められたのは36件で、認容率は約20.2%でした。
ただし、この数字には廃除取消しも含まれるため、相続廃除のみの認容率はさらに低いと考えられるでしょう。
司法統計のデータは、家庭裁判所が相続廃除の申立てに対して慎重な判断を下していることを示しています。
申立書の表現や提出する立証資料が不十分だと、たとえ事実であっても認められない場合があります。
そのため、申立書や資料の内容を精査し、適切な証拠を用意することが重要です。
認容率を高めるには、弁護士などの専門家に相談し、万全の準備を整えた上で申立てを行うことが有効でしょう。
まとめ
相続廃除は法的に複雑な手続きであり、個別の状況によって適用されるかどうかが大きく異なります。
この手続きでは、十分な証拠資料の準備が必要であり、法的な知識も欠かせません。
証拠の収集や手続きの進め方には慎重さが求められるため、一人で進めるのは難しい場合があります。
そのため、相続廃除を検討している場合、まずは専門家に相談することをおすすめします。
専門家と連携することで、申立てにかかる時間や労力を軽減し、状況に応じた最適な対応策を見つけることができます。
専門的なアドバイスにより、相続廃除が認められる可能性や手続きの詳細についても具体的な指針を得られるでしょう。

























