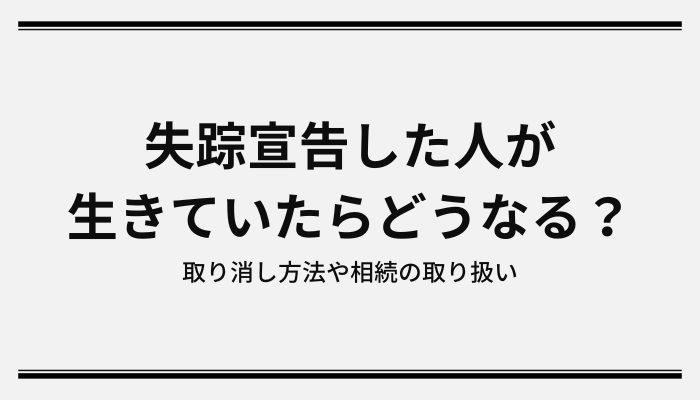この記事でわかること
- 失踪宣告後に生きていたらどうなるのか
- 失踪宣告後に生きていた事例とは
失踪宣告とは、行方不明となり生死がわからない人を家庭裁判所の手続きで死亡したとみなす制度です。
失踪宣告で死亡したとみなされた人が生きていたときは、家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを請求すると生存時の権利が復活します。
判例では、「行方不明のため両親の遺産を取得できなかった相続人が、失踪宣告を取り消し、他の相続人に権利侵害を訴えた」などがあります。
ここでは、失踪宣告を受けた人が生きていた場合に復活する権利や失踪宣告を取り消すための手続き方法などを確認していきましょう。
目次
失踪宣告した人が生きていたらどうなる?
失踪宣告した人が生きていた場合、相続や婚姻の状況が変わります。
- 失踪宣告した人の相続が取り消される
- 失踪宣告した人の財産の返還をする
- 婚姻の解消が取り消される
それぞれの状況について見ていきましょう。
失踪宣告した人の相続が取り消される
失踪宣告で死亡したとみなされると、相続が開始して被相続人の財産が相続人へ承継されます。
その後、被相続人の失踪宣告が取り消されると相続は開始しなかったと扱われるため、承継した財産は本人に返還しなければなりません。
相続人の中で行方不明となっている人がいる場合は、相続手続きを進めるために失踪宣告をするケースもあります。
相続人が生存しており、失踪宣告が取り消されたときは相続権も復活するため、相続手続きがやり直しになる可能性があります。
失踪宣告した人の財産の返還をする
失踪宣告の取り消しにより財産の所有権が復活するため、財産は本人に返還しなければなりません。
返還するタイミングは、家庭裁判所によって失踪宣告の取り消しが認められた後です。
返還する財産は、現に利益を受けている限度とされています。
現に利益を受けている限度とは、受け取った利益がそのまま残っている分だけでなく、形を変えて残っている分も含みます。
たとえば相続した預貯金をギャンブルで浪費した場合、残っている残額を返還します。
現預金を生活費として使った場合は、自分の財産の減少を免れているため、全額を返還しなければなりません。
婚姻の解消が取り消される
失踪宣告によって死亡したとみなされると、配偶者との婚姻関係が解消します。
失踪宣告が取り消されると身分関係が元通りになるため、婚姻関係も復活します。
失踪宣告の取り消し前に配偶者が再婚していた場合は、ケースによって異なるため注意しましょう。
配偶者と再婚相手が行方不明者の生存を知らなかったケースでは、再婚は有効に存続します。
配偶者と再婚相手のどちらかが行方不明者の生存を知っていたケースでは、再婚は無効となる可能性があります。
行方不明者と離縁したい場合は、裁判離婚の手続きをしなければなりません。
失踪宣告した人が生きていた場合の相続の取り扱い
失踪宣告をした人が生きていた場合、相続の取り扱いは生存を知っているかどうかで取り扱いが異なります。
それぞれの取り扱いについて見ていきましょう。
生存を知らずに行われた行為は取り消されない
相続人と相続財産の譲受人が行方不明者の生存を知らなかった場合、取引の安全が優先されるため、取引行為は取り消されません。
たとえば行方不明者Aの失踪宣告がされ、相続人の子どもBが土地を相続した後、第三者Cへ売却したとします。
失踪宣告が取り消されると、子どもBの承継した財産は行方不明者Aへ返還されます。
一方で、子どもBと第三者Cが行方不明者Aの生存を知らなかった場合、土地の売却は有効のままです。
子どもBは、土地以外の承継した財産は現に得ている利益を限度に行方不明者Aへ返還しなければなりません。
生存を知ったうえで行われた行為は取り消される
相続人と相続財産の譲受人のうち、どちらかが行方不明者の生存を知っていた場合は取引行為が取り消されます。
生存を知った上で取引が行われた場合、取引の当事者を保護する必要はなく、行方不明者の権利の復活が優先されるためです。
たとえば行方不明者Aの失踪宣告がされ、相続人の子どもBが土地を相続した後、生存を知りながら第三者Cへ売却したとします。
この場合、子どもBの相続した財産だけでなく、第三者Cの購入した土地もすべて行方不明者Aへ返還しなければなりません。
生存が確認できても失踪宣告の効力は消滅しない
失踪宣告が行われた場合、失踪者は法律上、死亡したとみなされます(民法第31条)。
失踪宣告の手続きは家庭裁判所で行われており、生存が確認できたとしても、失踪宣告の効力は消滅しません。
失踪宣告の効力を消滅させるためには、家庭裁判所に対して失踪宣告の取消を申し立てて、取消の審判を受ける必要があります。
失踪宣告の取消方法
失踪宣告取消の申立ては、本人または利害関係者が本人が現実に居住している地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
利害関係者とは、以下のような失踪宣告に対して法律上の利害関係がある人を指します。
- 失踪者の配偶者
- 相続人
- 財産管理人
- 受遺者(失踪者から遺言で財産の無償譲渡を受ける人)
失踪宣告取消の手続きの流れ
失踪宣告取消をする際は、まず家庭裁判所に申し立てます。
申立人が以下の申立書・添付書類を提出し、以下の申立て費用を支払います。
- 収入印紙代:800円
- 連絡用の郵便切手代:4,816円
申立てを受けた家庭裁判所は、書面照会や調査官の調査、審問などを行います。
審理が終了すると、失踪宣告取消の決定または申立て却下の審判が行われます。
失踪宣告取消審判の場合、通常は申立てが行われれば取消が可能です。
審判が確定すると、当該家庭裁判所から申立人に対して、審判書謄本が郵送で届きます。
審判書謄本が届いてから14日以内に異議申立て(即時抗告)が行われなければ、審判が確定します。
審判確定後、10日以内に審判所謄本を添付して、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に戸籍回復の届出を行ってください。
失踪宣告取消申立ての必要書類
失踪宣告取消し申立てにあたっては、取消申立書及び添付書類を裁判所に提出します。
失踪宣告取消申立書記載にあたっては、該当する記載を丸で囲む他、申立ての実情や申立てまでの経緯を可能な限り詳細に記載しましょう。
申立書の添付書類として、以下の書類が必要です。
- 1.失踪者本人が申立人の場合
・失踪者の戸籍謄本
・失踪者の戸籍の附票
・取消事由を証明する資料
・失踪者の写真3枚 - 2.利害関係人が申立人の場合
1.の書類に加えて、以下の書類が必要です。
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人と不在者の利害関係を証明する資料
失踪宣告後に生きていたことが判明する事例
失踪宣告後に以下のように、生きていた事実が判明する場合があります。
- 家庭裁判所から連絡が来るケース
- 警察から連絡が来るケース
それぞれのケースについて見ていきましょう。
家庭裁判所から連絡が来るケース
家庭裁判所から連絡がくるのは、行方不明者が生存しており、本人から家庭裁判所に失踪宣告の取消しを申し立てた場合などです。
行方不明者が生活保護などの行政手続きをする場合、失踪宣告によって死亡したとみなされたままでは手続きができません。
本人から失踪宣告を取り消すために家庭裁判所に申立てがされると、確認のために親族への連絡される可能性があります。
失踪宣告の取り消しが認められると財産の返還が必要になるケースがあるため、対応方法は弁護士に相談するとよいでしょう。
警察から連絡が来るケース
行方不明者の中には、事故や事件に巻き込まれて既に死亡しているケースがあります。
警察の捜査によって行方不明者の遺体や所持品が見つかると、親族に身元確認などの連絡を受ける可能性があるでしょう。
警察から連絡を受けた場合、指定の警察署や病院を訪問し、遺体の本人確認や事情聴取などに対応しなければなりません。
失踪宣告によって死亡とみなされた日と実際の死亡日が異なると判明した場合、失踪宣告の取消しにより戸籍上の死亡日を訂正できます。
まとめ
失踪宣告の取り消しが認められると、死亡したとみなされていた人の財産関係や身分関係が元通りに復活します。
遺産の相続や婚姻の解消もなかったと扱われるため、財産の返還を求められるなど、様々なトラブルが起きるかもしれません。
一方で、行方不明者の生存を知らなかった場合は、財産の返還などが不要になる可能性があります。
自宅や土地などの重要な財産に影響を与える可能性があるため、失踪宣告を申し立てるときは事前に弁護士へ相談しましょう。