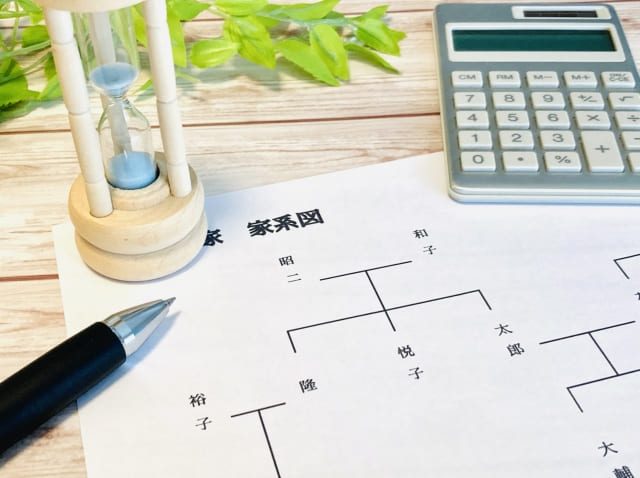この記事でわかること
- 10年以上前の生前贈与が相続に与える影響
- 過去の生前贈与が特別受益に該当するケース
- 特別受益の持ち戻しの計算例
家族や親族など身近な人が亡くなった場合、遺産の相続が発生します。
中には、相続税の節税を目的として、亡くなる前に生前贈与で遺産の前渡しを行うケースがあります。
生前贈与は相続争いの原因となるため、税金の取り扱いや特別受益の持ち戻し、遺留分などの問題を検討する必要があります。
10年以上前の生前贈与であっても、相続に一定の影響を与えます。
この記事では、10年以上前の生前贈与が相続に与える影響や特別受益に該当するケース、特別受益の持ち戻しの計算例を解説します。
目次
10年以上前の生前贈与が相続に与える影響
亡くなる10年以上前に生前贈与をしていた場合、相続発生時に一定の影響を与えます。
相続発生時に考えるべき内容は、次の3つです。
- 相続税・贈与税などの税金関係
- 特別受益
- 遺留分
遺産分割時の揉め事を避けるためにも、あらかじめ生前贈与の影響を把握しておく必要があるでしょう。
そもそも生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人(=財産を遺す人)が亡くなる前に、特定の人に対して無償で財産を分け与えることです。
「贈与」と名前はついていますが、生前に行う相続と捉えられるため、遺産分割時に問題になる恐れがあります。
相続は原則1回のみですが、生前贈与に回数制限はなく、生きている間に何度も行うことができます。
このため、配偶者や子どもに計画的に資金を譲り渡すことが可能です。
贈与税の控除制度を利用すれば、一括で財産を譲り受ける相続よりも節税できる可能性があります。
中には、10年以上前からコツコツと子どもに財産を分け与えている場合も考えられます。
10年以上前の生前贈与は相続税がかからない
生前贈与に相続税がかかるかどうかは、贈与から相続発生までの経過年数が判断基準になります。
原則として、被相続人の死亡した日からさかのぼって7年の間にした生前贈与が相続税の対象です。
10年以上前の生前贈与であれば、相続税は問題になりません。
ただし、最初の生前贈与が10年以上前であっても、亡くなる前まで生前贈与を繰り返してきた場合には一部に相続税が課税されます。
贈与税と相続税の関係
生前贈与においては、相続税と関連して贈与税が問題になります。
贈与税と相続税は、どちらも財産を譲り渡す際に発生する税金です。
特に相続においては、贈与税は相続税を補う立ち位置にあります。
先に説明したように、相続税には期間制限があるため、一部の生前贈与には適用されません。
早めに生前贈与をすれば相続税の課税を免れるため、贈与税でそれを補うこととしています。
生前贈与における贈与税の課税方法は、下記の2パターンから選べます。
| 課税制度 | 説明 | 具体的な課税方法 |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 年ごとに贈与税を課税する |
年間110万円まで基礎控除 残額に贈与税率をかけた金額が課税される |
| 相続時精算課税 | 相続時にまとめて贈与税を課税する |
年間110万円まで基礎控除+生前贈与の累計額に最大2,500万円の特別控除 2500万円を超えた額について税率20%が課税される |
2023年税制改正による生前贈与への影響
2023年の税制改正により、生前贈与における相続税・贈与税の取り扱いが変更されています。
従来は、被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内の生前贈与が相続税の課税対象でした。
2024年1月以降、死亡日から7年以内に相続税の課税対象が広がっています。
ただし、新たな税制は段階的に適用されます。
移行期間中においては、延長された4年間の生前贈与は総額100万円まで加算されません。
10年以上前の生前贈与は特別受益に当たる可能性がある
被相続人が亡くなると、相続人の間で遺産分割が行われます。
このとき、問題となりがちなのが生前贈与です。
一部の相続人のみが過去に生前贈与を受けていた場合、相続時にも他の相続人と同じだけの財産がもらえるとなると、不公平になる可能性があります。
生前贈与は相続時の財産額を減らす効果もあるため、そもそも分割できる遺産自体が減ってしまうことにも繋がるでしょう。
相続人間の不公平を防ぐため、生前贈与の一部は特別受益として遺産分割時の考慮対象となります。
特別受益には時効の概念がなく、10年以上前の生前贈与であっても対象となる可能性があります。
特別受益とは
相続遺産の前渡しと見なされるため、相続人間の公平を図るために特別な規定が設けられています。
特別受益もそのひとつで、特別受益とは、一部の法定相続人のみが被相続人から特別に受け取った利益のことです。
特別受益には生前贈与の他、遺贈や死因贈与が当てはまります。
特別受益を受けた者のことを「特別受益者」と呼びます。
なお、生前贈与で問題になるのは、法定相続人が特別受益者に当たる場合のみです。
特別受益は持ち戻しの対象となる
特別受益は、持ち戻しの対象となります。
「持ち戻し」とは、特別受益の金額を遺産の総額に加算することです。
遺産分割を行う際、公平な相続を行うために、一度特別受益をなかった(生前贈与は行われなかった)こととして扱います。
相続発生時に残された遺産額に特別受益を加算し、その合計額を事実上の遺産総額とみなしてそれぞれの相続分を算出します。
特別受益者は、算出した相続分から特別受益を差し引いた金額を相続します。
特別受益の持ち戻しにより、他の相続人の取り分が増えることになり、相続人間の不公平の解消に繋がります。
基本的には10年以上前の特別受益も持ち戻しの対象となりますが、それよりも昔の生前贈与は特定が難しい場合が多いでしょう。
10年以上前の生前贈与は遺留分に影響しない
被相続人が財産のほとんどを生前贈与したようなケースでは、相続時の遺産が大幅に減ってしまうことが考えられます。
法定相続人には最低限受け取ることのできる遺産の取り分が保証されており、これを遺留分と呼びます。
残された財産が相続人の遺留分に満たなければ、生前贈与を受け取った人に対して不足分の支払いを求める(遺留分侵害額請求)ことが可能です。
ただし、10年以上前の生前贈与であれば、原則として遺留分の算定には含まれません。
古すぎる生前贈与を考慮するとなると、遺留分の争いが複雑化してしまう恐れがあるためです。
遺留分制度の概要
遺留分侵害額請求の権利を持っているのは一部の法定相続人に限られます。
遺留分が保障されている法定相続人は次の3パターンです。
- 配偶者
- 子ども(子どもがすでに死亡している場合には孫などの直系卑属)
- 親(親がすでに死亡している場合には祖父母などの直系尊属)
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分がないことに注意しましょう。
法定相続人が請求できる遺留分は家族構成によって異なりますが、一般的には法定相続分の2分の1または3分の1です。
たとえば、配偶者のみが法定相続人となっている場合、遺産総額の2分の1が遺留分として保障されています。
遺留分を請求できる期間
2017年の民法改正により、生前贈与に対して遺留分の侵害を請求できる期間が規定されました。
2019年7月1日以降に発生した相続については、改正民法が適用されています。
旧民法と改正民法のルールは次の通りです。
| 2019年6月末日までの相続(旧民法) | 2019年7月1日以降の相続(改正民法) | |
|---|---|---|
| 原則 | 相続開始前1年以内の生前贈与 | 相続開始前1年以内の生前贈与 |
| 例外 | 相続人に対する生前贈与が特別受益に該当する場合は期間無制限 | 相続人に対する生前贈与が特別受益に該当する場合は10年以内 |
なお、改正民法においても、当事者(被相続人と受贈者)双方が遺留分を侵害することを知って生前贈与を行った場合には、期間の制限なく遺留分の侵害を請求できます。
10年以上前の生前贈与であっても、それが遺留分権者に損害を与える目的で行われたことが証明されれば、遺留分の算定に含まれることに注意しましょう。
過去の生前贈与が特別受益に該当するケース
10年以上前の生前贈与であっても、それが特別受益に該当する場合には持ち戻し計算の対象になります。
つまり、遺産分割の際には、生前贈与が特別受益に該当するかを判断する必要があります。
特別受益に該当する可能性のある贈与は「遺贈」「婚姻・養子縁組としての贈与」「生計の資本としての贈与」の3つです。
このうち、遺贈は相続発生後に遺言によって行われる贈与となるため、生前贈与で問題となるのは残りの2つに限られます。
婚姻・養子縁組としての贈与
婚姻・養子縁組に関連して被相続人が贈与を行った場合、特別受益と見なされる可能性があります。
婚姻関連費用としては、結婚の支度金や挙式費用、結納金などが挙げられます。
養子縁組関連費用としては、子どもを養子縁組に出す際に実親が用意する持参金があります。
ただし、これらが特別受益となるかどうかは、専門的な判断が必要となります。
一般的に、扶養の範囲内と呼べる金額であれば、特別受益に当たらないとされています。
一方で、明らかに常識的な範囲を超えた高額な贈与であるケースでは、特別受益として持ち戻しの対象となる可能性があります。
生計の資本としての贈与
生計の資本として生前贈与を受けた場合、特別受益とされる可能性があります。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 学費や仕送り
- マイホーム資金
- 事業の開業資金
このうち、学費や仕送りは扶養義務の範囲内と見なされることが多いです。
ただし、私立大学医学部に入学したケースや月額10万円以上の仕送りをしているケースでは、他の相続人との公平性の観点から特別受益とされる可能性が高いでしょう。
マイホーム資金や事業の開業資金を援助する目的での贈与については、基本的に特別受益となります。
ただし、相続人全員に同様の援助をしていれば、例外的に特別受益でないと判断される可能性があります。
10年以上前の生前贈与に特別受益の持ち戻しを適用する方法・計算例

10年以上前の生前贈与でも特別受益と見なされれば、原則として特別受益の持ち戻しが適用されます。
例外的に、被相続人が遺言などで特別受益の持ち戻し免除の意思表示をした場合には、その意思に従います。
特別受益の持ち戻しは、相続人の誰かが主張することで適用可能です。
他の相続人が生前贈与に納得していれば、特別受益の持ち戻しをせずに遺産分割に進むこともあります。
では、特別受益の持ち戻しをする場合には、どのように計算されるのでしょうか。
例として、親の遺産2,000万円を長男Aと長女Bが相続する場合を検討しましょう。
このとき、すでに長男Aがマイホーム資金1000万円を生前贈与として受け取っていたとします。
通常の計算方法では、遺産総額2,000万円を子ども2人が半分ずつ受け取ることになります。
長男Aは生前贈与を含めて2,000万円、長女Bは1,000万円を相続することになり、不公平が生じますが、長女Bが生前贈与に納得していれば、このままの遺産分割で完了します。
一方、特別受益の持ち戻しを適用すると、生前贈与を加算した3,000万円が遺産総額として扱われます。
子ども2人の相続分はともに1,500万円ずつとなるため、遺産分割時に受け取る金額は長男Aが500万円、長女Bが1,500万円となります。
まとめ
10年以上前の生前贈与であっても、公平な相続実現のためには慎重な取り扱いが必要です。
相続税の課税範囲は7年のため、10年以上前の生前贈与は相続の範囲外となり、贈与税でカバーされることになります。
しかし、生前贈与が特別受益に該当する場合には、遺産分割時に持ち戻し計算が適用されます。
もっとも、特別受益に該当するかどうかはケースバイケースで判断されます。
相続人間のトラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら遺産分割を進めるようにしましょう。