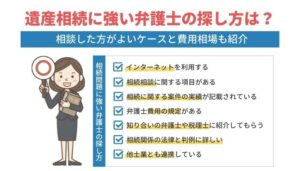この記事でわかること
- 生前贈与の基本的な流れと贈与契約書の作成手順
- 年間110万円の非課税枠を有効活用する際の注意点
- 不動産を生前贈与する場合のリスクや節税対策
- 名義預金が生前贈与と認められない理由と回避法
- 贈与税の確定申告や相続時の生前贈与加算のしくみ
生前贈与は、資産を事前に分配し、相続税を節約するための対策として使われていますが、様々な注意しなくてはならないポイントがあります。
そのポイントを踏まえて正しく行わなければ、思わぬ税負担やトラブルを招く可能性がある方法だと言えます。
本記事では、生前贈与に関する基本的な流れや契約書作成、110万円以内の贈与時の注意点、名義預金の問題点などを詳しく解説します。
また、不動産贈与特有の留意事項や確定申告の方法、相続時の加算ルールなどもわかりやすく説明します。
適切な知識を身につけ、生前贈与や節税対策の参考としてください。
目次
生前贈与の正しいやり方
生前贈与は、将来の相続を見据えた計画的な資産移転です。
正しい方法を理解することで、贈与後のトラブル回避やスムーズな財産移転が可能になるでしょう。
ここでは、基本的な流れと贈与契約書の作り方を詳しく解説します。
生前贈与の基本的な流れ
生前贈与を行う際の基本的な流れを説明します。
1)贈与者と受贈者の合意:贈与者・受贈者で贈与財産を特定し、現金、不動産、株式など種類と評価額を確認します。
2)贈与契約書の作成と署名押印:契約書を用意し、当事者情報や財産内容、日付を記載し、署名・押印を行うことで法的効力を明確にします。
3)登記手続き(不動産の場合):不動産贈与の場合、所有権移転登記が必須です。
4)贈与税申告(必要な場合):年間110万円を超える贈与や相続時精算課税制度利用時は、贈与税確定申告が必要です。
この流れを押さえることで、後の紛争や税務上の問題を未然に防げます。
適切に進めることで、スムーズに生前贈与を行うことができるでしょう。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書は、生前贈与を正式な取引とする基盤です。
記載必須事項は、以下の通りです。
- 当事者情報:贈与者と受贈者の氏名、住所
- 贈与財産の明細:現金の場合は金額、不動産の場合は登記情報、株式の場合は銘柄・数量
- 契約日:契約書を作成した日付
- 署名押印:贈与者と受贈者の署名押印
- 負担付き贈与の場合の負担内容(該当する場合のみ):債務や条件がある場合は具体的な内容を明記
贈与の目的、実行時期、費用負担、解除条件などを加えると明確性が増し、後のトラブル防止に役立ちます。
特に不動産や高額な財産の贈与では、詳細な内容を記載し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
法的効力を高めることができるでしょう。
生前贈与の注意点

生前贈与は相続税対策として効果的ですが、110万円非課税枠の使い方や相続加算ルール、名義預金問題など、押さえておかなければならないポイントがあります。
ここでは、生前贈与を行う際の重要な注意点を解説し、正しい方法で資産を移転する方法を紹介します。
生前贈与110万円以内の注意点
年間110万円の基礎控除枠による贈与は、シンプルで多くの人が利用している節税方法ですが、以下の点に注意しましょう。
- 受贈者1人あたり110万円:贈与された人1人あたりの非課税枠は年間110万円です。
複数の人からの贈与で110万円を超える場合は、超過分に課税されます。 - 定期贈与リスク:毎年同額・同時期の贈与で「定期贈与」とみなされると、累計した額に多額の贈与税が課せられるリスクがあります。
金額や時期を一定にしないようにしましょう。 - 生前贈与加算:相続開始前3年(または7年)以内の贈与は、非課税枠内の贈与でも相続財産に加算されます。
相続税増加の恐れがあるため、注意しましょう。 - 現金手渡しは避ける:銀行振込で履歴を残し、贈与契約書も整備して贈与の事実を明確にしましょう。
これらの点に留意することで、110万円非課税枠を有効活用できます。
ただし、生前贈与加算は税制改正があったため、計算が複雑になっています。
プランに不安がある場合は、状況に応じて専門家のアドバイスを受け、適切な贈与計画を立てることをおすすめします。
名義預金は生前贈与とみなされない
名義預金とは、実際の所有者と口座名義人が異なる預金のことです。
たとえば、親が子どもの名義で口座を開設し、資金を管理するケースがこれに当たります。
しかし、税務上、名義預金は生前贈与とはみなされません。
つまり、口座名義を変更しただけでは、贈与税の非課税枠を利用することはできません。
実際に受贈者の口座に資金を移動し、受贈者が口座を管理し、自由に使える状態にすることが必要です。
名義預金は税務調査の対象となる可能性が高く、名義預金と判断されると、その全額が相続財産として扱われることになります。
正式な贈与手続きを踏み、贈与契約書を作成することで、適切な生前贈与を行いましょう。
贈与の確定申告
贈与税の確定申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ただし、暦年贈与で110万円以下の贈与を受けた場合は、確定申告の必要はありません。
一方、暦年贈与で110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税制度を選択した場合は確定申告を行わなければなりません。
申告漏れがあると追徴課税やペナルティの対象となる可能性があるため、注意してください。
確定申告の際には、贈与契約書や振込み記録、評価証明などの証拠書類を準備し、正確に申告することが重要です。
また、生活費や教育費として贈与された金銭には非課税となる特例もあるため、これらの条件についても確認しておくとよいでしょう。
不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
不動産贈与に関する注意事項
不動産の生前贈与には、特有の注意点がいくつかあります。
まず、不動産は価格が高いため、贈与税が高額になる場合があります。
また、贈与税は相続税よりも税率が高いため、不動産の生前贈与には計画的な対策が求められます。
特に、不動産のみを贈与する場合、受贈者が贈与税など納税資金の確保が難しくなる可能性があるため、注意しましょう。
また、相続開始前の3年から7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算され、相続税の対象になる可能性があります。
このため、不動産贈与を計画する際には、贈与のタイミングを十分に配慮しなければなりません。
節税対策としては、相続時精算課税制度の活用や、配偶者への居住用不動産贈与における特例が選択肢として挙げられます。
これらの制度は、適用条件や手続きが複雑な場合もあるため、正確な理解が必要です。
最適な方法を選択するためには、専門家のアドバイスを受け、リスクを理解した上で計画的に進めることをおすすめします。
相続時の生前贈与の扱い
生前贈与は相続時に影響を与える可能性があり、特に注意しなくてはならないのは相続開始前3年から7年以内に行われた贈与です。
これらの贈与は、前述したように、相続財産に加算されて相続税の計算対象となる可能性があります。
ただし、暦年贈与の基礎控除額110万円以内の贈与については、相続開始前3年以内のものだけが加算対象となります。
一方、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与時期に関わらず全額が相続財産に加算されますが、既に支払った贈与税は相続税から控除されます。
相続税対策として生前贈与を行う場合は、これらの規定を踏まえた長期的な計画が必要です。
また、贈与の記録を適切に保管し、相続時に備えることも重要です。
まとめ
生前贈与を考える際には、様々な注意点を理解しておく必要があります。
事前に知識を持つことで、不必要なトラブルを避けることができるでしょう。
しかし、生前贈与はタイミングや計算が難しく、個々の事情や財産状況、家族構成によって、大きく異なってきます。
特に、複雑な状況や特別な事情がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
自身の状況に合った最適なアドバイスを受けられ、安心して生前贈与を進めることができるでしょう。