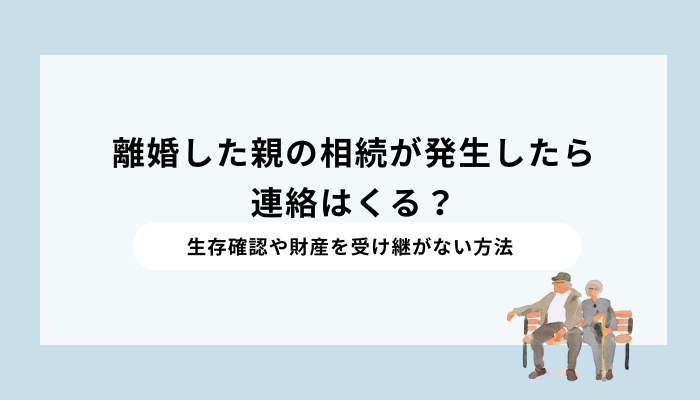この記事でわかること
- 離婚した親が亡くなったとき連絡が来る先/来ない場合の確認手順
- 相続放棄の熟慮期間と起算点(原則・伸長申立の考え方)
- 疎遠・後妻や異母兄弟がいるときの実務上の初動
- 弁護士ができること(相続人・財産調査/交渉代理/期間伸長申立 ほか)
目次
結論|離婚した親の“相続”はこう動く
- ■連絡は警察・親族(後妻側含む)・役所/病院・債権者・大家などから来る場合があります(事案により)。
- ■連絡が来ない場合は、戸籍等で生死・相続人の確認→財産の有無を概観→方針(承認/放棄等)を整理。
- ■相続放棄・限定承認の熟慮期間は原則3カ月。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」で、家庭裁判所への伸長申立が認められる例もあります(一般に)。
- ■疎遠・後妻/異母兄弟と連絡を取りたくない場合、弁護士が窓口を一本化し、相続人・財産調査や交渉/調停代理を担えます。
連絡が来ない場合・来る場合
連絡が来ない時の確認手順(先に対処)
- 親族・知人に確認(後妻側の親族も含む)。
- 戸籍で生死と相続人を確認:子(直系卑属)は戸籍(全部事項証明等)を請求できます。第三者は原則不可で、正当な利害関係等が求められます。
- 郵便物・通帳・保険証券等から財産の手掛かりを把握。
連絡が来る典型例
よくある連絡元(例)
- 警察:孤独死・事故・事件性の有無の調査後に連絡が来ることがあります。
- 親族・相続人:兄弟姉妹、再婚相手(後妻/夫)やその親族から。
- 役所・病院・葬儀社:保管品・費用支払・手続き連絡など。
- 債権者・賃貸管理会社:未納や明渡しに関連した連絡。
※どこから来るかは事案により異なります。自然死等では直ちに連絡が来ない場合もあります。
相続放棄・限定承認のポイント
熟慮期間と起算点
相続放棄・限定承認は原則3カ月の熟慮期間内に検討します。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」で、単に死亡を知った時点と一致しない場合があります。事情により家庭裁判所で伸長申立が認められることもあります(一般に)。
限定承認は共同申述
限定承認は共同相続人全員での申述が必要です。疎遠で連絡が付きにくい場合は、現実的かどうかを早めに検討します。
初動チェック(目安)
- 最初の7日:戸籍の手配、相続人と連絡窓口の設定、通帳・郵便物の保全。
- 2〜3週:財産の仮把握(預貯金・不動産・保険・負債)、方針メモ作成。
- 1〜2カ月:承認/放棄の判断、必要に応じて熟慮期間の伸長申立。
遺体の引取り・費用について
一般に、遺体の引取り義務が一律に課されるわけではありません。引受人不在の場合は、自治体が行旅死亡人法・墓地埋葬法に基づき火葬等を実施し、費用は原則として故人の遺留財産等から弁償が図られます。相続人・扶養義務者への請求の要否は自治体の実務に幅があり、相続放棄受理後は請求対象としない運用とする自治体もあります。詳細は各自治体に確認してください。
疎遠ケースの手続きの流れ(概要)
- 生死と相続人の確認(戸籍収集)。未成年が相続人に含まれる場合は特別代理人の選任が必要になることがあります。
- 財産調査(預貯金・不動産・保険・負債/郵便物・通帳等の手掛かり)。
- 承認/放棄の選択(限定承認の可否含む)。
- 遺産分割(相続人全員で協議→協議書作成/調停・審判の検討)。
- 税務手続き(基礎控除・申告期限の確認)。※詳解は税理士サイトへ。
税務(VSG相続税理士法人の記事へ)
弁護士ができること
- 相続人・財産調査の代理(戸籍収集、残高照会、遺産の洗い出し)
- 熟慮期間伸長の申立、相続放棄・限定承認の申述サポート
- 後妻や異母兄弟等との交渉・調停代理(連絡窓口の一本化)
- 未成年者の特別代理人選任申立のサポート
- 遺産分割協議書の作成と提出先ごとの段取り
よくある質問(遺体の引取りの費用・元配偶者の相続権の有無 など)
離婚した親が亡くなったら連絡は来ますか?来ない場合は?
来ることも来ないこともあります。まず戸籍(全部事項証明・除籍)で生死・相続人を確認し、役所・病院・警察・賃貸管理会社・債権者等の連絡元を当たります。連絡がないままでも、相続放棄の熟慮期間(原則3か月)は進む可能性があるため、起算点の把握と伸長申立を早めに検討しましょう(一般に)。
連絡が来なかったのですが、相続放棄の期限は過ぎていますか?
熟慮期間3カ月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。死亡の事実を知った時点とズレるケースもあります。事情により伸長申立が認められることもあります(一般に)。
限定承認は一人だけで申し立てできますか?
できません。共同相続人全員での申述が必要です。
遺体の引取りを断ったら費用請求されますか?
自治体の運用に幅があります。原則は故人の遺留財産等からの弁償が先で、相続人・扶養義務者への請求要否は各自治体の実務により異なります。相続放棄受理後は請求しない運用が見られる自治体もあります。
まとめ
離婚した親の訃報は、必ず連絡が来るとは限りませんし、どこから届くかも事案により異なります。
連絡の有無にかかわらず、あなたが法定相続人となる可能性は残るため、まずは戸籍で生死と相続人関係を確認し、通帳や郵便物などから財産の手がかりを押さえることが出発点です。
相続を受けるか相続放棄・限定承認にするかの判断は早めに進めましょう(熟慮期間は原則3カ月。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」で、事情により伸長申立が認められる場合もあります)。
疎遠でやり取りが負担だったり、後妻・異母(父)兄弟との関係で不安があるときは、弁護士が連絡窓口の一本化、相続人・財産調査、交渉・調停まで代理できます。
感情的な対立や期限の徒過を避けるためにも、早い段階で専門家に相談し、税務の詳解は税理士と役割分担するのが現実的です。
VSG弁護士法人では、相続の実績が多い弁護士が状況整理から連絡・交渉の代行、必要な申立てまで一貫してサポートします。