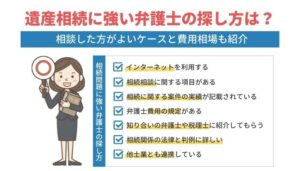この記事でわかること
- 相続税の生前贈与加算について
- 2024年からの7年ルールの詳細
- 相続税計算の生前贈与7年ルールの対象者
- 生前贈与の相続税負担を軽減する方法
- 相続時精算課税制度と特定贈与の非課税制度
相続税計算では、生前贈与が相続財産に加算される期間を正しく理解し、適切な戦略を立てることが重要です。
2024年1月1日以降、贈与に関してはさかのぼる年数が延長されました。
このため、早期からの対策が求められ、長期的な資産移転計画が必要になりました。
この記事では、従来ルールとの差異や生前贈与加算のしくみ、そして税負担を軽減するためのポイントについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
相続税計算のために生前贈与は何年前までさかのぼる?
相続税計算では、相続開始前に行われた贈与は一定期間さかのぼって相続財産に加算されます。
2024年からは、その対象期間が段階的に拡大され、最終的に7年までの贈与が加算対象となりました。
そのため、これまで以上に計画的な生前贈与が必要となります。
ここでは、生前贈与加算の概要や新しい7年ルールについて解説します。
この改正により、相続が発生する前の贈与にどのように影響するか見ていきましょう。
相続税の生前贈与加算とは?
相続税の生前贈与加算とは、相続開始前に被相続人から贈与を受けた財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する制度です。
従来は、相続開始前3年以内の贈与が対象でした。
2024年1月1日以降に実施された贈与は、段階的に計算期間が延長され、最終的に相続開始前7年まで対象となります。
被相続人の相続開始日に応じた生前贈与加算の加算対象期間は、次の表のとおりです。
参考にしてください。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
この制度により、相続税計算が複雑化するため、早めの対策や専門家への相談が求められます。
個々の状況によって、専門家に相談しながら計画的贈与をするとよいでしょう。
2024年1月1日からの7年ルールとは?
2024年1月1日から適用が始まる7年ルールは、生前贈与加算期間を拡大する改正点として大きな注目を集めています。
すべての贈与が、即座に7年間分加算されるわけではありません。
以下のような段階を踏んで延長されます。
- 2024年~2026年:従来の3年ルールを維持
- 2027年~2030年:加算対象期間を4年から6年に段階的に拡大
- 2031年以降:完全に7年ルールを適用
また、2027年1月2日以降の相続開始分については、4年~7年前の贈与に対して100万円が控除される特例が設けられています。
このような複雑なルール改正により、生前贈与で思わぬ税負担を招く可能性もあります。
したがって、資産状況や家族構成、相続時期などを踏まえ、専門家と相談しながら長期的な計画を立てることが求められます。
事前に適切な計画を立てて実行することにより、税負担の軽減や円滑な資産承継が期待できるでしょう。
相続税計算の生前贈与7年ルールの対象者
生前贈与の7年ルールの対象者は、基本的には相続人や受贈者ですが、特定の条件によって異なる場合もあります。
ここでは7年ルールの対象者になる人と対象者にならない人について解説します。
家族の状況により、適切な贈与計画を立てるための参考にしてください。
生前贈与加算の7年ルールの対象者になる人
国税庁によると、7年ルールの対象者は、以下の条件に該当する人です。
引用:
相続等により財産を取得した人で、その相続等に係る被相続人から加算対象期間内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した人
7年ルールの対象者は、基本的に相続または遺贈によって財産を取得する人で、以下のような人が該当します。
- 相続人:法定相続人である配偶者や子
- 遺言による受遺者:遺言で指定された受取人
- みなし相続財産を受け取る人:生命保険受取人、死亡退職金の受取人など
将来的に相続する可能性がある人への贈与は、7年ルールの影響を受けるため、注意しましょう。
生前贈与加算の7年ルールの対象者にならない人
一方で、7年ルールの対象者にならないケースもあります。
以下の人への生前贈与の場合、贈与が相続税計算に影響しません。
- 相続放棄をした人:相続放棄により相続人ではなくなるため対象外
- 法定相続人や受遺者でない親族:被相続人の孫、子の配偶者などへの贈与は原則として対象外
遺言や生命保険で財産を取得する場合は対象となります。
これらの対象外となる人々への贈与は、通常、相続税計算には加算されません。
そのため、配偶者や子など法定相続人がいる場合は、孫などへの贈与を検討するのもよいでしょう。
ただし、特定の条件下で例外が適用される可能性があるため、個別の状況に応じた慎重な確認が必要です。
不安がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
生前贈与の相続税負担を軽減する方法

生前贈与を計画的に活用することで、将来の相続税負担を大幅に軽減できます。
特定の非課税枠や特例制度を上手に利用することで、長期的な資産承継を円滑に行うことが可能になるでしょう。
ここでは代表的な制度や控除を取り上げ、その活用ポイントを紹介します。
生前贈与の基礎控除を活用する
年間110万円までの基礎控除を利用すれば、毎年非課税で資産を受け渡せるため、多くの人がこの枠を利用して資産移転を行っています。
例えば、親から子へ10年間にわたり毎年110万円ずつ贈与すれば、合計1,100万円を非課税で渡すことができます。
また、同じ年に複数の受贈者がいる場合、それぞれに110万円ずつの控除が適用され、家族全体で効果的な資産分散が行えます。
例えば、親が子ども2人にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、1年間に合計220万円まで非課税で資産を移転できることになります。
この方法は特別な手続きが不要で、単純で継続的な資産移転に向いています。
この仕組みを活用することで、家族全体で計画的に資産を移転することが可能になります。
ただし、長期間にわたる計画性が求められる点に留意しましょう。
相続時精算課税制度の利用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母が、18歳以上の子や孫に生前贈与を行う際に利用できる制度です。
この制度では、累積2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月31日までに申告を行う必要があるため、忘れずに申告しましょう。
将来の相続時には累計贈与額が相続財産に合算され、最終的な相続税計算に反映されます。
しかし、この制度を一度選択すると暦年課税に戻せないため、親世代の保有資産や相続時期などを総合的に考慮したうえで判断することが望まれます。
また、相続時にはこれまでの累積贈与額と相続財産を合算して相続税が計算されるため、将来の税負担を見据えた利用が求められるでしょう。
特定贈与の非課税制度を利用する
特定贈与の非課税制度は、教育資金、結婚・子育て資金、住宅資金など、特定の目的のために行われる贈与に適用される特例です。
教育資金の一括贈与は、直系尊属が30歳未満の子や孫に対し、教育に必要な資金をまとめて贈与する際に利用できます。
この制度では、最大1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。
結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚や子育てに必要な費用を支援するための制度です。
直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫への贈与に利用できます。
この制度では、一括で最大1,000万円まで非課税で贈与することが認められています。
住宅取得等資金の贈与は、居住用住宅を購入や増改築の資金を直系尊属から贈与された場合に利用できる制度です。
省エネ住宅やバリアフリー住宅の場合は最大1,000万円、その他の住宅では最大500万円まで非課税となります。
これらの制度を活用すれば、大きな資金移転を行いながら相続税負担を軽減することが可能です。
いずれの制度も申告が必須で、申告を怠った場合は非課税措置が適用されません。
また、各制度には受贈者の年齢条件や用途制限など細かな規定があるため、適用前に制度内容を正確に把握する必要があります。
長期的な視野で計画する必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
2024年からの「7年ルール」を踏まえ、早期に戦略を立てることが節税対策の鍵となります。
しかし、税制は複雑で、家族構成や財産状況によって最適な方法は異なります。
そのため、専門家へ相談し、将来のリスクを軽減する準備を行いましょう。
自分や家族に合った生前贈与の手法を見つけ、積極的に行動することで、円滑な資産承継と税負担軽減を実現できるでしょう。