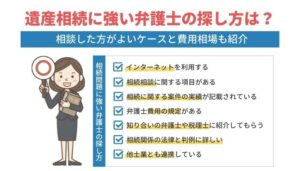この記事でわかること
- 共有名義人の片方が死亡した場合のケース別相続手続き
- 相続登記の必要書類や手続きの流れ
- 相続税の計算方法と実例
- 相続税に関する特例や控除
- 共有トラブルを避けるための対策と注意点
不動産の共有名義人が亡くなった場合、残された共有名義人が当然にその持分を引き継ぐわけではありません。
亡くなった人の持分は被相続人の相続財産として扱われ、相続の対象となります。
この記事では、共有名義人が亡くなった際の相続手続き、相続税の計算方法や実例、控除や特例を含め、具体的なケースを挙げながら解説します。
さらに、共同名義を相続する際の注意点や、トラブルを防止するための方法にも触れていきます。
スムーズな相続手続きを進め、共有名義によるトラブルを未然に防ぐために、本記事を参考にしてください。
目次
共有名義人の片方が死亡した際の相続はどうなる?
共有名義人の一方が亡くなった場合、亡くなった人の持分のみが相続の対象となります。
遺言書がある場合は、遺言書で指定された人がその持分を相続します。
遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、誰が持分を相続するかを決定することになります。
ここでは夫婦、親子、兄弟姉妹で共有していた場合の3つのケースについて解説します。
夫婦共有名義の片方が死亡した場合の相続
夫婦共有名義でも、配偶者が当然にすべてを相続できるわけではありません。
遺言書があればその内容に従いますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人がいる場合は、持分をどのように分けるか協議が必要です。
民法では、法定相続分が規定されています。
基本となる法定相続分を表にまとめましたので、参考にしてください。
法定相続人の順位と法定相続分
| 順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 他の相続人と共同相続 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は人数割り) |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 配偶者2/3、直系尊属1/3(複数の場合は人数割り) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数の場合は人数割り) |
法定相続分は基本となる指標ですが、実際の分配は遺産分割協議で全員の合意に基づいて決定します。
そのため、妻が全部を相続する、あるいは長男が全部相続する、といった分割も可能です。
不動産の共有名義は将来の権利関係が複雑になるため、単独所有が望ましいです。
たとえば、他の相続人に相続分相当の金銭を支払い(代償分割)、公平を図りながら単独所有にする方法もあります。
親子で共有名義の場合
親子で共有名義の場合、親が亡くなると、その共有持分は相続対象となります。
遺言書がある場合はその内容を優先しますが、ない場合は相続人全員の協議で決める必要があります。
もし親の相続人が子ども1人だけであれば、その子は親の持分をすべて取得し、不動産の完全な所有権を得ることになるでしょう。
しかし、他に相続人がいる場合は、遺産分割協議を経て持分を分ける必要があります。
たとえば、父と長男が1/2ずつの共有名義で父が死亡し、相続人は母と長男と二男、というケースを考えてみましょう。
その場合、法定相続分と持分割合は以下の通りです。
| 相続人 | 法定相続分 | 不動産の持分 |
|---|---|---|
| 母 | 1/2(父の持分の1/2) | 1/4 |
| 長男 | 1/4(父の持分の1/4)+1/2(元々の持分) | 5/8 |
| 二男 | 1/4(父の持分の1/4) | 1/8 |
法定相続分に基づく分割では、不動産の持分が細かく分割されてしまいます。
この状態から、もし次の相続が発生すると、持分がさらに細かく分割され、トラブルの原因となる可能性が高まるでしょう。
そのため、共有名義の財産は、可能な限り単独所有にすることが推奨されます。
実際の相続では、遺産分割協議や代償分割を活用し、単独所有を目指すことがおすすめです。
兄弟姉妹で共有名義の場合
兄弟姉妹で共有名義の場合、共有者の一人が死亡すると、その持分のみが相続の対象となります。
遺言書がある場合はその内容で相続され、遺言書がない場合は、亡くなった兄弟の配偶者と子どもたちが相続人となります。
たとえば、兄弟2人で1/2ずつ共有名義、兄が亡くなり、兄の配偶者と子3人が相続人の場合を考えてみましょう。
| 共有名義人または相続人 | 法定相続分 | 不動産の共有持分 |
|---|---|---|
| 弟 | – | 1/2 |
| 兄の配偶者(相続人) | 1/2 | 1/4 |
| 兄の長男(相続人) | 1/6 | 1/12 |
| 兄の二男(相続人) | 1/6 | 1/12 |
| 兄の三男(相続人) | 1/6 | 1/12 |
法定相続分で分割すると、共有名義人が5人となり、持分割合を見ても非常に複雑です。
固定資産税を持分割合で支払う場合や、不動産を売却、賃貸、修繕する際には、5人で話し合わなくてはなりません。
次の相続が起きた場合は、さらに遠戚の相続人が共有名義人となり、共有名義の人数も増える可能性があります。
共有名義の不動産は多くのリスクをはらんでいるため、専門家への相談を検討し、適切な対策を講じましょう。
共有名義人の片方が死亡したときの相続手続き
共有名義人の一方が亡くなった場合、亡くなった方の持分を相続人名義に変更するための相続登記を行う必要があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った時から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
ここでは、手続きの流れや必要書類、相続登記の申請方法について説明します。
相続登記の必要書類と手続きの流れ
相続登記を行うには、まず法務局で不動産登記簿謄本を取得し、不動産の状況を確認しましょう。
次に、以下の必要書類を準備します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書
- 遺言書(遺言書がある場合)
- 検認済証明書(検認手続きが必要な遺言書の場合)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 登記申請書
必要な書類を揃えたら、登録免許税を納付し、その不動産を管轄する法務局に登記申請書を提出します。
登録免許税は、固定資産評価証明書の不動産価格によって算出します。
相続の登録免許税は「不動産価格×被相続人の持分割合×0.4%」で計算されます。
法務局で書類の不備がないか確認され、問題がなければ相続登記が完了します。
相続登記の申請方法
相続登記の申請は、不動産を取得する相続人が、その不動産を管轄する法務局に対して行います。
申請方法には、対面での窓口提出、郵送、オンライン申請がありますが、オンライン申請をするには電子証明書が必要です。
相続登記の申請書を書く際は、登記の目的は「A持分全部移転」、原因は「令和〇年〇月〇日相続」と記載します。
遺言書による登記原因は「令和〇年〇月〇日遺贈」と記載する場合もあります。
「A」は被相続人の氏名、「令和〇年〇月〇日」は死亡した日付を記載します。
自分で作成することも可能ですが、書類に不備があると登記が完了しないため、法務局の相談窓口を活用することをおすすめします。
また、共有名義の登記は複雑なケースが多いため、司法書士に依頼すると確実です。
共有名義人の片方が死亡したときの相続税はどうなる?
共有名義の片方が死亡した場合の相続税は、少し複雑な計算になります。
ここでは、相続税の計算方法を実例によって詳しく説明します。
また、配偶者が相続した場合の税額軽減制度や小規模宅地等の特例についても解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算は、まず正味の遺産額を把握することから始まります。
正味の遺産額は、すべての遺産から非課税財産(葬儀費用など)と債務を引いた額で求めます。
計算式
正味の遺産額=相続財産-非課税財産-債務
次に、基礎控除額を計算し、正味の遺産額から差し引きます。
基礎控除額は、以下の式で求められます。
計算式
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額
こうして課税遺産総額が算出され、法定相続分に応じて各相続人に割り振られた金額に対して税率を適用します。
相続税の計算事例
以下の条件を想定し、相続税の課税遺産総額を計算してみましょう。
事例相続税の課税遺産総額
- 法定相続人:3人
- 不動産価格:5,000万円(被相続人の持分は1/2)
- その他の相続財産:6,000万円
- 債務や葬儀費用:100万円
1)相続対象の不動産価格を計算
5,000万円×1/2=2,500万円
2)課税対象額を算出
不動産価格+その他の相続財産-債務や葬儀費用
2,500万円+6,000万円-100万円=8,400万円
3)基礎控除額を算出
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
4)課税遺産総額を算出
課税対象額-基礎控除額
8,400万円-4,800万円=3,600万円
この相続における課税遺産総額は3,600万円となります。
相続税の計算は、課税遺産総額を法定相続分に応じて各相続人に配分し、それぞれに適用される税率によって各自が納付すべき金額が決まります。
また、相続税の総額は、これらの個別の納付すべき相続税額を合計して求めます。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例
配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減の特例」が適用されることがあります。
この特例により、配偶者が取得した財産については一定金額まで相続税が軽減されます。
配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。
また、「小規模宅地等の特例」も利用できる場合があります。
この特例は、自宅や事業用地など特定の宅地について評価額を減額できる制度です。
たとえば、被相続人と同居していた自宅に住み続けていた場合、その土地について、330㎡を上限として評価額の80%が減額されます。
これらの特例を活用することで、相続税を大幅に減らすことが可能です。
ただし、将来的には二次相続に伴う相続税の負担も考慮する必要があるでしょう。
二次相続を含めた計画的な相続対策については、専門家への相談をおすすめします。
共有名義の片方が死亡した場合の注意点
共有名義の不動産は、できるだけ共有関係を解消し、単独所有にすることが望ましいです。
ここでは、共有名義の不動産が、相続でさらに共有名義になることのデメリットや遺産分割協議で単独所有にすることについて説明します。
他人との共有で起こるデメリット
共有名義の不動産は、片方の名義人が亡くなると、その持分は相続人に引き継がれ、権利関係が複雑になることがあります。
たとえば、共有名義の片方が亡くなり、兄弟姉妹が相続するなどで、会ったこともない遠方の共有者が加わる場合があります。
また、相続人がいない場合や相続放棄された場合、その持分は国庫に帰属し、国が共有者となる可能性もあります。
さらに、相続人が不動産の持分を売却すれば、赤の他人が共有者になることもあります。
結果的に、共有者の同意が必要な不動産管理や処分が困難となり、不動産の有効活用が滞ります。
こうした不確定要因の積み重ねは、資産価値低下や追加コスト、精神的負担の増大といった深刻なデメリットを招くでしょう。
共有を解消するための方法
共有関係を解消し、単独所有にするには、以下の方法が有効です。
- 遺産分割協議で全持分を集約
- 代償分割で他者の持分を金銭補償
- 生前贈与で事前に持分を整理
- 遺言書で承継者を指定
これらを組み合わせることで、将来のトラブルを回避し、不動産の管理・活用が円滑になります。
状況に応じて活用し、共有による複雑な権利関係を整理しましょう。
不動産の共有名義のトラブルを防ぐ方法

前述したように、共有名義の不動産のトラブルを未然に防ぐためには、単独所有にする方法を検討することが重要です。
ここでは、遺言書や生前贈与で単独所有にする方法を説明します。
生前贈与で単独所有に
生前贈与を利用することで、自分の持分を他の名義人に無償で譲渡することも可能です。
たとえば、夫婦間で自宅の持分を配偶者に贈与する場合、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用できる場合があります。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する際に適用できる特例です。
条件に合えば最大2,000万円まで非課税となり、基礎控除枠110万円も適用されます。
この方法によって、亡くなる前に持分を整理し、相続時以降のトラブルを回避することができるでしょう。
遺言書で単独所有に
生前に遺言書を作成することで、共有名義の不動産について自分の持分を特定の相続人に相続させることができます。
たとえば、夫婦で不動産を共有している場合、遺言書に「自分の持分を配偶者に相続させる」と明記することで、配偶者の単独所有にできます。
これにより、共有名義が解消され、不動産の管理や利用がスムーズになります。
また、遺言書は法的効力があるため、相続人同士のトラブルの可能性も減少させることができるでしょう。
まとめ
共有名義人の片方が亡くなった場合の相続のポイントは、将来的に権利関係が複雑にならないようにすることです。
相続の機会に単独所有にできれば、将来のトラブルを防止することができます。
また、これから発生する相続については、遺言書の作成や生前贈与を検討し、将来的な問題を未然に防ぐことを検討しましょう。
共有名義の相続は複雑な側面があるため、状況によっては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。