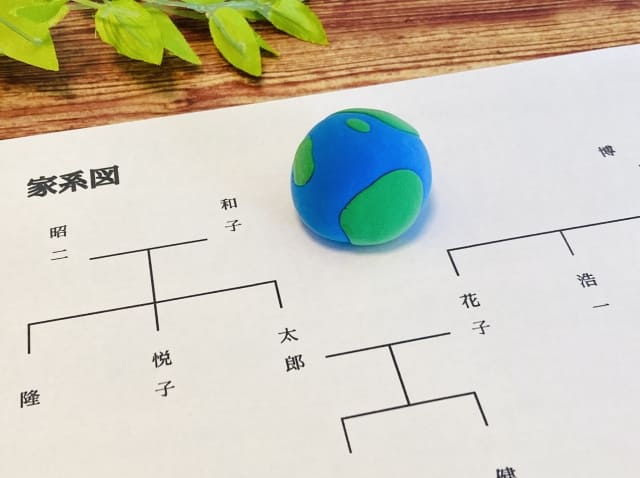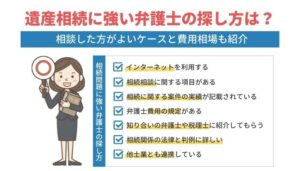この記事でわかること
- 国際相続の基本ルールと準拠法
- ケース別の国際相続の方法
- 国際相続特有の必要書類と事前準備のポイント
- 国際相続を専門家に依頼する際の費用目安
国際相続とは、被相続人や相続人が海外居住している、または外国籍である場合や、相続財産に海外資産が含まれる場合の相続手続きを指します。
複数の国の法律が関わるため、手続きが複雑になりがちです。
本記事では、国際相続における準拠法の決定方法や相続税の扱い、ケース別の手続き方法、必要書類、さらに専門家への依頼費用など、詳細に解説します。
国際相続に該当する方が、スムーズに手続きを進めるためのガイドとしてご活用ください。
目次
国際相続の基本ルール
国際相続では、被相続人や相続人の国籍、居住地、財産の所在地によって適用される法律や税制が異なります。
複雑な手続きを円滑に進めるためには、まず準拠法の決定と相続税の取り扱いという2つの基本ルールを理解することが重要です。
国際相続における準拠法
国際相続における準拠法とは、相続手続きを進める際にどの国の法律を適用するかを決定するルールです。
日本では「法の適用に関する通則法」第36条と第37条が該当し、原則として被相続人の本国法が準拠法となります。
引用:
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。第2条 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
以下のケースでは、準拠法の決定が重要なポイントになります。
- 被相続人が日本国籍で海外に遺産がある場合、原則として日本の相続法が適用されますが、海外の不動産にはその所在地の法律が適用される可能性があります。
- 日本国籍の被相続人が長期海外滞在でも日本の相続法が適用されますが、外国籍を取得していれば、その国の法律が適用されることがあります。
- 相続人の居住地に関係なく、被相続人の本国法が適用されますが、海外在住の相続人には特別な対応が必要です。
準拠法の決定は相続手続きに大きく影響するため、慎重な判断が求められるでしょう。
国際相続の相続税
国際相続における相続税の課税は、被相続人と相続人の居住地や国籍、財産の所在地によって異なります。
日本の相続税法では、原則として被相続人または相続人が日本に住所を有する場合、全世界の財産に対して相続税が課税されます。
一方、両者とも日本に住所がない場合、日本国内にある財産のみが課税対象です。
ただし、日本国籍を有している場合、過去10年以内に日本に住所があったかどうかで課税範囲が変わります。
また、国際相続では二重課税が問題となることもあります。
これを避けるため、日本は多くの国と租税条約を結び、外国で納付した相続税を日本の相続税から控除する制度を設けています。
相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日から10カ月以内ですが、海外居住者には6カ月の期限延長が認められています。
【ケース別】国際相続の方法
国際相続では、被相続人や相続人の国籍、居住地、資産の所在地によって手続きが大きく異なります。複雑な国際相続を円滑に進めるためには、各ケースの特徴を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
ここでは、国際相続の方法を主な3つのケースに分けて解説します。
被相続人が海外資産を持っていた場合
被相続人が海外に資産を持っている場合、その取り扱いは国によって異なり、相続統一主義と相続分割主義の2つの考え方があります。
相続統一主義では、動産と不動産を区別せず、被相続人の最後の住所地や国籍国の法律に基づき、すべての財産を一括で相続処理します。
一方、相続分割主義では、特に不動産についてはその所在地の法律が適用されます。
日本は原則として相続統一主義を採用していますが、海外の不動産については現地の法律に従わなければなりません。
また、預金や有価証券などの金融資産についても、各国の法律や金融機関の規則に従って手続きを進めます。
日本での相続税申告時には、これらの海外資産も含める必要がありますが、為替レートの変動や二重課税にも注意しましょう。
被相続人または相続人が海外在住の場合
被相続人が海外在住の場合、その国の相続法が適用される可能性があります。
日本の「法の適用に関する通則法」では、原則として被相続人の本国法が準拠法となりますが、被相続人の最後の住所地の法律を選択することも可能です。
国際的な協定や条約がある場合、それが影響を及ぼすこともあります。
特に、国際結婚や海外での長期滞在などの状況では、相続手続きが複雑化する可能性があるため、専門家のサポートを受けることが重要です。
また、相続人が海外在住の場合、日本の相続手続きを海外から行う際には署名証明書や在留証明書など特定の書類が求められます。
相続税についても注意が必要です。
海外に居住している相続人でも日本国内外の財産に対して相続税が課されるため、申告期限や納付方法を把握しておくことが求められます。
二重課税を避けるため、外国税額控除を利用することも考慮するとよいでしょう。
被相続人または相続人が外国籍の場合
被相続人または相続人が外国籍の場合、適用される法律や相続税の取り扱いが変わってきます。
被相続人が外国籍の場合、その国の相続法が適用される可能性が高くなります。
日本の「法の適用に関する通則法」では、被相続人の本国法が準拠法となるため、その国の相続法に従って遺産分割を行います。
ただし、日本に所在する不動産については、日本法が適用される場合もあります。
一方、相続人が外国籍の場合、日本の相続税法上の取り扱いが日本国籍の相続人とは異なる場合があります。
たとえば、一時居住者や非居住者の場合、課税対象となる財産の範囲が限定されます。
また、相続人の本国でも相続税が課税される可能性があるため、二重課税を回避するための措置を検討する必要があるでしょう。
海外在住の相続人が手続きするための必要書類
国際相続では、海外在住の相続人が手続きを行う際に特別な書類が必要です。
主に必要となるのは署名証明書、在留証明書、そして相続人証明書です。
ここでは、これらの書類について詳しく説明します。
署名証明書と在留証明書
海外在住の相続人が印鑑証明書の代わりに求められるのが署名証明書です。
署名証明書は、日本の在外公館(大使館や総領事館)で発行され、本人の署名が真正であることを証明します。
一方、住民票の代わりとなるのが在留証明書で、現地の役所や日本の在外公館で取得できます。
署名証明書と在留証明書を取得する際には、パスポートや運転免許証などの身分証明書が必要です。
有効期限は通常6カ月程度のため、相続手続きの進行に合わせてタイミングよく取得することが重要です。
相続人証明書
相続人証明書は、相続人が法定相続人であることを証明する公的文書です。
日本では戸籍謄本や除籍謄本がこれに該当しますが、海外では国や地域によって異なる形式の証明書が使用されます。
たとえば、アメリカ合衆国では、裁判所が発行する「Letters of Administration」や「Letters Testamentary」が相続人証明書に該当します。
相続人証明書の取得方法や必要書類は国によって異なるため、現地の法律や手続きを確認しましょう。
また、海外で取得した相続人証明書は、日本の相続手続きで使用する際に翻訳や認証が必要になる場合があるため注意してください。
国際相続に備えて準備しておくこと
国際相続では、複数の国の法律や税制が関係するため、事前の準備が大切になります。
ここでは、財産目録の作成や検認裁判(プロベート)について解説します。
国際相続の財産目録作成と更新
国際相続における財産目録作成は、複数国にまたがる資産を正確に把握し、管理するための重要な準備です。
財産目録には、不動産、預金口座、投資、事業資産などすべての財産を記載し、各資産の所在地、金額、権利関係も明確にします。
為替レートの変動を踏まえた金額換算も必要となるため、換算の基準日も明記しておきます。
国際相続の複雑さを考慮すると、専門家のアドバイスを受けながら作成することが望ましいでしょう。
また、財産状況の変化や法制度の改正に対応するため、少なくとも年1回は内容を更新することをおすすめします。
正確で最新の財産目録を維持することで、円滑な相続手続きや相続税の適切な計算が可能となります。
日頃から準備しておくことで、急な国際相続に直面した際も、不要な混乱を防ぐことができるでしょう。
検認裁判(プロベート)の有無の確認
検認裁判(プロベート)は、英米法系の国々などで行われ、主に遺言の有効性を確認する裁判手続きです。
国際相続では、関係する国によってプロベートの必要性が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
たとえば、アメリカやイギリスでは、一定額以上の資産がある場合、プロベートが必要となります。
プロベートが必要な国では、遺言執行者の指名や遺言の方式に特別な要件が必要なこともあるため、これらの点も確認しておかなくてはなりません。
プロベートの手続きは複雑で時間がかかるため、事前に必要性を把握することで、相続手続きの遅れを防ぐことができるでしょう。
国際相続を専門家に依頼する費用

国際相続の手続きは複雑で、専門家の助けが必要不可欠です。
弁護士や税理士に依頼する場合の費用は、案件の複雑さや資産規模によって大きく異なります。
また、相続人が海外在住の場合など、追加の費用が発生する可能性があります。
ここでは、各専門家に依頼する際の費用の目安と、海外在住の相続人がいる場合の追加費用について説明します。
国際相続を弁護士に依頼する場合の費用目安
国際相続の弁護士費用は、案件の複雑さや資産規模により大きく異なります。
一般的に、着手金と報酬金の二段階制が採用されますが、タイムチャージ制を採用する事務所もあります。
着手金は、相続財産の価格に応じて段階的に設定されることが多く、1000万円以下で30万円~60万円程度、1億円以上で110万円~140万円程度が目安です。
報酬金は、相続財産の3%~7%程度が一般的ですが、複数国が関係する場合や争いがある場合は、さらに高額になることがあるでしょう。
また、翻訳費用、海外弁護士との連携費用、出張費用なども別途必要です。
相続人が多い場合や海外在住の場合は、追加費用が発生することもあります。
これらはあくまで目安であり、実際の費用は個々のケースや弁護士により異なるため、弁護士との相談で決定することになるでしょう。
国際相続を税理士に依頼する場合の費用目安
国際相続の税務処理を税理士に依頼する場合の費用は、相続財産の規模や複雑さによって変動します。
一般的に、基本料金と財産額に応じた変動料金の組み合わせで算出されることが多く、個々のケースにより追加料金が発生します。
たとえば、ある事務所は相続財産1億円に対して20万円~50万円程度の基本料金ですが、状況により20~50%が加算されるなどの変動があります。
海外資産の評価や二重課税の調整、各国の税務当局とのやり取りや、外国語での書類作成が必要な場合なども別途追加費用がかかります。
個別ケースによって、かなりの幅があるため、実際には個別に税理士と相談の上、料金を決める必要があるでしょう。
相続人が海外在住の場合の追加費用目安
相続人が海外在住の場合、通常の国際相続に加えて特殊な費用が追加費用として発生する可能性があります。
海外で必要な書類の取得や認証に関する費用も、考慮する必要があるでしょう。
たとえば、署名証明書や在留証明書の取得費用、アポスティーユ認証の費用などが発生します。
アポスティーユ認証とは、文書が確かに日本の公的機関によって出されたものだと証明するものです。
また、海外の弁護士や税理士との連携が必要な場合、その費用も加算されます。
海外在住の場合の追加費用は、数十万円から数百万円程度の追加料金として発生する可能性があるでしょう。
実際には、個別事案により変動するため、国際相続の専門家に相談し、詳細な見積もりを取ることをおすすめします。
まとめ
国際相続の手続きは非常に複雑で、専門的な知識が欠かせません。
相続に関する法律や税制が国ごとに異なるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
準備段階から専門家にサポートを依頼することで、将来のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを実現しやすくなるでしょう。
まずは、国際相続に対応した専門家に相談し、具体的なアドバイスを得ることを検討してみましょう。