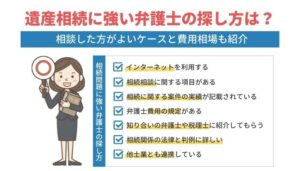この記事でわかること
- 相続土地国庫帰属制度の概要
- 制度利用の要件や手続き方法について
- その他の土地の手放し方
「相続により土地を取得したものの、処分も利用もできず放置している」
このような土地が日本全国にあふれています。
今後利用される見込みがなく、放置され荒れ果てた土地でも個人の所有地である以上、国は手出しができず傍観するしかありませんでした。
このような相続や少子高齢化の問題により、土地活用の課題が浮き彫りになってきたことから、国は2023年から、相続土地国庫帰属制度の運用をスタートしました。
制度を利用することで、土地の取り扱いはどうなるのでしょうか。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要や、制度利用に関する詳細について解説します。
目次
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続により取得した土地を手放し、所有権を国に引き渡す制度です。
簡単に言えば、いらない土地を国に引き取ってもらうということです。
2023年4月に制度が制定され、施行後1年半で約3000件の利用申請がされています。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」
今後は利用が増えていくと見込まれています。
そもそもなぜ、国が土地を引き取る制度ができたのでしょうか。
ここでは、相続土地国庫帰属制度が制定された背景について解説します。
相続土地国庫帰属制度ができた背景
本来、土地は代々受け継がれ、また自由に売買できるものです。
それを国に帰属させ、国が管理する制度を作った目的と背景には、以下のような理由があります。
- 土地の需要減
- 土地は簡単に捨てられない
- 土地だけの相続放棄ができない
- 費用の負担が大きい
- 所有者不明土地の対策
一つずつ見ていきましょう。
土地の需要減
近年の少子高齢化に伴い、日本全国で、特に地方の人口は減少の一途をたどっています。
都市部に人口が集中しているため、地方の土地の需要は減っていく一方です。
需要がない土地を所有者個人で活用することは難しく、放置された結果、荒地となることが少なくありません。
荒れ果てた土地を放置していると、景観や治安悪化の要因にもなります。
そこで相続土地国庫帰属制度を制定することによって、国が土地活用や景観保持をできるようになりました。
土地は簡単に捨てられない
一度土地の所有権を得ると、そう簡単に手放すことはできません。
特に需要の減った地方の土地は、買い手が見つからないことも少なくないため、売却することは簡単ではありません。
もし無償で譲ることができたとしても、これは贈与にあたります。
契約書の作成や登記申請、税金の支払いなど、手続き全般を個人ですることになり、トラブルのもととなる可能性もあるでしょう。
相続土地国庫帰属制度は、このように手放したくても手放せない土地を国が管理し、活用しようという取り組みです。
土地だけの相続放棄ができない
相続放棄は、相続財産のすべてを放棄することであり、一部の財産だけを放棄することはできません。
土地を放棄するなら、他の財産も一緒に放棄することになります。
そのため不要な土地があっても、他の財産を相続したい場合は、土地を含めて相続するしかありません。
相続された不要な土地は、活用や売却することができず放置されることになります。
その点、相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続した後に土地だけを手放すことができるようになりました。
費用の負担が大きい
土地は普段利用していなくても、所有しているだけで固定資産税や、場所によって都市計画税が課されます。
居住用の建物が建っている宅地の場合は、小規模宅地の特例が使えるため、固定資産税を軽減できます。更地の場合、この特例は利用できません。
そのため、土地と家を相続した後、節税のために家をそのまま放置する人が増え、その結果空き家が増えてしまった経緯があります。
現在は特別措置法により、空き家認定されれば小規模宅地の特例から除外されるため、固定資産税の節税はできません。
しかしこれまでに所有者不明の空き家が増加し、空き家数は2023年に過去最多の900万戸となりました。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、土地の処分が容易になり、相続人の負担の軽減や空き家対策にもつながります。
所有者不明土地の対策
2024年に、不動産の相続登記が義務化されました。
それまでは名義を変更せずとも問題なかったため、利用する予定のない不動産では、相続登記をしない人も多くいました。
しかし、登記をしないまま相続を繰り返した結果、登記上の名義と本来の所有者が異なるというケースが増加しました。
登記を確認しても現在の所有者がわからず、所有者がわかったとしても、所在が不明で連絡が取れないことも少なくありません。
所有者不明土地は勝手に処分することもできず、国も地方自治体もその処理に手をこまねいている状態です。
相続土地国庫帰属制度は、今後このような土地が増えることを防ぐ目的があります。
相続土地国庫帰属制度を利用できる要件
不要だからと言って、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、要件がそろった土地である必要があります。
要件は、以下のものが挙げられます。
- 相続や遺贈で取得した土地であること
- 共有者がいる場合、共有者全員の同意があること
- 却下事由に相当しない土地であること
一つずつ見ていきましょう。
相続や遺贈で取得した土地
相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、相続や遺贈により、相続人が取得した土地に限られます。
そのため相続人ではない、第三者が遺贈により取得した場合は対象外です。
※遺贈・・・遺言により特定の個人や団体に特定の財産を相続させること
2023年4月27日の制度施行前に相続した土地も対象です。
相続したものの処分に困っている土地があれば、制度利用を検討しましょう。
共有者全員の同意がある
共有物の処分は、共有者全員の同意があることが原則です。
この原則は相続土地国庫帰属制度にもあてはまり、制度利用は共有者全員の同意と共同申請が条件となります。
一部の相続人が独断で申請することはできません。
もし共有者が自分の持ち分を売却し、相続人と第三者が共有している場合は、第三者の同意があれば、相続人が申請人となり制度を利用することができます。
却下事由に相当しない土地であること
申請の却下や不承認となる理由は、以下のようなものがあります。
これらに該当している土地であれば、制度の利用はできません。
- 建物が建っている
- 建物以外にも樹木や工作物がある
- 担保権や何らかの権利が設定されている
- 通路、墓地など他人が使用する予定がある
- 土壌汚染対策法で定められる有害物質で汚染されている
- 隣近所と境界が曖昧で所有権などの争いがある
- 地下に埋蔵物があり取り除く必要がある
要は、土地の利用に際し、国や地方自治体が余分な費用や労力を使わなければいけない場合は認められません。
このような場合、却下事由の原因を取り除けば、申請が通る可能性があります。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリット・デメリット
相続土地国庫帰属制度は国の制度であるため、安心して利用できるものですが、メリットとともにデメリットも存在します。
ここで詳しく解説します。
制度利用を検討する際の参考にしてください。
メリット
相続土地国庫帰属制度のメリットは、以下の通りです。
- いらない土地だけを手放せる
- 売却先や土地の引受先を探す必要がない
- 引き取り後の管理も安心
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続した財産の中から不要な土地だけを手放すことができます。
そのため不要な土地のために相続放棄をする必要はなく、他の財産を守ることができます。
個人で土地を手放す場合は、売却先や譲渡相手を自ら探さなければいけませんが、この制度ではその必要はありません。
国に申請するだけで処分できます。
また、売却や贈与を選択すると、譲渡所得税や贈与税など新たな税金がかかります。
しかし制度を利用する場合、税負担は相続時の相続税のみであるため負担も少ないでしょう。
国庫帰属後は国が管理をするため、近隣に迷惑をかける心配もありません。
デメリット
一方で、デメリットは以下の通りです。
- 利用条件が限定的で限られた土地にしか適用できない
- 手続きの費用がかかる
- 審査、手続きに時間がかかる(数カ月~1年ほど)
一番の大きなデメリットは、利用条件が限定的であることです。
争いがある場合や工作物などにより利用が難しい場合など、早く手放してしまいたいと思うような条件の土地は、却下事由に相当する可能性が高いです。
そのため、制度の利用は簡単ではありません。
建物や工作物がある場合の撤去費用や、争いがある場合の解決費用は自己負担となります。
さらに制度利用の審査手続きにも費用がかかるため、申請時には金銭的な負担を考慮する必要があるでしょう。
また、審査には書類審査や実施調査が含まれるため、数カ月~1年ほど時間がかかる場合があります。
申請以前に却下事由の解消が必要な場合は、さらに時間を要する可能性もあります。
相続土地国庫帰属制度を利用するための手続き
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは、以下の通りです。
- 審査申請
- 法務局の書面調査
- 実地調査
- 審査結果の通知
- 負担金の納付
- 国庫帰属
段階ごとに解説していきます。
審査申請
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は、土地一筆あたり14000円です。
申請書に収入印紙を貼って申請します。
申請先は、土地がある都道府県の法務局です。
提出先は法務局のHPで確認できます。
法務局の書面調査
申請をすると法務局で書面による調査が行われ、申請書類の不備や申請者の要件について確認されます。
添付書類として提出する写真や図面、相続人の確認書類なども念入りに確認されるため、抜け漏れのないように準備しましょう。
抵当権などの権利設定がされている場合は、ここで却下事由として判断されます。
実地調査
書類審査が終われば、土地の実地調査が行われます。
現状を確認し、構造物や汚染状況など、却下・不許可事由に相当するものがないか確認します。
近隣との境界線や土地の利用に関して疑義が生じる場合は、調査が長引くこともあるでしょう。
審査結果の通知
審査が終了すると、国庫帰属の承認の可否について通知書が届きます。
承認されれば、負担金の納付書が同封されて送られてきます。
不承認であっても、審査手数料の返金はありません。
もし虚偽申請などが発覚した場合、一度承認されても申請の取り消し処分となります。
その場合、国から損害賠償請求を起こされる可能性もあるでしょう。
負担金の納付
審査が通り、土地が国庫に帰属されることが決まれば、負担金を支払う必要があります。
負担金は10年分の土地管理費用相当額とされ、一般的な宅地や田畑であれば、原則20万円です。
山林や市街化区域など特定の土地であれば、面積に応じて金額は変動します。
負担金は納付書が届いてから30日以内に納付しましょう。
相続土地国庫帰属制度以外に土地を手放す方法

相続土地国庫帰属制度の利用が難しい場合は、他の方法で土地を手放すことを検討しましょう。
土地を相続する前なのか、あるいはすでに所有しているのかで選択する手段が異なります。
ここでは、相続土地国庫帰属制度以外に土地を手放す方法を解説します。
遺産分割で他の相続人に相続してもらう
相続が発生する前、あるいは遺産分割を行う段階であれば、土地を他の相続人に相続してもらうことを検討しましょう。
遺産分割は相続人全員の同意があれば、任意の方法で分割できます。
もし土地の所有や利用に前向きな人がいれば、協議で打診してみるのもよいでしょう。
相続税を支払った後に分割しようとすると、相続人の間で売買や贈与を行うことになり、譲渡所得税や贈与税を支払うことになります。
相続が発生する前や遺産分割協議の段階で、有効な手段です。
相続放棄する
相続が発生した後、3カ月以内であれば相続放棄が可能です。
しかし相続放棄は、すべての相続財産を放棄することになります。
土地以外の財産も必要ない、ということであれば放棄も検討しましょう。
放棄すれば土地は自動的に国庫帰属となります。
相続発生から3カ月を過ぎると放棄できなくなることに注意が必要です。
また、相続が発生していない段階で、前もって相続放棄することはできません。
売却や贈与をする
すでに土地を相続し所有している場合、売却や贈与により手放す方法が一般的です。
売却は不動産屋に鑑定を依頼し、土地が売却可能かどうか確認することから始めましょう。
不動産屋に仲介を依頼すれば、処分できます。
土地を譲り渡す場合は、まず譲渡先を見つける必要があります。
譲渡先が見つかれば、贈与契約書や登記手続きなどを行いましょう。
贈与する場合、受贈者側に贈与税の支払い義務が発生することに注意が必要です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は所有者不明土地の解消と、土地活用を目的とした制度です。
相続人であれば利用することができるため、管理に困っている土地があれば制度利用を検討しましょう。
ただし、利用条件は限定的であるため、土地の現状をよく確認する必要があります。
費用と時間がかかることも念頭に、相続土地国庫帰属制度以外の方法も含め処分方法を検討するとよいでしょう。