この記事でわかること
- 不在者財産管理人の6つのデメリット
- 不在者財産管理人の予納金と費用
- 不在者財産管理人のメリット
- 不在者財産管理人と相続財産管理人の違い
- 民法改正による相続財産管理人と相続財産清算人の違い
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理するために選任される制度です。
行方不明の相続人がいた場合にも遺産分割協議を進めることができるメリットがありますが、デメリットもあります。
本記事では、不在者財産管理人のデメリットを6つに分けてわかりやすく解説します。
また、選任にかかる費用や予納金の相場についても紹介し、相続手続きを進める上で知っておきたいポイントを説明します。
不在者財産管理人のデメリットを正しく把握し、納得できる相続手続きを進める際の参考にしてください。
目次
不在者財産管理人のデメリット6つ
不在者財産管理人を選任することで、相続人の中に行方不明者がいても相続の手続きを進めることができます。
一方で、申立人や関係者にとっては無視できないデメリットも存在します。
ここでは、あらかじめ知っておきたい6つのデメリットについて、わかりやすくご紹介します。
手続きに時間がかかる
不在者財産管理人の選任手続きは、申立てから選任まで3カ月から数カ月かかることが一般的です。
書類の準備、予納金の納付、家庭裁判所による審査など複数のステップがあり、手続きが滞る場合は期間が長引くこともあります。
また、遺産分割や不動産の売却など「権限外行為」を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となり、その分手続きが長期化します。
不在者財産管理人の選任は、想定よりも時間がかかる可能性がある点に注意しましょう。
予納金の負担
不在者の財産の中に現金が十分にあれば、管理人の報酬や財産管理に必要な費用は不在者の財産から支払われます。
しかし、不在者の財産が不動産などで現金化できない場合や財産が少ない場合は、申立人が負担しなくてはなりません。
その負担金は予納金と呼ばれ、数十万円から100万円以上になることもあります。
予納金は、管理人の報酬や不動産の管理費用、預金の手数料など、財産管理に必要な経費や管理人の報酬に充てられます。
予納金の額は申立て後に家庭裁判所が調査の上で決定され、不在者の財産状況によって大きく変動します。
もし予納金が高額になり負担が重いと感じれば、申立て自体を取り下げることも可能です。
なお、予納金は管理終了時に余れば返還されますが、残らないことも多く、費用負担は大きなリスクとなるでしょう。
毎月費用が発生し続ける
不在者財産管理人には、管理が終了するまで、継続して報酬が発生します。
たとえば、不動産の固定資産税や管理に継続的な費用が発生する場合は、その費用も管理終了まで発生します。
管理人は一般的に弁護士や司法書士などの専門家が選任されますが、報酬として月額1万円~5万円程度が必要です。
これらは予納金に含まれていますが、管理が長期化した場合は、追加の支払いを求められることがあるでしょう。
管理が長引くほど費用負担が増大するリスクが高くなり、費用負担は管理が終了するまで続きます。
目的達成後も管理が継続する
遺産分割や特定の財産処分といった当初の目的が達成された後も、不在者財産管理人の職務は続きます。
不在者財産管理人の職務は、以下の事由により終了します。
- 不在者が見つかった
- 不在者の失踪宣告
- 不在者が死亡
- 不在者の管理すべき財産がなくなった
管理が終了しない限り、管理人は引き続き財産管理を行う必要があり、報酬や管理費用の負担も継続します。
目的が果たされても管理は終了せず、いつまで費用負担が続くか見通しが立たない点もデメリットといえるでしょう。
第三者が選任される可能性
不在者財産管理人は家庭裁判所が選任するため、希望する人が申立人に選ばれるとは限りません。
多くは弁護士や司法書士などの専門家が選任され、家族や親族など身近な人が管理人になるケースは少数です。
第三者が選任されることで、家庭事情や不在者と関係者の背景を十分に理解しないまま管理が進められる可能性があります。
そのため、遺産分割や管理において柔軟な対応が難しくなることや、関係者の意向が反映されにくくなることがあります。
不在者財産管理人は、不在者の利益のために職務を遂行します。
必ずしも申立人や相続人の意向に沿わない可能性があることを頭に入れておきましょう。
不在者の財産保全が優先される
不在者財産管理人の最大の任務は、不在者の財産を保全することです。
そのため、遺産分割協議や不動産の処分などを行う際も、不在者の法定相続分や利益を最優先で守らなければなりません。
結果として、他の相続人の希望や事情があっても、不在者の利益を損なう内容では手続きが進められません。
たとえば、遺産分割で他の相続人が多く取得したい場合や、不動産を早期に売却したい場合でも、家庭裁判所の許可が下りないことがあります。
関係者全体の合意が得られても、不在者の利益保護が優先されるため、希望通りに進まないケースがある点に注意しましょう。
不在者財産管理人のメリット
不在者財産管理人を選任する最大のメリットは、行方不明が原因で滞ってしまう法律行為を進められる点です。
相続人全員の同意が必要な遺産分割協議も、不在者財産管理人が代理人として参加することで成立します。
それにより、不在者の財産が放置されることによる価値の低下や、損失発生のリスクを予防することができるでしょう。
また、裁判所の監督のもとで安全かつ公正に管理できるのも大きなメリットです。
たとえば、不在者名義の預金の払い戻しや不動産の管理・処分、賃貸借契約の解約などは裁判所の許可が下りれば可能です。
不在者財産管理人に関するよくある質問
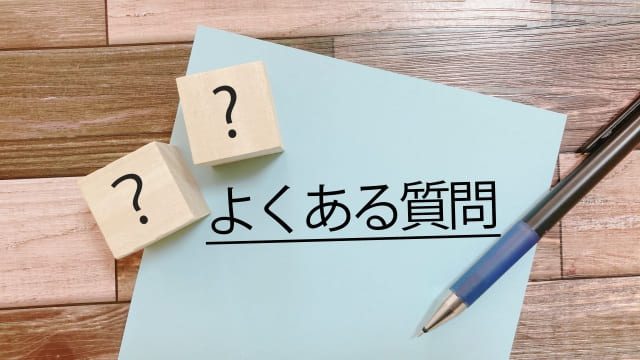
不在者財産管理人は似た名称の制度が複数あるため、違いがわからない、という声が多く聞かれます。
ここでは、不在者財産管理人と相続財産管理人の違い、さらに民法改正による相続財産管理人と相続財産清算人の違いについて解説します。
不在者財産管理人と相続財産管理人の違いは?
前述したように、不在者財産管理人は、相続人の中に行方不明者がいる場合に、家庭裁判所が選任する管理人です。
主な役割は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、その財産を保存・管理することにあります。
一方、相続財産管理人は、主に相続人がいるか不明な場合や相続人全員が相続放棄した場合に選任されます。
この場合、管理人は公告を行って相続人や債権者を探索し、最終的には財産を清算して国庫に納めることが主な業務です。
不在者財産管理人は「相続人はいるが行方不明」、相続財産管理人は「相続人がいない、または不明」という状況で選任されます。
混同しやすいですが、役割や目的が大きく異なるため、注意しましょう。
民法改正による相続財産管理人と相続財産清算人の違いとは?
2023年4月1日に施行された民法改正によって、相続財産管理人と相続財産清算人は明確に分けられました。
従来は、相続財産管理人が財産の保存から清算まで一括して担当していましたが、改正後は目的に応じて役割が異なります。
相続財産管理人は、主に財産の現状維持や保存行為などの管理を行い、処分行為は家庭裁判所の許可を得て行います。
一方、相続財産清算人は、債権者や受遺者への弁済、特別縁故者への分配、最終的な国庫帰属など清算の役割を担っています。
これにより、相続人がいない場合や相続放棄があった場合でも、状況に応じて適切な管理・清算が進められる体制に変更されました。
不在者財産管理人、相続財産管理人、相続財産清算人の3つは混同しやすいため注意しましょう。
まとめ
不在者財産管理人のデメリットを考慮すると、その選択が適切なのかどうかも判断に迷うことでしょう。
また、手続きや費用、管理期間、管理人の選任基準などはケースごとに異なり、家庭裁判所の傾向は専門家でなければわかりません。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、早期に相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
最適な手続きの進め方や費用負担の見通し、将来的なリスクへの備えなど、状況に応じた具体的なアドバイスを受けましょう。

























