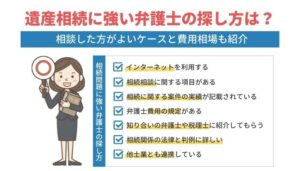この記事でわかること
- 事実婚のパートナーに認められない権利
- 事実婚のパートナーに財産を渡す方法
- 事実婚のパートナーが財産を受け取るときの注意点
結婚と事実婚は、どちらも同居して生活を共にするなど共通点が多くみられます。
しかし結婚をしていると認められる権利が、事実婚でも認められるわけではありません。
結婚と事実婚の扱いが法律上、異なるためです。
特に相続において、事実婚に認められない権利や制度は、いくつも存在します。
そのため、結婚している夫婦とは異なる方法で、パートナーに財産を渡す必要があります。
この記事では、事実婚で財産を渡す方法や注意点を中心に、詳しく解説していきます。
事実婚のパートナーに相続する権利は原則ない
事実婚のパートナーに相続をする権利があるのかは、事実婚をされている方にとって大きな関心事の一つかもしれません。
自分が亡くなったときは、パートナーに財産を渡したいと考える方も多いのではないでしょうか。
結婚をしている場合、配偶者は亡くなった方の財産の半分を相続できます。
しかし事実婚は結婚と違い、パートナーに相続する権利は原則としてありません。
そのため事実婚の場合、亡くなった方の財産を相続できません。
また、パートナーは相続する権利がないために、相続に関する制度を利用できない場合も多くなっています。
事実婚が何年経過すればパートナーは相続できるのか
前述したように、事実婚のパートナーには、相続する権利はありません。
では、事実婚を何年くらい続けると、相続する権利は発生するのでしょうか。
相続する権利は、事実婚を何年続けても発生しません。
そのため、事実婚の状態がどれだけ長くても、パートナーは相続できないのです。
事実婚のパートナーに相続する権利がない理由
結婚をしている夫婦は、法律で婚姻関係にあると認められています。
そのため夫婦のどちらかが亡くなったときは、残された側が法律で定められた法定相続人になります。
一方で事実婚のパートナー同士は、婚姻関係にあると認められていません。
事実婚を何年続けても、パートナーが相続人になれないのは、上記の理由のためです。
事実婚のパートナーに認められない権利
相続の他にも、事実婚のパートナーには認められない権利が存在します。
主な事実婚では認められない権利には、以下のものが挙げられます。
- パートナー同士の同姓
- 嫡出の推定
- 税金面での優遇
- 給付金や手当の支給
共通しているのは、すべて結婚をしていると認められる権利である点です。
それぞれ詳しく解説します。
事実婚はパートナー同士の同姓が認められない
結婚すると婚姻関係となり、夫婦の同姓は法律で認められています。
しかし事実婚のパートナー同士は、同姓にできません。
ただし、家庭裁判所で氏の変更許可申立てをして、パートナーの苗字に変更することは可能です。
気をつけたいのは、氏の変更許可申立てをしても、許可が下りない場合がある点です。
確実にパートナーと同姓になるには、結婚をするのが確実な方法かもしれません。
事実婚は嫡出の推定が認められない
嫡出の推定とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもは、夫の子どもと推定される法律上の決まりです。
事実婚には、嫡出の推定は認められていません。
そのためパートナーとの間に生まれた子どもと父親は、父子関係になりません。
父子関係を成立させるためには、父親の認知が必要です。
また子どもの共同親権が、事実婚では認められていません。
親権を持つパートナーが亡くなった場合は、親権者変更の審判が必要になります。
ただし変更が認められない場合もあるため、注意が必要です。
事実婚は税金面での優遇が認められない
結婚していると、単身者より税金面で優遇される場合があります。
たとえば、配偶者控除や配偶者特別控除などです。
しかし上記の制度は、単身者だけではなく、事実婚にも適用されません。
また前述したように、事実婚のパートナーに相続する権利がないため、相続税の税額軽減制度を利用できません。
事実婚は給付金や手当の支給が認められない
ここでいう給付金や手当は、婚姻関係を前提として支給される制度のことです。
国民すべてを支給対象とした給付金や手当などは、事実婚をされている方にも支給されますが、婚姻関係を前提としたものはその限りではありません。
結婚している夫婦であれば、出産すると国から出産育児一時金や出産手当が支給されます。
また育児中の給付金として、育児休業給付金や育児手当などがあります。
しかし、事実婚のパートナーが出産や育児をしても、給付金や手当は支給されません。
事実婚で認められている権利
事実婚で認められない権利を中心に紹介しましたが、事実婚で認められている権利もあります。
- 健康保険の扶養家族
- 国民年金の第3号被保険者
- 介護休業、介護休暇など
- 労働災害の遺族補償年金
上記の権利は、結婚と同じように事実婚でも加入や支給等がされます。
また結婚とまったく同じ扱いではないものの、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できます。
住民票の記載は、事実婚をしている証明書として利用できる場合があります。
余程の事情がなければ、記載をしたほうが便利な場合が多いでしょう。
事実婚のパートナーに財産を渡す方法
前述したように、事実婚のパートナーに相続をする権利はありません。
しかし、もし自分が亡くなったら、パートナーに財産を譲り渡したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、相続以外で事実婚のパートナーに財産を渡す方法を、5つ紹介していきます。
生前に贈与をする
まず、最初に紹介するのは生前贈与です。
生前贈与は、贈与する側とされる側の関係性を問わないため、事実婚のパートナー同士でも行えます。
自分の財産を無償で譲り渡す意思表示をして、パートナー側が受け取る意思表示をすることで、贈与契約は成立します。
また、生前贈与は口約束だけでも契約が成立します。
しかし、後でトラブルにならないように、贈与契約書を作成しておくといいでしょう。
贈与する財産が年間で110万円以下であれば、非課税になります。
こうしたことを念頭に置いて、生前贈与を行うことをおすすめします。
遺言書を作成する
次に紹介するのは、遺言書の作成です。
パートナーに財産を譲り渡す旨を、遺言書に記載して作成します。
遺言書は作成した方が、亡くなった後に効力が発生します。
効力発生後は、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要です。
検認が済むと、検認済証と呼ばれる書類が発行されます。
検認済証明書が発行された遺言書でなければ、不動産登記や銀行口座の名義変更ができなくなります。
検認の手続きを忘れないように、注意しましょう。
生命保険の受取人にする
財産を渡す方法の3つ目は、生命保険の受取人をパートナーにすることです。
生命保険の受取人は、一般的には配偶者、1親等、2親等の血族までとされています。
しかし生命保険会社によっては、一定の条件が揃えばパートナーを受取人にできます。
一定の条件とは、たとえばお互いに戸籍上の配偶者がいないことや、生計を一つにして同居していた期間の長さなどです。
生命保険の受取人にする方法の注意点
相続人が保険金を受け取る場合は、500万円に法定相続人の数を掛けた金額が非課税になります。
しかしパートナーが受取人の場合、相続税の非課税控除が受けられません。
そのため、保険金の全額が課税対象になります。
非課税控除は受けられませんが、財産を渡す方法の一つとして検討の余地はあるでしょう。
特別縁故者の財産分与制度をつかう
財産を渡す方法の4つ目は、特別縁故者の財産分与制度を利用することです。
特別縁故者の財産分与とは、亡くなった方に法定相続人がいない場合、その方と特に縁のあった人が財産を取得できる制度をいいます。
法定相続人がいないことが前提となっているため、誰でも利用できる制度ではないことに注意しましょう。
特別縁故者の財産分与は、家庭裁判所に申立てをして行います。
申立てが可能な期間は、相続人がいないことが確定してから3カ月以内です。
家庭裁判所から財産分与が認められると、パートナーは特別縁故者として財産を取得できます。
ただし、亡くなった方のすべての財産を取得できるわけではありません。
取得できる財産は、家庭裁判所が決定した金額だけになることに注意が必要です。
遺族年金を受給する
最後に紹介する財産を渡す方法は、遺族年金を受給することです。
遺族年金の受給対象者は、配偶者だけでなく事実婚のパートナーも含まれています。
ただし受給対象者になるには、一定の要件を満たす必要があります。
要件は「事実婚関係にある者」と「生計維持関係にあった者」の2つです。
手続きには、要件を満たしていることを証明する書類が必要になります。
必要書類を揃えたら、年金事務所や年金相談センターで遺族年金の請求をしましょう。
請求が認められれば、パートナーは遺族年金を受給できるようになります。
なお遺族年金は、請求をすれば必ず受給できるわけではありません。
支給される確率をあげるために、しっかりと事前の準備をすることをおすすめします。
事実婚のパートナーが財産を受け取るときの注意点

パートナーが財産を受け取るときに、気をつける点がいくつかあります
たとえば、結婚している夫婦に認められている相続税の軽減措置は、事実婚のパートナーに適用されません。
そのため結婚している場合よりも、相続税を多く支払うことになるかもしれません。
また亡くなった方に法定相続人がいたときは、財産を受け取ったことが原因で、トラブルが発生する可能性もあります。
あとで困らないように、財産を受け取るときの注意点を覚えておくとよいでしょう。
相続税の配偶者控除は適用されない
事実婚のパートナーには、相続税の軽減措置である配偶者控除が適用されません。
配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち1億6000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までは、相続税が課されない制度をいいます。
そのため事実婚のパートナーは、配偶者と比べて相続税を多く納付する可能性があります。
相続税が2割加算される
事実婚のパートナーが受け取った財産には、相続税が2割加算されます。
相続税が2割加算されるのは、配偶者と1親等の血族以外が相続したときです。
事実婚のパートナーは、2割加算の対象者になることに注意が必要です。
障害者の税額控除は適用されない
相続人が障害者の場合、85歳になるまで年間10万円まで相続税が控除されます。
しかし、事実婚のパートナーが障害者であっても、事実婚のパートナーは相続人ではないために障害者の税額控除は適用されません。
小規模宅地等の特例は適用されない
配偶者が自宅として使用していた土地を相続すると、小規模宅地等の特例が適用されることがあります。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が所有していた土地を相続した場合、土地の評価額が最大80%まで減額できる制度です。
事実婚のパートナーが土地を受け取っても、小規模宅地等の特例が適用されない点に注意しましょう。
寄与分は認められない
亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した相続人は、他の相続人より相続財産を多くしてもらえる場合があります。
この多くもらえる相続分は、寄与分と呼ばれています。
ただ、寄与分が認められているのは相続人だけです。
遺留分侵害額の請求をされる場合がある
法定相続人は遺留分が侵害されたとき、侵害した相手に遺留分の返還を請求できます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている、最低限の相続財産の割合をいいます。
もし亡くなった方に法定相続人がいた場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
その結果、事実婚のパートナーは、受け取った財産を返還する必要に迫られるかもしれません。
亡くなったパートナーに法定相続人がいるときは、注意したほうがいいでしょう。
まとめ
事実婚は結婚と比較すると、相続で利用できる法律上の制度は多くありません。
亡くなったパートナーに法定相続人がいる場合といない場合で、トラブルが発生する可能性も変わってきます。
そのため、パートナーが亡くなられたときは、まず法定相続人の有無を確認するといいでしょう。
また亡くなった方と事実婚だったと証明しなければ、利用できない制度もあります。
事実婚であったと証明するのは、人によっては手間や時間がかかるかもしれません。
パートナーが亡くなられた後でトラブルや手続きで困ったときは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。